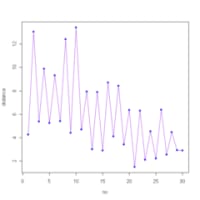・Iくんから戻ってきたトドマツ交雑論文の考察を読む。なるほど、SLAやNAのパートは遠交弱勢の遺伝的な要因よりは前に持ってきたほうがよいようだ。しかし、このままだと、”売り”である交雑によるパフォーマンス低下の話がえらく後に出てくることになってしまう。そもそも、交雑危険性に関する章はこんなに前にある必要があるのか、などと色々と考えた末に、最初のパラグラフに交雑によるパフォーマンス低下があったことをきちんと述べるようにした。さらに、交雑危険性に関する章は最後から2番目のところに移動し、今回は人工交配を用いて交雑後のパフォーマンス評価を行ったが、自然状態では起こりうるのか、というように主題を明確にすることに・・・。
・最初のパラグラフの出来がイマイチのような気がしたが、煮詰まってしまったのでいったん送信。すぐにIくんからの電話で、方針を確認し、本研究の目的を最初にきちんと定義した上で、local adaptationの部分は思い切って削ること、新たに加えた開花期のズレに関する考察はイントロとマテメソに全て移してしまうという方針を決定。すぐさま作業にかかり、30分ほどで終了。ようやく、これまで少しもやもやとしていた考察の流れがすっきりした。やっぱり議論しながら方針を固めていくのが一番大事である。また、思い切ったパラグラフの移動は、こうした流れをすっきりさせる上で、しばしば有効な手段となる。
・ちょっと論文執筆が落ち着いたので、放置されていたアカエゾマツ針葉の形態写真の整理。4集団を加えたのだが、それらの写真は撮りっぱなしになっていた。まずは個体番号をつけて、1年生・2年生シュートと3年生シュートと1年生シュートの横からの画像に分けていく。前山の湿地以外のところの針葉形態がちょっと変な感じ(薄い)である。とりあえず、撮影し忘れたサンプルがないことを確認して一安心。アカエゾ調査隊ではいろんなことが起こるからねえ。
・さらにIくんとやりとりを行った後、校閲前の微修正。ワードにしてみると、やはり複数形のミスとかが残っている。ワードの英文校正機能は本当に秀逸である。ワードで検出されたミスをTexに反映させる作業をしばらく行う。せっかくTexで美しい体裁を作ったのに、最後はワードに直して校閲に出さなければならないところが悲しい。ようやく作業が一段落したところで、ようやく英文校閲に出すことができた。今回の論文の着手は11月19日だったので、論文執筆開始から校閲に出すまで、2ヶ月とちょっとの計算になる(もちろん、その前に既にかなりの解析を終えていたわけだけど・・・)。うーん、順調だ。ま、問題はここからなのだが、とりあえずは一段落。
・明日のアカエゾマツ調査についての下準備。道具、野帳などをチェックする。荒れるといわれていた天候もそれほどではなかったが、明日はどうなるか・・・。山の天気は分からないわけだが、久しぶりの調査は楽しみである。
・最初のパラグラフの出来がイマイチのような気がしたが、煮詰まってしまったのでいったん送信。すぐにIくんからの電話で、方針を確認し、本研究の目的を最初にきちんと定義した上で、local adaptationの部分は思い切って削ること、新たに加えた開花期のズレに関する考察はイントロとマテメソに全て移してしまうという方針を決定。すぐさま作業にかかり、30分ほどで終了。ようやく、これまで少しもやもやとしていた考察の流れがすっきりした。やっぱり議論しながら方針を固めていくのが一番大事である。また、思い切ったパラグラフの移動は、こうした流れをすっきりさせる上で、しばしば有効な手段となる。
・ちょっと論文執筆が落ち着いたので、放置されていたアカエゾマツ針葉の形態写真の整理。4集団を加えたのだが、それらの写真は撮りっぱなしになっていた。まずは個体番号をつけて、1年生・2年生シュートと3年生シュートと1年生シュートの横からの画像に分けていく。前山の湿地以外のところの針葉形態がちょっと変な感じ(薄い)である。とりあえず、撮影し忘れたサンプルがないことを確認して一安心。アカエゾ調査隊ではいろんなことが起こるからねえ。
・さらにIくんとやりとりを行った後、校閲前の微修正。ワードにしてみると、やはり複数形のミスとかが残っている。ワードの英文校正機能は本当に秀逸である。ワードで検出されたミスをTexに反映させる作業をしばらく行う。せっかくTexで美しい体裁を作ったのに、最後はワードに直して校閲に出さなければならないところが悲しい。ようやく作業が一段落したところで、ようやく英文校閲に出すことができた。今回の論文の着手は11月19日だったので、論文執筆開始から校閲に出すまで、2ヶ月とちょっとの計算になる(もちろん、その前に既にかなりの解析を終えていたわけだけど・・・)。うーん、順調だ。ま、問題はここからなのだが、とりあえずは一段落。
・明日のアカエゾマツ調査についての下準備。道具、野帳などをチェックする。荒れるといわれていた天候もそれほどではなかったが、明日はどうなるか・・・。山の天気は分からないわけだが、久しぶりの調査は楽しみである。