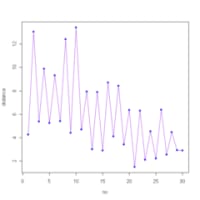・実に久しぶりに,岩魚沢にTさんと倒木上のトドマツとエゾマツの実生の生存調査に行く.事務所近くでは,昨晩から明け方にかけて雪が積もっており,もはや実生の調査は無理かと思われたが,現地では意外と積もっておらず,ぎりぎりセーフである.5haをくまなく歩き回りながら,以前,サンプリングした実生の生存状況をチェックしていく.
・岩魚沢の平坦部はクマイザサでかなり密に覆われている.もちろん,針葉樹の多さによっても異なるわけだが,広葉樹地帯ではそもそも倒木が笹の下に埋もれていたりして,見つけるのがまず一苦労である.ここで,昨日,地道に作成した倒木の位置図が早速役に立つわけだ.
・プロット中心部では,倒木もまばらで実生も少ないので,かえって効率が悪いことに気がつき,倒木も実生も集中している沢沿いから攻める.徐々に5月ごろのサンプリングの記憶もよみがえり,倒木の相対的な位置が頭に入ってくる.こうした調査は,いつもTさんとペアで行っているので,”あ・うん”の呼吸でびしびしと調査は進む.何とかお昼までに沢沿いの集中箇所を終えることができた.

・山で食べるお弁当はやっぱりうまい.これだけ,雪の季節になると,あったかいお茶が体にしみわたる感じだ.それにしても,実生たちは案外元気で,サンプリングしてから今までの季節を無事に過ごしたものが8割は超えるだろう.もちろん,雪解け時期を乗り切れるかどうかが問題になるのだろうが,わずか4本しかない子葉を1本採取された1年生の実生がけなげに生きていたのには感心した.林床では,かなりの実生が死んでいるのに対して,倒木が確かに"セーフ"な場所であることを実感する.倒木上でも,落ち窪んでいて,落葉が溜まっているような場所では枯死率が高いようにも思える.”むれ”とか,虫による被害がありそうだ.また,倒木のはじっこにぎりぎりしがみついてた実生が,コケごとずりおちているのも見られた.
・倒木上の実生をどうやってラベルをするかということが問題なのだが,北海道では雪の関係でやわな苗畑用ラベルだと簡単に落ちてしまう.そこで,標準地で使用しているステンレス製の釘(7.5cm)を幹に直接金槌で打ち付け,ビニールテープでナンバーを書くという手法を取った.今のところ,これでほぼ追跡できるが,一部,それでも釘が抜けてしまっているところがあった(コケでふかふかなためか・・・) .また,どういうわけか,ビニールをぎりぎりと食べる輩(ネズミであろうか・・・)もいて,旗が三角になっているものもあった(が,ナンバーは読めた).この方法で,ほぼ問題はなさそうだが,むしろ倒木の位置が分かりにくくなることの方が今後の調査効率上の問題になりそうだ.
・こうして,トドマツ実生の430本くらいと,エゾマツ実生の453本くらいの調査が終わった!が,わずか数本の倒木の実生調査と風向風速のデータが残ってしまった.ということで,明日も再び岩魚沢に行くのだが,今度は少しゆっくりと観察してみよう.とにかく,今夜雪が積もったとしても,掻き分けてでも実生を見つけだすべく,がんばろう.何はともあれ,たまのフィールドは楽しい!
・岩魚沢の平坦部はクマイザサでかなり密に覆われている.もちろん,針葉樹の多さによっても異なるわけだが,広葉樹地帯ではそもそも倒木が笹の下に埋もれていたりして,見つけるのがまず一苦労である.ここで,昨日,地道に作成した倒木の位置図が早速役に立つわけだ.
・プロット中心部では,倒木もまばらで実生も少ないので,かえって効率が悪いことに気がつき,倒木も実生も集中している沢沿いから攻める.徐々に5月ごろのサンプリングの記憶もよみがえり,倒木の相対的な位置が頭に入ってくる.こうした調査は,いつもTさんとペアで行っているので,”あ・うん”の呼吸でびしびしと調査は進む.何とかお昼までに沢沿いの集中箇所を終えることができた.

・山で食べるお弁当はやっぱりうまい.これだけ,雪の季節になると,あったかいお茶が体にしみわたる感じだ.それにしても,実生たちは案外元気で,サンプリングしてから今までの季節を無事に過ごしたものが8割は超えるだろう.もちろん,雪解け時期を乗り切れるかどうかが問題になるのだろうが,わずか4本しかない子葉を1本採取された1年生の実生がけなげに生きていたのには感心した.林床では,かなりの実生が死んでいるのに対して,倒木が確かに"セーフ"な場所であることを実感する.倒木上でも,落ち窪んでいて,落葉が溜まっているような場所では枯死率が高いようにも思える.”むれ”とか,虫による被害がありそうだ.また,倒木のはじっこにぎりぎりしがみついてた実生が,コケごとずりおちているのも見られた.
・倒木上の実生をどうやってラベルをするかということが問題なのだが,北海道では雪の関係でやわな苗畑用ラベルだと簡単に落ちてしまう.そこで,標準地で使用しているステンレス製の釘(7.5cm)を幹に直接金槌で打ち付け,ビニールテープでナンバーを書くという手法を取った.今のところ,これでほぼ追跡できるが,一部,それでも釘が抜けてしまっているところがあった(コケでふかふかなためか・・・) .また,どういうわけか,ビニールをぎりぎりと食べる輩(ネズミであろうか・・・)もいて,旗が三角になっているものもあった(が,ナンバーは読めた).この方法で,ほぼ問題はなさそうだが,むしろ倒木の位置が分かりにくくなることの方が今後の調査効率上の問題になりそうだ.
・こうして,トドマツ実生の430本くらいと,エゾマツ実生の453本くらいの調査が終わった!が,わずか数本の倒木の実生調査と風向風速のデータが残ってしまった.ということで,明日も再び岩魚沢に行くのだが,今度は少しゆっくりと観察してみよう.とにかく,今夜雪が積もったとしても,掻き分けてでも実生を見つけだすべく,がんばろう.何はともあれ,たまのフィールドは楽しい!