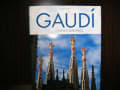いまゴッホの展覧会が開催されている。ポスターに使われている夜のカフェの店先の場面を描いた絵。空には星が輝いている。しかしその輝き方がどうも尋常ではない。いくら今から百何十年ほど前の空とはいえ、星があのような輝き方をするものだろうか。星がたくさん見えるというのならば話はわかる。東京だって天気具合いによっては星の多く見える日があるのだから。しかしゴッホの描くこの星の輝き方は異様だ。これはいわゆる芸術的表現といったものではなく、おそらくはゴッホ自身の目に見えた光景だったと思う。今日この絵を観る善良にして健康的な一般市民はちょっと変わったきれいな絵、くらいにしか思わないかもしれないが、実際に自分にあのような光景が見える状況を想像してほしい。これはかなり辛いのではないだろうか。少なくともわたしには耐えられない。同じように耐えられない思いをさせられる絵は他にもある、例えばムンクとか。ちょっと毛色は違うけれどもココシュカなんかもそうかな。はっきり言って「狂気」なのだ。観るものを引き付ける絵には「狂気」か或る。いや絵だけではない、脚本にも「狂気」はある。例えば向田邦子とか。とっておきはやはり「舞踏」か。
で、そのような「狂気」はいわゆる創作家の特権かというと、どうもそうでもないようだ。わたしの周囲にも時として「狂気」を感じさせる人間がいる。正直な話、そんな人物とはかかわり合いたくないのだが、仕事上どうしてもかかわらなくてはならない場合もある。創作に向かえばあるいは未来のゴッホやムンクになれるかもしれない(もちろん単なるアホ馬鹿が圧倒的に多いのだが)、そんなパーソナリティーと付き合うのはかなり苦痛である。
で、そのような「狂気」はいわゆる創作家の特権かというと、どうもそうでもないようだ。わたしの周囲にも時として「狂気」を感じさせる人間がいる。正直な話、そんな人物とはかかわり合いたくないのだが、仕事上どうしてもかかわらなくてはならない場合もある。創作に向かえばあるいは未来のゴッホやムンクになれるかもしれない(もちろん単なるアホ馬鹿が圧倒的に多いのだが)、そんなパーソナリティーと付き合うのはかなり苦痛である。