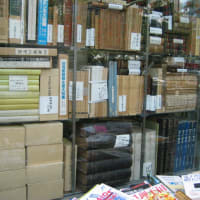先週土曜日、西神田の西秋書店の前を通ったら店先に『廣文庫群書索引補訂』が三百円で並んでいたので手に入れた。『廣文庫』『群書索引』と聞いてどのような本かすぐにわかる人がそれほど多いとも思えない。以前に「群書索引的効験」の回でこれらの本がどのようなものか少し触れているので興味ある方はそちらを参照願います。
わたしの持っている『廣文庫』『群書索引』は旧版だが、この名著普及会刊行の『廣文庫群書索引補訂』は新旧両版とも通用するので購入した。百頁にも満たないA5版の本なのだが定価は四千八百円となっていた。ついでに名著普及会で復刻した『廣文庫』が定価二十万円だったということもこのたび初めて知った。
わたしは元版の『廣文庫』を西神田の日本書房でもう随分と前に買った。じつはこの『廣文庫』の数冊が一万いくらの値で日本書房の店先に置かれているのをみたとき、わたしはこれがどのようなものなのかをまったく知らなかった。店の旦那に聞けばおそらく丁寧に教えてくれたことだろうが、こちらにも一応プライドってものがあったので、その日はやり過ごして帰宅してさっそく手元にあった新潮社の『日本文学大辞典』で調べてみて、やっとその来歴を知りそしてこのとき『群書索引』のことも同時に知った。数日後、再び日本書房を訪れたら『廣文庫』はまだ売れずに店先に置かれていた。今考えてみればこれはほとんど奇跡的といってもよいことなので、元版ゆえ大きく分厚く重たいため扱いにはことの外めんどうには違いないが、古文献の一大図書館とでもいうべき『廣文庫』がまだそこにあったということは、もうなにか自分との運命的な繋がりがあるとしかおもえなかった(ちとオーバーかな)。さっそく店の奥の帳場にいた大旦那に「店先にある廣文庫をください」と頼んだ。「持って帰れますか」とたずねたら、「そりゃあ無理ですよ」と笑われた。このとき初めて『廣文庫』が全部で二十巻もあることが判った。
『廣文庫群書索引補訂』は上にも書いたように百頁もないくらいの本だが、そこに『廣文庫』と『群書索引』の正誤表が載っている。考えてみればこの浩瀚な両書の文字を一々チェックする仕事は、ほとんど気の遠くなるようなことなのだ。例えばある引用文章の漢字が間違っているのか、正しいのかは引用した元ネタを見ればそれで済むとつい思ってしまうが、先ずはその元ネタとなった本を探さねばならない。公立図書館にあればこれは幸運といえる。稀覯本になるほど個人所有のものが多い。そうなると該当する所蔵家のもとを訪れて閲覧をお願いすることとなるが、彼らは概して筋金入りの書痴だから二つ返事で見せてくれるとは限らない。そこをなんとかお願いしてやっと閲覧できたとしても、何時間でも自由に調査できるわけではない。むかしTBSで日曜日の朝に「時事放談」という硬い番組を放送していた。出演者は細川隆元と小汀利得(おばまとしえ)だった。じつはこの小汀利得という人は名だたる稀覯本コレクターで、学者などもときどき小汀の蔵書を閲覧させてもらっていたそうだが、そのようなとき小汀は本を見ている学者の前にどっかと座ってその一挙手一投足を監視していた、という話を誰かが書いていた。そんな悪条件下で目的の書物を調べてもそこで問題が解決するとは限らない。同じ題名でも元ネタとして使用したものとは版が違うかも知れないからだ。膨大な文献学的知識と書誌学的知識のほか、文学、言語、思想、政治、宗教とあらゆる分野にわたる専門的素養を要求され、しかも大々的に評価されることのほとんどない、なんとも辛い仕事なのだ。そのようなことを勘案すると『廣文庫群書索引補訂』の四千八百円はけっして高い値段ではないのかもしれない。
始めのところで『廣文庫』の定価が二十万円だったと書いたが、この『廣文庫群書索引補訂』には「群書索引廣文庫購入者御芳名録」というのが載っていて「昭和五十二年十月二十日までに「群書索引」「廣文庫」のうちひとつまたは両方をお求めくださった方々」の姓名と都道府県名が記されている。じつはこれもけっこう面白い。大学図書館、公立の博物館などはまあ当たり前としても(それでも少ないが)、結構出版社が購入しているのにはさすがだと感心した。個人名をみて見ると、前尾繁三郎なんて政治家が東京都の部のトップに掲載されているのは、これはヨイショかなと思ったり、慶応義塾女子高校図書室なんえてのを見ると秀才お嬢ちゃんの通う学校だけあるなあと感心したり、その他気が付いた有名人としては、加藤郁乎、上笙一郎、平岩弓枝、佐伯梅友、児島襄、諸橋徹次、児玉幸多、大岡信。そうそう、神奈川県の部には澁澤龍彦(鎌倉市)というのもあった。
わたしの持っている『廣文庫』『群書索引』は旧版だが、この名著普及会刊行の『廣文庫群書索引補訂』は新旧両版とも通用するので購入した。百頁にも満たないA5版の本なのだが定価は四千八百円となっていた。ついでに名著普及会で復刻した『廣文庫』が定価二十万円だったということもこのたび初めて知った。
わたしは元版の『廣文庫』を西神田の日本書房でもう随分と前に買った。じつはこの『廣文庫』の数冊が一万いくらの値で日本書房の店先に置かれているのをみたとき、わたしはこれがどのようなものなのかをまったく知らなかった。店の旦那に聞けばおそらく丁寧に教えてくれたことだろうが、こちらにも一応プライドってものがあったので、その日はやり過ごして帰宅してさっそく手元にあった新潮社の『日本文学大辞典』で調べてみて、やっとその来歴を知りそしてこのとき『群書索引』のことも同時に知った。数日後、再び日本書房を訪れたら『廣文庫』はまだ売れずに店先に置かれていた。今考えてみればこれはほとんど奇跡的といってもよいことなので、元版ゆえ大きく分厚く重たいため扱いにはことの外めんどうには違いないが、古文献の一大図書館とでもいうべき『廣文庫』がまだそこにあったということは、もうなにか自分との運命的な繋がりがあるとしかおもえなかった(ちとオーバーかな)。さっそく店の奥の帳場にいた大旦那に「店先にある廣文庫をください」と頼んだ。「持って帰れますか」とたずねたら、「そりゃあ無理ですよ」と笑われた。このとき初めて『廣文庫』が全部で二十巻もあることが判った。
『廣文庫群書索引補訂』は上にも書いたように百頁もないくらいの本だが、そこに『廣文庫』と『群書索引』の正誤表が載っている。考えてみればこの浩瀚な両書の文字を一々チェックする仕事は、ほとんど気の遠くなるようなことなのだ。例えばある引用文章の漢字が間違っているのか、正しいのかは引用した元ネタを見ればそれで済むとつい思ってしまうが、先ずはその元ネタとなった本を探さねばならない。公立図書館にあればこれは幸運といえる。稀覯本になるほど個人所有のものが多い。そうなると該当する所蔵家のもとを訪れて閲覧をお願いすることとなるが、彼らは概して筋金入りの書痴だから二つ返事で見せてくれるとは限らない。そこをなんとかお願いしてやっと閲覧できたとしても、何時間でも自由に調査できるわけではない。むかしTBSで日曜日の朝に「時事放談」という硬い番組を放送していた。出演者は細川隆元と小汀利得(おばまとしえ)だった。じつはこの小汀利得という人は名だたる稀覯本コレクターで、学者などもときどき小汀の蔵書を閲覧させてもらっていたそうだが、そのようなとき小汀は本を見ている学者の前にどっかと座ってその一挙手一投足を監視していた、という話を誰かが書いていた。そんな悪条件下で目的の書物を調べてもそこで問題が解決するとは限らない。同じ題名でも元ネタとして使用したものとは版が違うかも知れないからだ。膨大な文献学的知識と書誌学的知識のほか、文学、言語、思想、政治、宗教とあらゆる分野にわたる専門的素養を要求され、しかも大々的に評価されることのほとんどない、なんとも辛い仕事なのだ。そのようなことを勘案すると『廣文庫群書索引補訂』の四千八百円はけっして高い値段ではないのかもしれない。
始めのところで『廣文庫』の定価が二十万円だったと書いたが、この『廣文庫群書索引補訂』には「群書索引廣文庫購入者御芳名録」というのが載っていて「昭和五十二年十月二十日までに「群書索引」「廣文庫」のうちひとつまたは両方をお求めくださった方々」の姓名と都道府県名が記されている。じつはこれもけっこう面白い。大学図書館、公立の博物館などはまあ当たり前としても(それでも少ないが)、結構出版社が購入しているのにはさすがだと感心した。個人名をみて見ると、前尾繁三郎なんて政治家が東京都の部のトップに掲載されているのは、これはヨイショかなと思ったり、慶応義塾女子高校図書室なんえてのを見ると秀才お嬢ちゃんの通う学校だけあるなあと感心したり、その他気が付いた有名人としては、加藤郁乎、上笙一郎、平岩弓枝、佐伯梅友、児島襄、諸橋徹次、児玉幸多、大岡信。そうそう、神奈川県の部には澁澤龍彦(鎌倉市)というのもあった。