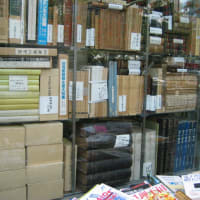どこの世界にも専門用語というものがある。しかし大抵の場合それらは説明されればあるていど理解可能なものだ。
哲学という学問分野にも専門用語というものがある。例えば「所与」、これを英語では"given data"、ドイツ語では"die Gegebenheit"という。外国語で書かれるとかえって判りやすくなってしまうのも考えてみれば問題だ。"given data"のどこにも難しさなどない。「与えられた、データ」と聞けばこれば何を意味するかは大方の人が直感的に理解できるはずだ。しかし「所与」などといわれても何のことだか見当がつかない。専門家が議論するとき一々「与えられた、データ」などといっていてはまどろっこしいのでこれを「所与」と称するのだと聞けば、まあそれなりに納得はできるが。
「超越」、これも哲学ではよく聞く専門用語だが「所与」よりは少々わかりづらい。英語では"transcendence"ドイツ語では"die Transzendenz"でほとんど綴りが同じなのは元になったラテン語"trans"(対格支配の前置詞「~を超えて」)と"scando"(向こうの上に登る)の合成語"tarnscendo"(~を超えてあちら側へ歩く)に因るわけだけれども、厳密には名詞"die Transzendenz"と形容詞"transzendent"、同じく形容詞"transzendental"では意味がいくらか異なる。名詞"die Transzendenz"を「超越」と訳すのはよいとして、形容詞"transzendent"(超越的)は「知覚できる範囲を超えている」というほどの意味であり、一方"transzendental"はスコラ哲学においては「アリストテレス的なカテゴリーを越えた概念」といったらよいか、つまり"ens"(有)、"unum"(一)、"verum"(真)、"bonum"(善)、などを指していう。そしてさらにカントによって"transzendental"は新しい意味を持たされる。これを「先験的」或いは「超越論的」と訳したりしているが、要するに内的直感形式としての時間や外的直感形式としての空間、純粋悟性概念、統覚などがそれに当たるのだそうで、だからカント哲学を超越論的哲学ともいう。このあたりは少々煩瑣ではあるけれども、まあなんとか判らないでもない。注意しなければならないのは、「超越的」と「超越論的」とではその表す意味はことなるということで、この点を理解していていないと議論がかみ合わない事態が発生する。
「即自」「対自」、これはドイツ語の"an sich"、"für sich"を訳したもので、ヘーゲリアンの哲学プロパーはごく気安く「即自」「対自」を連発するけれども、これがわたしには結構難解だったし今でも難解なのだ。普通のドイツ語辞典を引くと"an sich"は「それ自体として」、また"für sich"についても「それ自体として」「それだけで」「独りで」などの意味が載っている(注1)。しかしこれでは両者とも同じ意味となってしまいわけが判らない。ヘーゲル関係の事柄を調べるのならこれがいいんじゃないかと『ヘーゲル用語辞典』ってのを開いてみた。以下に引用する。
「ドイツ語のan sichは直訳すれば「自己に即して」、つまりその物にぴったりと重なり、分裂がない状態を意味する。an sichはふつう「それ自体として」などと訳されるが、哲学では「即自」、「自体」などと訳される。für sichは直訳すれば、「自己にたいして」、「自己と向き合って」となるが、普通「それ自体として」、「独りで」などと訳される。für sichは哲学では「対自」、「向自」などと訳され事物(自己)が二重化ないし分化することを示す」(注2)
白状するとわたしはこれを読んで何を言っているのかさっぱり判らなかった。この文章を素直に読めば"an sich"は「それ自体として」という意味であり、"für sich"も同じく「それ自体として」という意味であるがしかし哲学では「事物(自己)が二重化ないし分化すること」という意味となるということだ。まあそうであるとして、ではなぜ「独りで」が「自己の二重化」ということになるのかまったく理解できない。書いた人間の文章作成能力に問題があるのは確かだが、なにもここまで判りづらくしなくともよさそうなものだと思った。
これはそんなに難しい話ではない。"an sich"、"für sich"はそれぞれ「そのものとして」、「絶対的に」と訳せばよいのである。そもそも「事物が二重化する」の、イワシの頭のと妙な説明をつけるから判るものでも判らなくなってしまう。何でもかんでも平べったく言えば済むという話ではないが、かといって面妖な漢字で言い換えても返って馬鹿馬鹿しさを露呈するだけになってしまう。
(注1)『独和広辞典』1227頁 三修社 1986年12月15日第1版
(注2)『ヘーゲル用語辞典』72頁 岩佐茂 島崎隆 高田純 編 未来社 1991年7月30日第1刷
哲学という学問分野にも専門用語というものがある。例えば「所与」、これを英語では"given data"、ドイツ語では"die Gegebenheit"という。外国語で書かれるとかえって判りやすくなってしまうのも考えてみれば問題だ。"given data"のどこにも難しさなどない。「与えられた、データ」と聞けばこれば何を意味するかは大方の人が直感的に理解できるはずだ。しかし「所与」などといわれても何のことだか見当がつかない。専門家が議論するとき一々「与えられた、データ」などといっていてはまどろっこしいのでこれを「所与」と称するのだと聞けば、まあそれなりに納得はできるが。
「超越」、これも哲学ではよく聞く専門用語だが「所与」よりは少々わかりづらい。英語では"transcendence"ドイツ語では"die Transzendenz"でほとんど綴りが同じなのは元になったラテン語"trans"(対格支配の前置詞「~を超えて」)と"scando"(向こうの上に登る)の合成語"tarnscendo"(~を超えてあちら側へ歩く)に因るわけだけれども、厳密には名詞"die Transzendenz"と形容詞"transzendent"、同じく形容詞"transzendental"では意味がいくらか異なる。名詞"die Transzendenz"を「超越」と訳すのはよいとして、形容詞"transzendent"(超越的)は「知覚できる範囲を超えている」というほどの意味であり、一方"transzendental"はスコラ哲学においては「アリストテレス的なカテゴリーを越えた概念」といったらよいか、つまり"ens"(有)、"unum"(一)、"verum"(真)、"bonum"(善)、などを指していう。そしてさらにカントによって"transzendental"は新しい意味を持たされる。これを「先験的」或いは「超越論的」と訳したりしているが、要するに内的直感形式としての時間や外的直感形式としての空間、純粋悟性概念、統覚などがそれに当たるのだそうで、だからカント哲学を超越論的哲学ともいう。このあたりは少々煩瑣ではあるけれども、まあなんとか判らないでもない。注意しなければならないのは、「超越的」と「超越論的」とではその表す意味はことなるということで、この点を理解していていないと議論がかみ合わない事態が発生する。
「即自」「対自」、これはドイツ語の"an sich"、"für sich"を訳したもので、ヘーゲリアンの哲学プロパーはごく気安く「即自」「対自」を連発するけれども、これがわたしには結構難解だったし今でも難解なのだ。普通のドイツ語辞典を引くと"an sich"は「それ自体として」、また"für sich"についても「それ自体として」「それだけで」「独りで」などの意味が載っている(注1)。しかしこれでは両者とも同じ意味となってしまいわけが判らない。ヘーゲル関係の事柄を調べるのならこれがいいんじゃないかと『ヘーゲル用語辞典』ってのを開いてみた。以下に引用する。
「ドイツ語のan sichは直訳すれば「自己に即して」、つまりその物にぴったりと重なり、分裂がない状態を意味する。an sichはふつう「それ自体として」などと訳されるが、哲学では「即自」、「自体」などと訳される。für sichは直訳すれば、「自己にたいして」、「自己と向き合って」となるが、普通「それ自体として」、「独りで」などと訳される。für sichは哲学では「対自」、「向自」などと訳され事物(自己)が二重化ないし分化することを示す」(注2)
白状するとわたしはこれを読んで何を言っているのかさっぱり判らなかった。この文章を素直に読めば"an sich"は「それ自体として」という意味であり、"für sich"も同じく「それ自体として」という意味であるがしかし哲学では「事物(自己)が二重化ないし分化すること」という意味となるということだ。まあそうであるとして、ではなぜ「独りで」が「自己の二重化」ということになるのかまったく理解できない。書いた人間の文章作成能力に問題があるのは確かだが、なにもここまで判りづらくしなくともよさそうなものだと思った。
これはそんなに難しい話ではない。"an sich"、"für sich"はそれぞれ「そのものとして」、「絶対的に」と訳せばよいのである。そもそも「事物が二重化する」の、イワシの頭のと妙な説明をつけるから判るものでも判らなくなってしまう。何でもかんでも平べったく言えば済むという話ではないが、かといって面妖な漢字で言い換えても返って馬鹿馬鹿しさを露呈するだけになってしまう。
(注1)『独和広辞典』1227頁 三修社 1986年12月15日第1版
(注2)『ヘーゲル用語辞典』72頁 岩佐茂 島崎隆 高田純 編 未来社 1991年7月30日第1刷