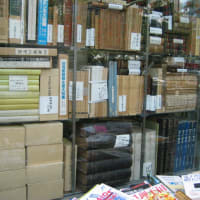"Jupiter, postquam terram caede Gigantum pacavit, homines novum genus, in eorum locum collocavit. Hos homines Prometheus, Japeti filius, ex luto et aqua finxerat. Prometheus autem, misericordia motus, ubi paupertatem eorum et inopiam vidit, ignem e caelo terram secreto deportavit. Principio enim homines, ignari omnium artium, per terram errabant, famem grandibus et baccis aegre depellentes. Propter hoc furtum Jupiter iratus Prometheum ferreis vinculis ad montem Caucasum affixit. Huc ferox aquila quotidie volabat, rostroque jecur ejus laniabat. Denique post multos annos Hercules aquilam sagitta transfixit, et captivum longo supplicio liberavit."(注1)
「ユピテルが地上の巨人族を殺戮することによって平定して以来、人類という新しい種族を、彼ら(巨人族)のいた場所に置いた。これらの人々をユピテルの息子であるプロメテウスは泥と水から創造したのである。しかしプロメテウスは彼ら(人間たち)の貧困と欠乏を見たとき、同情につき動かされて、燃えるものを隠れて天から地上に持ち帰った。というのも最初のうち人間たちはなんの技術も知らず、すなわち巨大なオリーブの実でもって苦しみつつ飢えを追いやりながら、地上をうろつきまわっていたからである。この盗みにより怒ったユピテルはプロメテウスを堅固な鎖でカウカスス山に縛り付けてしまった。そこに持ってきて大胆不敵な鷲が毎日飛んできては、嘴で彼の肝臓をついばんだ。結局何年もの後、ヘラクレスが鷲を矢で貫き、そしてこの囚われ人を永きにわたった罰から開放したのである。」
今回の課題は比較的易しかった。易しかったというのは文法的事項についてもそうなのだけれど、じつはそれよりなにより、わたしがプロメテウスのお話を知っていたということによる。これはとても大事なところで、つまり何が書かれているのかを事前に知っていれば、文法的にあやふやな部分でも想像力で理解できてしまうということなのだ。だから自分の熟知している分野について書かれた外国語ならば、まったく未知の領域よりはいかほどか読みやすいということになる。むかし学校に通っていた頃、効果的な外国語学習の方法として自分に興味のあることが書かれた文章を読むことを勧めた先生がいらっしゃったが、要すれば興味があるのなら聖書でも経済学でも、あるいはジョイスでもポルノでもよいから読んでみることだというのだ。当時わたしはなるほどそれはよいかもしれない、と納得したものだが、実際に外国語をじっくりと勉強してみると、ことはそれほど単純でないことが判ってきた。この伝にしたがって自分の好きな話題、それは例えばドイツ近代史だったとしようか。これをドイツ語で読んだとしておそらくフランス革命を論じた本よりは速く読めるかも知れない。しかしいくら速く読めたとしてはたしてどのくらい厳密に文章を読み込んでいるのかはかなり怪しくなってくる。というのも上にも書いているように「文法的にあやふやな部分でも想像力で理解できてしまう」というとんでもない陥穽があるからだ。わたしなどネイティブ・ランゲージである日本語で記述されている本だって実のところかなりいい加減に読んで判った気になっているのが再三なのであって、ときどき恥をかいている。
要すればたしかに自分の知っている分野に係る文章が理解し安いのは判るのだけれども、それだけに思い込みで読んでしまう危険も多く孕んでいるということ。だからわたしは今では件の先生のアドバイスは外国語学習にとっては、そして特に初心者にとっては返って有害なのではないかと考えるようになった。つまり意識せずに文章を思い込みで読んでしまい、副詞や形容詞の一つ一つ、動詞の活用が何に当たるのか、ドイツ語でいうなら接続法Ⅰ式なのか単なる過去形なのかを厳密に読み込んでいく必要があるというわけだ。
さて本題に取り掛かる。形容詞については既にみているが、この品詞については性と数による局用のほかに比較級、最上級という形がある。英語でも同じ言い方をしているけれども、例えば原級、比較級、最上級というと"good","better"."best"、"much","more","most"、あるいは"tall","taller","tallest"、それから"useful","more useful","best useful"なんてのもあった。最初の例は不規則変化、二番目は規則変化、そして三番目は二音節以上の形容詞における原級、比較級、最上級の作りかたとなる。
ラテン語の形容詞での比較級、最上級についてまず規則変化をみると、例えば"fortis"(勇敢な)は比較級が"fortior"、最上級が"fortissimus"となるが、最上級の語尾は現代イタリア語の絶対的最上級に"issimo"という形で残っているのでちょっと親近感を覚えるが、当然ながら性、数、格による曲用があるわけで、まず比較級の局用を見てゆく。
単数・男性形、女性形は"fortior","fortio-ris","fortio-ri-","fortio-rem","fortio-ri-"となる。
単数・中性形は"fortius","fortio-ris","fortio-ri-","fortius","fortio-ri-"で主格と対格の形は第一変化形容詞と混同しやすいので注意する必要があるが、"fortis"が第二変化形容詞であることを知っていれば間違えることもない。なお奪格は"fortio-re"ともいう。
複数・男性形、女性形は"fortio-re-s","fortio-rum","fortio-ribus","fortio-e-s","fortioribus"で対格は"fortio-ri-s"ともいう。単数属格との違いは"ris"と"ri-s"つまり短母音と長母音の違いなので文字の上では違いがまったく判らないのでこれも注意しなくてはならない。困ったものだ。
最後に複数・中性形は"fortio-ra","fortio-rum","fortio-ribus","fortio-ra","fortio-ribus"
次に最上級の局用も見ておこうか。こちらは"fortissimus"、"fortissima"、"fortissimum"で要すれば第一変化形容詞の局用をおこなえばよい。
このほかに不規則変化する形容詞もいくつかあるが、今回はこのあたりで止めておこう。不規則変化する形容詞と副詞の比較級、最上級、ならびにこれらの実際的な使い方に関しては次回でみて見たいと思う。
今回の自分への宿題はプリニウスの文章から。
"Bene est mihi, quia tibi bene est. habes uxorem tecum, habes filium. Frueris mari, fontibus , viridibus , agro, villa amoenissima. Neque enim dubito esse amoenissimam, in qua se composuerat homo felicior, antequam felicissimus fieret. Ego in tuscis et venor et studeo, quae interdum alternis, et interdum simul facio: nec tamen adhuc possum pronuntiare, utrum sit difficilius capere aliquid, an scribere. Vale"(注2)
(注1)『新羅甸文法』111頁 田中英央 岩波書店 昭和11年4月5日第4刷
(注2) 同上 129頁
「ユピテルが地上の巨人族を殺戮することによって平定して以来、人類という新しい種族を、彼ら(巨人族)のいた場所に置いた。これらの人々をユピテルの息子であるプロメテウスは泥と水から創造したのである。しかしプロメテウスは彼ら(人間たち)の貧困と欠乏を見たとき、同情につき動かされて、燃えるものを隠れて天から地上に持ち帰った。というのも最初のうち人間たちはなんの技術も知らず、すなわち巨大なオリーブの実でもって苦しみつつ飢えを追いやりながら、地上をうろつきまわっていたからである。この盗みにより怒ったユピテルはプロメテウスを堅固な鎖でカウカスス山に縛り付けてしまった。そこに持ってきて大胆不敵な鷲が毎日飛んできては、嘴で彼の肝臓をついばんだ。結局何年もの後、ヘラクレスが鷲を矢で貫き、そしてこの囚われ人を永きにわたった罰から開放したのである。」
今回の課題は比較的易しかった。易しかったというのは文法的事項についてもそうなのだけれど、じつはそれよりなにより、わたしがプロメテウスのお話を知っていたということによる。これはとても大事なところで、つまり何が書かれているのかを事前に知っていれば、文法的にあやふやな部分でも想像力で理解できてしまうということなのだ。だから自分の熟知している分野について書かれた外国語ならば、まったく未知の領域よりはいかほどか読みやすいということになる。むかし学校に通っていた頃、効果的な外国語学習の方法として自分に興味のあることが書かれた文章を読むことを勧めた先生がいらっしゃったが、要すれば興味があるのなら聖書でも経済学でも、あるいはジョイスでもポルノでもよいから読んでみることだというのだ。当時わたしはなるほどそれはよいかもしれない、と納得したものだが、実際に外国語をじっくりと勉強してみると、ことはそれほど単純でないことが判ってきた。この伝にしたがって自分の好きな話題、それは例えばドイツ近代史だったとしようか。これをドイツ語で読んだとしておそらくフランス革命を論じた本よりは速く読めるかも知れない。しかしいくら速く読めたとしてはたしてどのくらい厳密に文章を読み込んでいるのかはかなり怪しくなってくる。というのも上にも書いているように「文法的にあやふやな部分でも想像力で理解できてしまう」というとんでもない陥穽があるからだ。わたしなどネイティブ・ランゲージである日本語で記述されている本だって実のところかなりいい加減に読んで判った気になっているのが再三なのであって、ときどき恥をかいている。
要すればたしかに自分の知っている分野に係る文章が理解し安いのは判るのだけれども、それだけに思い込みで読んでしまう危険も多く孕んでいるということ。だからわたしは今では件の先生のアドバイスは外国語学習にとっては、そして特に初心者にとっては返って有害なのではないかと考えるようになった。つまり意識せずに文章を思い込みで読んでしまい、副詞や形容詞の一つ一つ、動詞の活用が何に当たるのか、ドイツ語でいうなら接続法Ⅰ式なのか単なる過去形なのかを厳密に読み込んでいく必要があるというわけだ。
さて本題に取り掛かる。形容詞については既にみているが、この品詞については性と数による局用のほかに比較級、最上級という形がある。英語でも同じ言い方をしているけれども、例えば原級、比較級、最上級というと"good","better"."best"、"much","more","most"、あるいは"tall","taller","tallest"、それから"useful","more useful","best useful"なんてのもあった。最初の例は不規則変化、二番目は規則変化、そして三番目は二音節以上の形容詞における原級、比較級、最上級の作りかたとなる。
ラテン語の形容詞での比較級、最上級についてまず規則変化をみると、例えば"fortis"(勇敢な)は比較級が"fortior"、最上級が"fortissimus"となるが、最上級の語尾は現代イタリア語の絶対的最上級に"issimo"という形で残っているのでちょっと親近感を覚えるが、当然ながら性、数、格による曲用があるわけで、まず比較級の局用を見てゆく。
単数・男性形、女性形は"fortior","fortio-ris","fortio-ri-","fortio-rem","fortio-ri-"となる。
単数・中性形は"fortius","fortio-ris","fortio-ri-","fortius","fortio-ri-"で主格と対格の形は第一変化形容詞と混同しやすいので注意する必要があるが、"fortis"が第二変化形容詞であることを知っていれば間違えることもない。なお奪格は"fortio-re"ともいう。
複数・男性形、女性形は"fortio-re-s","fortio-rum","fortio-ribus","fortio-e-s","fortioribus"で対格は"fortio-ri-s"ともいう。単数属格との違いは"ris"と"ri-s"つまり短母音と長母音の違いなので文字の上では違いがまったく判らないのでこれも注意しなくてはならない。困ったものだ。
最後に複数・中性形は"fortio-ra","fortio-rum","fortio-ribus","fortio-ra","fortio-ribus"
次に最上級の局用も見ておこうか。こちらは"fortissimus"、"fortissima"、"fortissimum"で要すれば第一変化形容詞の局用をおこなえばよい。
このほかに不規則変化する形容詞もいくつかあるが、今回はこのあたりで止めておこう。不規則変化する形容詞と副詞の比較級、最上級、ならびにこれらの実際的な使い方に関しては次回でみて見たいと思う。
今回の自分への宿題はプリニウスの文章から。
"Bene est mihi, quia tibi bene est. habes uxorem tecum, habes filium. Frueris mari, fontibus , viridibus , agro, villa amoenissima. Neque enim dubito esse amoenissimam, in qua se composuerat homo felicior, antequam felicissimus fieret. Ego in tuscis et venor et studeo, quae interdum alternis, et interdum simul facio: nec tamen adhuc possum pronuntiare, utrum sit difficilius capere aliquid, an scribere. Vale"(注2)
(注1)『新羅甸文法』111頁 田中英央 岩波書店 昭和11年4月5日第4刷
(注2) 同上 129頁