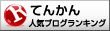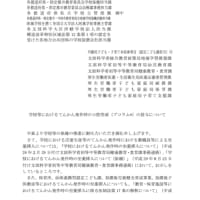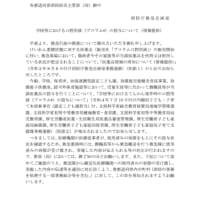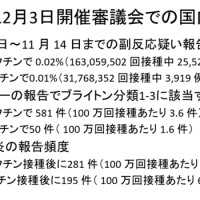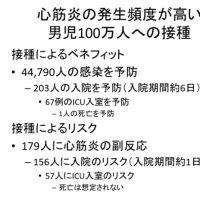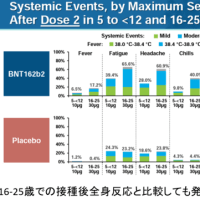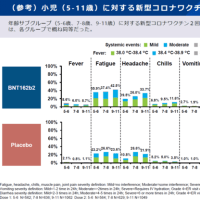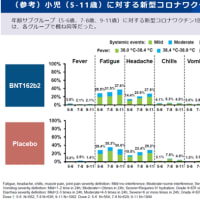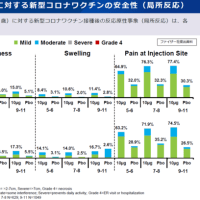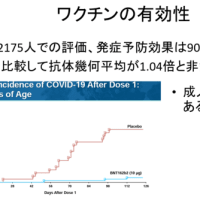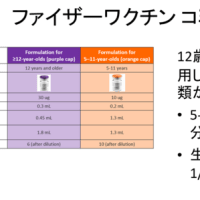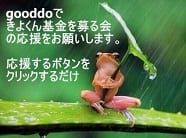脂質からのケトン体(アセト酢酸、βヒドロキシ酪酸、アセトン)生成が増加し、アセト酢酸とβヒドロキシ酪酸が脳のエネルギー源として利用される他、様々な薬理作用を示す。
断食によるてんかん発作改善が食事再開後も持続することを受けて、ケトン血症(ケトーシス)にその効果があると考え、高脂肪、低糖質食のケトン食によっててんかん発作が改善することを1921年にWilderらが報告した。
カルバマゼピンやバルプロ酸による治療が主流となってからは使用されなくなったものの、難治性てんかんである点頭てんかん(West症候群)に有効性の高い副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)療法の代替療法として、約20年前から米国や韓国を中心にケトン食が再評価されている。
わが国でも、ケトン食用の特殊ミルク(ケトンフォーミュラ)の月間出缶数は2005年に300缶であったが、2012年には1200缶と増加している。
古典的ケトン食以外の方法
中鎖脂肪酸(MCT)ケトン食:ケトン体を生成しやすいMCTを多く接種することによりケトン比を3以下に下げても古典的ケトン食と同様のケトーシスを得る方法。下痢を伴いやすい。
アトキンス食:糖質を制限するだけの食事療法でケトーシスを伴う。
低炭水化物インデックス食:血糖上昇の少ない糖質40-60g/日を摂取可能で献立が豊かになるが、血中ケトン体上昇は軽度に留まり、有効性低下の可能性が指摘されている。
- 食事療法は難治性の小児てんかんに対して、効果的、安全、投薬以外の治療であり、38-60%(30-90%)の患児で50%以上のけいれんを減らす。
Epilepsia, 2009
J Child Neurol, 2006
- ほとんどの専門家がケトン食は2剤の抗けいれん薬で症状をコントロールできない患児に対する有効な治療の選択肢であると考えており、ケトン食が有効と考えられる特定の病態では、早期の導入が提案されうる。
ドラベ症候群は難治性のけいれんが特徴であり、特に非特異的欠神発作等のけいれんの頻度を減少させうる。
Epilepsia. 2005;46(9):1539
J Child Neurol. 2007;22(2):185.
Epilepsia. 2011;52(7):e54.
その他の適応疾患
- 乳児けいれん[Infantile spasms](West症候群)
- ミオクローヌス失立発作てんかん(Doose症候群)
- レット症候群
- 結節性硬化症(プリングル病)
- GLUT1欠損症
- ピルビン酸デヒドロゲナーゼ(PDH)欠損症
- 胃瘻からのチューブや人工栄養児
幾分のケトン食の効果が報告されている特殊なてんかん - Landau Kleffner症候群
- レノックス(Lennox Gastaut)症候群
- 小児欠神てんかん
- 亜急性硬化性全脳炎(SSPE)
- ミトコンドリア呼吸鎖複合体欠損症
- 難治性てんかん重積
- 外科的治療適応ががある難治性焦点てんかんの患児ではケトン食よりも外科的治療に良好な反応を示す。
Seizure. 2007;16(7):615.
Pediatrics. 2008;122(2):e330. - ケトン食を開始する前に、ケトン食の禁忌となる病態や治療を困難とする要素についてスクリーニングしておく必要がある。
絶対禁忌事項 (Epilepsia. 2009;50(2):304.)
- 原発性カルニチン欠損症
- カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼI or II 欠損症
- カルニチントランスロカーゼ 欠損症
- ポルフィリン症
- 脂肪酸酸化異常症
- ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症
- 外科的治療適応者
- 経口摂取困難等で十分な栄養を確保できない場合、成長障害
- 完全菜食主義等の特別な食事制限や嗜好
- 親または介護者のノンコンプライアンス
- 食事によって悪化することが予想される病態(腎結石、脂質異常症、肝疾患、逆流性食道炎、便秘、慢性代謝性アシドーシス等)
- 特定の抗てんかん薬レジメン(フェノバルビタールを服用しているものではケトン食の効果が低下するとの報告あり[Epilepsia. 2009;50(8):1999.])
- ケトン食は、てんかんセンターで訓練を受けた栄養士が管理する必要がある
-
一般的にはケトン食は入院して、24-48時間絶食して開始する(場合によっては、入院や絶食は必ずしも必要とされない)
-
古典的にはケトン比4を目安に総カロリーや水分摂取量を調整し、尿中ケトン訂正2+以上、血中ケトン体のβヒドロキシ酪酸4000μmol/L以上を目標とする。
-
ケトンフォーミュラはケトン比3に調整されており、ミルクとして飲む以外にも各種料理に利用可能で、患者は病院を通じて無償で入手できる。
-
患児は、臨床検査、身長、体重、およびけいれん発作頻度の頻繁なモニタリングを行いながらと注意深く経過観察される。
-
開始後2週間は低血糖やアシドーシスへの配慮が特に必要であり、嘔吐を繰り返したりぐったりする場合には一時的に糖分の投与や点滴が必要となることがある。
-
長期的には、便秘や下痢、発育不良、骨粗鬆症、尿路結石、セレン等の微量元素欠乏、カルニチン欠乏の可能性がある。
-
セレンや亜鉛などのミネラルを含むマルチビタミン、カルシウム、ビタミンDのサプリメントが全ての患児の食事に加えられる。一部のには更なるサプリメントを必要とする患児もいる。
-
ケトン食の効果はたいてい開始から1-3カ月で現れる。もしけいれん発作がコントロールされれば、抗けいれん薬は緩徐に減量できるかもしれない。
-
代替食には、ケトン食と同等の効果が示されている中鎖脂肪酸食が含まれる。修正アトキンスダイエットと低グリセミック指数ダイエット(低血糖食)にも効果的であることが示されており、患児や成人にも有用かもしれない。
修正アトキンスダイエットとケトン食の比較において、介入開始3ヶ月時点ではケトン食のほうが効果が有意さをもって高い(50%以上のけいれん減少が65% vs 20%)が6か月時点では有意差なし(41% vs 20%)
Seizure. 2009;18(5):359. -
副作用は通常、軽度で、予測と予防可能であり、ほとんどケトン食の中止にはつながらない。重要副作用は便秘、アシドーシス、成長の遅延、脂質異常症、腎臓結石、および骨折などがある。ゾニサミド、トピラマート、アセタゾラミドの服用時尿路結石が生じやすい。
-
ケトン食開始とともにフェノバルビタール、フェニトイン、バルプロ酸等の抗てんかん薬の血中濃度低下に伴う発作増悪もみられることがあり、必要に応じて用量調整を行う。
-
ケトン食の有効例の90%は開始1か月以内に何らかの効果を認める。それ以降に効果の現れる場合もあるため、副作用が許容できれば最短で3カ月間、最長2年間実施することが推奨される。しかしながら、さらに長期間、効果的に実施できたとする報告もある。重篤な有害事象がない場合には、徐々に通常食に戻すことが勧められる。
-
6か月以上発作消失例のケトン食中止後の発作再発率は20%との報告があり、抗てんかん薬中止後の再発率とほぼ同等である。
-
てんかん以外のの適応症(例えば、自閉症、脳腫瘍、およびアルツハイマー病)のためのケトン食の実施の効果は、まだ報告が少ないため、推奨するには、さらなる研究が必要である。
引用資料
てんかんの食事療法 日本臨牀72巻5号2014年 p875-880
The ketogenic diet, UpToDate
参考資料
てんかんのケトン食療法について(日本小児神経学会)
低グリセミック指数食の一覧(暮らしドットコム)