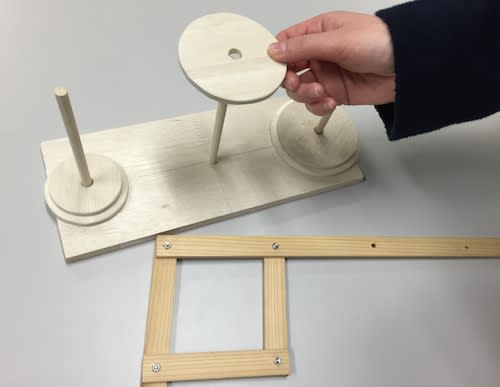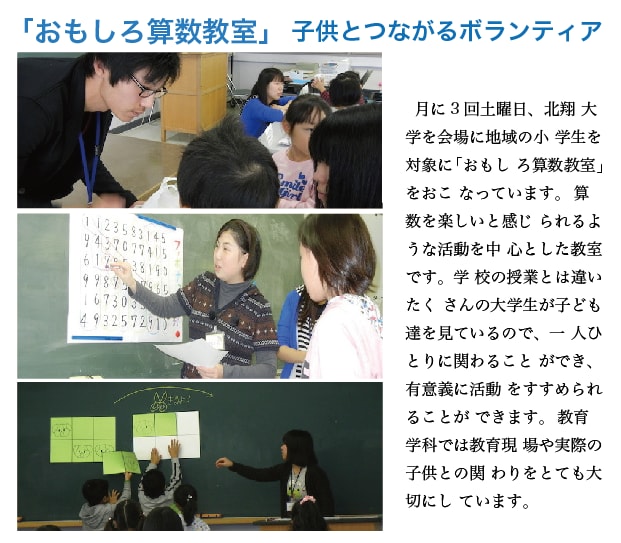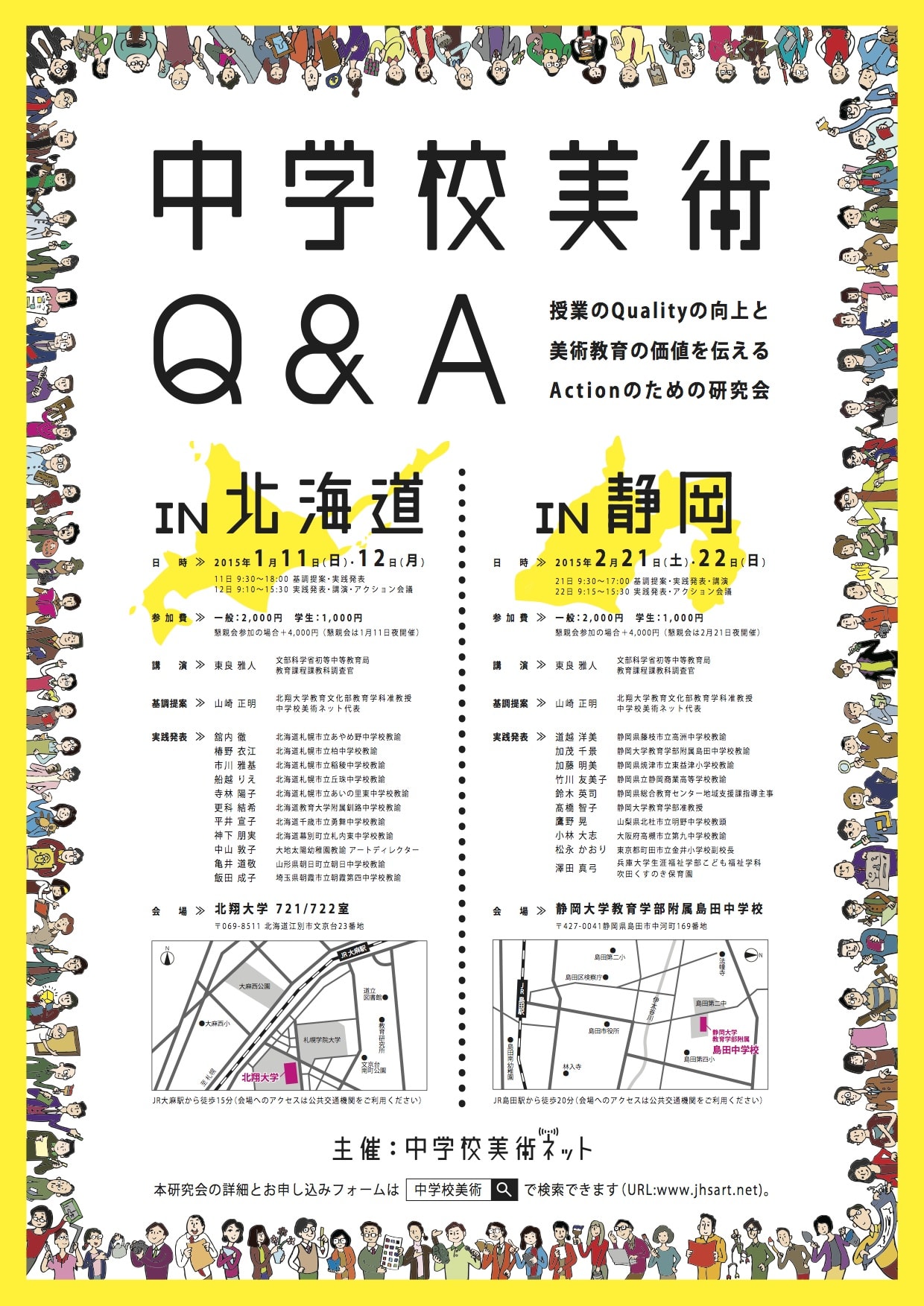教育学科の掲示板は、各講義などの作品などを掲示している。この掲示板を見ながら、互いに学び合う。

小学校の書写の時間をどうつくっていくか、そのためにも、学生自らが体験を通して子供の視点で学ぶことが大切だ。
この掲示板を見ると、この時間を通して、楽しく学ぶことを大切にしていることが伝わってくるとともに、その人らしさが出てくるような授業のつくる方をしていることがわかる。
書写といえば雲花紙に掲示することも多いが、こうした色模造紙に貼るとまた印象が違う。「あっぱれ」という言葉とイラストが親しみを持たせる刑事にしている。朱色のアクセントもすてきだ。

上の写真の右は「図画工作指導法1」を通して、図工の時間のあり方について自分の考え方を書いたものである。このようなものを掲示し、他者の考えを知り、自分の考えを広げ、深めていく。講義の中だけで学びはとどまらない。やがてはそれが教師になったとき、生きてはたらいていくことになる。掲示板は学び合う場でもある。そういう意識でこれを見ると実におもしろい。


(山崎正明)





















 こんにちは、そして初めまして!教育学科1年生・音楽コースの藤江です。
こんにちは、そして初めまして!教育学科1年生・音楽コースの藤江です。