平成27年度多文化理解体験研修(フィリピン・カオハガン島)の報告会を
以下とおり開催いたします。


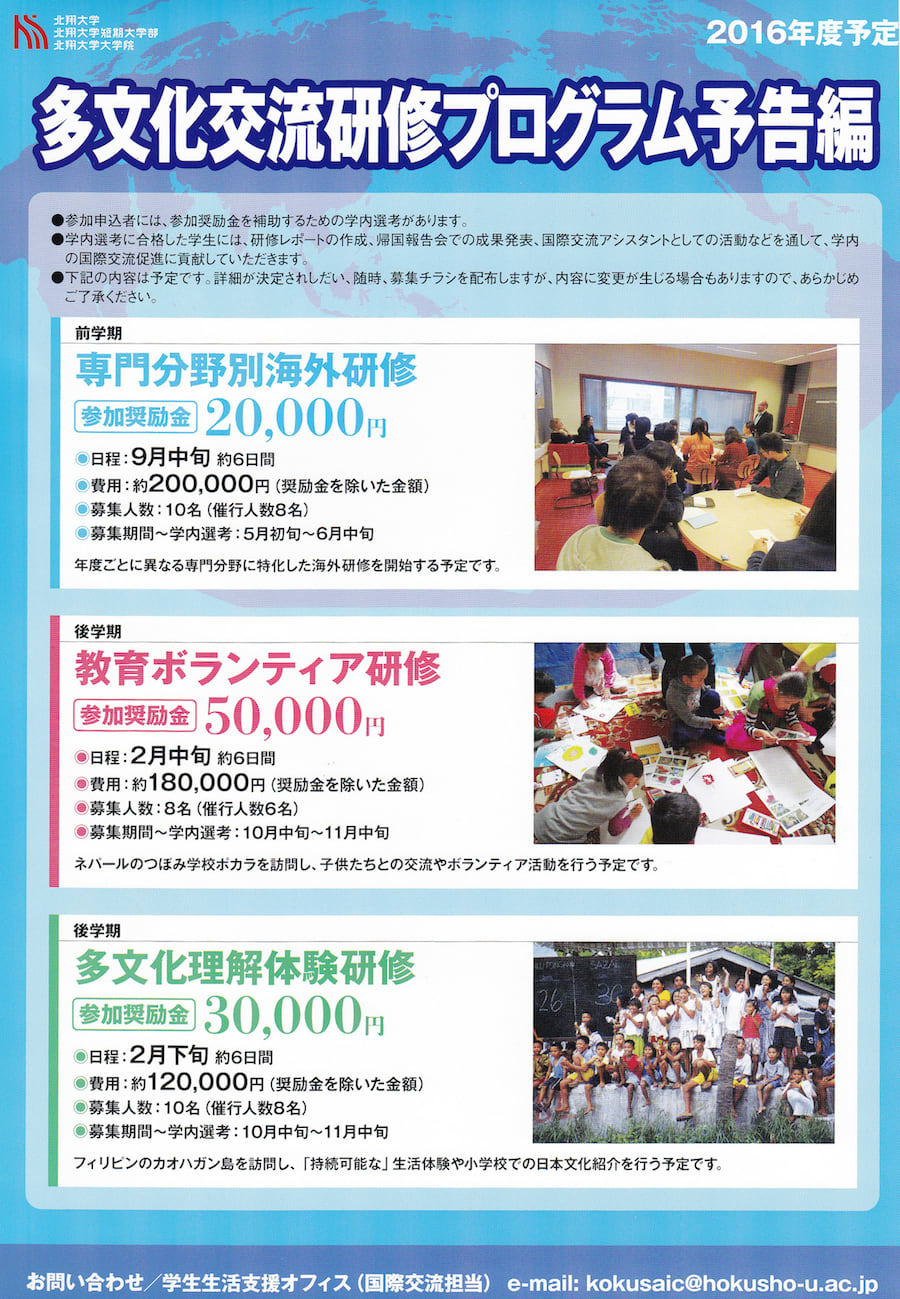




















2015年12月、中国の高校生4名が研究室を訪ねてくれ、佐々木邦子ゼミ生や2年生、他ゼミの3年生と交流をした。4人とも自分の夢に向かう姿勢が、素晴らしい高校1年生と2年生である。
会話は主に英語であったが、外国生活の経験がある学生の流暢な通訳でスムーズに進んだ。他の学生も、笑顔を交えた英語で語り、コミュニケーションは十分である。
中国の地図を一緒に見て住んでいる都市の確認をしたり、“黒ひげ危機一髪”で遊んだりと、和気あいあいとした楽しい時間を過ごした。
(佐々木邦子)
北翔大学の2年生が、小学校に授業に行きました。彼女がカンボジアで体験してきたこと(子供達と関わってきたこと)を、小学生に話して欲しいというリクエストがあって実現したものです。
観光ではなく自分で計画をたたて自分の力で行ってきただけに、深い学びがあったのでしょう、彼女が撮った写真はカンボジアの子供と積極的な関わりがあったからこその、素晴らしいものでした。
こうしたて彼女が日本の小学生とカンボジアの子供をつなぐ役割をしてくれました。

(山崎正明)







 ↑玄関です。コート掛け。
↑玄関です。コート掛け。 ↑小学校2年生の教室。
↑小学校2年生の教室。
 ↑小学校の給食です。
↑小学校の給食です。
6月4日(水)16:30より北翔大学エクステンションセンター主催の平成26年度国際交流講演会
『フィンランド伝統文化に魅せられて』が開催されました。定員をはるか
に上回る来場者が訪れて大盛況の会となりました。

講師は札幌カンテレクラブ会員の河野千恵さん。フィンランドの紹介から始まり、
日本人にはあまり馴染みのない楽器カンテレの歴史やカンテレ製作のワークショップ
体験について画像とともにお話ししてくださいました。
そしてお待ちかねのカンテレの生演奏。同じくカンテレクラブに所属されているお二人とともに奏でられたカンテレの美しく繊細な音色に、聴衆の皆さんは一様に聞き惚れていました。

最後に、簡単なフィンランド語の歌を練習してから、河野さんたちが持参してくだ
さった数台の小型カンテレを使って、来場者の皆さんがお一人ずつカンテレ演奏を体
験しました。心を癒されるカンテレの音色と多彩な内容で、あっという間に楽しく充
実した時間が終了しました。
小グループになってのカンテレ体験では、繊細な音色をそれぞれの参加者が楽しんで
いました。