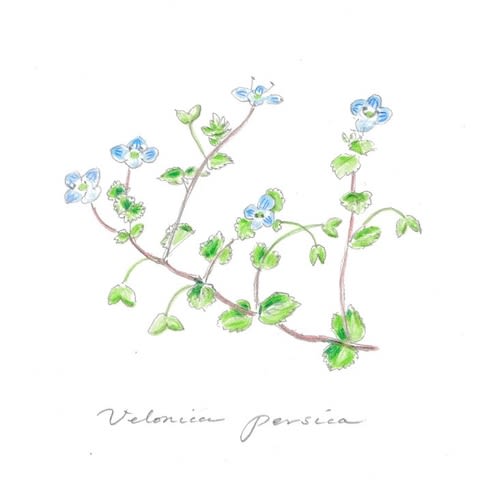クサボケ
ウメの花などに通じる5弁の花を咲かせ、早春の明るい草原のようなところを彩る。その朱色は素朴な印象があり、同じ頃に咲くチゴユリやヒメウズなどの洗礼された美しさとは対照的な気がする。背が低いし、名前に「クサ」がつくから草本のようだが、ガッチリした幹を持つ木本で、枝がトゲのようになる。これはズミなどほかのバラ科の木本で見られることだ。クサボケは思いがけないほど大きな果実をつけるが、これは近縁なカリンも同様である。


 果実 7月
果実 7月
 果実 11月
果実 11月
 果実 5月末
果実 5月末
田舎の福島県白河村の近くではシドミと呼んでいました。おもしろ半分にかじりましたが、まずかったです。また、「火事花」と言って、家には持ち帰らないように言われたことを思い出しました。
加藤嘉六
まだ冬枯れた草の間に朱色の花を咲かせているのが印象的です。秋には「地梨」と呼ばれる黄色の果実がなり、砂糖漬けにするとおいしいということなので食べてみたくなります。枝が横に広がる姿が気に入ってミニ盆栽を始めました。
佐久間

クサボケ
ウメの花などに通じる5弁の花を咲かせ、早春の明るい草原のようなところを彩る。その朱色は素朴な印象があり、同じ頃に咲くチゴユリやヒメウズなどの洗礼された美しさとは対照的な気がする。背が低いし、名前に「クサ」がつくから草本のようだが、ガッチリした幹を持つ木本で、枝がトゲのようになる。これはズミなどほかのバラ科の木本で見られることだ。クサボケは思いがけないほど大きな果実をつけるが、これは近縁なカリンも同様である。


 果実 7月
果実 7月 果実 11月
果実 11月 果実 5月末
果実 5月末田舎の福島県白河村の近くではシドミと呼んでいました。おもしろ半分にかじりましたが、まずかったです。また、「火事花」と言って、家には持ち帰らないように言われたことを思い出しました。
加藤嘉六
まだ冬枯れた草の間に朱色の花を咲かせているのが印象的です。秋には「地梨」と呼ばれる黄色の果実がなり、砂糖漬けにするとおいしいということなので食べてみたくなります。枝が横に広がる姿が気に入ってミニ盆栽を始めました。
佐久間

クサボケ














 果実
果実 果実
果実


 果実
果実 果実
果実