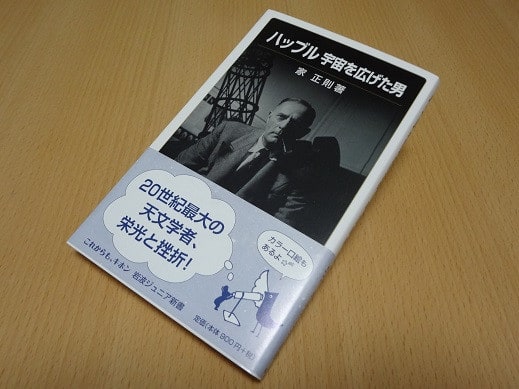
☆『ハッブル 宇宙を広げた男』(家正則・著、岩波ジュニア新書)☆
天文学に興味を持ちはじめた小中学生の頃、世界最大の望遠鏡といえばパロマー山天文台(アメリカのカリフォルニア州)にある口径5メートルのヘール望遠鏡だった。日本では岡山県にある岡山天体物理観測所(当時は東大附属東京天文台、現在は国立天文台に所属)の口径188センチの反射望遠鏡だった。大きな望遠鏡に夢や憧れを抱いていたが、まさか大きな望遠鏡が大気圏外に設置される(地球周回軌道に載る)ことになるとは思ってもみなかった。1990年スペースシャトル「ディスカバリー号」によって打ち上げられ、当初のトラブルに打ち勝って、いまや数々の成果を挙げているハッブル宇宙望遠鏡である。
宇宙望遠鏡にその名が冠せられたのは、エドウィン・ハッブル(1889~1953)の偉大な業績によるものだ。セファイド型変光星(☆)を用いてアンドロメダ大星雲(銀河系外銀河の1つ、M31)までの距離を測り、地球を含むわれわれの銀河系が宇宙に存在する無数の銀河の1つにすぎないことを示し、銀河の分類や分布についても大きな足跡を残した。現代につながる銀河研究の草分け的な存在である。しかし、最も偉大な業績は宇宙の膨張を証拠づけた「ハッブルの法則」の発見だろう。とくに天文学にくわしくない人であっても、「宇宙は膨張している」という話をどこかで耳にした人は少なくないだろう。ハッブルの挙げた成果は、自らの著書『銀河の世界』(原著1936年、邦訳1999年)でも紹介されている。この本は観測家の視点から書かれていて、ハッブルが観測に命をかけた観測天文学者だったことを如実に示している。

ハッブルはこれほどまでの業績を挙げた一方で、性格的には偏りがあったというべきだろうか、周囲に対して奔放に振る舞うことも少なくなかった。シャプレーとカーチスによる渦巻星雲に関する論争は、天文学上でも「大論争」と呼ばれ有名であるが、この論争の決着に大きな役割を果たしたのもハッブルであった。その過程でシャプレーの同僚であったファン・マーネンとハッブルとは大きな確執を抱えることになった。いまハッブルが生きていれば、あまり友人にはなりたくない人物かもしれない。家庭においては、妻のグレースと終生仲睦まじく過ごしたようで、ホッとさせられる一面もある。グレースは一度妊娠したが流産してしまい、ハッブル夫妻に子どもはいなかったようである。本書では天文学的な業績を紹介し評価するばかりでなく、私生活や人柄についてもかなり触れられていて、ハッブルの伝記としては過不足のないおもしろさである。最初に登場人物の紹介(多くは顔写真付きで)があり、読者にとっては嬉しい配慮である。ハッブルの伝記は、調べた限りでは、いままで日本で書かれたり邦訳されたものはないようである。その意味でも本書の価値は大きい。さらにハッブル以後の観測的宇宙論の進展についても一章が割かれていて、今後の研究への期待が語られている。著者の家正則さんがハッブル同様、観測天文学者だからか、たんなる付けたしで終わっていないのもすばらしい。
宇宙望遠鏡の名前がハッブルに由来するほどの業績を挙げたにもかかわらず、ハッブルはノーベル賞を受賞していない。ノーベル賞に「天文学賞」がないからと言ってしまえばそれまでだが、例えば日本人ではニュートリノ天文学の分野で小柴昌俊さんと梶田隆章さんが「物理学賞」を受賞している。ハッブルは生前「物理学賞」に天文学も入れるべきだと訴えたのだが、その要求は通らなかった。ところが、1960年代末になってノーベル賞選考委員会は方針を転換し、天文学の業績も物理学と同等の権利があるとした。ハッブルが亡くなってから十数年後のことである。著者の家さんは、もしハッブルが長生きしていれば、「セファイド型変光星による銀河の距離決定」と「宇宙膨張の発見」で二度受賞した可能性もあるという。ハッブルは残念ながらノーベル賞を受賞できなかったが、その偉大な業績は揺らぐものではなく、また一癖ある人物であったとしても、20世紀最大の天文学者であったことはたしかである。
(☆)セファイド型変光星の「周期光度関係」から、例えば銀河までの距離を測ることができるので「宇宙の物差し」ともいわれている。そのきっかけを作ったのが女性天文学者のリービットである。

天文学に興味を持ちはじめた小中学生の頃、世界最大の望遠鏡といえばパロマー山天文台(アメリカのカリフォルニア州)にある口径5メートルのヘール望遠鏡だった。日本では岡山県にある岡山天体物理観測所(当時は東大附属東京天文台、現在は国立天文台に所属)の口径188センチの反射望遠鏡だった。大きな望遠鏡に夢や憧れを抱いていたが、まさか大きな望遠鏡が大気圏外に設置される(地球周回軌道に載る)ことになるとは思ってもみなかった。1990年スペースシャトル「ディスカバリー号」によって打ち上げられ、当初のトラブルに打ち勝って、いまや数々の成果を挙げているハッブル宇宙望遠鏡である。
宇宙望遠鏡にその名が冠せられたのは、エドウィン・ハッブル(1889~1953)の偉大な業績によるものだ。セファイド型変光星(☆)を用いてアンドロメダ大星雲(銀河系外銀河の1つ、M31)までの距離を測り、地球を含むわれわれの銀河系が宇宙に存在する無数の銀河の1つにすぎないことを示し、銀河の分類や分布についても大きな足跡を残した。現代につながる銀河研究の草分け的な存在である。しかし、最も偉大な業績は宇宙の膨張を証拠づけた「ハッブルの法則」の発見だろう。とくに天文学にくわしくない人であっても、「宇宙は膨張している」という話をどこかで耳にした人は少なくないだろう。ハッブルの挙げた成果は、自らの著書『銀河の世界』(原著1936年、邦訳1999年)でも紹介されている。この本は観測家の視点から書かれていて、ハッブルが観測に命をかけた観測天文学者だったことを如実に示している。

ハッブルはこれほどまでの業績を挙げた一方で、性格的には偏りがあったというべきだろうか、周囲に対して奔放に振る舞うことも少なくなかった。シャプレーとカーチスによる渦巻星雲に関する論争は、天文学上でも「大論争」と呼ばれ有名であるが、この論争の決着に大きな役割を果たしたのもハッブルであった。その過程でシャプレーの同僚であったファン・マーネンとハッブルとは大きな確執を抱えることになった。いまハッブルが生きていれば、あまり友人にはなりたくない人物かもしれない。家庭においては、妻のグレースと終生仲睦まじく過ごしたようで、ホッとさせられる一面もある。グレースは一度妊娠したが流産してしまい、ハッブル夫妻に子どもはいなかったようである。本書では天文学的な業績を紹介し評価するばかりでなく、私生活や人柄についてもかなり触れられていて、ハッブルの伝記としては過不足のないおもしろさである。最初に登場人物の紹介(多くは顔写真付きで)があり、読者にとっては嬉しい配慮である。ハッブルの伝記は、調べた限りでは、いままで日本で書かれたり邦訳されたものはないようである。その意味でも本書の価値は大きい。さらにハッブル以後の観測的宇宙論の進展についても一章が割かれていて、今後の研究への期待が語られている。著者の家正則さんがハッブル同様、観測天文学者だからか、たんなる付けたしで終わっていないのもすばらしい。
宇宙望遠鏡の名前がハッブルに由来するほどの業績を挙げたにもかかわらず、ハッブルはノーベル賞を受賞していない。ノーベル賞に「天文学賞」がないからと言ってしまえばそれまでだが、例えば日本人ではニュートリノ天文学の分野で小柴昌俊さんと梶田隆章さんが「物理学賞」を受賞している。ハッブルは生前「物理学賞」に天文学も入れるべきだと訴えたのだが、その要求は通らなかった。ところが、1960年代末になってノーベル賞選考委員会は方針を転換し、天文学の業績も物理学と同等の権利があるとした。ハッブルが亡くなってから十数年後のことである。著者の家さんは、もしハッブルが長生きしていれば、「セファイド型変光星による銀河の距離決定」と「宇宙膨張の発見」で二度受賞した可能性もあるという。ハッブルは残念ながらノーベル賞を受賞できなかったが、その偉大な業績は揺らぐものではなく、また一癖ある人物であったとしても、20世紀最大の天文学者であったことはたしかである。
(☆)セファイド型変光星の「周期光度関係」から、例えば銀河までの距離を測ることができるので「宇宙の物差し」ともいわれている。そのきっかけを作ったのが女性天文学者のリービットである。

























