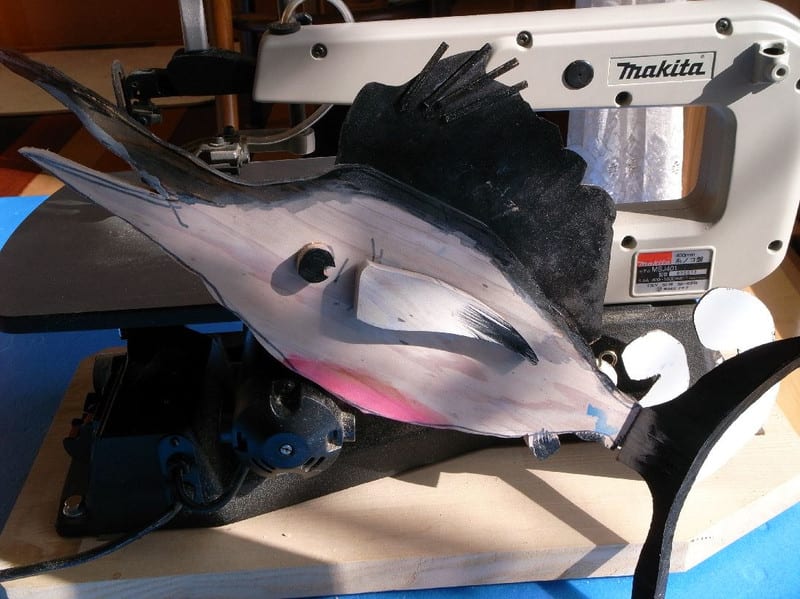入会時にスケッチブックを渡し、毎回一枚の絵(なんでもOK)を描いてくるように伝えています。学校や習い事が忙しい中でも「教室に来るクルマの中で描きました」と正直に、ブレブレの絵を持ってくる子。絵具でしっかりと描いてくる子。さまざまな情景とともに、その時々の想いがリアルに伝わってくるのが私の励みにもなり、その子の意欲に十分に応えたいとのおもいから、個別のアドバイスを挿絵とコメントに交えて返答している。
入会時にスケッチブックを渡し、毎回一枚の絵(なんでもOK)を描いてくるように伝えています。学校や習い事が忙しい中でも「教室に来るクルマの中で描きました」と正直に、ブレブレの絵を持ってくる子。絵具でしっかりと描いてくる子。さまざまな情景とともに、その時々の想いがリアルに伝わってくるのが私の励みにもなり、その子の意欲に十分に応えたいとのおもいから、個別のアドバイスを挿絵とコメントに交えて返答している。多くの中から二人を紹介します。Mちゃんはスポーツも大好きで、私からの難しい課題にも果敢に挑んでくる子です。壁を前にしてもMちゃんならできるよ!と挑発にも素直に乗ってきます。でも、ちょっと気をゆるめるとすぐに「できな~い。先生やって~。」と甘えてきます。もちろん突き放します。そんな挑発に対抗してか、私へ逆に課題を出してきます。「先生の考えた○○を描いてみましょう」「先生の好きな○○はどんなものでしょうか」おそるべしMちゃん先生です。
私も安易な受け答えはできません。先生だって、まだまだMちゃんの自由で豊かな発想に負けるわけには。ある時は先生らしく、またある時はマイッタと言わせるように、真剣勝負が続くことを、また、もう教えることがなくなって、終わりの時が早く来ることを願って。
Sちゃんは短歌が好きな少しシャイな落ち着いた子です。大きな賞の経験もあります。感受性が豊かで、自分なりの表現方法を模索努力しています。描画も頑張っていますが、やさしさがじゃまをしているのでしょうか、思い切った展開が出し切れていないようです。そこで、スケッチブックの自分の絵に短歌を添えるように伝えました。私も短歌を知らないながらも「短いおもい」だとおもって返答します。そこで気付かされたことがあります。アドバイスは的を貫く矢のようにスパッと伝えるほうが良い。弓道では矢を射る際、呼吸を止めるそうですが、そんなイメージでアドバスが出来たらと感じています。
子に伝えたい想いや実技指導は必要なことを、削いで削ぎ落として真意を伝え、あとは子にゆだねる。長々とアドバイスすることが本当に良いとは思わない。無責任な指導に聞こえますが間違いないことだと思います。
この春、第一期生の六年生が多く卒業していきました。新しい仲間も入りました。新しいスケッチブックを開いて、一人ひとりにいろいろな想いがあるでしょう。新しい芽(眼)が開かれることを願っています。














 尻尾をつかもうとしても、すでに走り去り、追いつくことはできない。
尻尾をつかもうとしても、すでに走り去り、追いつくことはできない。