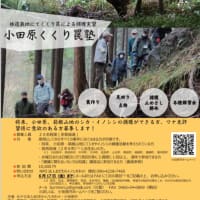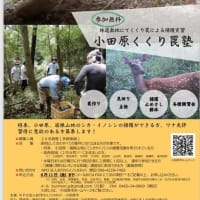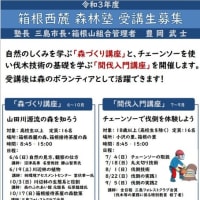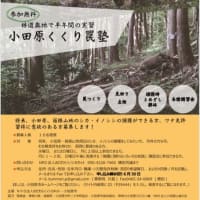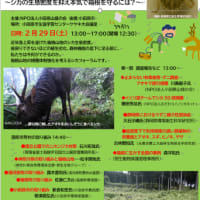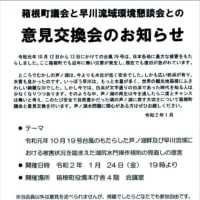2016年2月13日(土)に県地球博で行われた公開シンポジウム「箱根、丹沢、富士山、伊豆半島におけるニホンジカ対策の現状」発表について、参加者による一部傍聴記録を掲載させていただきます。
小田原山盛の会では27年度箱根山系のシカ調査を実施しております。箱根でもシカ害により明神ヶ岳、明星ヶ岳等外輪山一体で下層植生の劣化が始まり、早急な対策が望まれます。
静岡県の対策に関わっておられる大橋さんの発表には、箱根で行われるべきいろいろな課題を感じる事ができました。
箱根では環境省主催で国立公園を対象としたシカ対策委員会が始まっておりますが、外輪山周辺の対策はまだこれからの状態です。
是非参考にしていただき周辺市町村のシカ対策を加速していただけたらと思います。
公開シンポジウム「箱根、丹沢、富士山、伊豆半島におけるニホンジカ対策の現状」より抜粋
「富士山南麓と伊豆半島地域のシカの現状と対策」
大橋正孝 (静岡県農林技術研究所 森林・林業研究センター )
傍聴記録;柏木聰(仙石原野生鳥獣クリニック)
山入りの注意。シカの尻は白い。山に入る時に白い帽子は誤射の危険大。
なかなか減らせないニホンジカ。
伊豆におけるH18年の推定生息数2万頭をH26年には一万頭に減らす計画を立てて捕獲開始したが。H14年1,669頭、H21年4,999頭、H26年8,324頭(H14年の5倍)頑張って捕獲したが、頭数は減らせず2万頭強のまま。この間、県のシカ対策を強化して来た。H15年有害捕獲を強化、県事業による捕獲を開始。H16年メス狩猟獣化、特定計画策定。H20年メスの無制限化、第2期特定計画策定。H22年狩猟期間延長。
ニホンジカ低密度化のための管理技術の開発。
一人体制で進めていたのを4人体制に増強し、静岡県プロジェクト研究(2010-2012年度)として低密度化のための管理技術の開発に取り組んだ。問題点の洗い出しを行なった結果。管理のための生態基礎情報が不足。捕獲効率が低い。メスが獲れていない。⇒達成目標を立てた。
A. 管理のための生態基礎情報の収集
B. 効率的なメス捕獲技術の開発。
A.管理のための生態基礎情報の収集。
GPS(伊豆17頭、富士11頭、南アルプス9頭)をシカの首に装着して行動分析による地域個体群の評価を行った。その結果、伊豆地域では、行動圏平均54haと狭く季節移動は殆どしない。⇒伊豆ではシカが多い場所を把握して繰り返し捕獲する事が有効。季節変化は考慮不用。富士地域では、一晩に5㎞移動したり行動圏は複雑で149haと伊豆の3倍。夏季には高標高で冬季には低標高の西南麓へと集中して来る。季節移動をする。⇒富士ではシカが集まる季節・場所で集中的に効率よく捕獲する。季節変化の考慮必要。
森林被害から見た適正な生息密度。
嗜好性から見た密度指標種として、①嗜好性種:アオキ・イヌツゲ②中・低嗜好性種:ヒサカキ・クロモジ③不嗜好性種:アセビ・シロヨメナ・マツカゼソウ。シカ密度の上昇により植物の種類・量が減少する。
アオキは、1頭/㎢未満でも消失する。イヌツゲは高耐性で消失しない。0頭/㎢を目標にした管理が必要な場所もある。
DNA分析による地域個体群の評価。
静岡・神奈川で捕獲された1081頭の結果。「南アルプス・富士・丹沢」と「伊豆」の大グループ⇒県を跨いだ広域管理が必要。遺伝的多様性は伊豆も同程度。「伊豆」は比較的最近、高い捕獲圧によると考えられる個体群の著しい縮小(ボトルネック)を経験している。この結果、定期的なDNA分析による評価をしながら、今以上の捕獲圧をかけても大丈夫と評価。
今後必要なシカの管理。
行動追跡結果から2頭/㎢でも、利用集中エリアでは6頭/㎢に相当する食圧が掛かる。生息密度と食圧の関係は、1頭/㎢未満が必要な場合もある。
DNA分析で、ボトルネックがあっても遺伝子の多様性は大丈夫と評価した。以上のことから次の二通りの管理が必要。①個体数を大幅に削減(捕獲)する管理。伊豆地域個体群・富士地域個体群(県・広域)。②守りたいエリアから加害個体・群れを除去する管理(防鹿柵も含む)(個人・市町・県・環境省・国有林) 。
広域的な観点からの地域個体群管理が必要。
富士山ニホンジカ行動調査情報交換会(2012.7.3)によるシカ21頭の行動調査結果を共有し、全体で何頭居て、毎年何頭増えるから何頭以上捕獲する必要がある。と認識を共有する必要がある。
2012年に初めて国有林での県管理計画を立てることができた。
B.効率的なメス捕獲技術の開発。
富士国有林での誘引捕獲の実績は、射手2人×43日間で680頭15.8頭/日従来捕獲法牧狩りの32~48倍の成績。誘引法の方法は、給餌により日中にシカを誘引し、専門的・職能的捕獲技術者が車上から狙撃する。
捕獲する季節・場所・方法が重要。
富士山のシカは、3パターンがある。①定住個体②半定住個体(冬季低標高に垂直移動する)。③季節移動個体(冬季山梨県側から静岡側に移動する)。 冬季は西・南麓に集中し、捕獲しやすく、夏期は広く分散して捕獲しづらい。⇒南麓の越冬地(11月中旬~3月上旬)で効率的に捕獲することが重要⇒誘引捕獲の導入。
捕獲の実行における連携。
冬季誘引により捕獲しようとするシカは、他の時期・場所で、あるいは隣接地でスレさせない。(警戒心を高めない)配慮が望ましい。
逃げ込める場所をつくらない。
国有林は、国民共有の財産である野生動物の管理に取り組む根拠法令がない。鳥獣保護法には、管理の実行者についての記載がない。また、国有林野法には、部分林の保護(防除)義務のみの記載。県は、広大な国有地のシカは管理できないとして特定計画を策定していなかった。
誘引捕獲成功の秘訣:チーム連携
①森林管理者(森林管理署)の役割:警察署ほか対外調整、安全管理・森林整備事業ほか他事業との調整・給餌によるシカの誘引・捕獲個体処分地確保・除雪ほか基盤整備。
②研究者(静岡県農林技術研究所)の役割:値域のシカの情報を提供・最新、最適な情報を提案・調査、立案、分析、評価。
③富士宮市協議会(構成員、市・猟友会・県・JA・開拓農協・森林組合)の役割:事前協議、安全管理で参加、協力・猟友会は別のエリアでの捕獲を分担。
④捕獲技術者(NPO法人若葉)の役割 :最高の捕獲技術を提供。四者が情報を共有し合意形成をしていく。平成26年(2014)から公共事業化スタート:実行委員会としてほぼ同様の体制で実施し、科学性・持続性を保持。
平成24年(2012)から、
ゾーン分け・作業分担・共働で捕獲強化。
2012年度の国有林内の捕獲頭数は708頭(2010年度の2.5倍、推定生息数の31%)・猟友会選抜者によるわな(班体制、賃金)による捕獲始まる。2012年6月から県事業による管理捕獲(くくりわな・班体制) 始まる。2013年7月から特措法による緊急捕獲始まる。2013年度、市・県・国捕獲(狩猟以外)計1483頭(2010年度の4.5倍)、この捕獲手法の内訳は、くくりわな68%、狙撃法23%、巻狩り9%。2014年度からは、公共事業化により地域の狩猟者による捕獲がストップ。
「富士宮市鳥獣被害対策実施隊」に発展活躍。
2014年4月1日から始動。選抜者10名で構成。隊員の資格は、非常勤公務員特別職(活動中の事故は公務災害)、報酬は、13,000円/頭(7,000円:国交付金+5,000円:市)、活動日については、+1,000円/日、わなを貸与・捕獲個体の処分地も市が準備。富士宮市鳥獣被害対策実施隊設置要綱第3条(隊員) :「富士宮猟友会員又は西富士山麓猟友会員で、狩猟隗災害共済及び狩猟者保険に加入しているもののうちから所属する猟友会会長が推薦するもの」。猟友会会長の推薦者の条件:次のいずれも満たす者①わな・銃猟免許両方を所持する者②平日も活動可能なもの③地域分担可能な者。
この実施隊の捕獲実績は、(4月~10月)で561頭(1,640人日)。この実績は、富士宮市における狩猟以外の捕獲等数1,640頭(内NPO法人若葉159頭)の38%
であった。富士宮市鳥獣被害対策実施隊の実績から⇒少人数でも大きな成果が挙げられることが実証された。
地域で連携、協働による担い手の育成。
ホールアース自然学校で狩猟者を育成。「地域ぐるみの捕獲推進モデル事業」(環境省→静岡県)、事業主体:富士宮市(H24~26)。これまでに150名受講し、45名が狩猟免許を取得し、25名が捕獲に従事している。
地域連携によりシカ捕獲未参加者(自衛隊演習場)への理解促進と捕獲への協力を呼びかける。
市・県・国有林が連携し、演習場へ働きかけることで、罠による捕獲が試行的に認められた。誤って罠にかかった場合のはずし方パネルを罠を掛けた木に掲示している。
今後の課題。
各役割を担う人材をバランスよく育成。高い専門性を要求されるシカ管理事業をPDCAサイクルで実行する行政担当者(監督者)の育成。シカ管理事業を公共事業として実行する資質を備えた事業者(現場代理人・監督技術者)の育成。実働従事者(調査・設計・分析・捕獲技術者)の育成。①野生動物調査・設計・分析技術者。②専門的捕獲技術者。高度な技術を求められる環境では、「捕獲のプロ」による捕獲が必要。③地域の基幹となる地域に根ざした捕獲技術者。これまでの捕獲を支えてきた地域の狩猟者からの選抜者+次世代の担い手。
・・・・
現在全国的にシカの捕獲に苦慮しております。
静岡県も富士山南嶺等は冬期にシカが集まり、樹皮の食害によってバタバタ木が倒れている地域もあります。
一度増えてしまうと森林や林業に及ぼす影響は大変なダメージとなります。
箱根は拡大防止区域となっており、今すぐ生息密度を低下させる事ができれば植生を守って行く事ができます。
ヘクタールあたり0頭を目指して早急な対策をしていただきたいと思います。
特に県の対策課は市町村の管理捕獲を指導する立場となっております。
頑張っていただきたいと思います。
「箱根のシカ対策に向けて」2015シカ調査報告 小田原山盛の会
http://blog.goo.ne.jp/burinomori/e/2c472172980a50c05c9377e308d85bf1
二ホンジカ過食圧地をみる視察・見学会レポート~箱根の山を丹沢の二の舞にしないために~http://blog.goo.ne.jp/burinomori/e/a3f3b71b414235966662939b2603af04
ぶり森のらこ(小田原山盛の会 川島範子)