冬みず田んぼやって交付金(8000円/10a)をもらおう!
冬みず田んぼ、つまり冬期湛水の水田が神奈川県も他県に数年遅れて、H29年度(H29年4月~)から環境保全型農業直接支払交付金での地域特認取組の1つに追加される見込みです。
議員が農水省に2/21にヒアリングし、神奈川県がそのような予定であると
農水省が回答(正式には3月頃決まるとのこと)。
冬期湛水を交付金対象に追加する要望を各方面へしてきましたが、やっと叶いました。
■環境保全型農業直接支払交付金とは?
化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援する制度。
■詳細は農水省hpにパンフレットや手引きpdfがあります。
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/mainp.html
■相談と申請窓口:市町村の農業担当部署(小田原市では農政課 農林業振興係0465-33-1494)
■■■■今後の課題■■■■
①神奈川県は環境保全型農業直接支払交付金自体が全国ワースト2(H27年度面積)という非常に恥ずかしい事態となってます。
②小田原市役所農政課は、「希望者が少ないから宣伝してない」とのことで、いままでは農家への広報アピールが消極的でした。
卵が先か鶏が先かの理論です。
そもそもこの制度は、「農家はやりたくないが、地域の環境に貢献するので、お金あげるからやってね」という制度です。この主旨を理解すれば、希望者が「少ないから」というのは本末転倒、希望者を増やすのが法律の主旨です。
③交付対象農家となるための要件が、個人農家では厳しい。
しかし団体ではゆるいです。
団体の条件
・代表者、組織の規約、組織としての口座がある。
・2人以上の農家を含む組織ならばOK
NPOや会社組織でなくともOKです。仲の良い農家2人と新規に団体を作ってもOKです。団体の作り方は、小田原市では農政課農林業振興係が説明してくれます。
組織の規約は、一般的な雛型をもとに、団体名や住所等を変えてもOKです。
手引き:http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/attach/pdf/mainp-20.pdf
④江の設置も地域特認に追加する要望活動を続けよう!
江の設置は、水田の端に少し深い部分を作り、中干しや稲刈りの時に、カエルやトンボ、メダカなどの水生動物が逃げ込める場所を作る取り組みです。4000円/10aもらえます。
制度の概要。この中の「地域特認」の中の「冬期湛水」。
地域特認とは、県が独自に対象とするか否かが決められる項目です。

しかし、関東甲信越では神奈川県と東京だけが、冬期湛水は未対象だった。
千葉県は先進的で、江の設置も交付金対象。

これまでの要望書

投稿:あしがら冬みず田んぼの会 会長 伊豆川哲也
https://www.facebook.com/fuyumizutanbonokai/ アドレス変更2月
冬みず田んぼ、つまり冬期湛水の水田が神奈川県も他県に数年遅れて、H29年度(H29年4月~)から環境保全型農業直接支払交付金での地域特認取組の1つに追加される見込みです。
議員が農水省に2/21にヒアリングし、神奈川県がそのような予定であると
農水省が回答(正式には3月頃決まるとのこと)。
冬期湛水を交付金対象に追加する要望を各方面へしてきましたが、やっと叶いました。
■環境保全型農業直接支払交付金とは?
化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援する制度。
■詳細は農水省hpにパンフレットや手引きpdfがあります。
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/mainp.html
■相談と申請窓口:市町村の農業担当部署(小田原市では農政課 農林業振興係0465-33-1494)
■■■■今後の課題■■■■
①神奈川県は環境保全型農業直接支払交付金自体が全国ワースト2(H27年度面積)という非常に恥ずかしい事態となってます。
②小田原市役所農政課は、「希望者が少ないから宣伝してない」とのことで、いままでは農家への広報アピールが消極的でした。
卵が先か鶏が先かの理論です。
そもそもこの制度は、「農家はやりたくないが、地域の環境に貢献するので、お金あげるからやってね」という制度です。この主旨を理解すれば、希望者が「少ないから」というのは本末転倒、希望者を増やすのが法律の主旨です。
③交付対象農家となるための要件が、個人農家では厳しい。
しかし団体ではゆるいです。
団体の条件
・代表者、組織の規約、組織としての口座がある。
・2人以上の農家を含む組織ならばOK
NPOや会社組織でなくともOKです。仲の良い農家2人と新規に団体を作ってもOKです。団体の作り方は、小田原市では農政課農林業振興係が説明してくれます。
組織の規約は、一般的な雛型をもとに、団体名や住所等を変えてもOKです。
手引き:http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/attach/pdf/mainp-20.pdf
④江の設置も地域特認に追加する要望活動を続けよう!
江の設置は、水田の端に少し深い部分を作り、中干しや稲刈りの時に、カエルやトンボ、メダカなどの水生動物が逃げ込める場所を作る取り組みです。4000円/10aもらえます。
制度の概要。この中の「地域特認」の中の「冬期湛水」。
地域特認とは、県が独自に対象とするか否かが決められる項目です。

しかし、関東甲信越では神奈川県と東京だけが、冬期湛水は未対象だった。
千葉県は先進的で、江の設置も交付金対象。

これまでの要望書

投稿:あしがら冬みず田んぼの会 会長 伊豆川哲也
https://www.facebook.com/fuyumizutanbonokai/ アドレス変更2月

















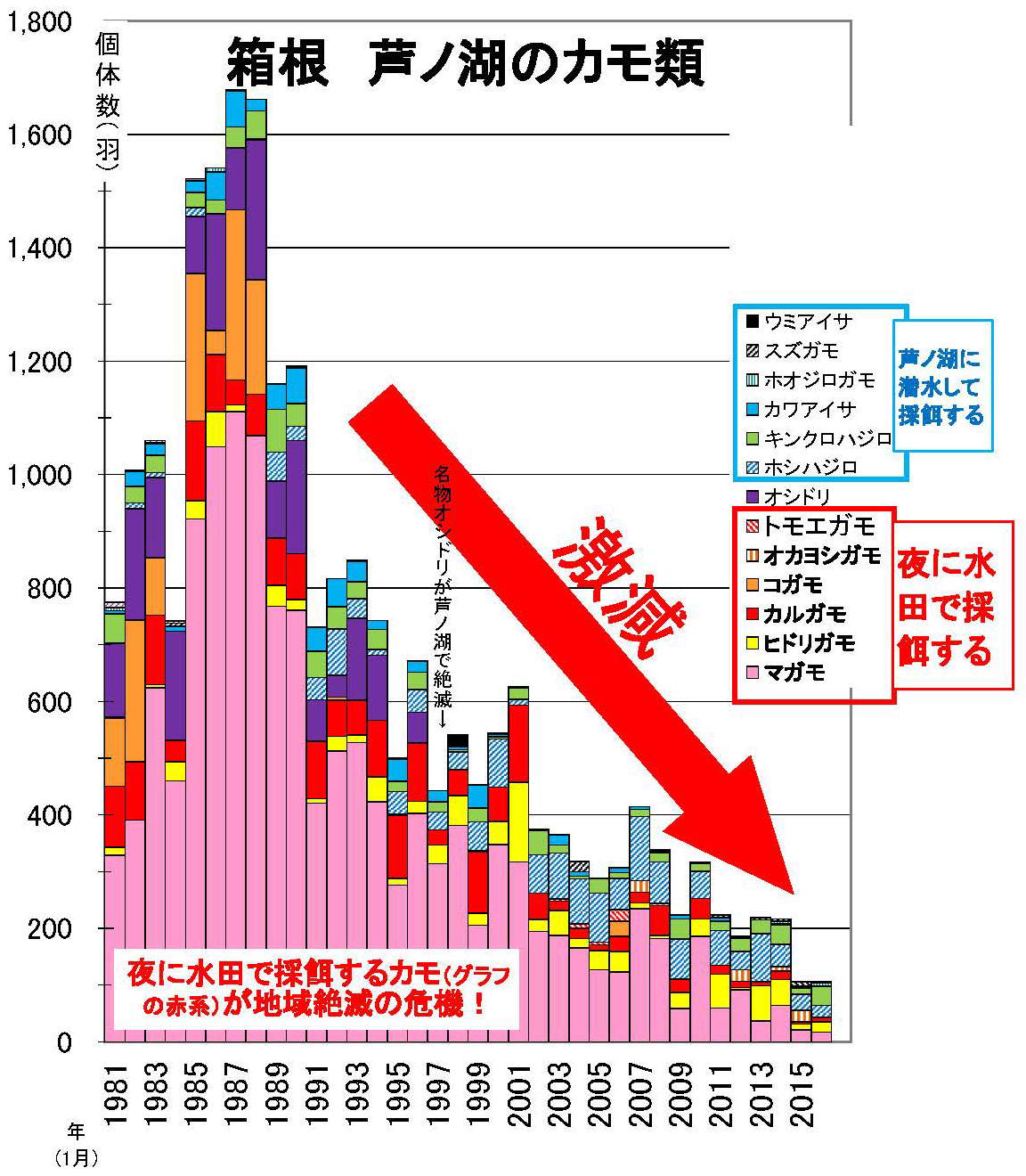



 今年の市民田植えは、去年まで休耕田だったところです。地元農家の林さんが地主の了解を得て再生させました。林さんは、上の写真の一番左で、田植えの説明をしてるお兄さんです。
今年の市民田植えは、去年まで休耕田だったところです。地元農家の林さんが地主の了解を得て再生させました。林さんは、上の写真の一番左で、田植えの説明をしてるお兄さんです。












