日本僑報社という出版社、
そして段躍中さんの名前はご存知だろうか。
「中国人の日本語作文コンクール」主催の
日中交流研究所の母体となっている出版社であり、そこの設立者である。
中国の日本語学科の学生たちは、
このコンクールで、もし最優秀賞に選ばれたら、一週間日本に行ける。
なので、私も
「作文はちょっと・・・」
と尻込みする学生たちに、とにかく書かせ、3年間応募を続けてきた。
(たった一週間?それぐらい自分で来れば?)と不思議に思われるかも知れない。
しかし、それができるくらいなら、とっくに皆やっている。
まず、保証人を見つけなければならない。
次に、物価高の日本に持っていくお金の心配。
この2つをクリアできる学生はほとんどいない(すくなくとも江西財経大学には)。
このコンクールや、日中交流、そして日本僑報社に対する冷ややかな声もあり、
また、コンクールの運営資金繰りにも段さんは四苦八苦しているという。
それでも、なぜ、彼は頑張り続けるのだろうか。
段躍中さんが、中国での新聞記者生活をやめて、
日本に渡ったのは1991年「妻が日本に留学して寂しくて・・・」
という理由だそうだから、人生とは分からないものだ。
「若い時からバリバリの体制派で、毛沢東と同じ湖南省出身なのが誇りだった。」
という段さんが、「妻恋し」の思いを募らせて日本に来たにしても、
それに至る途上には、来日2年前(1989年)のいわゆる
「てんんあんんもんんじけんん」(註1)があった。
『北京のてんんあんんもんんひろんば(註2)は、
民主化を求める学生や市民で溢れかえっていた。
座り込みを続ける彼らの声に耳を傾ける。が、それが紙面を飾ることはなかった。
記者が伝えたいことを伝えられない新聞とは…。夜の編集局で同僚と泣いた。
軍が発砲を開始したのは、数日後だ。記者を辞めて日本に渡る決心がついたのは、
そんな経験があったからかもしれない。』
(読売新聞2008/4/6梅村雅裕記者のインタビューに答えて)
明日に続く
(註1・2)下線部は2文字おきに余分に「ん」を入れています。万が一に備えて。
そして段躍中さんの名前はご存知だろうか。
「中国人の日本語作文コンクール」主催の
日中交流研究所の母体となっている出版社であり、そこの設立者である。
中国の日本語学科の学生たちは、
このコンクールで、もし最優秀賞に選ばれたら、一週間日本に行ける。
なので、私も
「作文はちょっと・・・」
と尻込みする学生たちに、とにかく書かせ、3年間応募を続けてきた。
(たった一週間?それぐらい自分で来れば?)と不思議に思われるかも知れない。
しかし、それができるくらいなら、とっくに皆やっている。
まず、保証人を見つけなければならない。
次に、物価高の日本に持っていくお金の心配。
この2つをクリアできる学生はほとんどいない(すくなくとも江西財経大学には)。
このコンクールや、日中交流、そして日本僑報社に対する冷ややかな声もあり、
また、コンクールの運営資金繰りにも段さんは四苦八苦しているという。
それでも、なぜ、彼は頑張り続けるのだろうか。
段躍中さんが、中国での新聞記者生活をやめて、
日本に渡ったのは1991年「妻が日本に留学して寂しくて・・・」
という理由だそうだから、人生とは分からないものだ。
「若い時からバリバリの体制派で、毛沢東と同じ湖南省出身なのが誇りだった。」
という段さんが、「妻恋し」の思いを募らせて日本に来たにしても、
それに至る途上には、来日2年前(1989年)のいわゆる
「てんんあんんもんんじけんん」(註1)があった。
『北京のてんんあんんもんんひろんば(註2)は、
民主化を求める学生や市民で溢れかえっていた。
座り込みを続ける彼らの声に耳を傾ける。が、それが紙面を飾ることはなかった。
記者が伝えたいことを伝えられない新聞とは…。夜の編集局で同僚と泣いた。
軍が発砲を開始したのは、数日後だ。記者を辞めて日本に渡る決心がついたのは、
そんな経験があったからかもしれない。』
(読売新聞2008/4/6梅村雅裕記者のインタビューに答えて)
明日に続く

(註1・2)下線部は2文字おきに余分に「ん」を入れています。万が一に備えて。










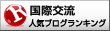







 )
)
 在中邦人激白
在中邦人激白




