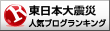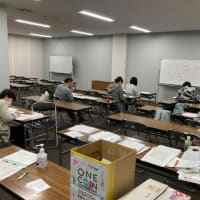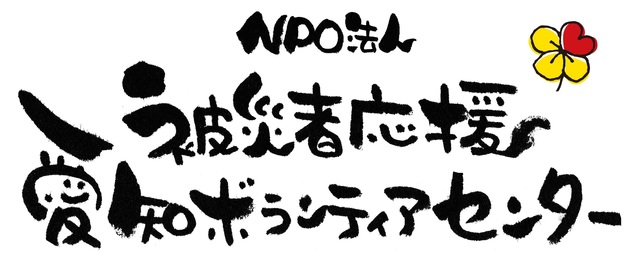代表の久田です。
熊本の避難所では、今、支援物資にあふれています。
これまで大きな災害があるたびに繰り返されていることです。
まず、以下の東日本大震災を経験された方のレポートをお読みください。
http://synodos.jp/fukkou/16991
愛知ボラセンは、東日本大震災で、愛知県の皆さんに春物新品衣類の提供をお願いし、
提供のお願いと、名古屋での活動として、物資の仕分け分類のボランティアさんを募集。
ほぼ同じサイズの箱6,000箱に、男性用、女性用、子ども用、インナー、アウター、サイズなど細かく分類し、
中身の分かる大きなシートを箱に貼り、
合計約30万着の春物新品衣類をはじめとした応援物資を、石巻市の被災者に直接届け、お渡ししました。
直接お渡しすることで、いろいろな要望を伺い、新たに追加で募集したもの、募集を打ち切ったものなどがありました。
女性下着はパーティーションで仕切り、女性スタッフを配置し、男性の立ち入りをお断りするということも実施してきました。
応援物資に関しては、完全に自己完結の活動を、大規模に実施しました。
そのノウハウは2013年のフィリピン台風30号被災者へ、776箱約35,000着の応援衣類を届けることにつながっていきました。
その愛知ボラセンは、今回の熊本地震に際して、応援物資を集めることはしませんでした。
テレビではリポーターが水や食糧などがないと伝えていました。
テレビをご覧になられた方々はいてもたってもいられなく、物資を送られ方がおおくいらっしゃいました。
愛知ボラセンが物資を集めず、送らなかった理由は、かんたんです。
私たちの物が届く頃には、まちがいなく、避難所は物資で溢れていると考えたからです。
そして、今、その通りになっています。
東日本大震災の被災者は津波で家を流され、何もかも失ってしまいました。
ですから、4月なって、春物新品衣類は必要でした。
しかし、石巻市内中心部で商店の営業が再開された頃には、商店の営業妨害になりかねませんので、
応援物資の提供は中止しました。
今でも仮設住宅で物資を配布されている団体も見受けます。受け取られた方がよろこばれるでしょうが、
愛知ボラセンは、今現在も東日本大震災の仮設住宅でお米などの物資を提供することは
総合的に考えると適切なことではないと考えています。
1998年に神戸の復興住宅の自治会役員さんから、「自分たちは乞食じゃないから、いつまでもモノを配らないでくれ」と言われました。
もとより私にはその考えはありませんでしたが、それは災害ボランティア=物資提供と思い込んでいる人たちがいるということです。
それはおそらく今も変わっていません。
自己満足的な活動ではないこと。
できるだけ自己完結の活動であること。
できるだけ継続的な活動をすること。
こういったことが重要なことだと考えています。
今回の熊本地震ではも、継続的な自己完結型の活動をめざしています。
応援先の高齢者施設グリーンヒルみふねさんの依頼で活動をすすめていきます。
活動にあたっては、4月25日と5月2日に活動現場を、熊本まで私が確認に行っています。
今後も必要があれば、私が確認に行きます。
電話やメールでは細かな所までわかりませんし、伝わりません。
自己完結型というのは、宿泊や交通手段程度のことをいうのではなく、
活動のしかたそのものも、他者にできるだけ負担をかけることなく、
どれだけ自前でできるのかということが大切だと考えています。
こうした活動にもとづいて、第1回は、関連施設の小規模施設の「みどりの丘」 の片付け。
第2回以降は、利用者さんの自宅の片付けになって「いきますが、
これは第1回の見事な片付けによって愛知ボラセンへの信頼感の反映と考えられます。
いくらボランティアとはいえ、見知らぬ人たちを自宅にあげるのは不安なものだと思います。
しかし、愛知ボラセンとしてまとまった団体で、活動の実績や信頼があれば、
その不安は少しは和らぐと思います。
自己完結型だからこそ、継続的な活動ができると私は考えています。
まっさきに被災地に駆けつける活動は大切です。
瓦礫の中から大切なものをとりだす活動
災害ボランティアセンターの運営に関わる活動
温かいものを提供する炊き出し・・・、
少し遅れても、週に1回だけでも、大勢の参加者で、継続的な活動。
それが愛知ボラセンのめざす、被災者応援活動です。
応援物資も必要と考えれば、徹底してやりきります。
その場合は、東日本大震災の時のように、名古屋で集め、名古屋で仕分け・分類し、
同じサイズの箱に積みかえ、自分たちで持っていき、被災者に直接渡し、
ニーズをきいて、確実に必要なものを届けます。
もしも次に大きな災害が起きたとき、愛知ボラセンの動きを参考にしてください。