本年屈指の本。間違いなく面白い。心揺さぶられる。かつてない「難病」書。壮絶なる「究極のエンタメ・ノンフィクション」。必読。多くのところで話題になっているようですが、僕も一読、これは書いておかなくてはと思いました。上智大学大学院でビルマ難民の研究、支援活動をしていた女性が、突然原因不明の難病になる。その壮絶な闘病記。大野更紗「困ってる人」(ポプラ社)はとりあえずそんな本。
まず、この人は「ビルマ難民」の支援活動を半端じゃなくしてた人で、その時の活動ぶりがすごい。タイ、ビルマ国境の難民キャンプに乗り込んでいくのだが、その辺は本で。しかも、生地は原発事故避難地域すぐ近くの山奥の限界集落(「ムーミン谷」と呼ぶ)で、そこから進学校の女子高に進学し全国一の合唱部で活動する。この大学以前もかなりすごい。そこから上智でフランス語、そこからさらにビルマ難民支援と一直線で、難病以前も濃い人生なのだ。その後、タイで調子が悪くなり、なんとか帰って、診断を求めて、病院をさすらう。ここも大変。結局「自己免疫疾患」で、前に書いた森まゆみさんの「原田病」もそっち系だが、この「自分の免疫機構がおかしくなる」というのは、本質的に「自分とは何か」という問いを自分に突きつけるような根源的な病だ。結局ついた病名は「筋膜炎脂肪織炎症候群」という読むのも大変な病気だった。
ある「病院」にたどりつき、そこで入院(ゆえに、ここは「オアシス」と呼ぶ)、そこでの検査、ステロイド投与の治療、これでもかこれでもかと上には上、下には下、奥には奥、と世界の深さは果てしないことを思い知らされる。が、ついに「おしり」が崩壊、「おしり有袋類」となる。これ、わからないでしょ。本を是非読んでほしいが、あまりにも悲惨ですごい。が、悪いけど(悪くないけど)爆笑ものである。そのあとは、医療、社会福祉の谷間に落ち込みながら、必死に生きていくわけだけど、軽妙洒脱(けいみょうしゃだつ)な文章で書かれているけど、日本と言う国を自己認識するときに大切なことがいっぱい書かれている。つまり、日本が難民に冷たい国だと「発見」して驚いた著者は、日本が「難病者」に冷たい制度に満ち満ちていることにも驚く。なってみないとわからないことは多いのだ。
冗舌なる口語体で一気読みできるけど、そこが油断ならない。自己客観化の仕掛けでもあるけど、人間は親や家族が一番描きにくい。そこで実の両親は「ムーミン」(なぜかフグスマ弁をしゃべるムーミン)にしてしまい、第二の親である医者も「クマ先生」「パパ先生」などとネーミングしてしまう。親にあたる人との関係を書くのは大変だと思うけど、この人は自分の体験がすごすぎて、それを書きたい気持ちが強いから、そういう手で軽々と乗り越えてしまった。そこは感心なんだけど、自分のことを「現代っ子だから、ほめられると伸びるタイプ」なんて軽く書いてしまう。これはいけません。
現在は退院して都内某所で生存中とのこと。近況はブログで見ることができる。かなりあちこちで「作家」として活躍中。開沼博さんと大野更紗さんの、福島出身院生対談なんて企画もあった。(行けなかったが。)二人ともちょっと前まで全然知らなかった人なわけだが。さて、で次は開沼博の本に取り掛かる。
*追記
「困ってる人」が売れているようです。本屋に積んであるから。それにつれて、ブログのこの記事も毎日30人位が読んでくれる日が多くなっています。このブログは、もともと「教員免許更新制」に反対するために開設しましたが、いろいろと記事を書いています。もしよかったら、「ブログ開設半年の総まとめ①」「ブログ開設半年の総まとめ②」「ブログ開設半年の総まとめ③」を見て、他の記事も見て頂けるとありがたいなと思っています。
★さらに追伸。「コメント」を入れてくれた人がいます。どんなコメントも歓迎です。「なんで?」ってあるからすぐに応えてもいいんだけど、僕が書いてしまう前に誰か思うことがあれば書き込んでくれるとうれしいです。そのうち、僕も書きたいと思いますが。
追記2.
追記を書いた後で、「ほめられると伸びるタイプだから問題」を書いています。(2011.10.20)ここに書き込むのを忘れていたのですが。「困ってる人」という素晴らしい本に関する話の中では、本質に関わる問題ではありません。スピン・オフなので、この後自分でコメントを書いてオシマイにしたいと思っています。(2012.2.10)
まず、この人は「ビルマ難民」の支援活動を半端じゃなくしてた人で、その時の活動ぶりがすごい。タイ、ビルマ国境の難民キャンプに乗り込んでいくのだが、その辺は本で。しかも、生地は原発事故避難地域すぐ近くの山奥の限界集落(「ムーミン谷」と呼ぶ)で、そこから進学校の女子高に進学し全国一の合唱部で活動する。この大学以前もかなりすごい。そこから上智でフランス語、そこからさらにビルマ難民支援と一直線で、難病以前も濃い人生なのだ。その後、タイで調子が悪くなり、なんとか帰って、診断を求めて、病院をさすらう。ここも大変。結局「自己免疫疾患」で、前に書いた森まゆみさんの「原田病」もそっち系だが、この「自分の免疫機構がおかしくなる」というのは、本質的に「自分とは何か」という問いを自分に突きつけるような根源的な病だ。結局ついた病名は「筋膜炎脂肪織炎症候群」という読むのも大変な病気だった。
ある「病院」にたどりつき、そこで入院(ゆえに、ここは「オアシス」と呼ぶ)、そこでの検査、ステロイド投与の治療、これでもかこれでもかと上には上、下には下、奥には奥、と世界の深さは果てしないことを思い知らされる。が、ついに「おしり」が崩壊、「おしり有袋類」となる。これ、わからないでしょ。本を是非読んでほしいが、あまりにも悲惨ですごい。が、悪いけど(悪くないけど)爆笑ものである。そのあとは、医療、社会福祉の谷間に落ち込みながら、必死に生きていくわけだけど、軽妙洒脱(けいみょうしゃだつ)な文章で書かれているけど、日本と言う国を自己認識するときに大切なことがいっぱい書かれている。つまり、日本が難民に冷たい国だと「発見」して驚いた著者は、日本が「難病者」に冷たい制度に満ち満ちていることにも驚く。なってみないとわからないことは多いのだ。
冗舌なる口語体で一気読みできるけど、そこが油断ならない。自己客観化の仕掛けでもあるけど、人間は親や家族が一番描きにくい。そこで実の両親は「ムーミン」(なぜかフグスマ弁をしゃべるムーミン)にしてしまい、第二の親である医者も「クマ先生」「パパ先生」などとネーミングしてしまう。親にあたる人との関係を書くのは大変だと思うけど、この人は自分の体験がすごすぎて、それを書きたい気持ちが強いから、そういう手で軽々と乗り越えてしまった。そこは感心なんだけど、自分のことを「現代っ子だから、ほめられると伸びるタイプ」なんて軽く書いてしまう。これはいけません。
現在は退院して都内某所で生存中とのこと。近況はブログで見ることができる。かなりあちこちで「作家」として活躍中。開沼博さんと大野更紗さんの、福島出身院生対談なんて企画もあった。(行けなかったが。)二人ともちょっと前まで全然知らなかった人なわけだが。さて、で次は開沼博の本に取り掛かる。
*追記
「困ってる人」が売れているようです。本屋に積んであるから。それにつれて、ブログのこの記事も毎日30人位が読んでくれる日が多くなっています。このブログは、もともと「教員免許更新制」に反対するために開設しましたが、いろいろと記事を書いています。もしよかったら、「ブログ開設半年の総まとめ①」「ブログ開設半年の総まとめ②」「ブログ開設半年の総まとめ③」を見て、他の記事も見て頂けるとありがたいなと思っています。
★さらに追伸。「コメント」を入れてくれた人がいます。どんなコメントも歓迎です。「なんで?」ってあるからすぐに応えてもいいんだけど、僕が書いてしまう前に誰か思うことがあれば書き込んでくれるとうれしいです。そのうち、僕も書きたいと思いますが。
追記2.
追記を書いた後で、「ほめられると伸びるタイプだから問題」を書いています。(2011.10.20)ここに書き込むのを忘れていたのですが。「困ってる人」という素晴らしい本に関する話の中では、本質に関わる問題ではありません。スピン・オフなので、この後自分でコメントを書いてオシマイにしたいと思っています。(2012.2.10)










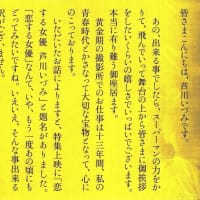
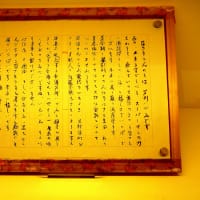








なんで?
なにそれ。
そう言いながら苦難を一つの笑いにして乗り越える。多くの人がやっている行為ですよね。
いけませんの一言ですますなんて。
行間を読めないというか、自分の考えと違えば即否定する、人間味がない感想ですね。
否定のコメントには返さないでしょうけどね、自分が一つの何かを否定するブログなのに。
“困ってるひと”になったのは今に始まったことではありませんが…。
とりあえず、大野さんを見習って、きながに困っていこうと思いますです。
お気遣い、ありがとうございましたー。
それは若干、面倒くさいですぅ。
記事内容に関する間違いの指摘やポレミック(論争的)なコメントにはすぐ応えることもありますが、一般論としては、あまりすぐコメントに応えるのもどうかなと思っています。反応がリアルタイムに近いほどいいというのはおかしいです。自分の考え方、感じ方には間違うことも多いと思うので、ツイッターのようにすぐ書き込むのは違和感があります。
また電子空間も「公的空間」ですから、あまり個人的なことを書き込まれたり、聞かれても困ることになります。(僕を個人的に知ってる人、特に生徒だった人はその限りにあらず。)ここでは何も書きませんが、それこそ「週刊金曜日」2011年8月26日号をご覧ください。(ある程度書いてあります。)
ところで、そもそもが「困ってる人」という大変意義のある本の中で、本質的な部分ではないところを取り上げるのは、もうやめにしたいと思っています。僕は自分が違和感がある表現に対して軽く触れただけで、それ以上の何物でもありません。自分を含めて、何気なく使ってしまう表現はあるもので、それがその表現の本質に関わらなければ、あまり問題視する必要はないでしょう。
この書き込みに対しては、10月20日に記事を書いたけど、それをこちらに書き込むのを忘れていました。今日書いた「追記2」をご覧ください。それを読んでくれればいいようなもんなんだけど。一応誤解のないように、書いておきます。
「ほめられればうれしい」のは誰だってそうでしょう。だから「私も頑張ったから、たまにはほめて欲しいな」などという表現には何の違和感も感じません。(中身にではなく、表現にですよ。)僕が違和感を持つのは「私は○○のタイプだから」という表現に対してです。「ほめられると伸びる」かどうかではなく。
この社会の中には、実際に「上の立場」に立つ人がいます。生徒にとっては先生、お店のアルバイトにとっては店長などなど。上に立つ人が「上から」人を見るのは当然です。それが仕事です。だから、そういう立場の人が「上から」「○○をほめて育てよう」と考えても、何の問題もありません。(それがうまくいかされているか、とは別に。発想の問題としては、問題がないということです。)
一方、それを部下の側から、「私はほめられると伸びるタイプだから、ほめて下さいね」と言ってしまっては、表現として違和感があるということです。
しかし、医者と患者というのは、サービスの供給者と需要者で立場の上下はない、と言っていいはずです。とは言うものの、やはり実際のところは、サービスの知識・技量は医者の側に圧倒的に存在し、患者は受け身になってしまいます。だからこそ、大野さんも「ほめて欲しかった」んでしょうから。だから、内容には違和感はないのです。違和感があるのは、表現の仕方の部分ということです。(その詳しい中身は、10月20日の記事で書きました。)
何人かのコメントを見ると、僕が違和感を感じた部分に対して、間違った解釈をしている方がいると思うので、念のため書いておきます。