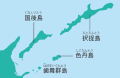厚生労働省は分割するべきだと思う。今回のような「統計不正」問題を起こしたからというわけではない。「省庁再編」が行われた2001年時点から、そう思っていた。まあ書くまでもないと思っていたけれど、この際だから簡単に書いておきたい。省庁再編は大臣ばかり多くても仕方ない、似たような仕事は統合するべきだという「行政改革」の一環で行われた。1998年に橋本内閣で消費税が3%から5%へと増税された。そういう時には「政府も身を切るべきだ」となりやすい。
2001年1月6日(森内閣)に実施された省庁再編では、「1府22省庁」が「1府12省庁」に改編された。大臣数は19人が18人になった。12省庁にしても、「特命大臣」がけっこう多いので、やはり減らないのである。現在は総理大臣を入れて20人で、東京五輪担当がいるから、一人多い。「復興庁」担当相を含めて、大臣のもとにきちんとした組織があるのは、13人ほどだ。
あとは何だろうというと、「地方創生担当」「1億総活躍担当」「女性活躍担当」「少子化対策担当」「消費者及び食品安全担当」とか、いろんな特命事項を担当しているのである。兼務ではあるけれど、「マイナンバー制度担当」とか「クールジャパン戦略担当」なんて大臣までいるのだ。そんなの、どこか関連している省庁でやればいいことだろう。「地方創生」とか「1億総活躍」とか、総理が思いつくたびに大臣だけ増えていくのである。そういう大事なことを本気でやるなら、特命大臣を置くだけじゃなくて、ちゃんとしたお役所の組織がいるだろう。
 (厚生労働省が入る合同庁舎)
(厚生労働省が入る合同庁舎)
「厚生労働省」と言えば、年金、医療制度を担当しているから、国民の最大関心事の担当省である。それに加えて雇用確保や「働き方改革」も担当だから、国民一人ひとりの生活にものすごい影響がある。この20年間ぐらい、国会の議論も厚労省担当のテーマが多かった。それを見るたびに、僕は大臣一人で大丈夫なのか、と思い続けて来た。まあ大臣はすぐに代わるからどうでもよくて、官僚がしっかりしてるから大丈夫なんだなどと言われていたけど、そんなのが真っ赤な嘘だったことは、昨年の財務省、今回の厚労省でよく判る。
分割すれば良くなるのか。そう言われると、安倍政権に官僚も「忖度」している現状では、「改悪競争」にならないとは言えない。大臣が一人で手が回らないからまだよくて、別の二人の大臣になればそれぞれ「競争」して悪政が暴走するかもしれない。そうなんだけど、そう言っては制度改革の話ができない。一応、大臣も官僚組織も真面目に仕事をすることを前提にすれば、社会福祉行政と労働法制行政は一人では把握不能だと思う。
歴史を振り返ると、もともと「厚生行政」は旧内務省の担当だった。1938年(昭和13年)に分離して厚生省が誕生した。これは保健衛生、人口政策などが日中戦争下の戦時体制下に進められたことを示している。ナチスドイツでは「国民は健康である義務」があり、その反対に「健康ではない(病気や障害がある)国民」には存在価値がない。そのような「ファシズム的健康観」が厚生省発足に影響している。戦後の1947年になって、労働省が分離する。労働行政は労働組合の合法化で大きく変わったからだ。(その歴史から厚生省と労働省の統合には一定の合理性はあった。)
ところで「厚生」とは何か。もはや日常語では全く使わない。アメリカでは「保健福祉省」というようだ。韓国でも「保健福祉部」らしい。日常語で判りやすいという意味では、日本でも「保健福祉省」といったネーミングがふさわしいと思う。
2001年1月6日(森内閣)に実施された省庁再編では、「1府22省庁」が「1府12省庁」に改編された。大臣数は19人が18人になった。12省庁にしても、「特命大臣」がけっこう多いので、やはり減らないのである。現在は総理大臣を入れて20人で、東京五輪担当がいるから、一人多い。「復興庁」担当相を含めて、大臣のもとにきちんとした組織があるのは、13人ほどだ。
あとは何だろうというと、「地方創生担当」「1億総活躍担当」「女性活躍担当」「少子化対策担当」「消費者及び食品安全担当」とか、いろんな特命事項を担当しているのである。兼務ではあるけれど、「マイナンバー制度担当」とか「クールジャパン戦略担当」なんて大臣までいるのだ。そんなの、どこか関連している省庁でやればいいことだろう。「地方創生」とか「1億総活躍」とか、総理が思いつくたびに大臣だけ増えていくのである。そういう大事なことを本気でやるなら、特命大臣を置くだけじゃなくて、ちゃんとしたお役所の組織がいるだろう。
 (厚生労働省が入る合同庁舎)
(厚生労働省が入る合同庁舎)「厚生労働省」と言えば、年金、医療制度を担当しているから、国民の最大関心事の担当省である。それに加えて雇用確保や「働き方改革」も担当だから、国民一人ひとりの生活にものすごい影響がある。この20年間ぐらい、国会の議論も厚労省担当のテーマが多かった。それを見るたびに、僕は大臣一人で大丈夫なのか、と思い続けて来た。まあ大臣はすぐに代わるからどうでもよくて、官僚がしっかりしてるから大丈夫なんだなどと言われていたけど、そんなのが真っ赤な嘘だったことは、昨年の財務省、今回の厚労省でよく判る。
分割すれば良くなるのか。そう言われると、安倍政権に官僚も「忖度」している現状では、「改悪競争」にならないとは言えない。大臣が一人で手が回らないからまだよくて、別の二人の大臣になればそれぞれ「競争」して悪政が暴走するかもしれない。そうなんだけど、そう言っては制度改革の話ができない。一応、大臣も官僚組織も真面目に仕事をすることを前提にすれば、社会福祉行政と労働法制行政は一人では把握不能だと思う。
歴史を振り返ると、もともと「厚生行政」は旧内務省の担当だった。1938年(昭和13年)に分離して厚生省が誕生した。これは保健衛生、人口政策などが日中戦争下の戦時体制下に進められたことを示している。ナチスドイツでは「国民は健康である義務」があり、その反対に「健康ではない(病気や障害がある)国民」には存在価値がない。そのような「ファシズム的健康観」が厚生省発足に影響している。戦後の1947年になって、労働省が分離する。労働行政は労働組合の合法化で大きく変わったからだ。(その歴史から厚生省と労働省の統合には一定の合理性はあった。)
ところで「厚生」とは何か。もはや日常語では全く使わない。アメリカでは「保健福祉省」というようだ。韓国でも「保健福祉部」らしい。日常語で判りやすいという意味では、日本でも「保健福祉省」といったネーミングがふさわしいと思う。