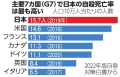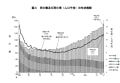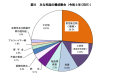書こうと思っていて放ってある問題が幾つかある。4月の統一地方選で「日本維新の会」が好調だった。次回総選挙では「野党第一党」を目標にしているとか。この「維新」をどう考えるか、一度まとめて書きたいと思っているけど、当面解散・総選挙はないということで、まだ後でいいだろう。結構ちゃんと調べることが多くて面倒なのである。その「維新」は橋下徹元大阪府知事に始まるが、石原慎太郎都知事以来何かとお騒がせな「暴言系地方首長」が各地に増えてきた。
名古屋の河村たかし市長も、2009年に当選以来「大阪維新の会」や後の「都民ファーストの会」のような独自の地方政党「減税日本」を立ち上げた。その後、金メダルを囓ってみたり、愛知トリエンナーレ2019をめぐって大村知事と対立し、市の負担金は払わないと通告したりした。その問題は裁判になって、名古屋市は地裁、高裁で敗訴している。上告中だが、その間も遅延金が発生している。その名古屋市でずっと揉めてるのが「名古屋城天守閣再建問題」である。

2023年6月3日に、木造再建を目指す天守閣のバリアフリー問題で、名古屋市主催の市民討論会が開かれた。そこで参加者が障害者差別発言を行ったが、市長や市当局は発言を制止しなかった。市長はむしろ当日のまとめとして「活発な発言があった」などと述べたという。今月起こった問題だから、今月中に書いておくことにしたい。名古屋城復元問題はもう10年以上揉めているけど、僕は今まで書いていない。名古屋市民と文化庁当局が了解するならば、特に僕が何か言う必要もないと思うからだ。
 (討論会であいさつする河村市長)
(討論会であいさつする河村市長)
だが、6月6日付朝日新聞が報じる以下の発言を見て、やはり論点を書いておくべきかなと思った。まず「車いすの男性(70)」が(最上階まで車いすを運べるエレベーターが設置されないのは)「障害者が排除されているとしか思えない」と発言した。これに対し、2人の男性が発言し、最初の男性は「河村市長が造りたいというのはエレベーターも電気もない時代に作ったものを再構築するって話なんですよ。その時になぜバリアフリーの話がでるのかなっていうのは荒唐無稽で。我慢せえよって話なんですよ。お前が我慢せえよ」と話した。次の男性は「差別表現」を使ったという。(具体的には出ていない。)
これはまたすさまじい発想だと思ったが、こういう発言が出て来るのは、河村市長の責任が大きいと思ったのである。今回の天守閣再建は「エレベーターも電気もない時代に作ったものを再構築する」という話ではないのである。名古屋城天守閣は1612年に建築され、明治以後も残っていたが、周知のように名古屋大空襲で焼失してしまった。1959年に再建されたが、その時は消防法の規定で木造再建は不可能だった。そのためコンクリート建築になったけれど、すでに60年以上経って老朽化が進むとともに、現行の建築基準法上の耐震基準を満たせなくなった。そのため、2018年から天守閣への入場が禁止されている。
 (名古屋城の現行天守閣)
(名古屋城の現行天守閣)
「エレベーターも電気もない時代の再構築」なら、もちろん耐震基準もなければ防火設備もないはずである。そんなものを作ろうとしても、もちろん建築基準法を満たせず、建築は出来ない。今回の再建は、「現代の技術を使って、耐震基準をクリアーする」のが目的なのである。その上で、河村市長がなぜ「木造」にこだわるかと言えば、観光目的だろう。静岡県の掛川城が1994年に木造で再建され、観光地として大きな注目を集めた。そのため、当選直後から木造再建を言いだし、当初は2020年東京五輪までを目標としていた。戦前の国宝時代に詳細な調査が行われており、技術的には可能だとされる。
このバリアフリー問題もずっと揉めているが、文化庁の許可が出ないのは違う問題だという。工事のために江戸時代に作られた石垣を崩すことが問題視され、文化庁の解体、木造再建の許可が出ないまま数年が経っている。それが解決しないうちは解体工事にも入れない。名古屋城は全体として「特別史跡」に指定されているが、天守閣自体は昔のものが失われているので国宝でも重要文化財でも何でもない。史跡としての意味はなく、文化財としての扱いは「博物館施設」に過ぎない。
名古屋城には焼失を免れた櫓なども残っているが、そこにエレベーターを設置せよという話はない。市長が「史実に忠実な復元」と呼んでも、それは実は「博物館」なんだから、障害者や高齢者にも可能な限りアクセス出来るものが求められるのである。何故なら、日本は「障害者権利条約」を批准していて、「障害者差別解消法」も制定されているからである。「史実に忠実」なら、そもそも公開も出来ない。内部を博物館として解説パネルなどを設置するのもおかしくなる。しかし、観光施設として作るんだったら、現代ではエレベーター設置は必須のはずである。
今回の討論会は「住民基本台帳から無作為に選んだ18歳以上の参加希望者約40人」が参加したという。だから特定の団体関係者が押しかけて来たわけではない。そのことが深刻なのである。参加者の中から「差別発言」があったのは、愛知トリエンナーレ問題、その後の大村知事リコール問題などを見て、発言者は河村市長は「自分の味方」だと認識していたからだと思う。先のLGBT法に使われた「不当な差別」はいけないが、「史実に忠実な」復元だからエレベーターがなくても「不当」ではない。それを批判する障害者の方が「不当な言いがかり」であるという意識である。
例えば、討論会参加者に事前に「障害者権利条約」の条文を配布していただろうか。そういうことが大切で、そこを前提にして議論しないからおかしくなる。この問題はもう時間も長くなっていて、解体工事も出来ないのに、契約した会社(竹中工務店)にはお金を払っているという。エレベーターは出来る限り上の方まで設置するようにして、早く石垣問題を解決するべきだ。名古屋城には僕も昔行っているが、今の城ブームの中でむしろ天守閣再建そのものを問うべきかと考えている。再建はあっても良いが、別になくても良いぐらいの気持ちである。残された石垣や櫓などの方が貴重で、天守閣再建のため石垣を壊しては本末転倒だ。
名古屋の河村たかし市長も、2009年に当選以来「大阪維新の会」や後の「都民ファーストの会」のような独自の地方政党「減税日本」を立ち上げた。その後、金メダルを囓ってみたり、愛知トリエンナーレ2019をめぐって大村知事と対立し、市の負担金は払わないと通告したりした。その問題は裁判になって、名古屋市は地裁、高裁で敗訴している。上告中だが、その間も遅延金が発生している。その名古屋市でずっと揉めてるのが「名古屋城天守閣再建問題」である。

2023年6月3日に、木造再建を目指す天守閣のバリアフリー問題で、名古屋市主催の市民討論会が開かれた。そこで参加者が障害者差別発言を行ったが、市長や市当局は発言を制止しなかった。市長はむしろ当日のまとめとして「活発な発言があった」などと述べたという。今月起こった問題だから、今月中に書いておくことにしたい。名古屋城復元問題はもう10年以上揉めているけど、僕は今まで書いていない。名古屋市民と文化庁当局が了解するならば、特に僕が何か言う必要もないと思うからだ。
 (討論会であいさつする河村市長)
(討論会であいさつする河村市長)だが、6月6日付朝日新聞が報じる以下の発言を見て、やはり論点を書いておくべきかなと思った。まず「車いすの男性(70)」が(最上階まで車いすを運べるエレベーターが設置されないのは)「障害者が排除されているとしか思えない」と発言した。これに対し、2人の男性が発言し、最初の男性は「河村市長が造りたいというのはエレベーターも電気もない時代に作ったものを再構築するって話なんですよ。その時になぜバリアフリーの話がでるのかなっていうのは荒唐無稽で。我慢せえよって話なんですよ。お前が我慢せえよ」と話した。次の男性は「差別表現」を使ったという。(具体的には出ていない。)
これはまたすさまじい発想だと思ったが、こういう発言が出て来るのは、河村市長の責任が大きいと思ったのである。今回の天守閣再建は「エレベーターも電気もない時代に作ったものを再構築する」という話ではないのである。名古屋城天守閣は1612年に建築され、明治以後も残っていたが、周知のように名古屋大空襲で焼失してしまった。1959年に再建されたが、その時は消防法の規定で木造再建は不可能だった。そのためコンクリート建築になったけれど、すでに60年以上経って老朽化が進むとともに、現行の建築基準法上の耐震基準を満たせなくなった。そのため、2018年から天守閣への入場が禁止されている。
 (名古屋城の現行天守閣)
(名古屋城の現行天守閣)「エレベーターも電気もない時代の再構築」なら、もちろん耐震基準もなければ防火設備もないはずである。そんなものを作ろうとしても、もちろん建築基準法を満たせず、建築は出来ない。今回の再建は、「現代の技術を使って、耐震基準をクリアーする」のが目的なのである。その上で、河村市長がなぜ「木造」にこだわるかと言えば、観光目的だろう。静岡県の掛川城が1994年に木造で再建され、観光地として大きな注目を集めた。そのため、当選直後から木造再建を言いだし、当初は2020年東京五輪までを目標としていた。戦前の国宝時代に詳細な調査が行われており、技術的には可能だとされる。
このバリアフリー問題もずっと揉めているが、文化庁の許可が出ないのは違う問題だという。工事のために江戸時代に作られた石垣を崩すことが問題視され、文化庁の解体、木造再建の許可が出ないまま数年が経っている。それが解決しないうちは解体工事にも入れない。名古屋城は全体として「特別史跡」に指定されているが、天守閣自体は昔のものが失われているので国宝でも重要文化財でも何でもない。史跡としての意味はなく、文化財としての扱いは「博物館施設」に過ぎない。
名古屋城には焼失を免れた櫓なども残っているが、そこにエレベーターを設置せよという話はない。市長が「史実に忠実な復元」と呼んでも、それは実は「博物館」なんだから、障害者や高齢者にも可能な限りアクセス出来るものが求められるのである。何故なら、日本は「障害者権利条約」を批准していて、「障害者差別解消法」も制定されているからである。「史実に忠実」なら、そもそも公開も出来ない。内部を博物館として解説パネルなどを設置するのもおかしくなる。しかし、観光施設として作るんだったら、現代ではエレベーター設置は必須のはずである。
今回の討論会は「住民基本台帳から無作為に選んだ18歳以上の参加希望者約40人」が参加したという。だから特定の団体関係者が押しかけて来たわけではない。そのことが深刻なのである。参加者の中から「差別発言」があったのは、愛知トリエンナーレ問題、その後の大村知事リコール問題などを見て、発言者は河村市長は「自分の味方」だと認識していたからだと思う。先のLGBT法に使われた「不当な差別」はいけないが、「史実に忠実な」復元だからエレベーターがなくても「不当」ではない。それを批判する障害者の方が「不当な言いがかり」であるという意識である。
例えば、討論会参加者に事前に「障害者権利条約」の条文を配布していただろうか。そういうことが大切で、そこを前提にして議論しないからおかしくなる。この問題はもう時間も長くなっていて、解体工事も出来ないのに、契約した会社(竹中工務店)にはお金を払っているという。エレベーターは出来る限り上の方まで設置するようにして、早く石垣問題を解決するべきだ。名古屋城には僕も昔行っているが、今の城ブームの中でむしろ天守閣再建そのものを問うべきかと考えている。再建はあっても良いが、別になくても良いぐらいの気持ちである。残された石垣や櫓などの方が貴重で、天守閣再建のため石垣を壊しては本末転倒だ。