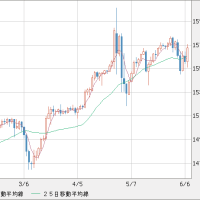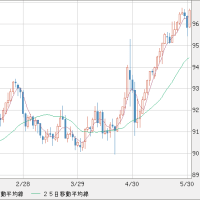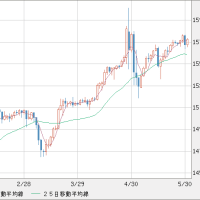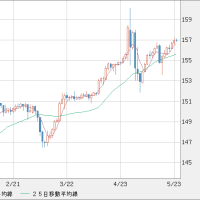年頭に相応しい報道を御紹介します。
三井造船がグローバル環境企業として
世界市場に挑もうとしているとのこと。
かつて世界の隅々までメイド・イン・ジャパンを売り込んだ
日本企業の冒険的なDNAは脈々と生きていました。
こうした果敢な試みを続ける企業がいる限り、
日本経済は大丈夫です。他所ながら応援したい。
新技術取り入れた太陽熱発電所で世界市場へ参入・三井造船(日本経済新聞)
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20091220AT1D1900D19122009.html
”米国西部や地中海周辺など、豊富な日射が得られる地域で太陽熱発電所の建
設が進みつつある。太陽の光を反射鏡で集めて高熱を作り出し、お湯を沸か
して発電機を回す。アイデア自体は古いが、技術革新で再び注目されている。
溶融塩という特殊な液体を、熱を運んだり蓄えたりするのに利用するのが新
しい。
三井造船はアラブ首長国連邦(UAE)のアブダビで日本の研究者が考案し
たユニークな太陽熱プラントの建設を請け負い、それを契機に太陽熱発電の
世界市場への参入を宣言した。同社機械・システム事業本部の奥幸之介事業
開発部長に太陽熱発電の市場やアブダビ・プロジェクトの中身などを聞いた。
――太陽熱発電は、日本国内でこそ太陽光発電(太陽電池)に比べて、注目
されていませんが、海外では動きが活発ですね。
「世界的にブームが起きている。将来の市場規模については、絵に描いた餅
に過ぎないという人もいるが、2008年の世界の太陽熱発電の設備能力(電気
出力)は600メガワット(メガは100万)程度だったが、12年には3~5ギ
ガワット(ギガは10億)、20年には16~28ギガワットに成長するといわれ
ている」
「米国とスペインで建設計画が活発で、UAEやオーストラリア、リビアな
どでも大きな計画が動いている。米国ではカリフォルニアやネバダ、アリゾ
ナなどの州で次々とプラントの建設が進む」
「国際エネルギー機関(IEA)が08年に出した報告書で、仮に2050年時点
の世界の二酸化炭素(CO2)排出量を現在と同じ水準まで抑えることを目
指すなら、250メガワット級の太陽熱発電を毎年45基ほど建設していく必要
があるとしている。50年に排出半減を目指すなら、毎年80基だ」
「1メガワット当たりの建設費を4~5億円とみて、計算すると、市場規模
は年間5~8兆円に達する」
――サハラ砂漠に発電所をつくって欧州に送るなど、海外の構想はスケール
が大きいですね。
「デザーテックと呼ばれるプロジェクトは、北アフリカ、中東で発電し、直
流送電網で欧州に電気を送り、50年までに欧州の電力の50%を賄うという。
欧州は52兆円を投資する計画とされ、送電線などのメーカーは目の色が変わ
っている」
「夢物語に聞こえるかもしれないが、北アフリカと欧州の間には、すでに海
底送電線が通っており、具体性はある。発電した現地で電気を使って、余っ
た分を欧州に送る。太陽熱発電は規模が大きいほど効率が高まるので、大き
なものをつくって余った分を送るという発想だ」
――国内では、石油ショック後に太陽熱発電の試験設備がつくられましたが、
実用化には至りませんでした。
「サンシャイン計画の四国での実験以降、日本では難しいとの見方が一般的
だ。しかし、日本にはかなりの日射量を得られる地域もあり、立地可能性は
再検討する必要がある」
――技術面でのブレークスルーがあったのですか。
「溶融塩と呼ばれる物質を太陽熱で加熱する。溶融塩はセ氏500度くらい
の高温まで液体の状態で熱を蓄える。雲が出て日射が減るくらいの変化では
熱出力が影響を受けにくく、熱い溶融塩を冷まさないよう断熱タンクに貯め
ておけば、夜間も含め24時間の運転ができる」
「大規模なプラントになれば、効率は太陽光発電をしのぐことになる。悪天
候が2~3日続いて溶融塩が固まってしまうのを避けるため、加熱用の補助
ボイラーを備える必要はあるが、潜在力は大きい」
――溶融塩とはどんなものなのですか。
「高温で液体になる特殊な塩のことで、化学プラントなどで広く使われてい
る。太陽熱発電プラントに適した性質を持つ組成の溶融塩を採用している」
――アブダビに建設中のプラントの特徴は。
「見るからに未来的な外観をしており、現在のタワー型の一歩先を行くプラ
ントだ。太陽光を2回反射させるビームダウン型の構造が特徴だ。タワー式
のデメリットを克服しようと東京工業大学の玉浦裕教授らが考案、採用され
たプロジェクトで、三井造船が建設を請け負っている」
〔中略〕
――三井造船が太陽熱発電分野に参入することになった経緯は。
「電子制御やメカトロニクスの技術を生かして、03年から太陽光の採光装置
をつくってきた。採光装置は例えば、マンション建設で日陰になった学校の
校庭に光を届けることなどに使う装置で、太陽を追尾し、同じ場所を照らし
続ける。これは太陽光発電用のヘリオスタット(平面反射鏡)と基本的に同
じ技術だ」
「07年に東工大とコスモ石油がアブダビのマスダール計画に参加、先進的な
ゼロエミッション技術の実証のために提案した計画が採用された。マスダー
ル社とコスモ石油が資金を折半して進めており、プラントの建設にあたって、
三井造船のヘリオスタット技術が注目されたという経緯だ」
「アブダビだけでなく世界に、反射効率に優れたヘリオスタットを売り込ん
でいく。溶融塩を流すレシーバーを作れるメーカーは世界でもまだ数が少な
いが、三井造船は化学プラント用に溶融塩を扱う実績があり、画期的なレシ
ーバーを実用化していく」”
私の知る限りでは、太陽熱発電は太陽電池に比べて
「発電コストが低く、効率的(但し初期投資は大)」
「太陽電池と違い、24時間発電できる」
「砂漠のような不毛の土地を活用できる」
という重要な3つの優位性を持っています。
○太陽熱発電のマーケットには巨大な成長余地がある
○海外で巨大プロジェクトが次々と立ち上がっている
○三井造船は太陽熱発電の中核的技術の一つを持っている
上記の記事を纏めると以上のようになるのでしょう。
スペースの都合で一部を割愛していますし、
元記事は素晴らしい図も付いておりますので
是非そちらもお読み下さい。
日本でも北海道の太平洋側、四国や南九州は
広大な土地と良好な日照条件が揃っているのですから、
この太陽熱発電の実証プラントを誘致した方がいいと思います。
▽ この本の続編が必要になるかも。
三井造船がグローバル環境企業として
世界市場に挑もうとしているとのこと。
かつて世界の隅々までメイド・イン・ジャパンを売り込んだ
日本企業の冒険的なDNAは脈々と生きていました。
こうした果敢な試みを続ける企業がいる限り、
日本経済は大丈夫です。他所ながら応援したい。
新技術取り入れた太陽熱発電所で世界市場へ参入・三井造船(日本経済新聞)
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20091220AT1D1900D19122009.html
”米国西部や地中海周辺など、豊富な日射が得られる地域で太陽熱発電所の建
設が進みつつある。太陽の光を反射鏡で集めて高熱を作り出し、お湯を沸か
して発電機を回す。アイデア自体は古いが、技術革新で再び注目されている。
溶融塩という特殊な液体を、熱を運んだり蓄えたりするのに利用するのが新
しい。
三井造船はアラブ首長国連邦(UAE)のアブダビで日本の研究者が考案し
たユニークな太陽熱プラントの建設を請け負い、それを契機に太陽熱発電の
世界市場への参入を宣言した。同社機械・システム事業本部の奥幸之介事業
開発部長に太陽熱発電の市場やアブダビ・プロジェクトの中身などを聞いた。
――太陽熱発電は、日本国内でこそ太陽光発電(太陽電池)に比べて、注目
されていませんが、海外では動きが活発ですね。
「世界的にブームが起きている。将来の市場規模については、絵に描いた餅
に過ぎないという人もいるが、2008年の世界の太陽熱発電の設備能力(電気
出力)は600メガワット(メガは100万)程度だったが、12年には3~5ギ
ガワット(ギガは10億)、20年には16~28ギガワットに成長するといわれ
ている」
「米国とスペインで建設計画が活発で、UAEやオーストラリア、リビアな
どでも大きな計画が動いている。米国ではカリフォルニアやネバダ、アリゾ
ナなどの州で次々とプラントの建設が進む」
「国際エネルギー機関(IEA)が08年に出した報告書で、仮に2050年時点
の世界の二酸化炭素(CO2)排出量を現在と同じ水準まで抑えることを目
指すなら、250メガワット級の太陽熱発電を毎年45基ほど建設していく必要
があるとしている。50年に排出半減を目指すなら、毎年80基だ」
「1メガワット当たりの建設費を4~5億円とみて、計算すると、市場規模
は年間5~8兆円に達する」
――サハラ砂漠に発電所をつくって欧州に送るなど、海外の構想はスケール
が大きいですね。
「デザーテックと呼ばれるプロジェクトは、北アフリカ、中東で発電し、直
流送電網で欧州に電気を送り、50年までに欧州の電力の50%を賄うという。
欧州は52兆円を投資する計画とされ、送電線などのメーカーは目の色が変わ
っている」
「夢物語に聞こえるかもしれないが、北アフリカと欧州の間には、すでに海
底送電線が通っており、具体性はある。発電した現地で電気を使って、余っ
た分を欧州に送る。太陽熱発電は規模が大きいほど効率が高まるので、大き
なものをつくって余った分を送るという発想だ」
――国内では、石油ショック後に太陽熱発電の試験設備がつくられましたが、
実用化には至りませんでした。
「サンシャイン計画の四国での実験以降、日本では難しいとの見方が一般的
だ。しかし、日本にはかなりの日射量を得られる地域もあり、立地可能性は
再検討する必要がある」
――技術面でのブレークスルーがあったのですか。
「溶融塩と呼ばれる物質を太陽熱で加熱する。溶融塩はセ氏500度くらい
の高温まで液体の状態で熱を蓄える。雲が出て日射が減るくらいの変化では
熱出力が影響を受けにくく、熱い溶融塩を冷まさないよう断熱タンクに貯め
ておけば、夜間も含め24時間の運転ができる」
「大規模なプラントになれば、効率は太陽光発電をしのぐことになる。悪天
候が2~3日続いて溶融塩が固まってしまうのを避けるため、加熱用の補助
ボイラーを備える必要はあるが、潜在力は大きい」
――溶融塩とはどんなものなのですか。
「高温で液体になる特殊な塩のことで、化学プラントなどで広く使われてい
る。太陽熱発電プラントに適した性質を持つ組成の溶融塩を採用している」
――アブダビに建設中のプラントの特徴は。
「見るからに未来的な外観をしており、現在のタワー型の一歩先を行くプラ
ントだ。太陽光を2回反射させるビームダウン型の構造が特徴だ。タワー式
のデメリットを克服しようと東京工業大学の玉浦裕教授らが考案、採用され
たプロジェクトで、三井造船が建設を請け負っている」
〔中略〕
――三井造船が太陽熱発電分野に参入することになった経緯は。
「電子制御やメカトロニクスの技術を生かして、03年から太陽光の採光装置
をつくってきた。採光装置は例えば、マンション建設で日陰になった学校の
校庭に光を届けることなどに使う装置で、太陽を追尾し、同じ場所を照らし
続ける。これは太陽光発電用のヘリオスタット(平面反射鏡)と基本的に同
じ技術だ」
「07年に東工大とコスモ石油がアブダビのマスダール計画に参加、先進的な
ゼロエミッション技術の実証のために提案した計画が採用された。マスダー
ル社とコスモ石油が資金を折半して進めており、プラントの建設にあたって、
三井造船のヘリオスタット技術が注目されたという経緯だ」
「アブダビだけでなく世界に、反射効率に優れたヘリオスタットを売り込ん
でいく。溶融塩を流すレシーバーを作れるメーカーは世界でもまだ数が少な
いが、三井造船は化学プラント用に溶融塩を扱う実績があり、画期的なレシ
ーバーを実用化していく」”
私の知る限りでは、太陽熱発電は太陽電池に比べて
「発電コストが低く、効率的(但し初期投資は大)」
「太陽電池と違い、24時間発電できる」
「砂漠のような不毛の土地を活用できる」
という重要な3つの優位性を持っています。
○太陽熱発電のマーケットには巨大な成長余地がある
○海外で巨大プロジェクトが次々と立ち上がっている
○三井造船は太陽熱発電の中核的技術の一つを持っている
上記の記事を纏めると以上のようになるのでしょう。
スペースの都合で一部を割愛していますし、
元記事は素晴らしい図も付いておりますので
是非そちらもお読み下さい。
日本でも北海道の太平洋側、四国や南九州は
広大な土地と良好な日照条件が揃っているのですから、
この太陽熱発電の実証プラントを誘致した方がいいと思います。
▽ この本の続編が必要になるかも。
 | 『日本経済の勝ち方 太陽エネルギー革命』(村沢義久,文藝春秋) |