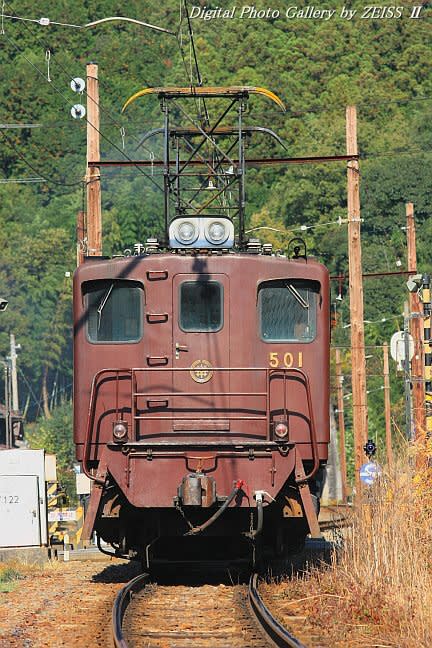『特急スペーシア通過!』
(1)

向島百花園の帰りに浅草行きの電車を東向島駅で待っていると、東武鉄道が誇る「スペーシア」がやって来ました。
駅の先には急カーブが待ち構えていますので、かなりスピードを落として通過していきます。
「しずしずと」といった表現がピッタリですね。
撮影地:東京都墨田区東向島四丁目「東武伊勢崎線東向島駅」(共通)
撮影機材:コニカミノルタ・ディマージュA200(共通)
撮影データ:ISO50 プログラムAE(SS1/320秒 f/4.0) -0.3EV 200㎜相当
撮影年月日:2008年3月22日(土)
(2)

駅を通過して右への急カーブに進入していくところです。
辛うじて全編成を入れることが出来ました。
一眼レフと違って、A200はシャッターのタイムラグが大きいので冷や冷やしました。
撮影データ:ISO50 プログラムAE(SS1/400秒 f/4.5) -0.3EV 200㎜相当
(3)

さらに進んで、北千住行き下り普通電車とすれ違います。
う~ん、ピッタリと揃わなかったかぁ・・・orz
東向島駅は白鬚駅や玉ノ井駅と名乗っていましたが、1987年に現在の駅名に改称されました。
現在でも、駅名標の下に「旧玉ノ井」と表示されているのは興味深いですね。
撮影データ:ISO50 プログラムAE(SS1/320秒 f/5.0) -0.3EV 200㎜相当
(4)

その普通電車はメタリックな感じの車体が印象的でした。
ワイド側で撮影しましたので全編成が収まりました。
こうやって鉄道写真を撮影すると心躍るものがあります。
何しろ私の写真の原点は鉄道写真ですから・・・
撮影データ:ISO50 プログラムAE(SS1/160秒 f/5.0) 0.0EV 28㎜相当
(1)

向島百花園の帰りに浅草行きの電車を東向島駅で待っていると、東武鉄道が誇る「スペーシア」がやって来ました。
駅の先には急カーブが待ち構えていますので、かなりスピードを落として通過していきます。
「しずしずと」といった表現がピッタリですね。
撮影地:東京都墨田区東向島四丁目「東武伊勢崎線東向島駅」(共通)
撮影機材:コニカミノルタ・ディマージュA200(共通)
撮影データ:ISO50 プログラムAE(SS1/320秒 f/4.0) -0.3EV 200㎜相当
撮影年月日:2008年3月22日(土)
(2)

駅を通過して右への急カーブに進入していくところです。
辛うじて全編成を入れることが出来ました。
一眼レフと違って、A200はシャッターのタイムラグが大きいので冷や冷やしました。
撮影データ:ISO50 プログラムAE(SS1/400秒 f/4.5) -0.3EV 200㎜相当
(3)

さらに進んで、北千住行き下り普通電車とすれ違います。
う~ん、ピッタリと揃わなかったかぁ・・・orz
東向島駅は白鬚駅や玉ノ井駅と名乗っていましたが、1987年に現在の駅名に改称されました。
現在でも、駅名標の下に「旧玉ノ井」と表示されているのは興味深いですね。
撮影データ:ISO50 プログラムAE(SS1/320秒 f/5.0) -0.3EV 200㎜相当
(4)

その普通電車はメタリックな感じの車体が印象的でした。
ワイド側で撮影しましたので全編成が収まりました。
こうやって鉄道写真を撮影すると心躍るものがあります。
何しろ私の写真の原点は鉄道写真ですから・・・
撮影データ:ISO50 プログラムAE(SS1/160秒 f/5.0) 0.0EV 28㎜相当