相撲(すもう)の土俵と女性について
| 動画で學ぶ◇倭塾・百人一首塾動画配信サービス |
| 週一の特別講座◇ねずさんのメールマガジン |
http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-3720.html
ただ批判したり、変えろと声高に叫ぶのではなく、伝統文化にはちゃんとそうした伝統が生まれた背景と理由があるのです。
市長ともあろう方なら、そうしたことをしっかりと勉強したうえで、発言をしてもらいたいものです。
ただ批判したり、変えろと声高に叫ぶのではなく、伝統文化にはちゃんとそうした伝統が生まれた背景と理由があるのです。
市長ともあろう方なら、そうしたことをしっかりと勉強したうえで、発言をしてもらいたいものです。

(画像はクリックすると、お借りした当該画像の元ページに飛ぶようにしています。
画像は単なるイメージで本編とは関係のないものです。)
4月7日(土)18:30 第25回 百人一首塾
4月15日(日)13:30 チャンネルAJER「古事記に学ぶ日本型経営学」
4月22日(日)13:30 第50回記念 倭塾公開講座
5月5日(土)18:30〜 第26回百人一首塾(公開講座)
5月19日(土)18:30 第51回倭塾(公開講座)
6月9日(土)18:30〜 第27回 百人一首塾 公開講座
6月30日(土)13:30〜 第52回 倭塾 公開講座
土俵で倒れた市長の救命のために看護師の女性が土俵に上り、その後に塩でお清めが行われたことが話題となっています。
緊急時の救命活動と伝統とどっちが大事なのかといった世論誘導ともとれる報道がなされていますが、なぜ土俵が女人禁制なのか、今日は、そこのところを考えてみたいと思います。
我が国と相撲(すもう)の歴史は、古くは『古事記』の葦原中国平定の神語にまでさかのぼります。
建御雷神(たけみかつちのかみ)に出雲の建御名方神(たけみなかたのかみ)が、
「然欲為力競(ちからくらべをなすことをほっする)」
と言って、建御雷神の腕をとって投げようとしたという神事が発端になります。
このあと建御名方神が諏訪にお鎮まりになられて、諏訪大社の御祭神となられています。
それが何百年前のことなのか、いまではまったくわかりませんが、すくなくとも初代天皇であられる神武天皇が即位されたよりも古い時代ですから紀元前7世紀よりも、もっとずっと古い昔から続く、相撲は我が国の伝統神事となっているわけです。
「相撲の始祖」とされているのは、野見宿禰(のうみのすくね)と当麻蹴速(とうまのけはや)です。
この試合は紀元前23年の垂仁天皇の時代にあった出来事です。
野見宿禰は、天穂日命(あめのほひのみこと)の一四世の子孫と伝えられる出雲国の勇士です。
このことは日本書紀に詳しく書かれていますので、現代語に訳してみます。
第11代垂仁天皇(すいにんてんのう)が即位して7年経った7月7日のこと、天皇の近習が、
「當麻邑(とうまむら)に當摩蹶速(とうまのけはや)という名のおそろしく勇敢な人がいて、力が強く、日頃から周囲の人に国中を探しても我が力に比べる者はいない。
どこかに強力者(ちからこわきもの)がいたら、死生を問わずに全力で争力(ちからくらべ)をしたいものだ」と言っていると述べました。
天皇はこを聞くと、
「朕も聞いている。
當摩蹶速(とうまのけはや)は天下の力士という。
果たしてこの人に並ぶ力士はいるだろうか」と群卿に問いました。
一人の臣が言いました。
「聞けば出雲国に野見宿禰(のみのすくね)という勇士がいるそうです。
この人を試しに召して蹶速(けはや)と当たらせてみたらいかがでしょう。」
そこで倭直(やまとのあたい)の先祖の長尾市(ながおち)を遣(つか)わして、野見宿禰を呼び寄せました。
即日、両者は相対して立ち、それぞれが足を上げて相い踏み、激突して野見宿禰が當摩蹶速の肋骨を踏み折りました。
またその腰骨を踏み折って殺しました。
勝者となった野見宿禰には大和国の當麻の地(現奈良県葛城市當麻)を与えました。
野見宿禰は、その土地に留まって朝廷に仕えました。
(中略)
垂仁天皇の皇后であられた日葉酢媛命(ひばすひめのみこと)が崩御されたとき、殉死に代えて人の形をした土器を埋めることを提案したのも野見宿禰です。
これが皆様もよくご存知の埴輪(はにわ)の由来です。
***********
というわけで、相撲は埴輪(はにわ)の由来にもなっていたのですね。
文中に7月7日という記述がありましたが、つい最近までは毎年田植えが終わった7月に、全国の神社で、町や村の青年たちによる奉納神前相撲が行われていました。
いまでも地方に行くと、行っているところがあるようです。
これはそもそもが野見宿禰の試合に依拠するもので、田植えのあとに、神官がまず土俵を塩で清め、その土俵に村の力自慢の力士たちがあがって四股(しこ)を踏みました。
塩をまくのは、「清めの塩」で「土俵の上」の邪気を祓い清めて怪我のないように安全を祈るためのものです。
力士たちが四股(しこ)を踏むのは、四股がもともとは「醜(しこ)」で、地中の邪気を意味します。
清められた土俵の上に力士たちが上り、そこで地中の「醜」を踏みつけて「地中の」邪気を祓うのです。
そうすることで、植えた苗がすくすくと育つようにと願うのです。
土俵が女人禁制とされるのは、これは「仙人が性欲を起こすと神通力を失う」とされたことと同じです。
力士は「地中の邪気を祓う」という重大な任務をもって、神通力を発揮しなければならないのです。
性にとちくるって、肝心の神通力を失ってしまったら、目も当てられません。
「土俵が女人禁制」であるということについて、「女性蔑視だ」とか「女神がヤキモチ焼く」とか騒ぎ立てるのは、全然意味が違うし、日本人的な考え方でさえもありません。
ChinaやKoreaでは、大地は女神とされています。
これは世界の多くの国も同じです。
大地が植物を生み育み、人々はそれを食して生きるのです。
恵みを与えてくれる=女神です。
ですから海も女神ですし、山も陸も女神です。
そして女神だと、女性の嫉妬は怖いから、女性を入れたら女神がヤキモチ焼くとされてきたわけです。
ところが日本の場合は、まったく事情が異なります。
日本は1万7千年前にはじまる縄文時代から、ずっと営みが続いてきている稀有な国です。
ひとくちに1万7千年前といいますが、それは途方もない昔です。
そんな途方もない昔から、日本人はずっと文化を継承してきているのです。
その縄文時代の生活は、いまでは考古学的に、かなり明らかになってきています。
人々はムラを営んで共同生活をするのですが、あたりまえのことですが人が生きていくためには食べ物を得なければなりません。
そこで男達は、山に猟に海に漁に出ます。
男の子は猟や漁に出られるようになったら一人前です。
猟や漁に出れないおじいさんや子供たちは、山で薪拾いをします。
女たちも、もちろん仕事があります。
山に山菜や木の実を取りに、海に貝や海藻を拾いに行くのです。
けれども身体の弱った老女や、幼い子供と、その幼子を抱える女性たちは、山や海に出かけることができません。
ですからムラで洗濯をしたり、生活用品をつくったり、みんなの食事をつくったりしました。
さて、おわかりいただけますように、老女や幼児を抱えた女性たち以外の女性たちは、山や海で食べ物を得るという生活が、我が国では万年の単位で継続してきたのです。
そのような生活しながら、山を女人禁制にする?
ありえないことです。
このように申し上げると「吉野の山のように、女人禁制の山があるではないか」と言われそうです。
実際、修行僧や修験者が山で修行する際の山は、女人禁制です。
しかしこれは意味が全然違うのです。
さきほど述べましたように、修行僧や修験者は、神通力を得るために厳しい修行をしているのであって、そこに女性を入れては修行にならないというだけの話です。
「仙人が性欲を起こすと神通力を失う」とされたことと同じです。
山で狩りをして暮らすマタギたちも、決して山に女たちを入れませんでした。
だから山の神は女性神なのだという人もいますが、これまたちょっと違います。
我が国における山の神といえば大山祇神(おほやまつみのかみ、大山津見神とも書く)です。れっきとした男性神です。
ではマタギたちがどうして山を女人禁制にしたのか。
マタギたちによっては、女性を入れないために山に入る前に男根を皆で一斉に露出するという風俗もあったそうです。
要するに女性たちに「来るな」と言っているのです。
なぜなら山には危険がいっぱいだからです。
大事な子を生み育てる女性が怪我でもしたらとりかえしがつきません。
しかしそのマタギのムラにしても、ムラの周囲の野山には女性たちは入ります。
なぜなら山菜やキノコ採りは女性たちの仕事だからです。
つまり女人禁制であることは、修行のさまたげを防いだり、山で大事な女性が怪我などをしないようにしているという、きわめて合理的な思考に基づくことであって、ChinaやKoreaのように「山が女神だから」とか「女神がヤキモチをやく」などといったアニミズムとは、まったく系統の異なることなのです。
ですから、そのような言い方をしている人は、日本の伝統文化を解しないか知らないか、日本に住みながら半島や大陸の伝統に従って生きている人たちということになります。
みっともないから、日本人ならそのような手合には乗らないことです。
土俵が子宮だから清めるのだなどという人もいるようですが、それも後講釈というべきものです。
なぜなら、そもそもなぜ土俵が子宮なのかの合理的説明がつきません。
さて今回の土俵事件では、倒れた市長さんを助けるために、女性の看護師さんたちが土俵に上がりました。
そして一定の初期手当が施されている状況で、
「女性の方は土俵から降りてください」とアナウンスがなされました。
そして倒れた市長が運び出された後、土俵には塩がまかれました。
まず、全国の各都道府県が相撲興行を呼ぶという習慣は、古い昔から我が国に続くものですが、これは土地の邪気を祓い五穀豊穣を祈るための神事としてのものです。
レクレーションではないのです。
だから地元を代表して市長さんが挨拶に立ちます。
次に舞鶴市長の挨拶は相撲興行が始まる前の開催の挨拶です。
つまり市長の挨拶のあとに、いよいよ塩で土俵を清め、力士たちが四股(醜)を踏んで、土地の邪気を祓います。
こうして、いよいよ相撲興行が始まります。
その土俵で市長が挨拶中に倒れました。
このときに緊急処置を行なうのは当然のことです。
男であるとか女であるとか、一切関係ないことです。
市長への緊急処置が終われば、当然、女性の方には土俵を降りていただき、力士の神通力を確保するために、大量の塩をまいて土俵を清めることになります。
塩をまくのは、「清めの塩」で「土俵の上」の邪気を祓い清めて怪我のないように安全を祈るためのものです。
そのうえで、力士たちが四股(醜)を踏みます。
そもそもそのために、力士たちはその土地に呼ばれて来ているのです。
そのためにも土俵は塩で清められなければなりません。
従って、相撲協会のアナウンスも、塩をまいたことも、普通の日本人の常識に照らせば、何の問題もないことです。
どこぞの女性市長が、土俵上のあいさつが断られたとして
「女性という理由で土俵の上で挨拶ができないのは悔しい。
変えるべきは変える勇気が大事」
と土俵際に用意された台の上で述べられたそうです。
勉強不足も甚だしいことです。
大相撲を、神事でなく、レクレーション興行と勘違いしています。
ただ批判したり、変えろと声高に叫ぶのではなく、伝統文化にはちゃんとそうした伝統が生まれた背景と理由があるのです。
市長ともあろう方なら、そうしたことをしっかりと勉強したうえで、発言をしてもらいたいものです。
さて昨今、相撲界は様々な出来事が連続して起きています。
相撲は神事であるだけでなく、武技のひとつでもあることは、ご理解いただけようかと思います。
その武のことを、古い大和言葉では「たける」と言いました。
わかりやすいのがヤマトタケルで、漢字では日本武尊と書きます。
「たける」というのは、「竹のように真っ直ぐにする」ことを言います。
ですから日本における武は、強さを誇るものではなく、どこまでも歪みや斜めになったものを真っ直ぐに立て直すために用いるものとされてきました。
たとえば軍隊にしてもそうで、日本の軍隊は古来、歪みを正し、物事を正道に戻すためのものとされてきたのです。
諸外国の軍や武が、王や貴族の利権保持のために用いられてきたことと、この点が大きく異なるところです。
いまの自衛隊が、被災地等で立派に活躍するのも、それは単に命令されたからではなくて、災害という歪みの中にあって、すこしでも真っ直ぐにすることに役立とうとする隊員ひとりひとりの胸中があるからといえます。
相撲も地中の醜を踏みつけ、土地を健全な「たける」土地にするために行なうものです。
だから相撲は神事なのです。
先日、東京の某八幡宮で宮司さんの刃傷沙汰がありました。
八幡さまというのは、武神です。
つまり歪みをただして、まっすぐにする神様です。
その八幡さまをお祀りした神社が金銭主義に走れば、八幡さまは当然、歪みを正すという動きとなります。
同様に、昨今の相撲界の一連の混乱も、相撲界にある何らかのおおきな歪み(何とは申しませんが)を神々がただそうとしている、真っ直ぐに「たける」を実施しようとされているのかもしれません。
相撲は神事であり、それがただの勝ち負けの興行に陥るなら、それを正そうとする見えない力が働いたとしてもおかしくはないように思えるのです。
今回の市長が土俵上で倒れるという事件も、八幡宮の事件同様、通常ではありえない事件です。
そのようなことが起きるということは、いまいちど、相撲というもの、土俵というもの、四股というものについて、女人禁制の意味から、しっかりと考え直して、真っ直ぐにただしなさい、という神様からのメッセージなのかもしれません。
歪みを竹のように真っ直ぐにただすのが日本の武なのです。
その武の代表格である国技の相撲に、歪みがあってはならないのです。
お読みいただき、ありがとうございました。










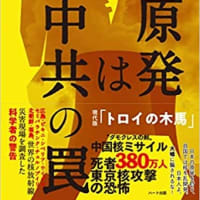
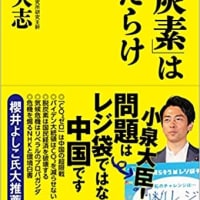
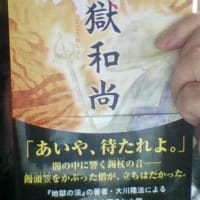






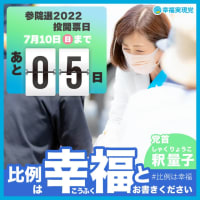
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます