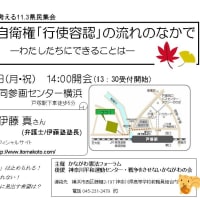“金銭的価値のついた「カード」の交換”から考えました・・・
自然界で生きる動物は
ヒナ(子ども)の自立のための教育といえば
エサの取り方。
外敵からの身の守り方。
少し前(昭和初期くらいかな)は
畑や漁仕事、家事の仕方、共同体のつき付き合い方…かな
で、現在
子どもの自立支援を考えると、「お金教育」は必須科目ですね
もちろん、学校では総合の時間などでも扱う内容でもありますが
やはり「力の見せどころ」は家庭 保護者でしょう
保護者でしょう
小学校の先生とお話をしていても
その必要性が、低年齢化の進行が著しいと実感します。
日本の歴史をみても
この列島社会では、貨幣の流通定着は決して早くはなく
近代においても、戦時中を代表するように「物々交換」の言葉が息づいています
そのためか…「お金教育」というと
「子どもが『お金』なんて言うのははしたない」
「『お金』への執着心が強くなってしまう」
等々と懸念する声や意識も強く残っていますよね
しかーし まったぁ
まったぁ なのです
なのです
「お金教育」は、しごと=生活を教えることと直結しています
働くことで、賃金・収入として「お金」が入り、それが人間生活を維持させる費用になるものですから。
これはまた別のテーマになるので、別の機会に…。
それぞれの家庭で、日常の暮らしのなかでできる「お金教育」
お金とのつきあい方(本来は「道具」なので扱い方ですね)
子どもを自立した人間に導いていくか
…が、「お金教育」の目的だと思います。
働いてお金を稼ぐ
収入内でやりくりする
貯金やその管理の方法
上手にお金を使うこと
…これらを健全にできるように成長させるのが目標ですよね。
 そこで、「はたらくこと」と「お金」は直結していくわけです
そこで、「はたらくこと」と「お金」は直結していくわけです
お金は社会生活の「道具」のひとつではあるけど
なんでも、「お金一辺倒にならないこと!」を教えることもここの要点です。
そもそも、人間の労働力(はたらく価値)までもが、お金(給料)で推し量ることに疑問もあること。
何より「お金に使われる」のではなく、お金を上手に「道具」として使っていくこと
…を教えていくのが、お金教育ですよね

自然界で生きる動物は
ヒナ(子ども)の自立のための教育といえば
エサの取り方。
外敵からの身の守り方。
少し前(昭和初期くらいかな)は
畑や漁仕事、家事の仕方、共同体のつき付き合い方…かな
で、現在
子どもの自立支援を考えると、「お金教育」は必須科目ですね
もちろん、学校では総合の時間などでも扱う内容でもありますが

やはり「力の見せどころ」は家庭
 保護者でしょう
保護者でしょう
小学校の先生とお話をしていても
その必要性が、低年齢化の進行が著しいと実感します。
日本の歴史をみても
この列島社会では、貨幣の流通定着は決して早くはなく
近代においても、戦時中を代表するように「物々交換」の言葉が息づいています
そのためか…「お金教育」というと
「子どもが『お金』なんて言うのははしたない」
「『お金』への執着心が強くなってしまう」
等々と懸念する声や意識も強く残っていますよね

しかーし
 まったぁ
まったぁ なのです
なのです「お金教育」は、しごと=生活を教えることと直結しています
働くことで、賃金・収入として「お金」が入り、それが人間生活を維持させる費用になるものですから。
これはまた別のテーマになるので、別の機会に…。
それぞれの家庭で、日常の暮らしのなかでできる「お金教育」
お金とのつきあい方(本来は「道具」なので扱い方ですね)
子どもを自立した人間に導いていくか
…が、「お金教育」の目的だと思います。
働いてお金を稼ぐ
収入内でやりくりする
貯金やその管理の方法
上手にお金を使うこと
…これらを健全にできるように成長させるのが目標ですよね。
 そこで、「はたらくこと」と「お金」は直結していくわけです
そこで、「はたらくこと」と「お金」は直結していくわけですお金は社会生活の「道具」のひとつではあるけど
なんでも、「お金一辺倒にならないこと!」を教えることもここの要点です。
そもそも、人間の労働力(はたらく価値)までもが、お金(給料)で推し量ることに疑問もあること。
何より「お金に使われる」のではなく、お金を上手に「道具」として使っていくこと
…を教えていくのが、お金教育ですよね