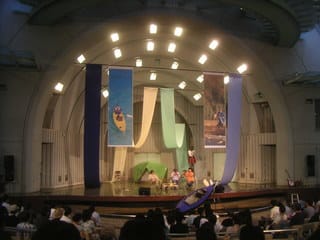2007年4月22日の投稿で、前日21日にバックパッカーのシェルパ斉藤氏の店「Team Sherpa」のトークショーを聴きに行ったことについて触れたが、その第2回が昨夜開催され、再び聴きに行ってみた。
前回はひとり参加だったが、今回は雑誌『BE-PAL』のウェブサイト内にあるメールマガジン「Air BE-PAL」の6月9日配信分でも告知されたとおり、ミニコミ誌『野宿野郎』のかとうちあき編集長を含む野宿仲間4人とともに参加した。現地への行き方はみんなバラバラだったけど。
今回も前回同様に70人ほどの参加者が集まるなか、19時15分頃から始まった。「Air BE-PAL」の効果はそんなにないようで、僕の、ひょっとしたら100人以上は来るかもしれない、という大胆予想は見事に外れた。まあこぢんまりとした催しなので、このくらいの人数がちょうどよいと思う。
今回からは斉藤さんが近況報告したあとは縁のあるゲストに登場して喋ってもらうというカタチになり、その第1回のゲストに、『BE-PAL』(以下、ビーパル)で連載を持っているつながりで、自転車世界一周の経験者であるエッセイストの石田ゆうすけ氏が招かれた。このふたりは昨夏のビーパルのイベントで一緒になったのが初めてでまだ関係性は浅いようだが、石田さんはよく引き受けたな。
斉藤さんの旅話は10年ほど前から東京都や大阪府などでの各種催しで7、8回は聴いていて聴き慣れているが、今回正式にお会いするのは初めての石田さんのほうはここ2年で東京都内のトークショーに2回行きそびれていたので、今回は3度目の正直で、どちらかと言うと石田さん目当てで行ってみた。彼が世界一周中から、本名の「石田祐輔」という名前は、世界レベルのチャリダー集団、JACC(日本アドベンチャー・サイクリストクラブ)の機関紙「ぺダリアン」をたまに読んでいて知ってはいたが(10年ほど前は、彼と待井剛氏の動向が特に目立っていたな)、実際の人と成りはどんな感じなんだろう? と帰国後にライター稼業を始めたことを知ってからはずっと気になっていた。
トークショーの内容は、石田さんが7年5か月かけて世界一周している最中に体験した、自著『行かずに死ねるか!』(実業之日本社刊)に関する話、さらにそこには挙げられなかったより細かい話を披露していた。その詳細はもちろんトークショー参加者のみの秘密ということで控えるが、僕個人的には、空砲、ツアーガイド、2リットルの水、の話が印象的であった。
さらに、『行かずに死ねるか!』の文庫版がつい最近に幻冬舎から発売されたが、その解説は椎名誠が書いていることについても(解説というよりは感想)、石田さんの旅においての観察力などをベタ褒めしている、その文中で少々本文のネタばらしをされた、帯の署名は著者である石田さんの名前よりも椎名さんの名前のほうが大きい(「権威付け」の典型例ですな)、などというくだりが面白かった。
また、その幻冬舎の社長で、出版業界の革命児的な扱われ方をされて近年注目され続けている見城徹氏が、普段よく力を入れて確認する自社の文芸書の単行本以外の文庫本にしては今回やけにこの本の販売に力を入れよ、と言っているらしい。最近特に勢いのある出版社からそんな好評価を受けるなんて、いいなあ。人気も部数もかなり少なめの僕とは大違いだ。でも僕もそれなりに頑張っているつもりなんですが。幻冬舎は最近はエッセイや旅本にも力を入れるようになり、石田さんもその勢いに上手く乗っかっている。うらやましい。
石田さんの話のあとは前回同様に、トークショー参加者全員を一巡する自己紹介大会があり、参加者は前回よりはやや多かったためか1時間以上かかった。なんか面白そうなことをやっていると聞きつけてふらっとやってきた近所の方も多かったが、二輪車で世界一周した経験のあるライダーが数人ふつうにいたりして、集まった面子は地平線会議と同様の多彩さと凄みがあった。
ちなみに、今回はかとう編集長が来ていることもあってか、店長(斉藤さんの奥様)からは自己紹介ついでにこれまでの野宿歴や印象的な野宿についても答えよ、というお達しがあり、みなさん困惑しながらもいろいろ喋っていた。ただし、これはテント泊も含めてよいとのことで、そうなると僕も『野宿野郎』5号のアンケートにも回答したとおりに400泊以上とふつうに答えたら、ちょっと驚かれた。3桁以上の数字を挙げていた人はかとう編集長や僕を含めて10人くらいだったかな。でも野宿経験が多いからと言ってもべつに偉くも何もないのだが。逆にいくらか社会から足を踏み外しかけている人だからこそ、そんなに野宿するのかもしれない。
出店のそばでは、石田さんのこれまでの著書を即売していて(『行かずに死ねるか!』の韓国語版もあった)、サインも書いていた。僕も2003年発売の単行本ではなくそれを少々書き直して新しい解釈になった? 最近発売された文庫本のほうを買った。そして、ちょっとした旅話(特に沖縄県のこと)を交しながらもサインも漏れなくいただいた。そのさいに、JACC絡みのちょっとしたおつかいも済ませることができ、これで僕の今回の任務は完了し、ここから前回と同様の手当たり次第の飲み食いを始めた。
トークショー終了後は、参加者はあとは早めに帰宅したり寝たり、起きていたい人は限りなく旅話をしたり適当に飲み食いしたり、というのが日付が変わって夜が更けても延々続いた。僕はビールと焼酎と日本酒をチャンポンしたり、余るとよろしくない焼き鳥を積極的に片付けたり、深夜1時すぎからしばらくはある女性グループが持参したマシュマロを炭火で焼いて柔らかくなった食感を楽しむ「マシュマロパーティー」に興じたりしてから、2時30分すぎに就寝。石田さんを含む数人は空が明るくなってきた4時近くまで喋っていたのだろうか。
泊まりはテントも利用できたが、天気は良いので僕らは当然ながらテントなしの野宿にこだわり(テントの設営・撤収が面倒だからということもある)、僕が就寝した3時間後の明るくなってきた5時に一度起きたがまだ誰も起きておらず、二度寝をしたりして、起床は結局8時になった。
そういえば、他人の家の敷地内で堂々と、良くも悪くも様々な人々の襲来をまったく気にする必要なく寝袋とエアマットのみで野宿できるということはめったにないことなので、今回の、ある程度の緊張感を強いられるいつもの旅の最中の野宿とは違って不安要らずで安眠できたのはとても新鮮であった。
そして朝食のあとに10時30分頃に店を離れ、解散となった。ちなみに僕は前回は往復ともにJR利用だったが、新宿←→岡谷間の高速バス利用のほうが若干安く行けて移動時間も少し短縮できるので今回、中央道日野バス停←→長坂高根バス停間を往復利用してみた。やはり予想以上に安いし速かった(僕の地元から片道、5000円弱、約4時間)。今後もこの路線には度々お世話になるだろう。
天気は先週の時点では雨が心配されたが、日に日に晴れる方向に向かい、当日は結局は2日間とも快晴で、八ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、鳳凰三山などの周囲の山の稜線もくっきり見渡すことができた。もちろん、3週間前に登った南方の富士山もバッチリ見え、14日に梅雨入りしているのがウソのような、恵まれた、というか恵まれすぎて逆に日焼けが進んだ好天のなか、今回の催しを存分に楽しむことができた。次はいつ行けるだろうか。

「Team Sherpa」に行く直前に、その最寄りの中央自動車道・長坂高根バス停付近から見た不可解な雲。すぐそばのスーパーの店員は地震の前兆である「地震雲」と言っていたが、ホントかね? まあたしかに、雨も降っていないのに虹が出ていたりしたので気にはなった。
でも結局は翌朝まで、地震も大きな天候の崩れもなく清々しい週末であったよ。

「Team Sherpa」の出店の一角にある、炭火焼き道具。七輪もある。出店の営業中は活気づくが(だいたい23時頃まで)、深夜にみなさんお腹一杯になるとほとんど見向きもされなくなるので、今度訪れる場合はここで密かに焼くための食材を持って行こうかな、と今から企んでいる。街暮らしをしていると炭火焼きをする機会はめったにないからね。

斉藤家の敷地内で野宿すると、朝はこのような光景が頭上に広がっている。天気は良く、環境も良く、まさに野宿日和であった。十数年前からシェルパ斉藤フリークである僕としては、斉藤さん家で野宿ができるなんて最近まで夢にも思わなかったよ。感無量。貴重な体験ができ、感謝であります。ぜひまた寝に行きたいものだ。
前回はひとり参加だったが、今回は雑誌『BE-PAL』のウェブサイト内にあるメールマガジン「Air BE-PAL」の6月9日配信分でも告知されたとおり、ミニコミ誌『野宿野郎』のかとうちあき編集長を含む野宿仲間4人とともに参加した。現地への行き方はみんなバラバラだったけど。
今回も前回同様に70人ほどの参加者が集まるなか、19時15分頃から始まった。「Air BE-PAL」の効果はそんなにないようで、僕の、ひょっとしたら100人以上は来るかもしれない、という大胆予想は見事に外れた。まあこぢんまりとした催しなので、このくらいの人数がちょうどよいと思う。
今回からは斉藤さんが近況報告したあとは縁のあるゲストに登場して喋ってもらうというカタチになり、その第1回のゲストに、『BE-PAL』(以下、ビーパル)で連載を持っているつながりで、自転車世界一周の経験者であるエッセイストの石田ゆうすけ氏が招かれた。このふたりは昨夏のビーパルのイベントで一緒になったのが初めてでまだ関係性は浅いようだが、石田さんはよく引き受けたな。
斉藤さんの旅話は10年ほど前から東京都や大阪府などでの各種催しで7、8回は聴いていて聴き慣れているが、今回正式にお会いするのは初めての石田さんのほうはここ2年で東京都内のトークショーに2回行きそびれていたので、今回は3度目の正直で、どちらかと言うと石田さん目当てで行ってみた。彼が世界一周中から、本名の「石田祐輔」という名前は、世界レベルのチャリダー集団、JACC(日本アドベンチャー・サイクリストクラブ)の機関紙「ぺダリアン」をたまに読んでいて知ってはいたが(10年ほど前は、彼と待井剛氏の動向が特に目立っていたな)、実際の人と成りはどんな感じなんだろう? と帰国後にライター稼業を始めたことを知ってからはずっと気になっていた。
トークショーの内容は、石田さんが7年5か月かけて世界一周している最中に体験した、自著『行かずに死ねるか!』(実業之日本社刊)に関する話、さらにそこには挙げられなかったより細かい話を披露していた。その詳細はもちろんトークショー参加者のみの秘密ということで控えるが、僕個人的には、空砲、ツアーガイド、2リットルの水、の話が印象的であった。
さらに、『行かずに死ねるか!』の文庫版がつい最近に幻冬舎から発売されたが、その解説は椎名誠が書いていることについても(解説というよりは感想)、石田さんの旅においての観察力などをベタ褒めしている、その文中で少々本文のネタばらしをされた、帯の署名は著者である石田さんの名前よりも椎名さんの名前のほうが大きい(「権威付け」の典型例ですな)、などというくだりが面白かった。
また、その幻冬舎の社長で、出版業界の革命児的な扱われ方をされて近年注目され続けている見城徹氏が、普段よく力を入れて確認する自社の文芸書の単行本以外の文庫本にしては今回やけにこの本の販売に力を入れよ、と言っているらしい。最近特に勢いのある出版社からそんな好評価を受けるなんて、いいなあ。人気も部数もかなり少なめの僕とは大違いだ。でも僕もそれなりに頑張っているつもりなんですが。幻冬舎は最近はエッセイや旅本にも力を入れるようになり、石田さんもその勢いに上手く乗っかっている。うらやましい。
石田さんの話のあとは前回同様に、トークショー参加者全員を一巡する自己紹介大会があり、参加者は前回よりはやや多かったためか1時間以上かかった。なんか面白そうなことをやっていると聞きつけてふらっとやってきた近所の方も多かったが、二輪車で世界一周した経験のあるライダーが数人ふつうにいたりして、集まった面子は地平線会議と同様の多彩さと凄みがあった。
ちなみに、今回はかとう編集長が来ていることもあってか、店長(斉藤さんの奥様)からは自己紹介ついでにこれまでの野宿歴や印象的な野宿についても答えよ、というお達しがあり、みなさん困惑しながらもいろいろ喋っていた。ただし、これはテント泊も含めてよいとのことで、そうなると僕も『野宿野郎』5号のアンケートにも回答したとおりに400泊以上とふつうに答えたら、ちょっと驚かれた。3桁以上の数字を挙げていた人はかとう編集長や僕を含めて10人くらいだったかな。でも野宿経験が多いからと言ってもべつに偉くも何もないのだが。逆にいくらか社会から足を踏み外しかけている人だからこそ、そんなに野宿するのかもしれない。
出店のそばでは、石田さんのこれまでの著書を即売していて(『行かずに死ねるか!』の韓国語版もあった)、サインも書いていた。僕も2003年発売の単行本ではなくそれを少々書き直して新しい解釈になった? 最近発売された文庫本のほうを買った。そして、ちょっとした旅話(特に沖縄県のこと)を交しながらもサインも漏れなくいただいた。そのさいに、JACC絡みのちょっとしたおつかいも済ませることができ、これで僕の今回の任務は完了し、ここから前回と同様の手当たり次第の飲み食いを始めた。
トークショー終了後は、参加者はあとは早めに帰宅したり寝たり、起きていたい人は限りなく旅話をしたり適当に飲み食いしたり、というのが日付が変わって夜が更けても延々続いた。僕はビールと焼酎と日本酒をチャンポンしたり、余るとよろしくない焼き鳥を積極的に片付けたり、深夜1時すぎからしばらくはある女性グループが持参したマシュマロを炭火で焼いて柔らかくなった食感を楽しむ「マシュマロパーティー」に興じたりしてから、2時30分すぎに就寝。石田さんを含む数人は空が明るくなってきた4時近くまで喋っていたのだろうか。
泊まりはテントも利用できたが、天気は良いので僕らは当然ながらテントなしの野宿にこだわり(テントの設営・撤収が面倒だからということもある)、僕が就寝した3時間後の明るくなってきた5時に一度起きたがまだ誰も起きておらず、二度寝をしたりして、起床は結局8時になった。
そういえば、他人の家の敷地内で堂々と、良くも悪くも様々な人々の襲来をまったく気にする必要なく寝袋とエアマットのみで野宿できるということはめったにないことなので、今回の、ある程度の緊張感を強いられるいつもの旅の最中の野宿とは違って不安要らずで安眠できたのはとても新鮮であった。
そして朝食のあとに10時30分頃に店を離れ、解散となった。ちなみに僕は前回は往復ともにJR利用だったが、新宿←→岡谷間の高速バス利用のほうが若干安く行けて移動時間も少し短縮できるので今回、中央道日野バス停←→長坂高根バス停間を往復利用してみた。やはり予想以上に安いし速かった(僕の地元から片道、5000円弱、約4時間)。今後もこの路線には度々お世話になるだろう。
天気は先週の時点では雨が心配されたが、日に日に晴れる方向に向かい、当日は結局は2日間とも快晴で、八ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、鳳凰三山などの周囲の山の稜線もくっきり見渡すことができた。もちろん、3週間前に登った南方の富士山もバッチリ見え、14日に梅雨入りしているのがウソのような、恵まれた、というか恵まれすぎて逆に日焼けが進んだ好天のなか、今回の催しを存分に楽しむことができた。次はいつ行けるだろうか。

「Team Sherpa」に行く直前に、その最寄りの中央自動車道・長坂高根バス停付近から見た不可解な雲。すぐそばのスーパーの店員は地震の前兆である「地震雲」と言っていたが、ホントかね? まあたしかに、雨も降っていないのに虹が出ていたりしたので気にはなった。
でも結局は翌朝まで、地震も大きな天候の崩れもなく清々しい週末であったよ。

「Team Sherpa」の出店の一角にある、炭火焼き道具。七輪もある。出店の営業中は活気づくが(だいたい23時頃まで)、深夜にみなさんお腹一杯になるとほとんど見向きもされなくなるので、今度訪れる場合はここで密かに焼くための食材を持って行こうかな、と今から企んでいる。街暮らしをしていると炭火焼きをする機会はめったにないからね。

斉藤家の敷地内で野宿すると、朝はこのような光景が頭上に広がっている。天気は良く、環境も良く、まさに野宿日和であった。十数年前からシェルパ斉藤フリークである僕としては、斉藤さん家で野宿ができるなんて最近まで夢にも思わなかったよ。感無量。貴重な体験ができ、感謝であります。ぜひまた寝に行きたいものだ。