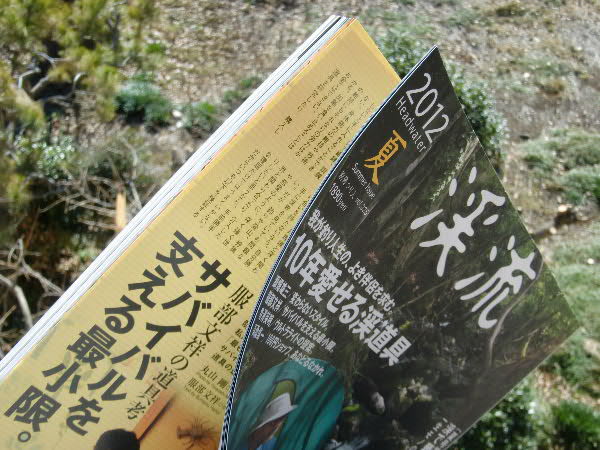今年観に行った写真展は以下。
・栂海新道を拓く(小野健、南町田、モンベルグランベリーモール店)
・Halluci Mountain -幻の山- (石川直樹、明治神宮前、EYE OF GYRE)
・第59回ニッコールフォトコンテスト入賞作品展 第2部カラー 第3部ネイチャー (新宿、新宿ニコンサロン)
・第59回ニッコールフォトコンテスト入賞作品展 第1部モノクローム 第4部U-31 (新宿、ニコンサロンbis新宿)
・奥利根抒情 ときめく季節の中へ (檜谷俊樹、新宿、ペンタックスフォーラム)
・四季逍遥 (飯倉豊啓、新宿、ペンタックスフォーラム)
・チベット・仏と牛とチョモランマ (保屋野厚、新宿、エプソンイメージングギャラリー エプサイト)
・冬陽 (千葉潤六、銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・五冊の余熱(ホトボリ) (樋口徹、銀座、銀座ニコンサロン)
・A TRIBUTE TO NATURE (ジム・ブランデンバーグ、新宿、コニカミノルタプラザ)
・光野 (丸山勇樹、新宿、新宿ニコンサロン)
・大サンパウロ (田中雄一郎、新宿、ニコンサロンbis新宿)
・菊地奈々子 元WBC世界チャンピオン 女子ボクサーの軌跡 (石渡知子、新宿、エプソンイメージングギャラリー エプサイト)
・山水の光響画 (勝山有一、新宿、ペンタックスフォーラム)
・第4回フォトアカデミー梓写真展 自然へのまなざし ~至福の瞬間~ (新宿、ペンタックスフォーラム)
・Facing Shibuya (Howard Weitzman、銀座、銀座ニコンサロン)
・High Tide (アレハンドロ・チャスキエルベルグ、銀座、リコーフォトギャラリーRING CUBE)
・RUN RUN まこと (川島小鳥、銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・津野力男写真展・前期 (津野力男、おもろまち、沖縄県立博物館・美術館)
・大和(だいわ)コレクション展II期 森山大道「新宿」 (おもろまち、沖縄県立博物館・美術館)
・丘の向こうの小さな村 ~ネパールの山村~ (佐藤敬久、新宿、コニカミノルタプラザ)
・ナティカシャ、カナシャ ~奄美の光~ (古林洋平、新宿、コニカミノルタプラザ)
・PEACE ASIA (武藤弘司、新宿、コニカミノルタプラザ)
・知らない顔 (細野晋司、銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・やがてわたしがいる場所にも草が生い茂る (石川直樹、銀座、銀座ニコンサロン)
・惨禍 -三陸沿岸部の定点記録- (和田直樹、新宿、新宿ニコンサロン)
・京都造形芸術大学通信教育部写真コース 卒業制作展 (新宿、ニコンサロンbis新宿)
・はまゆりの頃に (田代一倫、新宿、新宿ニコンサロン)
・日本写真芸術専門学校写真科フォトアート菊池東太ゼミ卒業作品展 (新宿、ニコンサロンbis新宿)
・葛飾小菅、昭和のある町 (川村容一、新宿、ペンタックスフォーラム)
・野の詩 (林潤、新宿、ペンタックスフォーラム)
・Here and There -明日の島 (新井卓、銀座、銀座ニコンサロン)
・ZERO写真展2012 (大村克巳、銀座、リコーフォトギャラリーRING CUBE)
・遠い水平線 (鷲尾和彦、新宿、新宿ニコンサロン)
・Yahoo! JAPAN 東日本大震災写真保存プロジェクト 「3.11震災と復興」写真展 (新宿、ニコンサロンbis新宿)
・子どもたちの元気便-震災からの出発 (長倉洋海、新宿、コニカミノルタプラザ)
・Under Ethiopian Skies (野町和嘉、銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・道路2011 -岩手・宮城・福島- (吉野正起、銀座、銀座ニコンサロン)
・No Curiosity, No Life (西村勇人、新宿、コニカミノルタプラザ)
・東京の片隅で (池口正和、新宿、コニカミノルタプラザ)
・PRIMROSE ~選んだ光景~ (大倉将則、新宿、コニカミノルタプラザ)
・儚き存在の証明 (平間美穂、新宿御苑前、PLACE M・メインギャラリー)
・Searchlight (林佳奈、新宿御苑前、PLACE M・ミニギャラリー)
・床屋 都会の中に息づくニッポンの技 (David Venture、新宿御苑前、M2ギャラリー)
・第17回キヤノンフォトクラブ東京フラワー写真展 季色(ときいろ)の中で (新宿御苑前、フォトギャラリーキタムラ)
・蝶の見た夢 (藤原敦、新宿御苑前、ギャラリー蒼穹舎)
・Time To Time 2008-2010 1983年からの、3年ごとの写真と詩による日録vol.9 (中島健、新宿御苑前、アイデムフォトギャラリー「シリウス」)
・大切/Comfortable pieces (コーサカトモ、新宿、エプソンイメージングギャラリー エプサイト)
・Pentax645D × EpsonPX-5V 体験イベント参加者写真展 猿島 (新宿、エプソンイメージングギャラリー エプサイト)
・Waterscape 海辺の風景 (山口史男、新宿、ペンタックスフォーラム)
・中禅寺湖の自然 (増田利夫、新宿、ペンタックスフォーラム)
・mother -まきばのお母ちゃん- (佐藤弘康、新宿、コニカミノルタプラザ)
・断章 (伊藤時男、新宿、コニカミノルタプラザ)
・ゲニウス・ロキ -地球に宿る精霊達- (角田直子、新宿、コニカミノルタプラザ)
・Fade Out Changdian/LOST WORLD (高橋ジュンコ、新宿、新宿ニコンサロン)
・2012東日本読売写真クラブ連合展 (新宿、ニコンサロンbis新宿)
・Go round Tokyo 山手線で行く (出牛敏夫、新宿、ペンタックスフォーラム)
・memento mori (冨田寿一郎、新宿、エプソンイメージングギャラリー エプサイト)
・海と人のあいだ ~After The Flood~ (小池英文、新宿、コニカミノルタプラザ)
・工場の呼吸 ~キューポラの町から~ (高橋あつこ、新宿、コニカミノルタプラザ)
・みさおとふくまる (伊原美代子、新宿、コニカミノルタプラザ)
・第31回土門拳賞受賞作品展 IN’ (高梨豊、銀座、銀座ニコンサロン)
・マグナム・フォト創設65周年記念写真展 マグナム・コンタクトシート (銀座、リコーフォトギャラリーRING CUBE)
・日本・ウズベキスタン外交関係樹立20周年記念展 (半蔵門、JCIIフォトサロン)
・雲南鄙街道 (植田英夫、半蔵門、JCIIクラブ25)
・なむとらやや (小沢竜也、新宿、コニカミノルタプラザ)
・identity (サイトウリョウ、新宿、コニカミノルタプラザ)
・第37回木村伊兵衛写真賞受賞作品展 東北 (田附勝、新宿、コニカミノルタプラザ)
・写真家たちの日本紀行2011 (銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・ソマリア 戦場に生きる人々 (瀧野恵太、新宿、新宿ニコンサロン)
・追想の地図 (神田開主、新宿、ニコンサロンbis新宿)
・散歩道 (山口繁夫、新宿、ペンタックスフォーラム)
・Leaf&Leaves2 葉っぱへのオマージュ (金城真喜子、新宿、ペンタックスフォーラム)
・Photo-Camarade 第6回仲間展 (新宿御苑前、フォトギャラリーキタムラ)
・国境なき子どもたち(KnK)写真展2012 岩手 この空の下、明日への道を探して (渋谷敦志・安田菜津紀・佐藤慧、新宿御苑前、アイデムフォトギャラリー「シリウス」)
・自然譜III (水野紘一、新宿御苑前、HCLフォトギャラリー新宿御苑)
・動物展示 ~ANIMAL DISPLAY~ (古財英昭、新宿、コニカミノルタプラザ)
・地球の上に生きる2012 -DAYS JAPAN フォトジャーナリズム写真展- (新宿、コニカミノルタプラザ)
・第18回酒田市土門拳文化賞受賞作品展 芦川-高齢・過疎の集落で-文明社会における芦川住民の精神性 (橋ぎいち、新宿、新宿ニコンサロン)
・栃木県立栃木工業高等学校写真部写真展 わが故郷(ふるさと)とちぎ (新宿、ニコンサロンbis新宿)
・カラコルムヒマラヤ大星夜 (藤田弘基、新宿、ペンタックスフォーラム)
・私的報道写真 (三澤武彦、新宿、エプソンイメージングギャラリー エプサイト)
・人の惑星(ほし) (石川梵、品川、キヤノンギャラリーS)
・日本野鳥の会写真展 「東北で、ともに生きる」 (品川、キヤノンSタワー2階オープンギャラリー)
・ROOMS floor-01 portfolio exhibition (新宿御苑前、PLACE M・メインギャラリー)
・陰と影の目 (根本真一郎、新宿御苑前、PLACE M・ミニギャラリー)
・風の皺 (冨士田錬子、新宿御苑前、M2ギャラリー)
・蜻蛉 (こくまい太、新宿御苑前、ギャラリー蒼穹舎)
・滝・幾千年を流れる (水島和實、アイデムフォトギャラリー「シリウス」)
・漆器職人の世界 (野嵜正興、新宿、東京都健康プラザハイジア・1階アートウォール)
・DISCOVERY (ミヒャエル・ポリツァ、新宿、コニカミノルタプラザ)
・『OGASAWARA』 ~小笠原、未来へつなぐ自然展~(新宿、コニカミノルタプラザ)
・砂町 (大西みつぐ、新宿、エプソンイメージングギャラリー エプサイト)
・雫景・宝石たちのメモリー (鈴木是清、新宿、ペンタックスフォーラム)
・第5回極楽蜻蛉Photoクラブ写真展 「山手線」一周カメラウォーク (新宿、ペンタックスフォーラム)
・TOKYOスナップショット (熊切圭介、六本木、ホテルアイビスミニギャラリー)
・ワスレジノアリカ (西岡潔、新宿、新宿ニコンサロン)
・帰化植物 (杉澤直哉、新宿、ニコンサロンbis新宿)
・ヤマダチ (木村肇、新宿、コニカミノルタプラザ)
・アダンの根 (西尾温、新宿、コニカミノルタプラザ)
・第13回コニカミノルタフォト・プレミオ年度賞受賞写真展 (新宿、コニカミノルタプラザ)
・旅の記憶 N-real color Z (梶山博明、渋谷、モンベル渋谷店)
・東浦奈良男写真展 (吉田智彦、神保町、iciclub神田アースプラザ)
・3×20の旅 (高島史於、新宿、エプソンイメージングギャラリー エプサイト)
・第三楽章 ~フリーハンドで描く風景~ (川村高弘、銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・New Island ~そこは風と命の島~ (野口純一、新宿、コニカミノルタプラザ)
・スクールガールジャパン (小林幹幸、新宿、ペンタックスフォーラム)
・いきものたち (吉野信、新宿、東京都健康プラザハイジア・1階アートウォール)
・新田次郎生誕100年記念写真展 新田次郎の愛した山々 富士山からスイスアルプスまで (六本木、富士フイルムフォトサロン)
・終生モダニズムを貫いた写真家 植田正治の写真世界 (六本木、写真歴史博物館)
・doughnuts企画写真展 都会の星 (東山正宜・石井ゆかり、銀座、リコーフォトギャラリーRING CUBE)
・INAYA TOL (伊ヶ崎忍、銀座、銀座ニコンサロン)
・星のある風景 (長嶋厚樹、銀座、フレームマン.ギンザ.サロン)
・リフレクションとの出逢い (慶田愛子、銀座、フレームマン.ギンザ.サロンミニギャラリー)
・第1回キヤノンフォトグラファーズセッション-キヤノン賞受賞作品展- (植田真紗美・堤賢悟、銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・カトマンズ (大山行男、新宿、エプソンイメージングギャラリー エプサイト)
・Partner and Passage (Garrett Hansen、新宿、新宿ニコンサロン)
・奇色(kiiro) (河合智子、新宿、ニコンサロンbis新宿)
・夜 (沢渡朔、新宿御苑前、PLACE M・メインギャラリー)
・CINEMA JAPON (UMA KINOSHITA、新宿御苑前、M2ギャラリー)
・365日フォトコンテスト2011(秋・冬) (新宿御苑前、フォトギャラリーキタムラ)
・After The Rain (鶴田厚博、新宿御苑前、ギャラリー蒼穹舎)
・ハチク会写真展 それぞれの顔2012 (アイデムフォトギャラリー「シリウス」)
・南極渡航のべ33回の4人による写真展 「南極の夏」 ~The Four Photographed Antarctic Summer ~ (池田宏・毛塚潤・谷ヶ崎智子・中島賢一、新宿、コニカミノルタプラザ)
・飛行機雲へ (松本明芳、新宿、コニカミノルタプラザ)
・汽罐車(きかんしゃ) ~よみがえる鉄路の記憶1963-72~ (大木茂、新宿、コニカミノルタプラザ)
・戸山公園・高尾山などの蝶の美を追い求めた写真展(第2回) (西早稲田、戸山公園屋外ギャラリー)
・Storm Last Night/Earth Rain House (津田直、品川、キヤノンギャラリーS)
・海のグレートジャーニー (関野吉晴、品川、キヤノンSタワー2階オープンギャラリー)
・ロンドンオリンピック雑誌速報写真展 (銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・古稀同人 第26回四字成句写真展 (新宿、コニカミノルタプラザ)
・楽しくなさそうにはしていない猫 ~大切なもの~ (津乗健太、新宿、コニカミノルタプラザ)
・私の武甲百景 (山口清文、新宿、コニカミノルタプラザ)
・日光 ~香りの情景~ (加藤真弓、銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・WATER (Alena Dvorakova Viktor Fischer、銀座、銀座ニコンサロン)
・あいの風吹く 黒部川扇状地の四季 (米田利昭、新宿、ペンタックスフォーラム)
・LIKE JUST A DOG (新保勇樹、新宿、コニカミノルタプラザ)
・さよ子 (濱大作、新宿、コニカミノルタプラザ)
・風に聴く ~ブラジル北東海岸~ (永竹ひかる、新宿、コニカミノルタプラザ)
・幻の島 (松井一泰、新宿、新宿ニコンサロン)
・第36回全国高等学校総合文化祭写真展 優秀作品展 (新宿、ニコンサロンbis新宿)
・ユングフラウの光と風 (織作峰子、新宿、ペンタックスフォーラム)
・『世界10大冒険』写真展 -アニマル石川と冒険仲間たち(1995-2012)- (アニマル石川、渋谷、NHKふれあいホールギャラリー)
・2012全日本山岳写真展 -未来に残そう美しい山河- (池袋、東京芸術劇場5階ギャラリー1・2)
・ARTIFACTS -日系人強制収容所からの「もの」- (渡邉博史、銀座、銀座ニコンサロン)
・西アフリカでもみんな生きている (青木仁志、新宿、エプソンイメージングギャラリー エプサイト)
・houses (石井保子、新宿、新宿ニコンサロン)
・site (津田隆志、新宿、ニコンサロンbis新宿)
・LIVING WITH NATURE (ステファノ・ウンターティナー、新宿、コニカミノルタプラザ)
・岩国・柳井・周防大島写真展 (新宿、新宿三井ビル・55SQUARE)
・記憶の行方 (八木隆、銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・マラムレシュ 家の記憶 (芦沢武仁、銀座、銀座ニコンサロン)
・ハレの日 ~秩父路だより~ (山田昇、新宿、コニカミノルタプラザ)
・海を渡るとカーニバル (丸山巌、新宿、コニカミノルタプラザ)
・Art in Ocean and Canoe (木下健二、銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・DAYS FUKUSHIMA (時津剛、銀座、銀座ニコンサロン)
・Rebuild 大槌造船記 (野田雅也、新宿、コニカミノルタプラザ)
・チャイニーズ・ドリーム (松本真理、新宿、コニカミノルタプラザ)
・コドモノクニ (齋藤亮一、新宿、コニカミノルタプラザ)
・道 OZE (JIU IWASAKI、新宿、ペンタックスフォーラム)
・遠くから来た舟 (小林紀晴、品川、キヤノンギャラリーS)
・キヤノンフォトコレクション展 前田真三写真展 (前田真三、品川、キヤノンSタワー2階オープンギャラリー)
・越冬 -命の鼓動- (山本純一、銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・写真家・石川直樹が見たバングラデシュ (石川直樹、芝公園、増上寺三縁ホール)
・FUJISAN (藤代冥砂、京橋、72Gallery)
・九十九里 (岡嶋和幸、新宿、エプソンイメージングギャラリー エプサイト)
・彩の国 ~安らぎの里山~ (荒川利夫、新宿、ペンタックスフォーラム)
・釜石呑ん兵衛横丁 -3.11 復興へ- (佐々木貴範、新宿、ペンタックスフォーラム)
・COMMONAGE (土屋友幸、新宿、新宿ニコンサロン)
・「飯舘村の暮らし」から (管野千代子、新宿、ニコンサロンbis新宿)
・東浦奈良男写真展 (吉田智彦、渋谷、モンベル渋谷店)
・旅ゆけば 東京~八戸 (秋山亮二、新宿、コニカミノルタプラザ)
・オオタカ(若鳥)展 (西早稲田、戸山公園屋外ギャラリー)
・North India (千葉雅人、新宿、コニカミノルタプラザ)
・関西札遊び (木藤富士夫、新宿、コニカミノルタプラザ)
・MY EYES ~東日本大震災。いま、私たちが思うこと~ (江田よしお・HidetakaOnoyama・クボタショウヤ・蓮見浩明・松木克信、新宿、ヨドバシフォトギャラリーINSTANCE)
・スパルタワークショップ写真展(熱血講師:小澤太一) (新宿、ヨドバシフォトギャラリーINSTANCE)
・報われない街 (比嘉ダビド久人リアオ、新宿、エプソンイメージングギャラリー エプサイト)
・Micro Landscape Part2 -アリの目で観る地上の景色- (栗林慧、新宿、ペンタックスフォーラム)
・Hello World (大塚広幸、新宿、新宿ニコンサロン)
・潜む光景 (池上洋平、新宿、ニコンサロンbis新宿)
・犬笛 (ホイキシュウ、新宿御苑前、PLACE M・メインギャラリー)
・ドッペルゲンガーの夢 (小島茂、新宿御苑前、M2ギャラリー)
・幸せな一会 ――アンコール展 (川隅勲、新宿御苑前、フォトギャラリーキタムラ)
・夢の島 夢の色 -江ノ島'79~'81- (柴田恭介、新宿御苑前、ギャラリー蒼穹舎)
・第11回写真を楽しむ仲間「せせらぎ」写真展 駅前原っぱ ~山手線各駅停車~ (アイデムフォトギャラリー「シリウス」)
・神おわします (鈴木一弘、新宿御苑前、HCLフォトギャラリー新宿御苑)
・フジフイルムスクエア企画写真展 星野道夫 アラスカ 悠久の時を旅する(六本木、富士フイルムフォトサロン)
・MAGNUMを創った写真家たち キャパ・カルティエ=ブレッソン・ロジャー・シーモア (六本木、写真歴史博物館)
・ちらがー 沖縄の素肌 (比嘉良治、銀座、銀座ニコンサロン)
・J-POWER写真展 a moment in time ~世界に伝えたい日本~ (銀座、J-POWER本店1階ロビー)
・2012第36回鉄道ファン/キヤノン フォトコンテスト入賞・佳作作品展 (銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・そら色の夢 (高砂淳二、新宿、コニカミノルタプラザ)
・冬のこだま (高橋和子、新宿御苑前、富士フォトギャラリー新宿)
・Mask Road (早川康文、新宿御苑前、PLACE M・メインギャラリー)
・Thinkings (西村勇人、新宿御苑前、M2ギャラリー)
・かのこ (松谷友美、新宿御苑前、ギャラリー蒼穹舎)
・第8回アイデム写真コンテスト はたらくすがた 2012年入選作品展 (アイデムフォトギャラリー「シリウス」)
・東京デジタルフォトクラブ 第一回記念写真展 (新宿御苑前、HCLフォトギャラリー新宿御苑)
・ズイコーデジタルアカデミー講師による OLYMPUS OM-D写真展 (淡路町、オリンパスギャラリー東京)
・KITSILANO (一之瀬ちひろ、銀座、銀座ニコンサロン)
・ゲーサンメド写真展 チベットへのいざない (銀座、フレームマン.ギンザ.サロン)・Breath of Genesis 原始小笠原 (古市智之、銀座、キヤノンギャラリー銀座)
・三木淳賞奨励賞受賞作品展 マトマニ (西岡潔、新宿、新宿ニコンサロン)
・三木淳賞奨励賞受賞作品展 大サンパウロ (田中雄一郎、新宿、ニコンサロンbis新宿)
・OH! my DIGITAL OLYMPUS OM-D E-M5に魅せられた6人による写真展 (なぎら健壱・本城直季・坂崎幸之助・石川直樹・田附勝・赤瀬川原平、淡路町、オリンパスギャラリー東京)
・異人/国東 (石川直樹、新宿御苑前、PLACE M・メインギャラリー)
・sorane 空音 (濱浦しゅう、新宿御苑前、M2ギャラリー)
・日本航空写真家協会2012写真展 SKY MOMENTS (アイデムフォトギャラリー「シリウス」)
・第34回山岳写真ASA写真展 「岳」山稜の光彩 (新宿御苑前、HCLフォトギャラリー新宿御苑)
・ペンタックスリコーフォトコンテスト展 (新宿、ペンタックスフォーラム)
・Designs (穂積大和、新宿、新宿ニコンサロン)
・maburi ~奄美の光~ (古林洋平、新宿、ニコンサロンbis新宿)
・九州産業大学大学院芸術研究科写真専攻写真展「Crux」 (新宿、コニカミノルタプラザ)
・Land's End North×South (百瀬俊哉、新宿、コニカミノルタプラザ)
今年は215本。昨年とほぼ同じ。また例年どおりに東京都内で観すぎた感はあるが、まあいいか。
そのなかでベスト10を挙げると以下。
1 みさおとふくまる (伊原美代子、新宿、コニカミノルタプラザ)
2 カラコルムヒマラヤ大星夜 (藤田弘基、新宿、ペンタックスフォーラム)
3 海のグレートジャーニー (関野吉晴、品川、キヤノンSタワー2階オープンギャラリー)
4 私的報道写真 (三澤武彦、新宿、エプソンイメージングギャラリー エプサイト)
5 マグナム・フォト創設65周年記念写真展 マグナム・コンタクトシート (銀座、リコーフォトギャラリーRING CUBE)
6 ヤマダチ (木村肇、新宿、コニカミノルタプラザ)
7 栂海新道を拓く(小野健、南町田、モンベルグランベリーモール店)
8 フジフイルムスクエア企画写真展 星野道夫 アラスカ 悠久の時を旅する(六本木、富士フイルムフォトサロン)
9 工場の呼吸 ~キューポラの町から~ (高橋あつこ、新宿、コニカミノルタプラザ)
10 ロンドンオリンピック雑誌速報写真展 (銀座、キヤノンギャラリー銀座)
『みさおとふくまる』は、この写真展の前後? から、伊原氏が連載を持つ『
DAYS JAPAN』の影響かどうかはよくわからないが外国で評価が高まり、その人気が国内に逆輸入された感じで国内でも写真集が売れているとか。僕は今春の写真展だけで1位と即断したけど。
2位に挙げた山岳(特にヒマラヤ)写真で知られる藤田氏、『岳人』で連載もあったが、今年亡くなってしまって残念。ヒマラヤの写真は好んで観ていたのに。今後の回顧展などに期待したい。
それから、昨年の震災関連の写真も、タイトルで殊更に主張するわけでもないが東北各地の風景や人物の写真を目にする機会は昨年よりも多かった。来年はさらに増えるかも。