
表題と写真を最初にご覧になられた皆様。
冒頭で、全く違った話題に触れなくてはいけません。ご容赦下さい。
「くだまき」をこれほど、放っておいたのは、昨年の入院以来のことです。ご心配もおかけいたしております。
さて、この「くだまき」のアクセスが今月に入り急増いたしました。
一時は「炎上したのではないか」と思わんばかりのアクセス数を記録致しました。
ツイッターでも話題になりました(模様です。)
では、どの記事がその対象になったのかと申しますと「究極のメニュー、至高のメニューそして酔漢のメニュー」の記事なのです。
「くだまき」が攻撃対象になったのではなく、「原作者の掘り下げ方の不備に対して酔漢が提案したことに対する意見」が殆どの様でした。
どういう使われ方をしたのか、具体的にお話しいたしますと。
「原作者の意見は主人公や海原雄山はじめ登場人物によって語られるが、その見方は偏ってはないか」こうしたものです。
実際「くだまき」では、宮城の飢饉の分析、郷土料理への偏り(宮城では「いのしし」「どじょう」を良く食すと言っているあたり・・)を指摘させていただきました。
酔漢のメニューとして提案もさせて頂きました(これはこれで、塩竃、海育ちの私でございますので、海産物に偏っておりますが)。
昨今の「美味しんぼ」の内容に対することを「うんぬん」するつもりはありません。
ここで語るのにも「大きな、多くの問題を含んでいる」話題には違いありませんが、くだまく内容にも値しないとも考えております。
今後の動向を注視して行こうかとは、考えております。
そんな中、しっかり花を愛でいている酔漢でございます。
今回は「芍薬」をご紹介いたしましょう。
芍薬には「大船系」と呼ばれる分類がございます。
酔漢が愛でいた芍薬は、自宅から車で8分ほどの距離にあります「大船フラワーセンター」の芍薬園です。
ここで誕生した品種が「大船系」と呼ばれます。
もともとは、県の園芸試験場です。
明治の終わりから昭和の初めまで、洋芍薬と和芍薬とを交配させて、600種もの園芸種がこの地で誕生致しました。
もう少し、詳しくお話しいたしますれば、県園芸試験場所長「宮澤文吾氏」の功績によるところなのです。
昨年、「菖蒲」をご紹介いたしましたが、これも同氏による交配、新種開発の結果なのです。
あまり知られるところの少ない氏ですが、芍薬、菖蒲を世に知らしめた功績は大きいものがあります。

「幽香」です。

「白玉盤」

「大谷早生」

「酔月」

「初桜」

「残春の楽しみ」

「金雲」

「暁」

「花筏」

「ペギー」

「ハワイアンコーラル」
和名ばかりではないのです。カタカナもあります。
これどうしてだかお分かりになられますでしょうか。
実は、芍薬は海外で大きな話題になるのです。
切り花としての需要が大きいことが解り、重要な輸出品になって来ます。
宮澤は、外貨獲得の品としての価値の高い芍薬の品種改良に努めます。
戦争中、贅沢品とされ、花より食糧と言われた時代。
一目を避けるように、花を残そうと、必死になった職員達の努力も忘れてはならないのです。
こんな歴史の深さも思いながら、芍薬を楽しんでまいりました。
追伸
リスナーの皆様へ
本当に放りっぱなしですみませんでした。
コメントは遅れますが、近々お返事差し上げようかと思っております。
また、ブログを認めている皆様の記事は、日々拝読させていただいております。
冒頭で、全く違った話題に触れなくてはいけません。ご容赦下さい。
「くだまき」をこれほど、放っておいたのは、昨年の入院以来のことです。ご心配もおかけいたしております。
さて、この「くだまき」のアクセスが今月に入り急増いたしました。
一時は「炎上したのではないか」と思わんばかりのアクセス数を記録致しました。
ツイッターでも話題になりました(模様です。)
では、どの記事がその対象になったのかと申しますと「究極のメニュー、至高のメニューそして酔漢のメニュー」の記事なのです。
「くだまき」が攻撃対象になったのではなく、「原作者の掘り下げ方の不備に対して酔漢が提案したことに対する意見」が殆どの様でした。
どういう使われ方をしたのか、具体的にお話しいたしますと。
「原作者の意見は主人公や海原雄山はじめ登場人物によって語られるが、その見方は偏ってはないか」こうしたものです。
実際「くだまき」では、宮城の飢饉の分析、郷土料理への偏り(宮城では「いのしし」「どじょう」を良く食すと言っているあたり・・)を指摘させていただきました。
酔漢のメニューとして提案もさせて頂きました(これはこれで、塩竃、海育ちの私でございますので、海産物に偏っておりますが)。
昨今の「美味しんぼ」の内容に対することを「うんぬん」するつもりはありません。
ここで語るのにも「大きな、多くの問題を含んでいる」話題には違いありませんが、くだまく内容にも値しないとも考えております。
今後の動向を注視して行こうかとは、考えております。
そんな中、しっかり花を愛でいている酔漢でございます。
今回は「芍薬」をご紹介いたしましょう。
芍薬には「大船系」と呼ばれる分類がございます。
酔漢が愛でいた芍薬は、自宅から車で8分ほどの距離にあります「大船フラワーセンター」の芍薬園です。
ここで誕生した品種が「大船系」と呼ばれます。
もともとは、県の園芸試験場です。
明治の終わりから昭和の初めまで、洋芍薬と和芍薬とを交配させて、600種もの園芸種がこの地で誕生致しました。
もう少し、詳しくお話しいたしますれば、県園芸試験場所長「宮澤文吾氏」の功績によるところなのです。
昨年、「菖蒲」をご紹介いたしましたが、これも同氏による交配、新種開発の結果なのです。
あまり知られるところの少ない氏ですが、芍薬、菖蒲を世に知らしめた功績は大きいものがあります。

「幽香」です。

「白玉盤」

「大谷早生」

「酔月」

「初桜」

「残春の楽しみ」

「金雲」

「暁」

「花筏」

「ペギー」

「ハワイアンコーラル」
和名ばかりではないのです。カタカナもあります。
これどうしてだかお分かりになられますでしょうか。
実は、芍薬は海外で大きな話題になるのです。
切り花としての需要が大きいことが解り、重要な輸出品になって来ます。
宮澤は、外貨獲得の品としての価値の高い芍薬の品種改良に努めます。
戦争中、贅沢品とされ、花より食糧と言われた時代。
一目を避けるように、花を残そうと、必死になった職員達の努力も忘れてはならないのです。
こんな歴史の深さも思いながら、芍薬を楽しんでまいりました。
追伸
リスナーの皆様へ
本当に放りっぱなしですみませんでした。
コメントは遅れますが、近々お返事差し上げようかと思っております。
また、ブログを認めている皆様の記事は、日々拝読させていただいております。















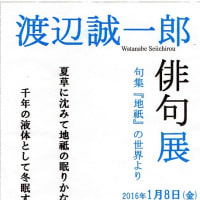

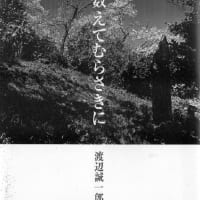








「美味しんぼ」柄見?でのアクセス数急上昇だったのでしょうね、でも驚きますよね(^_^;)。酔漢さんの記事は物事の掘り下げ方が深いのでとても読んでいて考えさせられます。私のように浅い人間にはわが身を振り返らされる部分があります。
さて芍薬。
美しいですね!花びら一枚一枚はこんなにも可憐なのに多くが集まるとその存在感に圧倒されます。
立てば芍薬・・・かつての日本女性を端的にあらわした言葉のようですね^^。
やっと、初夏らしい気温になりほっとしていますがどうも喉が痛い昨今です(^_^;)、酔漢さんにはくれぐれも御身大切にお過ごしくださいませ。