大和被弾をここで整理してみます。
「軍艦大和戦詳報」並びにアメリカ海軍の公式記録では若干被弾数が違っております。またご生還された方でも、例えば能村副長と第二艦隊宮本参謀でもその被弾数は違った証言となっております。
ラッセルスパー氏は英国ジャ-ナリストとして「戦艦大和の運命」を著されております。
まずはこの著から時系列で整理してみます。
(ラッセル・スパー著「A GLORIOUS TO DIE」和訳「戦艦大和の運命 英国人ジャーナリストのみた日本海軍 左近允尚敏 訳。新潮社)
12時41分 中型爆弾2発 後部射撃指揮所命中 臼淵大尉が戦死されております
12時45分 魚雷2本 左舷命中 大和の傾斜左舷約6度(推定)復原
13時37分 中型爆弾3発命中
魚雷3本 左舷命中
13時44分 徹甲爆弾4発命中
13時45分 魚雷左舷中部3本 右舷1本 それぞれ命中
14時02分 中型爆弾3発 左舷中部に命中
14時07分 徹甲爆弾3発命中
14時12分 魚雷2本左舷後部 1本左舷中部 1本右舷に命中(傾斜15度)
14時17分 魚雷2本右舷中部に命中
14時23分 大和沈没
各、記録により違っております。先にお断りいたします。
第一波、第一次攻撃では記録も整理されておりますが、第二次攻撃(アメリカ側からの見方ですが)では、個人個人、アメリカの搭乗員も含めて、記録が混乱しております。
大和でも、記録を取るべくすべもなく、(これでも、能村副長は懸命に整理しようと奮戦しております)被弾状況が正確には掴みきれない状況であったのだと推察いたします。
しかし、これだけの被弾数です。やはり並の戦艦ではなかったのです。
建造の過程からの視点では「なぜ大和が傾斜し、爆発したのか。そしてなぜ沈んだのか」
作戦の過程からの視点では「なぜ大和が沖縄へ出撃しなくてはならなかったのか、その為に沈ませたのか」
大和本隊からの視点では「なぜ爆撃、雷撃をかわせなかったのか、そしてなぜ沈んだのか」
「総員最上甲板の判断は遅れていなかったのか」
などなど、視点を変えても、これだけの大きな「なぜ」が出てまいります。
その「なぜ」に対する答えを多くの人が解こうとしている現在でございます。ですが、大和が沈み、爆発を起こし、酔漢祖父を含めて二七二三名(厚生省援護局 昭和41年記録)原勝洋氏、呉大和ミュージアム では二七四○名もの戦死者を出しております。
この作戦に参加しました第二水雷戦隊の戦死者数を含めますと三千七百名。
二時間にも満たない戦闘でこれだけの尊い命が失われております。
大和の戦闘までの「くだまき」は今回で最終話となります。
次回からは、本来ここからが「くだまき」な部分なのですが、私家族がどのような戦後を送ってきたかを語ります。
ここまでの語りはプロローグであったことをご理解いただきたく存じます。
さて、爆発の起こった大和です。その直前からの話です。
「総員最上甲板」が下令されております。
前檣楼が左傾した大和から海中に飛込んだが、しばらく泳ぐうちに大和の火薬庫からであろうか大爆発がおこり、この爆風というか衝撃で海上に叩きつけられて、気を失ってしまった。気がついたときは、雪風の士官室で寝込んでおり、翌八日の大詔奉載日の軍艦マーチを聞きながら起床したが、擦過傷を頭上部にうけており、血痕が枕カバーと敷布を汚していた。(渡辺光男少尉 証言 より抜粋)
大和の爆発は、多くの命を巻き込んでおりますが、また、爆発によって海中深くから海上へ浮上し、生還に至った方も大勢おられます。
副長手記を拝読いたしますれば、副長も例外ではございませんでした。
艦の傾斜は、三十五度、四十度、四十五度と、にわかに速さを増しはじめた。ついには横倒しとなり、巨鯨のような艦腹を水面にあらわして、さらに回転が続く。
沈みゆく艦を覆って奔流する怒涛の轟音。横転の瞬時に電灯は消え、真っ暗になった鉄桶の艦内では、くずれ落ちる機械器材にはさまれて、打ちたたかれつつ、奔流する海水の中で数百人の人々が死んだろう。
最上甲板で、傾いて高くなった右舷にはい上がっていった者は、一斉に海中に振り落とされて、渦に吸い込まれ、ある者は艦の下敷きとなって沈んだろう。
中部甲板に集まっていた者の中には、巨大な煙突の穴に流れ込む海水に巻き込まれて、艦内に逆戻りした者もあったろう。
わたしは第二艦橋の側壁にたったまま海水につかった、足場が下がるので、足、腹、胸、全身が水の中にはいった。そしてあわをあげながら、抵抗できない大きな力にひかれて、下へ、下へ、と吸い込まれていった。(中略)
少しずつ吐いてはとめる息が限度に来て、もう吐く息がない。実に苦しい。知覚錯乱の一歩手前だ。
突然、天地もつぶれるかと思われる重圧と真っ赤な閃光!
艦が転覆したので、弾火薬庫にあった一発一トン半の主砲弾数百発が、側壁の甲板に劇衝発火し、同時に全装薬を誘爆したものと思われる。(爆発の原因につきましては、多くの見解がありますが、ここではそのまま副長手記を掲載いたします)
無我夢中の数秒、急に水面に出た。爆発ではね上げられたのであろう。
(能村次郎 大和副長 手記より抜粋)
「爆発で助かった」これは多くの生還された方が申しております。父は、その事を多くの方から聞いております。
先の渡辺光男さん、そして三笠逸男さんもそうです。
「バンザーイ」と叫んで、その後気づいたときは海の中でした。上に行きたい。息が苦しくなって足と手をバタつかせておりまして、そりゃもう息ができないからもがいている感じだと思います。水中ではっきり明るくなるのが見えました水中です。日の光が海の中にあるように見えました。そしたらグッと体が持ちあがる。かなりの速さで水上に出ました。
(三笠逸男さん 一番副砲員 戦後慰霊祭昭和53年 靖国神社での証言。酔漢父メモより)
これよりさき私は、あの最期を寸前にむかえて大和が大爆発をおこしたその瞬間、足もとをすくわれたようになり、そのまま気が遠くなってゆくなかで、故郷の母の顔が暗雲のなかにふと浮かんできて「昌信、どうした」という大きな声を聞いたような気がした。が、そのまま気絶し、空高く吹き上げられ、海面に落ちたそのショックでようやく正気にもどったようである。(小林昌信一水 証言 手記より抜粋)
大和の艦体が真っ二つになったときの火災の熱さは、いまでもわすれられない。初霜は大和の右六○度、一五○○メートルの占位していたが、天からは船体破片が大小種々雑多、ハンドレールが、機銃の一部が、砲塔の一部が降ってくる。私は思わず鉄兜を頭につけた。
(藤井治美 初霜砲術長 証言 手記より抜粋)
生還された方もそうでなかった方も、これはまさしく紙一重のことであると。
石田恒夫少佐は、第一艦橋におりました。第二艦隊軍医長寺門正文少将は、艦橋から石田少佐に「お前も早くおりろ」と声をかけられ、その直後、第一艦橋から階下へ降りて行きます。しかしながら石田少佐は、長官休憩室へ向かった伊藤整一第二艦隊司令長官への思いが強く、しばらく第一艦橋に残ります。大和の傾斜が約50度近くになって、森下信衛第二艦隊参謀長が負傷しておられ、従兵に肩を担がれながら第一艦橋をおりようといたしますが、階段を降りる事が不可能な状態でした。石田少佐は、階段を降りるのをやめ、階段を上がることを決めます。これも運命でしょう。第一艦橋より階下へおりた方は戦死されます。寺門艦隊軍医長も同様です。階段を上がった、森下参謀長、石田副官は生還されます。
矢矧、原為一艦長は、廃材につかまりながら漂流しております。
そのとき、大和のきのこ雲を目撃しております。
「ああ大和だ。森下参謀長、有賀艦長は健在だろうか。あの様子ではまだ激しい戦闘がつづいているらしいなぁ」
等と心の中でボンヤリ考えているうちに大和の姿は消えて行った。暫くするとまた大和の艦影が視えて来た。距離が近い七、八千米。大分はっきりして大きい。矢張り前後に真白い並みを蹴立てている。二十節(ノット)は出ているなあ!と感心して見ていると、突然機関の爆発か、火薬の誘爆か、真綿のような真白い煙のかたまりが、艦の水線付近からムクムクと湧き上がったかと思うと、一瞬にして七万噸戦艦大和の巨体は、完全にこの白雲に覆われて、あたかも白雪をかぶった霊峰のように観えた。荘厳な姿に私は瞬時魂を奪われたが、その白雪はまた忽ちにして、頂上から麓に向かって拭うように消えうせて大和もろともあとかたもなくなった。
「アッ大和が!」
と思った瞬間、無気味な大音響がドシーンと、私の心臓を強く圧した。
(原為一 矢矧艦長 手記より抜粋)
前回の「くだまき」に最期の写真を掲載いたしました。「きのこ雲」の記憶は、酔漢の場合、原爆より先にこの「やまと爆発のきのこ雲」だったのです。
幼稚園の頃、祖母から「この雲の下にじいちゃんがいんだべ」と聞かされたのでした。
まだ、事の大きさが解らなかった酔漢は、「人は死んだら雲になるんだ」とその時、そう感じたのを覚えております。三千名の命がこの雲の中にいるんだと知ったのは小学校三年生の頃だったと思います。
副長手記「慟哭の海」巻末に「戦没者名簿」と「生還者名簿」が掲載されていて、酔漢祖父の名前を探すのに、探し方が解らず「第二艦隊司令部」とか「階級順」になっていることを知らなかったものですから、最初の頁の最初の名前「大将 第二艦隊司令長官 伊藤整一」から順に一人一人指をさして探したのです。祖父の名前はそから三十一頁目の中段にございました。漢字もロクに読めない頃のこの作業はしこたま疲れます。ですが、祖父の名を探そうと、必死に頁をめくりました。
(途中話がそれました・・・)
漂流中の原矢矧艦長です。
古村司令官の姿も見えなくなっています。暖流とはいうものの、春の海の冷たさが身体全部に行き渡っているようでした。
「天皇陛下万歳!」
遠くで聞こえます。
「疲労困憊で沈んで行く者の最期の声なのか」
そして、また「そら・・・耳?」
歌が聞こえてきます。
「夕焼け小焼けの赤トンボ」
大の男の叫び。
「歌うと、体力が消耗されるのだ」
そう理解しているものの、歌でも歌わなければ、自分の気力も体力も失われそうになるのです。
小雨が降ってきました。
と、そのとき、上空から爆音。
「敵機来襲。残存の駆逐艦を葬りにきやがった・・・だが!」
敵の戦闘機は低空で飛行したかと思うと、やたらと機銃を海面に向かって発射しております。
「やつらは浮かんでいる兵に銃を向けているんだ!」
原艦長は咄嗟に丸太の下にもぐりました。
海面上を跳ねる機銃弾の音が耳元で激しい音を立てております。
怒りに声を震わせます。
「そこまで、やるのか・・・」
とたんに、ふつふつとガッツが出てまいりました。
「こんなへなちょこ弾に当たってたまるか!生きてやる!」
憎悪が力となっていることに気づいた原為一矢矧艦長です。
最後の編隊が一四四三発艦しております。これは、単に機銃掃射の為に発進した戦闘機です。「血も涙もない」この攻撃には、批判が相次ぎます。
嘗て大和はレイテの際、海面に浮かんでいる米兵に機銃掃射した経緯がございます。
森下艦長は血相を変えて「何をしておるのか!」と激怒したと伝えられております。
清水副砲長は戦後、「ですがね、これが戦争。戦闘なのです」と淡々とした口調で語っておられました。
「戦争なのです」そして、これが現実なのです。
辺見じゅん氏は「この話を聞いたスプルアンスが『何と恥さらしな』と言った」と著されております(書名失念→丹治さんのコメントを待ちたいと存じます。→追加補足。下記丹治さんからのコメントにもございますが、この記述は「提督たちの大和」今野敏氏著によるものでございました。内容につきましては、丹治さんのコメントをご覧ください。)ですが、この「言葉はなかった」と確信している酔漢です。
冬月はその類まれな「六十五口径十サンチ砲」でもって無傷におります。
「真上に行くと危ない奴」その本領を発揮してました。ですが、今小雨の中。エンジンの音だけが静寂した風景の中に聞こえてきております。
第四十一駆逐隊司令「吉田正義大佐」は「いま、何をすべきか」迷っております。
「まだ、命令は変更されていない。旗艦(大和)は失った。作戦中止の命令は下されていない。我々だけで沖縄へ向かうのか」
しかし、これは不可能な戦闘力です。
「吉田司令。雪風。寺内中佐(艦長)から電文。『コレカラ如何サレル決心ナリヤ』以上」
冬月通信士「鹿士俊治中尉」は先に「大和沈没」をGFに打電しております。
艦長は山名寛雄中佐。吉田司令とはやはり名コンビでございます。
「司令、やはり、あのときと同じですな」
「艦長、そうだね」
「あのとき」とはレイテの時、冬月は、収容しきれないほどの生存者を救っております。
「艦長、もう収容するところがありません」と先任将校(当時は番井章少佐)の報告にも望遠鏡を離さず。
「おい、あそこに浮いているぞ」と艦を向かわせております。
最後の最後まであきらめず、生存者を救助する。これは、吉田司令、山名艦長ともそう信念を曲げずにおられます。
山名艦長はその時を思い出しているのでした。
「追加、通信」
「ワレ生存者ヲ救助シ、再起ヲハカラントス」
これは、残存各駆逐艦、そしてGFへも打電されます。
一三五○初霜はそれより少し前、GFへ打電。吉田司令発としております。
「一一四一ヨリ数次ニ亘ル敵艦上機大編隊ノ攻撃ヲ受ケ、大和、矢矧、磯風沈没、浜風、涼月、霞航行不能、其ノ他各艦多少ノ損害アリ。冬月、初霜、雪風を以テ生存者ヲ救助ノ後、再起ヲハカラントス」
「GFから返信が来るまで、三○分於きに発信するんだ!」
この電文は繰り返し、発信されます。
「作戦中止命令が来てからでは遅いのだ!敵機が去った今、救助するのだ」
残った駆逐艦三隻「雪風」「初霜」そして「冬月」は生存者の救助にあたります。
GF電令電令作第六一六号(16:39発令)「 1,第1遊撃部隊ノ突入作戦ヲ中止ス 2,第1遊撃部隊指揮官ハ 乗員ヲ救助シ佐世保ニ帰投スベシ」
一六二九。作戦中止命令が届きます。
午後一時ごろ、大和から「ワレ敵艦上機一○○機以上ト交戦中」との電報があり、ついで二水戦の各艦の被害状況もしだいに明らかになった。(中略)大和が午後二時五○分ごろの第二次空襲で大損害をうけ、沈没したことがわかったのは、その一時間ほどのちであった。
(時間経過に疑問を持ちます。証言手記をそのまま掲載しておりますが、「午後二時五○分」ではあまりにも遅すぎるような気がします。「午後一時五○分」であれば理解できますが、これは、記憶の違いが記述の違いかこれが事実なのか。検証することは出来ないのが残念です)
伊藤司令長官らも壮烈な戦死をとげられ、このうえ作戦の続行は不可能と判断されたので、午後四時三○分ごろに作戦中止が発令され、のこった艦は生存者を救助のうえ、佐世保に帰投するように電報した。
(市来崎秀丸 連合艦隊通信参謀 証言より抜粋)
「大和沈没」この極秘事項は知らされることのないまま、戦後を迎えることとなります。
しかしながら、多くを知ることにはならないこの事実を隠し通せるはずもございません。
大和会和歌山県世話人をお努めになられました「山東隆雄さん」の手記を見てみます。
四月七日停泊中の「呂六十四号」潜水艦に通信士として乗艦されておられます。レイテ海戦の際、「大和通信士」でした。
四月七日、波静かな瀬戸内の小島には桜が満開、なんとも穏やかな眺めである。今も各戦場では死闘が行われているのにこんなところもあるのか、何とも申し訳ない気持ちがする。(中略)一六○○呉通信隊の艦船短波系の定時連絡である発動発電機を廻し陸戦隊用のTM短波移動送受信機の調整ダイヤルを廻している時、ハワイの日本語放送が強力に入感する。
どうも大和のことを言っている様だ。ダイヤルを止めてみた「本日一四二五分大和を沖縄近海で沈めた」と勝ち誇る様に何度も何度も繰り返している。アナウンサーの声も上づっている。
一瞬脳天をバッターでそやされたような衝撃が走り、これがデマ放送であってくれたらと感ずるが、毎日受信する新聞電報の大本営海軍部発表よりぞくに言う敵のデマ放送の方が真実であり、不沈艦と云われた武蔵の沈没もこの身で体験した事実であることを思うにつけ、壮烈な艦隊特攻は成らなかったのか、紙一重の差で彼らと幽明を相隔つ乗員三千三百余名の戦友を思い深く黙とうしていた。
(山東隆雄「司令部勤務の一員として」「戦艦大和会会報瓦ばん号外」昭和五十八年十二月八日 戦艦大和会掲載 より抜粋→父資料より)
昭和二十年四月七日。宮城県七ヶ浜村 花渕。
父は叔父(父弟)共に、疎開しております。宮城はまだ桜が蕾。初春の日を過ごしております。先週呉より届いた「菓子詰め合わせ」は大事にしまっているのでした。
まだ、この戦闘の事実はもちろん「戦艦大和」の存在も知らされておりません。全ての国民に秘匿でした。まして、自身の父が最早この世に存在していないなどと考える術もないのです。
大和戦死者におきまして、宮城県出身者は十七名。(昭和四十一年厚生省援護局名簿より)大和ミュージアム、仙台護国神社十八名。祖父を含めての人数です。祖父は七ヶ浜出身者として、塩竈市ご出身者には「細谷宗蔵兵曹長」もおられました。(第二艦隊司令部。所属不明)
先にお話しいたしましたが、大和の顛末につきましては、これにて「最終話」といたします。次回からは「戦後と私どもの家族」そして「戦後の大和会と父とのつながり」を語ろうかと考えます。
私ども家族にとりまして「戦後はまだ続いている」のでした。
戦艦大和沈没地点
日本測地系 北緯三十度四十三・二分、東経百二十八度四・一分
世界測地系 北緯三十度四十三・二分、東経百二十八度四・〇分
水深三百四十五メートル。
今、奈良県天理市大和神社には、三七二一柱が国家鎮護の神として祀られております。
「軍艦大和戦詳報」並びにアメリカ海軍の公式記録では若干被弾数が違っております。またご生還された方でも、例えば能村副長と第二艦隊宮本参謀でもその被弾数は違った証言となっております。
ラッセルスパー氏は英国ジャ-ナリストとして「戦艦大和の運命」を著されております。
まずはこの著から時系列で整理してみます。
(ラッセル・スパー著「A GLORIOUS TO DIE」和訳「戦艦大和の運命 英国人ジャーナリストのみた日本海軍 左近允尚敏 訳。新潮社)
12時41分 中型爆弾2発 後部射撃指揮所命中 臼淵大尉が戦死されております
12時45分 魚雷2本 左舷命中 大和の傾斜左舷約6度(推定)復原
13時37分 中型爆弾3発命中
魚雷3本 左舷命中
13時44分 徹甲爆弾4発命中
13時45分 魚雷左舷中部3本 右舷1本 それぞれ命中
14時02分 中型爆弾3発 左舷中部に命中
14時07分 徹甲爆弾3発命中
14時12分 魚雷2本左舷後部 1本左舷中部 1本右舷に命中(傾斜15度)
14時17分 魚雷2本右舷中部に命中
14時23分 大和沈没
各、記録により違っております。先にお断りいたします。
第一波、第一次攻撃では記録も整理されておりますが、第二次攻撃(アメリカ側からの見方ですが)では、個人個人、アメリカの搭乗員も含めて、記録が混乱しております。
大和でも、記録を取るべくすべもなく、(これでも、能村副長は懸命に整理しようと奮戦しております)被弾状況が正確には掴みきれない状況であったのだと推察いたします。
しかし、これだけの被弾数です。やはり並の戦艦ではなかったのです。
建造の過程からの視点では「なぜ大和が傾斜し、爆発したのか。そしてなぜ沈んだのか」
作戦の過程からの視点では「なぜ大和が沖縄へ出撃しなくてはならなかったのか、その為に沈ませたのか」
大和本隊からの視点では「なぜ爆撃、雷撃をかわせなかったのか、そしてなぜ沈んだのか」
「総員最上甲板の判断は遅れていなかったのか」
などなど、視点を変えても、これだけの大きな「なぜ」が出てまいります。
その「なぜ」に対する答えを多くの人が解こうとしている現在でございます。ですが、大和が沈み、爆発を起こし、酔漢祖父を含めて二七二三名(厚生省援護局 昭和41年記録)原勝洋氏、呉大和ミュージアム では二七四○名もの戦死者を出しております。
この作戦に参加しました第二水雷戦隊の戦死者数を含めますと三千七百名。
二時間にも満たない戦闘でこれだけの尊い命が失われております。
大和の戦闘までの「くだまき」は今回で最終話となります。
次回からは、本来ここからが「くだまき」な部分なのですが、私家族がどのような戦後を送ってきたかを語ります。
ここまでの語りはプロローグであったことをご理解いただきたく存じます。
さて、爆発の起こった大和です。その直前からの話です。
「総員最上甲板」が下令されております。
前檣楼が左傾した大和から海中に飛込んだが、しばらく泳ぐうちに大和の火薬庫からであろうか大爆発がおこり、この爆風というか衝撃で海上に叩きつけられて、気を失ってしまった。気がついたときは、雪風の士官室で寝込んでおり、翌八日の大詔奉載日の軍艦マーチを聞きながら起床したが、擦過傷を頭上部にうけており、血痕が枕カバーと敷布を汚していた。(渡辺光男少尉 証言 より抜粋)
大和の爆発は、多くの命を巻き込んでおりますが、また、爆発によって海中深くから海上へ浮上し、生還に至った方も大勢おられます。
副長手記を拝読いたしますれば、副長も例外ではございませんでした。
艦の傾斜は、三十五度、四十度、四十五度と、にわかに速さを増しはじめた。ついには横倒しとなり、巨鯨のような艦腹を水面にあらわして、さらに回転が続く。
沈みゆく艦を覆って奔流する怒涛の轟音。横転の瞬時に電灯は消え、真っ暗になった鉄桶の艦内では、くずれ落ちる機械器材にはさまれて、打ちたたかれつつ、奔流する海水の中で数百人の人々が死んだろう。
最上甲板で、傾いて高くなった右舷にはい上がっていった者は、一斉に海中に振り落とされて、渦に吸い込まれ、ある者は艦の下敷きとなって沈んだろう。
中部甲板に集まっていた者の中には、巨大な煙突の穴に流れ込む海水に巻き込まれて、艦内に逆戻りした者もあったろう。
わたしは第二艦橋の側壁にたったまま海水につかった、足場が下がるので、足、腹、胸、全身が水の中にはいった。そしてあわをあげながら、抵抗できない大きな力にひかれて、下へ、下へ、と吸い込まれていった。(中略)
少しずつ吐いてはとめる息が限度に来て、もう吐く息がない。実に苦しい。知覚錯乱の一歩手前だ。
突然、天地もつぶれるかと思われる重圧と真っ赤な閃光!
艦が転覆したので、弾火薬庫にあった一発一トン半の主砲弾数百発が、側壁の甲板に劇衝発火し、同時に全装薬を誘爆したものと思われる。(爆発の原因につきましては、多くの見解がありますが、ここではそのまま副長手記を掲載いたします)
無我夢中の数秒、急に水面に出た。爆発ではね上げられたのであろう。
(能村次郎 大和副長 手記より抜粋)
「爆発で助かった」これは多くの生還された方が申しております。父は、その事を多くの方から聞いております。
先の渡辺光男さん、そして三笠逸男さんもそうです。
「バンザーイ」と叫んで、その後気づいたときは海の中でした。上に行きたい。息が苦しくなって足と手をバタつかせておりまして、そりゃもう息ができないからもがいている感じだと思います。水中ではっきり明るくなるのが見えました水中です。日の光が海の中にあるように見えました。そしたらグッと体が持ちあがる。かなりの速さで水上に出ました。
(三笠逸男さん 一番副砲員 戦後慰霊祭昭和53年 靖国神社での証言。酔漢父メモより)
これよりさき私は、あの最期を寸前にむかえて大和が大爆発をおこしたその瞬間、足もとをすくわれたようになり、そのまま気が遠くなってゆくなかで、故郷の母の顔が暗雲のなかにふと浮かんできて「昌信、どうした」という大きな声を聞いたような気がした。が、そのまま気絶し、空高く吹き上げられ、海面に落ちたそのショックでようやく正気にもどったようである。(小林昌信一水 証言 手記より抜粋)
大和の艦体が真っ二つになったときの火災の熱さは、いまでもわすれられない。初霜は大和の右六○度、一五○○メートルの占位していたが、天からは船体破片が大小種々雑多、ハンドレールが、機銃の一部が、砲塔の一部が降ってくる。私は思わず鉄兜を頭につけた。
(藤井治美 初霜砲術長 証言 手記より抜粋)
生還された方もそうでなかった方も、これはまさしく紙一重のことであると。
石田恒夫少佐は、第一艦橋におりました。第二艦隊軍医長寺門正文少将は、艦橋から石田少佐に「お前も早くおりろ」と声をかけられ、その直後、第一艦橋から階下へ降りて行きます。しかしながら石田少佐は、長官休憩室へ向かった伊藤整一第二艦隊司令長官への思いが強く、しばらく第一艦橋に残ります。大和の傾斜が約50度近くになって、森下信衛第二艦隊参謀長が負傷しておられ、従兵に肩を担がれながら第一艦橋をおりようといたしますが、階段を降りる事が不可能な状態でした。石田少佐は、階段を降りるのをやめ、階段を上がることを決めます。これも運命でしょう。第一艦橋より階下へおりた方は戦死されます。寺門艦隊軍医長も同様です。階段を上がった、森下参謀長、石田副官は生還されます。
矢矧、原為一艦長は、廃材につかまりながら漂流しております。
そのとき、大和のきのこ雲を目撃しております。
「ああ大和だ。森下参謀長、有賀艦長は健在だろうか。あの様子ではまだ激しい戦闘がつづいているらしいなぁ」
等と心の中でボンヤリ考えているうちに大和の姿は消えて行った。暫くするとまた大和の艦影が視えて来た。距離が近い七、八千米。大分はっきりして大きい。矢張り前後に真白い並みを蹴立てている。二十節(ノット)は出ているなあ!と感心して見ていると、突然機関の爆発か、火薬の誘爆か、真綿のような真白い煙のかたまりが、艦の水線付近からムクムクと湧き上がったかと思うと、一瞬にして七万噸戦艦大和の巨体は、完全にこの白雲に覆われて、あたかも白雪をかぶった霊峰のように観えた。荘厳な姿に私は瞬時魂を奪われたが、その白雪はまた忽ちにして、頂上から麓に向かって拭うように消えうせて大和もろともあとかたもなくなった。
「アッ大和が!」
と思った瞬間、無気味な大音響がドシーンと、私の心臓を強く圧した。
(原為一 矢矧艦長 手記より抜粋)
前回の「くだまき」に最期の写真を掲載いたしました。「きのこ雲」の記憶は、酔漢の場合、原爆より先にこの「やまと爆発のきのこ雲」だったのです。
幼稚園の頃、祖母から「この雲の下にじいちゃんがいんだべ」と聞かされたのでした。
まだ、事の大きさが解らなかった酔漢は、「人は死んだら雲になるんだ」とその時、そう感じたのを覚えております。三千名の命がこの雲の中にいるんだと知ったのは小学校三年生の頃だったと思います。
副長手記「慟哭の海」巻末に「戦没者名簿」と「生還者名簿」が掲載されていて、酔漢祖父の名前を探すのに、探し方が解らず「第二艦隊司令部」とか「階級順」になっていることを知らなかったものですから、最初の頁の最初の名前「大将 第二艦隊司令長官 伊藤整一」から順に一人一人指をさして探したのです。祖父の名前はそから三十一頁目の中段にございました。漢字もロクに読めない頃のこの作業はしこたま疲れます。ですが、祖父の名を探そうと、必死に頁をめくりました。
(途中話がそれました・・・)
漂流中の原矢矧艦長です。
古村司令官の姿も見えなくなっています。暖流とはいうものの、春の海の冷たさが身体全部に行き渡っているようでした。
「天皇陛下万歳!」
遠くで聞こえます。
「疲労困憊で沈んで行く者の最期の声なのか」
そして、また「そら・・・耳?」
歌が聞こえてきます。
「夕焼け小焼けの赤トンボ」
大の男の叫び。
「歌うと、体力が消耗されるのだ」
そう理解しているものの、歌でも歌わなければ、自分の気力も体力も失われそうになるのです。
小雨が降ってきました。
と、そのとき、上空から爆音。
「敵機来襲。残存の駆逐艦を葬りにきやがった・・・だが!」
敵の戦闘機は低空で飛行したかと思うと、やたらと機銃を海面に向かって発射しております。
「やつらは浮かんでいる兵に銃を向けているんだ!」
原艦長は咄嗟に丸太の下にもぐりました。
海面上を跳ねる機銃弾の音が耳元で激しい音を立てております。
怒りに声を震わせます。
「そこまで、やるのか・・・」
とたんに、ふつふつとガッツが出てまいりました。
「こんなへなちょこ弾に当たってたまるか!生きてやる!」
憎悪が力となっていることに気づいた原為一矢矧艦長です。
最後の編隊が一四四三発艦しております。これは、単に機銃掃射の為に発進した戦闘機です。「血も涙もない」この攻撃には、批判が相次ぎます。
嘗て大和はレイテの際、海面に浮かんでいる米兵に機銃掃射した経緯がございます。
森下艦長は血相を変えて「何をしておるのか!」と激怒したと伝えられております。
清水副砲長は戦後、「ですがね、これが戦争。戦闘なのです」と淡々とした口調で語っておられました。
「戦争なのです」そして、これが現実なのです。
辺見じゅん氏は「この話を聞いたスプルアンスが『何と恥さらしな』と言った」と著されております(書名失念→丹治さんのコメントを待ちたいと存じます。→追加補足。下記丹治さんからのコメントにもございますが、この記述は「提督たちの大和」今野敏氏著によるものでございました。内容につきましては、丹治さんのコメントをご覧ください。)ですが、この「言葉はなかった」と確信している酔漢です。
冬月はその類まれな「六十五口径十サンチ砲」でもって無傷におります。
「真上に行くと危ない奴」その本領を発揮してました。ですが、今小雨の中。エンジンの音だけが静寂した風景の中に聞こえてきております。
第四十一駆逐隊司令「吉田正義大佐」は「いま、何をすべきか」迷っております。
「まだ、命令は変更されていない。旗艦(大和)は失った。作戦中止の命令は下されていない。我々だけで沖縄へ向かうのか」
しかし、これは不可能な戦闘力です。
「吉田司令。雪風。寺内中佐(艦長)から電文。『コレカラ如何サレル決心ナリヤ』以上」
冬月通信士「鹿士俊治中尉」は先に「大和沈没」をGFに打電しております。
艦長は山名寛雄中佐。吉田司令とはやはり名コンビでございます。
「司令、やはり、あのときと同じですな」
「艦長、そうだね」
「あのとき」とはレイテの時、冬月は、収容しきれないほどの生存者を救っております。
「艦長、もう収容するところがありません」と先任将校(当時は番井章少佐)の報告にも望遠鏡を離さず。
「おい、あそこに浮いているぞ」と艦を向かわせております。
最後の最後まであきらめず、生存者を救助する。これは、吉田司令、山名艦長ともそう信念を曲げずにおられます。
山名艦長はその時を思い出しているのでした。
「追加、通信」
「ワレ生存者ヲ救助シ、再起ヲハカラントス」
これは、残存各駆逐艦、そしてGFへも打電されます。
一三五○初霜はそれより少し前、GFへ打電。吉田司令発としております。
「一一四一ヨリ数次ニ亘ル敵艦上機大編隊ノ攻撃ヲ受ケ、大和、矢矧、磯風沈没、浜風、涼月、霞航行不能、其ノ他各艦多少ノ損害アリ。冬月、初霜、雪風を以テ生存者ヲ救助ノ後、再起ヲハカラントス」
「GFから返信が来るまで、三○分於きに発信するんだ!」
この電文は繰り返し、発信されます。
「作戦中止命令が来てからでは遅いのだ!敵機が去った今、救助するのだ」
残った駆逐艦三隻「雪風」「初霜」そして「冬月」は生存者の救助にあたります。
GF電令電令作第六一六号(16:39発令)「 1,第1遊撃部隊ノ突入作戦ヲ中止ス 2,第1遊撃部隊指揮官ハ 乗員ヲ救助シ佐世保ニ帰投スベシ」
一六二九。作戦中止命令が届きます。
午後一時ごろ、大和から「ワレ敵艦上機一○○機以上ト交戦中」との電報があり、ついで二水戦の各艦の被害状況もしだいに明らかになった。(中略)大和が午後二時五○分ごろの第二次空襲で大損害をうけ、沈没したことがわかったのは、その一時間ほどのちであった。
(時間経過に疑問を持ちます。証言手記をそのまま掲載しておりますが、「午後二時五○分」ではあまりにも遅すぎるような気がします。「午後一時五○分」であれば理解できますが、これは、記憶の違いが記述の違いかこれが事実なのか。検証することは出来ないのが残念です)
伊藤司令長官らも壮烈な戦死をとげられ、このうえ作戦の続行は不可能と判断されたので、午後四時三○分ごろに作戦中止が発令され、のこった艦は生存者を救助のうえ、佐世保に帰投するように電報した。
(市来崎秀丸 連合艦隊通信参謀 証言より抜粋)
「大和沈没」この極秘事項は知らされることのないまま、戦後を迎えることとなります。
しかしながら、多くを知ることにはならないこの事実を隠し通せるはずもございません。
大和会和歌山県世話人をお努めになられました「山東隆雄さん」の手記を見てみます。
四月七日停泊中の「呂六十四号」潜水艦に通信士として乗艦されておられます。レイテ海戦の際、「大和通信士」でした。
四月七日、波静かな瀬戸内の小島には桜が満開、なんとも穏やかな眺めである。今も各戦場では死闘が行われているのにこんなところもあるのか、何とも申し訳ない気持ちがする。(中略)一六○○呉通信隊の艦船短波系の定時連絡である発動発電機を廻し陸戦隊用のTM短波移動送受信機の調整ダイヤルを廻している時、ハワイの日本語放送が強力に入感する。
どうも大和のことを言っている様だ。ダイヤルを止めてみた「本日一四二五分大和を沖縄近海で沈めた」と勝ち誇る様に何度も何度も繰り返している。アナウンサーの声も上づっている。
一瞬脳天をバッターでそやされたような衝撃が走り、これがデマ放送であってくれたらと感ずるが、毎日受信する新聞電報の大本営海軍部発表よりぞくに言う敵のデマ放送の方が真実であり、不沈艦と云われた武蔵の沈没もこの身で体験した事実であることを思うにつけ、壮烈な艦隊特攻は成らなかったのか、紙一重の差で彼らと幽明を相隔つ乗員三千三百余名の戦友を思い深く黙とうしていた。
(山東隆雄「司令部勤務の一員として」「戦艦大和会会報瓦ばん号外」昭和五十八年十二月八日 戦艦大和会掲載 より抜粋→父資料より)
昭和二十年四月七日。宮城県七ヶ浜村 花渕。
父は叔父(父弟)共に、疎開しております。宮城はまだ桜が蕾。初春の日を過ごしております。先週呉より届いた「菓子詰め合わせ」は大事にしまっているのでした。
まだ、この戦闘の事実はもちろん「戦艦大和」の存在も知らされておりません。全ての国民に秘匿でした。まして、自身の父が最早この世に存在していないなどと考える術もないのです。
大和戦死者におきまして、宮城県出身者は十七名。(昭和四十一年厚生省援護局名簿より)大和ミュージアム、仙台護国神社十八名。祖父を含めての人数です。祖父は七ヶ浜出身者として、塩竈市ご出身者には「細谷宗蔵兵曹長」もおられました。(第二艦隊司令部。所属不明)
先にお話しいたしましたが、大和の顛末につきましては、これにて「最終話」といたします。次回からは「戦後と私どもの家族」そして「戦後の大和会と父とのつながり」を語ろうかと考えます。
私ども家族にとりまして「戦後はまだ続いている」のでした。
戦艦大和沈没地点
日本測地系 北緯三十度四十三・二分、東経百二十八度四・一分
世界測地系 北緯三十度四十三・二分、東経百二十八度四・〇分
水深三百四十五メートル。
今、奈良県天理市大和神社には、三七二一柱が国家鎮護の神として祀られております。















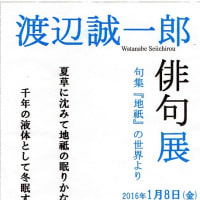

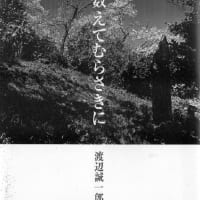







一応、長い間お疲れ様でした。
一応というのはまだ続きがある
ような気がしますので・・・。
しかし、やはり、歴史は語り継がれ
なければなりませんね。
日本がいかに戦ったかということは
学校でまったく教えないから、
もう、60代の人でもほとんど知らない状態。
大和の名は知ってても、ヤマトですからね。
マニア以外、もう日本の空母の名なんてほとんど知らない。
未だに日本は無謀な戦争をやった、
と考えている人が多いのには驚かされます。
戦死された方々の犠牲があって今がある。
亡くなられた方々は浮かばれませんね。
坂本竜馬や西郷隆盛などはもういいから、
(司馬遼の世界ももういい)から、
その後はないの?といいたいですね。
申し訳ありません。
『提督たちの大和』の著者は辺見じゅんさんではなくて今野敏さんでした。
『~たちの大和』シリーズの一冊なので、辺見じゅんさんと単純に思い込んでいたのでした。
こういう基本的なデータの確認を怠るようでは、文系の研究者は務まりません。
訂正するとともに御詫び申し上げます。
申し訳ありませんでした。
大和沈没に関して『提督たちの大和』に書いてある米側の場面の要点は次の通りです。
・ミッチャーに"You take them."と命令した後で、スプルーアンスが「デイヨにすまないと伝えてくれ」と参謀に言った。
・米軍機が漂流者を銃撃していると聞いたスプルーアン巣が激怒し、「すぐやめさせろ。ミッチャーに恥を知れ」と怒鳴った。
なお『提督たちの大和』には「小説伊藤整一」という副題がついています。
だとすればこの場面は、正確な証言に基く再構成ではなくて、
「こうあって欲しい」という今野さんの心情と考えた方がよいのかもしれません。
太平洋戦争というと、戦後のある時期から日本軍の残虐性がことさらに強調されます。
しかし次のような例もあります。
・インド洋作戦の際、木村昌福さんは鈴谷の艦長でした。攻撃した輸送船から脱出するボートを機銃で撃とうとする部下を「撃っちゃいかんぞぉ」と大声で制止しています。
・開戦初頭の南方作戦の際、坂井兵曹(当時)は民間人を載せて脱出する輸送機を逃がしています。
・太平洋を航行中の連合国側の帆船の前に伊号が浮上。万事休す。ところが伊号は「美シキ船ヨ、汝ヲ沈メルニ忍ビズ。安全ナル航海ヲ祈ル」(趣旨)と国際信号(英語だったでしょうか)で告げると、帆船の周りを一周して去っていきました(連合国側の証言)。
また連合国側がすべて人道的に振舞っていたかというと、そうでもありません。
会田雄次さんの『アーロン捕虜収容所』に書いてあることなど、その最たるものです。
また映画『硫黄島からの手紙』には、
預けられた日本兵の捕虜を、米軍の兵士が「面倒だ」と言って殺してしまう場面があります。
「日本軍は残虐だ」
「日本軍の残虐行為が裁かれのに、連合軍の残虐行為が裁かれないのはどういうことだ」
「結局米軍は黄色人種である日本人を蔑視していた。彼らがやっていたのは戦争ではなくて殺人ゲームだ」
・・・・・・・
これらはすべて、後世の者が立てた論に過ぎません。
「これが戦争、戦争なんです」という清水さんの言葉には説得力以上のものがあります。
戦後も十六年経って生れた私には想像もつかぬことですが、戦争では
「状況次第でどんなことでも起り得た」
ということなのでしょうか。
人間なら誰だって死ぬのはいやに決っています。
それでも自らの死が避けられぬと分った時、
人間は自らの死に意味を見出そうとします。
「新生日本に先駆けて散る。正に本望じゃないか」。
吉田満さんの『戦艦大和の最期』に出てくる臼淵大尉の言葉です。
臼淵さんが実際にこの言葉を口にしたかどうかはさておき、
これは特に戦争末期、戦場に赴いた若者の気持ちをよく表していると思います。
名前と内容をきちんと覚えておりませんが、
「学鷲は一応インテリです。この戦争の結末がどうなるかは分っています」
で始まる学徒出身の特攻隊員が従軍記者に残した言葉にも通じるものがあります。
今の日本はどうなってしまったのでしょうか。
戦場に散った皆さんは、このような日本を残すために命を捨てたのでしょうか。
これでは彼らが浮ばれません。
日本の現状を見るにつけ、寒心に堪えぬ思いです。
大和が徳之島沖の海底で眠りについたことで、一応の区切りですね。
御疲れ様でした。
さらなる健筆を期待しております。
その時、これを読んで更に自身の史観を確立させていってくれたらと思います。
歴史なのです。主義主張を後回しにしても、伝えるべきはあるはずだとそう信じております。
また、ご訂正ありがとうございます。大変参考になりました。
清水元副砲長は時ある度に「これは戦争なんだから」とおっしゃっておられました。
このお言葉は短いなかで大変重みのある発言です。「何でもありなんだよ」
そうなのです。「大和」も兵器である以上、その事を正しくつたえたかったに違いないのです。肉声を聞くことができた自身です。
重いものを感じます。
戦艦大和の歴史を知ることもなく 、 子供の頃大和のプラ模型 を作り風呂の湯船で遊んだものです。
動力はゴムでした。
酔漢さんのお陰で、 その歴史を知ることができました。
祖父の戦友「大高勇次」さんと一緒にお風呂に入っていた時、「おじいちゃんはこの艦のこのあたりにいたんだ」と初めて聞かされました。
祖母からは「大和さぇいたんだべ」ときかされておりましたものの、具体的には何の事か解らなかったのです。
幼稚園年長のときでした。