当時、昭和9年頃。日本はアメリカを仮想敵国としたシュミレーションを行っております。
「八八艦隊構想」(最新式の巡洋艦8隻、大型戦艦8隻となす連合艦隊構想)がワシントン条約により中止を与儀なくされ。(先にお話しました「金剛代替艦」はこの八八艦隊の主力となるべく建造される艦だったわけです)
これは海軍にとって用兵そのものを変更せざるを得ない状況でした。
「一艦の戦闘能力をアメリカ艦船の上を行く」
これは、大鑑巨砲主義の中では、しごく当然な発想でした。
艦政四部内、嘗て藤本の部下、平賀では東京大学での愛弟子であった、福田啓二は図面を書けずに悩んでおりました。
「46サンチの主砲。速力30ノット・・・可能なのか。今の技術で・・」
「福田さん、まず書いてみましょう」
江崎設計主任が言葉をかけます。
福田は、今や基本計画主任を任されている造艦学のホープでした。
そしてその部下江崎も。その卓越した設計思想は、平賀からも可愛がられ、藤本からも頼りにされておったのでした。
艦政部のバランサー。平賀と現艦政部との重要なパイプ役でもありました。
軍からの要求は以下のようなものでした。
46サンチ主砲。速力30ノット。
たったこれだけ。
しかし、46サンチという砲を搭載した艦が一体どれだけの大きさになるのか、造船学を学んだ者からすれば、未曾有な大きさになる事は容易に想像できたのでした。
昭和10年3月10日。最初の図面計画「A-140」が完成します。
公試排水量69500トン。294x41.2x10.4m(全長・全幅・全高)タービン200000軸馬力⇒速力31ノット。兵装9x46センチ(三連装) 他 割愛
「まるで、お化けのような艦」こう言われます。
技術的に不可能な部分も多く、まずは全長の見直し、速力を27ノットと致します。
「これだけの砲を搭載した場合、艦がでかすぎる。速力を30ノットを優先すればどうしても、主要兵装計画を見直さなければならない」
「それに、機関の問題もディーゼルなのかタービンなのか・・」
夜を徹した議論が続きます。
昭和10年4月1日 「A-140-B2」試案が完成。
公試排水量62000トン。247x40.4x10.3m。タービン140000軸馬力⇒速力27.5ノット他割愛
「タービンとディーゼルの併用はどうでしょう。日本はやはり4軸でなければ。これが軍艦を動かすのに一番効率がいいわけですから、二軸づつをディーゼルとタービンに分ければ・・」
ある若手研究員の発言でした。福井の頭にはなかった発想です。
「よし、試してみよう」
ここで解説を少し。プラモデルで艦船を作った方ならお解かりになられると存じますが、日本の艦船はスクリューの数が4本だと気づくと思います。ですが例えば「テルピッツ」(ドイツ海軍)であるとかは3軸であるのです。結果、大和も4軸でした。日本の艦船の特徴の1つと言えるのだと思います。
昭和10年8月10日 「A-140-O」試案が完成
公試排水量59000トン。244x38.9x10.4m。タービン55000馬力+ディーゼル55000馬力⇒速力26ノット。兵装8x46センチ(三連装x2+二連装x1)
他割愛。
その後、設計案ではタービン+ディーゼル併用が主となって設計試案が進められていくのでした。
当時、海軍には出力が1万馬力を超す強力なディーゼルエンジンを持っておりました。潜水母艦「大鯨」後の「空母 龍鳳」などに搭載されたエンジンです。ディーゼルとタービン。同じ推進力を持っていたと仮定するならばディーゼルの方が燃費が良い。ですが、機関の重量が重くなる欠点もございました。
桜が咲く前に始まった「A-140」計画。晩秋を迎えております。
昭和10年10月5日 「A-140-F3・F4」試案が完成しました。
公試排水量62545トン。248x38.9x10.4m。タービン75000軸馬力+ディーゼル60000軸馬力。速力27ノット。兵装9x46サンチ(三連装x3。前部2・後部1)
他割愛。
確かに完成時の大和に近づいております。
その後、半年、この基本設計でのシュミレーションが続きます。
「福田主任。電話です。内線です」
電話を取る福田。
「・・・判りました。」
「主任、どうされました?」
「長官だ」
「・・長官?えっ?山本長官・・・・ですか?」
「そうだ。ここに来るそうだ」
艦政四部内。大きな緊張が走ります。
ドアが開き、いつもの風体が入って来ました。やはり白い手袋は欠かしておりません。山本五十六(当時)長官です。
「福田主任」
「お久しぶりでございます」
「ジョージ五世大観以来かな?」
「よく、覚えで・・・私は末席でございましたから・・」
「率直に言おう。私は今後の海戦は空母を中心とした『機動艦隊』(話のあやです。当時まだこの言葉は定義づけされておりません)だと思うのだが・・最早大戦艦も無かろう、不沈艦はありえないのだと思うが・・資材と資金をわが国の空軍構想に当てるべきだと考えるのだが」
「お言葉ですが、長官。私達も不沈艦はありえないと考えてはおります。ですが、ですが長官、極めて沈みにくい艦。これは可能です。今ここで研究を中断したら今後の艦への進化は考えられません」
山本、ここで顔が笑うのでした。
「いや、仕事中悪かった。研究を続けたまへ」
山本、艦政部を去って行きます。
「主任、主任!長官に意見具申・・・でした・・ね」
「どうなる事かと思ったが・・」
「が?ですか?山本長官も懐の広いお方だ。私の意見を率直に聞いてくれた。さぁ研究を続けよう」
年が変わります。昭和11年。もうかれこれ1年が過ぎ、その年の夏でございます。
昭和11年7月20日。最終決定とも言える「A140-F5」試案が完成しました。
公試排水量65200トン。253x38.9x10.4m。タービン75000馬力+ディーゼル60000馬力。速力27ノット。
他割愛。
しかし、ここで思わぬ事態に直面いたしました。
「どうしても・・・・どうしたことか・・」
福田をはじめ、チーム全体がこの難局に直面いたしました。
「A-140」が出来てから、艦の防御は「バイタルアート」で進めております。これは、昨年若くして亡くなった「藤本喜久雄」の設計思想です。福田はそれを継承いたしておりました。ですが、エンジンルームは艦の命です。200mmの分厚い装甲板で覆われなければなりません。この装甲版は単に防御用としているのではなく、船体構造の一部であるため、エンジンをすえ付けたら、二度とエンジンを取り替える事が出来なくなるのでした。
「どうした・・ものか」
補足です。資源の乏しい日本では、燃費効率は出力と平行して考えなければなりませんでした。機関としてはタービンが優位な事は自明の理ではありましたが、燃費を少しでもアップさせようと、タービン+ディーゼル併用が主となっていたわけです。この両立と艦のメンテナンス。これが並び立たなくなりました。
福田。決心いたしました。
「もう私の力では、決定できない。相談しに出かけて来る」
「どちらへ・・・行くのですか?誰に・・・」
「平賀先生にだ」
「技術中将へ?ですが、今だ艦政部の中では、先生に頼るな・・と・・」
「何を言っておるのだ。この艦を完成させるには、やはり先生の判断が必要なんだ。わからんのか」
図面を持って平賀のところへ出かけました。
「平賀先生は何ておっしゃるか・・軽合金の使用、電気溶接の方法。主砲配置のバランス・・・藤本先生の案が多く採用された図面」
独り言のようにつぶやきながら、車に乗り込んだ福田でした。
場所が変わります。横須賀鎮守府です。
「おい牧野。お前ナイフとフォークを使わせたら『よこちん』(横須賀鎮守府の略)一だな。そんなに西洋料理がすきなのか?俺はどうもバタ臭くて嫌だな」
「ははは、ワインとチーズ。懐かしいなぁ。それとパンも。どうも日本のパンはいただけないし。チーズは手に入らない。フランス行きたいなぁ」
「お前、フランスが敵になるかもしれないご時勢に何悠長な事言ってるんだ」
牧野茂。(同姓同名のプロ野球コーチがおりましたが、違います)
昨年帰国。公費で「フランス国立造船大学『シェルブール』」を卒業したばかりの、若き技術者。
彼は未だこの計画の詳細を知らなかったのでした。
「八八艦隊構想」(最新式の巡洋艦8隻、大型戦艦8隻となす連合艦隊構想)がワシントン条約により中止を与儀なくされ。(先にお話しました「金剛代替艦」はこの八八艦隊の主力となるべく建造される艦だったわけです)
これは海軍にとって用兵そのものを変更せざるを得ない状況でした。
「一艦の戦闘能力をアメリカ艦船の上を行く」
これは、大鑑巨砲主義の中では、しごく当然な発想でした。
艦政四部内、嘗て藤本の部下、平賀では東京大学での愛弟子であった、福田啓二は図面を書けずに悩んでおりました。
「46サンチの主砲。速力30ノット・・・可能なのか。今の技術で・・」
「福田さん、まず書いてみましょう」
江崎設計主任が言葉をかけます。
福田は、今や基本計画主任を任されている造艦学のホープでした。
そしてその部下江崎も。その卓越した設計思想は、平賀からも可愛がられ、藤本からも頼りにされておったのでした。
艦政部のバランサー。平賀と現艦政部との重要なパイプ役でもありました。
軍からの要求は以下のようなものでした。
46サンチ主砲。速力30ノット。
たったこれだけ。
しかし、46サンチという砲を搭載した艦が一体どれだけの大きさになるのか、造船学を学んだ者からすれば、未曾有な大きさになる事は容易に想像できたのでした。
昭和10年3月10日。最初の図面計画「A-140」が完成します。
公試排水量69500トン。294x41.2x10.4m(全長・全幅・全高)タービン200000軸馬力⇒速力31ノット。兵装9x46センチ(三連装) 他 割愛
「まるで、お化けのような艦」こう言われます。
技術的に不可能な部分も多く、まずは全長の見直し、速力を27ノットと致します。
「これだけの砲を搭載した場合、艦がでかすぎる。速力を30ノットを優先すればどうしても、主要兵装計画を見直さなければならない」
「それに、機関の問題もディーゼルなのかタービンなのか・・」
夜を徹した議論が続きます。
昭和10年4月1日 「A-140-B2」試案が完成。
公試排水量62000トン。247x40.4x10.3m。タービン140000軸馬力⇒速力27.5ノット他割愛
「タービンとディーゼルの併用はどうでしょう。日本はやはり4軸でなければ。これが軍艦を動かすのに一番効率がいいわけですから、二軸づつをディーゼルとタービンに分ければ・・」
ある若手研究員の発言でした。福井の頭にはなかった発想です。
「よし、試してみよう」
ここで解説を少し。プラモデルで艦船を作った方ならお解かりになられると存じますが、日本の艦船はスクリューの数が4本だと気づくと思います。ですが例えば「テルピッツ」(ドイツ海軍)であるとかは3軸であるのです。結果、大和も4軸でした。日本の艦船の特徴の1つと言えるのだと思います。
昭和10年8月10日 「A-140-O」試案が完成
公試排水量59000トン。244x38.9x10.4m。タービン55000馬力+ディーゼル55000馬力⇒速力26ノット。兵装8x46センチ(三連装x2+二連装x1)
他割愛。
その後、設計案ではタービン+ディーゼル併用が主となって設計試案が進められていくのでした。
当時、海軍には出力が1万馬力を超す強力なディーゼルエンジンを持っておりました。潜水母艦「大鯨」後の「空母 龍鳳」などに搭載されたエンジンです。ディーゼルとタービン。同じ推進力を持っていたと仮定するならばディーゼルの方が燃費が良い。ですが、機関の重量が重くなる欠点もございました。
桜が咲く前に始まった「A-140」計画。晩秋を迎えております。
昭和10年10月5日 「A-140-F3・F4」試案が完成しました。
公試排水量62545トン。248x38.9x10.4m。タービン75000軸馬力+ディーゼル60000軸馬力。速力27ノット。兵装9x46サンチ(三連装x3。前部2・後部1)
他割愛。
確かに完成時の大和に近づいております。
その後、半年、この基本設計でのシュミレーションが続きます。
「福田主任。電話です。内線です」
電話を取る福田。
「・・・判りました。」
「主任、どうされました?」
「長官だ」
「・・長官?えっ?山本長官・・・・ですか?」
「そうだ。ここに来るそうだ」
艦政四部内。大きな緊張が走ります。
ドアが開き、いつもの風体が入って来ました。やはり白い手袋は欠かしておりません。山本五十六(当時)長官です。
「福田主任」
「お久しぶりでございます」
「ジョージ五世大観以来かな?」
「よく、覚えで・・・私は末席でございましたから・・」
「率直に言おう。私は今後の海戦は空母を中心とした『機動艦隊』(話のあやです。当時まだこの言葉は定義づけされておりません)だと思うのだが・・最早大戦艦も無かろう、不沈艦はありえないのだと思うが・・資材と資金をわが国の空軍構想に当てるべきだと考えるのだが」
「お言葉ですが、長官。私達も不沈艦はありえないと考えてはおります。ですが、ですが長官、極めて沈みにくい艦。これは可能です。今ここで研究を中断したら今後の艦への進化は考えられません」
山本、ここで顔が笑うのでした。
「いや、仕事中悪かった。研究を続けたまへ」
山本、艦政部を去って行きます。
「主任、主任!長官に意見具申・・・でした・・ね」
「どうなる事かと思ったが・・」
「が?ですか?山本長官も懐の広いお方だ。私の意見を率直に聞いてくれた。さぁ研究を続けよう」
年が変わります。昭和11年。もうかれこれ1年が過ぎ、その年の夏でございます。
昭和11年7月20日。最終決定とも言える「A140-F5」試案が完成しました。
公試排水量65200トン。253x38.9x10.4m。タービン75000馬力+ディーゼル60000馬力。速力27ノット。
他割愛。
しかし、ここで思わぬ事態に直面いたしました。
「どうしても・・・・どうしたことか・・」
福田をはじめ、チーム全体がこの難局に直面いたしました。
「A-140」が出来てから、艦の防御は「バイタルアート」で進めております。これは、昨年若くして亡くなった「藤本喜久雄」の設計思想です。福田はそれを継承いたしておりました。ですが、エンジンルームは艦の命です。200mmの分厚い装甲板で覆われなければなりません。この装甲版は単に防御用としているのではなく、船体構造の一部であるため、エンジンをすえ付けたら、二度とエンジンを取り替える事が出来なくなるのでした。
「どうした・・ものか」
補足です。資源の乏しい日本では、燃費効率は出力と平行して考えなければなりませんでした。機関としてはタービンが優位な事は自明の理ではありましたが、燃費を少しでもアップさせようと、タービン+ディーゼル併用が主となっていたわけです。この両立と艦のメンテナンス。これが並び立たなくなりました。
福田。決心いたしました。
「もう私の力では、決定できない。相談しに出かけて来る」
「どちらへ・・・行くのですか?誰に・・・」
「平賀先生にだ」
「技術中将へ?ですが、今だ艦政部の中では、先生に頼るな・・と・・」
「何を言っておるのだ。この艦を完成させるには、やはり先生の判断が必要なんだ。わからんのか」
図面を持って平賀のところへ出かけました。
「平賀先生は何ておっしゃるか・・軽合金の使用、電気溶接の方法。主砲配置のバランス・・・藤本先生の案が多く採用された図面」
独り言のようにつぶやきながら、車に乗り込んだ福田でした。
場所が変わります。横須賀鎮守府です。
「おい牧野。お前ナイフとフォークを使わせたら『よこちん』(横須賀鎮守府の略)一だな。そんなに西洋料理がすきなのか?俺はどうもバタ臭くて嫌だな」
「ははは、ワインとチーズ。懐かしいなぁ。それとパンも。どうも日本のパンはいただけないし。チーズは手に入らない。フランス行きたいなぁ」
「お前、フランスが敵になるかもしれないご時勢に何悠長な事言ってるんだ」
牧野茂。(同姓同名のプロ野球コーチがおりましたが、違います)
昨年帰国。公費で「フランス国立造船大学『シェルブール』」を卒業したばかりの、若き技術者。
彼は未だこの計画の詳細を知らなかったのでした。















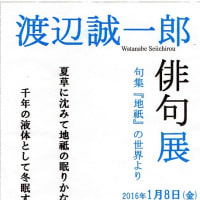

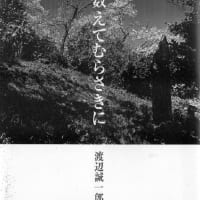







牧野氏の反応・・
気になりますね。
この設計図に付け加えられるものは?
もしくは、削除・・・
気になりますね。
あえて、酔漢さんの続きを待ちましょう。
大和の主砲が三連装。前部に2。後部に1。この配置は江崎のアイディアですが、藤本が嘗て手がけた金剛代替案、そのものです。平賀、これには一言も物言いをつけませんでした。
江崎は戦後、「私はこれだけしかしていない。後は前部福田さんが精魂込めて設計した」と言っておりました。
大和設計の過程で時たま名前は出てきますが、目立たない存在でもあります。
ですが、大きな仕事をしていたと敢えて名前を出しました。
週刊で部品が届き組み立ててゆくあのシリーズ。今度はビスマルクだと。どうすっぺ丹治さん!
ビスマルクは大きさもさることながら、ドイツの工業技術・光学技術(なんせツアイス!)の結晶ですね。
砲塔を旋回させるギアひとつとっても、またもちろん照準能力は特に、群を抜いた存在でした。
巡洋艦の利根はよくまとまった艦ですが、どうしても英国のロドネイを連想してしまいます。
あ、キングジョージⅤ世=プリンスオブウエールズの四連装砲塔もありましたね。やはり国民ごとに、建艦思想が異なり興味が尽きません。
パナマ運河の制約ギリギリに造られた米国のワシントン型。鳥かごもなくなり、やたらと艦首部が長く、スマートです。
どこか藤本案に近い思想で造られたような印象があります。
大和は友鶴事件の後、藤本さんの設計による艦船の安定性が疑問視された後のの艦(「フネ」と読んで下さい)。
しかし集中防禦方式の他は、案外に藤本さんの設計思想が生きているような気がします。
たとえば、次の二点です。
1)三連装三基の主砲と、前に二つ後に一つの配置
2)副砲を砲塔に収めて砲郭(金剛型から長門型までの副砲の配置)を廃止したこと
平賀さんの場合は
1)主砲は三連装と二連装が各二基
2)副砲は砲塔と砲郭の併用
です。
工事の数を考えれば、藤本案の方がすっきりします。
主砲も副砲も装備方式が一種類の方が、戦闘における砲戦指揮もやりやすいのではなかったでしょうか。
藤本さんが設計した水雷艇「千鳥」型は、特型駆逐艦を小さくしたような印象を受けますね。
あれだけの小さな艦体に砲塔式の主砲(駆逐艦以下の砲塔は単なる波よけですが)、大きな艦橋・・・見るからにトップヘビーです。
「初春」型駆逐艦も、艦橋のある艦首楼後半に、背負い式の砲塔。
魚雷発射管三連装三基のうち二基は甲板よりも高い所。しかも次発魚雷装填装置つき。
特型(魚雷発射管三連装三基、主砲は連装三基の六門)より二百トンも小さな艦に特型とほぼ同じ、あるいはそれ以上の武装(魚雷発射管三連装三基、特型は次発装填装置なし、主砲は連装二基の単装一基で五門)。
トップヘビーにならない方が、どうかしています。
しかしこのことから藤本さんを無能な設計者、軍令部の要求を呑み続けたイエスマンと言うことができるでしょうか。
まず藤本さんが活躍した時代は、条約時代だったということに注意しなくてはいけません。
ワシントン条約で戦艦、ロンドン条約で巡洋艦の保有が制限されました。
そこで巡洋艦の役割を駆逐艦に、駆逐艦の役割を水雷艇に・・・
いきおい重武装で個艦優秀の思想が生じます。
条約時代より前の平賀さんは、気にしなくてもよい条件でした。
また海軍の造船士官はほぼすべてが旧制高校、東大工学部の出身でした。
当時の東大は高校出身者以外の入学を認めず、造船学科があったのは東大工学部のみでした。
九大の工学部に造船学科ができたのは戦前ですが、ずいぶん後のことだと聞いております。
つまり平賀さんと藤本さんは、同じ研究室の先輩後輩の関係です。
「いつかは先輩を越える存在になりたい」とは、誰しも普通に抱く感情です。
また「不可能を可能にする」とは技術者ならば抱かぬことのない気持ちではないでしょうか。
しかも与えられた条件が困難であればあるほど、「不可能を可能にする」の思いは強くなるはずです。
考えてみれば藤本さんの場合、不幸な条件がさまざまに重なったということになるのではないかと思わざるをえません。
また藤本さんの場合、難点があったのは復元性のみということも可能です。
大和の設計に見られる金剛代艦・藤本さんとの共通性。
また現在の護衛艦にも通底する藤本さんの設計思想(溶接工法の採用、上部構造物に軽合金を採用することによる重量軽減)。
この二点を見るだけでも、藤本さんは先見性を備えた優秀な技術者だったと言えます。
少なくとも無能なイエスマンだったとは言えないと思うのです。
そういえば天一号作戦で大和に随伴した駆逐艦のうち、「初霜」は改装後の初春型、「響」は艦橋をコンパクトにした後の暁型(吹雪の後期型)でしたね。
但し「響」は内海で機雷に触れ、実際には出撃しませんでしたが・・・
クロンシュタットさんへ
ドイツの光学技術といえば・・・
ビスマルクがフッドを沈めた時、主砲の初弾が命中しています(モチロンのこと、轟沈です)。
光学照準による海上砲戦の場合、初弾命中はまずありえません。
まず目標を挟むように着弾させ(挟叉)、その距離を縮めてゆき命中弾を出すものです(それが早ければ早いほどよい)。
「偶然」という要素を除外すれば、ドイツの光学技術の優秀さと、ドイツ海軍の練度の高さのたまものでしょう。
それから米内さんも山本さんもナマっていました。
米内さんの場合「東洋英和」が「東洋イイワ」と聞えたそうですし、
山本さんの私的な第一人称は「おらぁ」だったそうです。
どちらも阿川弘之さんの本に出ています。
ビスマルクの模型、頑張って完成させて下さい。
フレー、フレー
ですが、集中配備方式は後ろに撃てない(当然)強烈な爆風が一箇所に集中し発砲の衝撃を吸収するのに相当のリスクを背負うなどマイナス面が大きくなります。実際、全門一斉射撃ができなかったとも言われております。
この前部集中方式はフランス艦の見事なまでのバランス感覚が生きているように思えます。
ですが、後期型は前後へ配備する図面もあります。やはり後方へ主砲を打てないことが問題となるのでした。
ネルソンの配置はジュットランド戦における防御の重要性を強調するような結果だったことは丹治さんのコメントにある通りです。
このフランス艦のバランス感を見につけた牧野が大和の開発に参加するのも面白いものです。
コメントへの返答遅れました。
ご容赦下さい。
外国艦の知識が不足しております。ご存知の事がございましたら、お知らせ下さい。