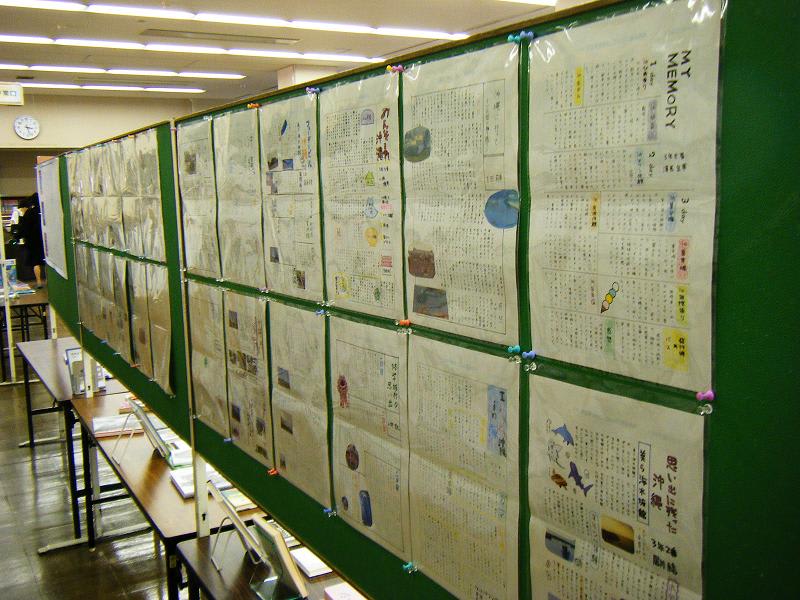9月に入ってからの雨と、台風の関係で、外での練習が進んでいません。明日、明後日も台風通過に伴って準備ができないことから、13日(日曜日)に延期をさせていただきます。
従いまして、
12日(土曜日)リハーサル、前日準備
13日(日曜日)鳥中体育祭
14日(月曜日)12日の振替休日
15日(火曜日)13日の振替休日
となります。12日にご予定いただいている方が多いと思います。ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程、よろしくお願いします。
保護者の皆様には、追ってお子様を通して文書でお知らせします。
従いまして、
12日(土曜日)リハーサル、前日準備
13日(日曜日)鳥中体育祭
14日(月曜日)12日の振替休日
15日(火曜日)13日の振替休日
となります。12日にご予定いただいている方が多いと思います。ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程、よろしくお願いします。
保護者の皆様には、追ってお子様を通して文書でお知らせします。