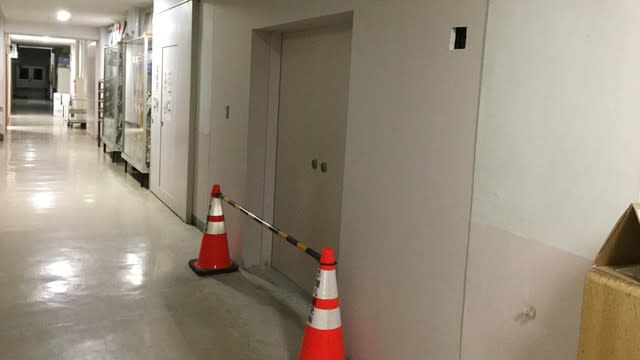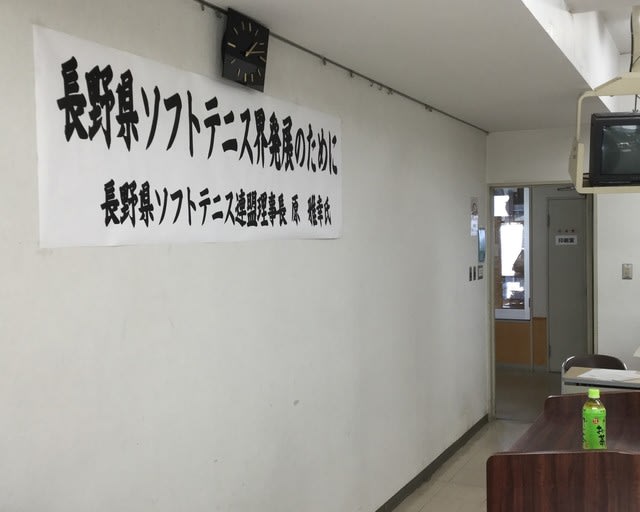本日朝、理数科の1年生が、筑波大学へ校外研修に出かけました。学校に6:45集合、6:50に出発し佐久平駅を経由して茨城県の筑波大学へ。早い生徒は6:20ごろには学校に到着していましたが、まだ薄暗い状況でした。写真は6:43ごろですが、学校で乗車する生徒は時間通りに集合し出発しました。
午前は、大学紹介のDVDを視聴し、その後、中央図書館を見学。
午後は、ミニ講義ということで「光エネルギーと化学」と題して、新井達郎先生(筑波大学名誉教授)の講義、その後、研究センター(生存ダイナミクス研究センター、プラズマ研究センター)を見学という日程です。
午後7時過ぎに佐久に戻ってくる予定です。(7時20分ごろ無事に到着しました!)
筑波大学のあるつくば市は晴れで、気温も14℃ぐらいまで上がり暖かかったそうです。ちなみに佐久市の本日の最高気温は8.3℃でした。
理数科は、大学や様々な研究施設を訪れ研修を行っています。様々な刺激を受け、科学への興味・関心を高めて、自身の将来についても考えていってほしいと思います。
本日2つ目の話題。音楽班の顧問の保科先生から、大変うれしい報告がありました。
2月2日に塩尻市のレザンホールで行われた第18回長野県ヴォーカル・アンサンブルフェスティバルで、本校音楽班が最高賞であるダイヤモンド賞を受賞し、全国大会へ推薦されることが決まりました。ダイヤモンド賞は参加56組の最高賞で1組だけが受賞となります。中学校部門エメラルド賞の信州大学附属長野中、一般の部エメラルド賞の男声アンサンブルだいだらも全国大会に推薦されました。おめでとうございます!!!
全国大会の正式名称は「第13回声楽アンサンブルコンテスト全国大会2020」。福島県福島市のふくしん夢の音楽堂(福島市音楽堂)で3月19日~22日に開催されます。高校部門は20日になります。12月24日の校長日記で、クリスマスコンサートについて触れましたが、美しいハーモニーで心が癒される合唱でしたが、高い評価をいただき、大変うれしく思います。全国大会での健闘を祈っています。
ちなみに、この大会は、3名以上16名以下、指揮者をおかない、曲のジャンルは問わない、アカペラとする、曲間を含め6分以内の演奏などの制限や内容となっています。(長野県の場合)