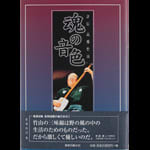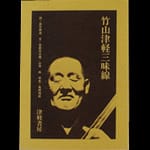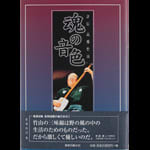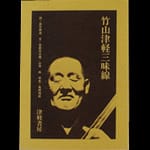青森で日本特殊教育学会に参加してきた。太宰の通った旧制弘前高校が母体となった弘前大学で開催されたものだった。そこで、高橋竹山についての講演を聞いた。東京にて人間の弱さを赤裸々に文学とした太宰の生き方とは対比的な、生き方をみる思いがした。太宰の書いた「津軽」も読んでみたいし、新籐兼人の「竹山ひとり旅」もみてみたいと思った。帰ってきて、kさんと話しながら、竹山について次のような文章を一緒につくった。
----------------------------------------------------------------------------------------
2010年は、津軽三味線とともに力強く生きた高橋竹山の生誕100年に当たる年だった。盲者一人、荒涼とした津軽の吹雪の中を、三味線を弾いて糊口をしのぐ日々の風景は、今回の三陸をおそった津波の果ての荒涼とした廃墟にたたずむ姿とかさなるものがある。
ニューヨークや渋谷ジャンジャンをはじめとするコンサートでの高橋竹山の弾く三味線のはげしく優しい音は、若者たちの心を揺さぶり、三味線のイメージ大きく変えた。しかし、その人生は決して平坦なものではなかった。
竹山がコンサートで「中じょんがら」を弾く前、竹山の語りは一段と高揚するかのようにみえたという。「中じょんがら」は、じょんがら節の中説を独奏用に竹山が編曲したもの。中節そのものは七年から十年ころにかけて、旧節から変化していった歌で、旧節に比べてリズムが骨太で明快になり、力強い中に深い哀愁がこもっていた。竹山の演奏は、自身のやりきれない怒りが相まって、強烈に聴衆の心を揺さぶる迫力があった。この曲を弾いて門付けをして歩いた昭和十年前後は、世の中が戦争一色となり、「おめえ、何が面白くて三味線弾いているんだ。ばがだもんだ」と、徹底的にいじめられた思いが鮮烈に焼きついているからだ。彼の弾く三味線から、目が見えないことで差別されてきた数々のくやしさ、戦争中の苦しみが音を超えて、伝わってくるのである。
竹山はよく語っていた。「何が苦しいたって戦争の時ほど苦しい時はなかった。門付けは仕事だし苦しいと思ったことはない。貧乏でも何とでもない。物が買えないだけで我慢すればいいんだから。戦争は人間を狂わせてしまう。兵隊は偉くて、年寄りや目の見えないものは穀つぶし扱いだった。弱いものをいじめて、ひきょうなもんだ。別におれが戦争してくれって頼んだわけじゃない。腹の中でそう思っていた。巡査や地区の見回りをするような、ちょっとした権力を持った人間にいびられた。三味線もっているだけで『非国民』とののしられ、ぶんなぐられた」
雪深い青森の地に、1910年、2男2の末子として生まれ、麻疹をこじらせ半失明、目のことでいじめられ、小学校も数日でやめてしまう。しかし、三味線と唄に出会ったことで、彼の人生を大きく変えていく。北海道、岩手、秋田、青森と門付けをし、お金がない時は、飴を売ったり、大道芸をして暮らす青年期。貧しさゆえに、一度の離婚を経験したのもこの時期であった。戦争中には三味線の演奏の機会もなく、生活は決して楽ではなかった。ものは配給制で、唄もはやらない。それでも慰問に参加したり、唄会の伴奏をしたりして食いつないでいく。
一度は三味線で食べていくことをあきらめ、33歳にして盲唖学校に入学し寄宿舎で学び、マッサージ師としてやっていく決断をしたこともあった。戦後進駐軍での演奏、民衆や労働者の民謡ブームに乗って、演奏の機会が増えていく。演奏活動はもちろんのこと編曲や「リンゴ節」をはじめとする新民謡の作曲と普及に尽力をした。彼の三味線は野の果てから、きこえてくる彼の生き様であり、大地の叫びとなった。
青年期の高橋竹山の姿は、新藤兼人の「竹山ひとり旅」(1977年、近代映画協会)にも描かれている。「竹山のたくましさは人生のどん底を覗き見たものの強さだった」と新籐は後に書いている。東日本大震災が東北を襲い、1日も早い復興を日本中の人が願っている。竹山の立った東北の大地が持つ力強さ、かれが弾いた大地の声が、人々の魂を揺さぶり、一人ひとりが立ち上がっていくことを願ってやまない。
松林拓司『魂の音色 評伝高橋竹山』(東奥日報社、2000年)