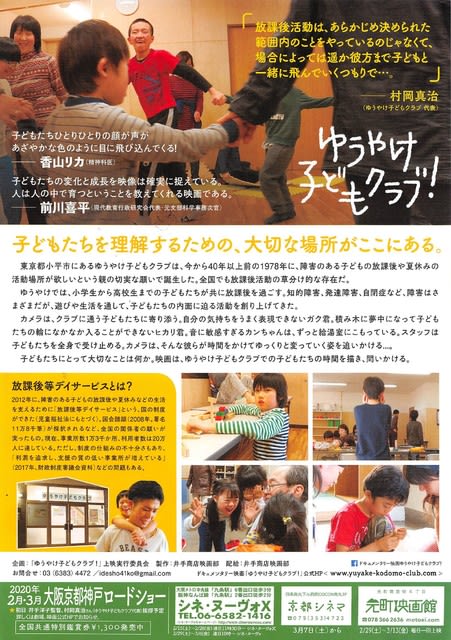「未来につながる子ら」(木村荘十二監督、1962年、共同映画社)。斉藤喜博の島小学校校長時代をモデルにした劇映画。共同映画社と群馬県教職員組合が製作したもの。1962年に公開されたが、その前の2年間、現地調査やシナリオの検討が行われた。
音響(効果)を担当したのが大野松雄さん。島小学校の分校などの現地に行って音を録音することなどを行った。利根川を渡の船で渡っていった記憶があり、斉藤喜博ともあったという。卒業式の場面では一人一人が手をあげてこたえる様子が映されている。チラシには、スタッフの中で音響として大野の名前があがっている。
ストーリー
北関東の山深い寒村、山の中腹には小さくひしゃげた小学校が見える。ここでは、今や卒業式の最中だ。心をこめて一人一人に卒業証書を手渡す校長先生。この学校は小さいが、皆の心が通い合い用務員の小父さんさえも職員会議に仲間入りするような解放的な雰囲気だ。「子供たちを理解せよ」をモットーに校長先生は生徒の生活の中に入りこみ、教室ですごす方が多かった。この学校へ隆一が大阪から転校して来た。隆一は父が死んだため、母親といっしょに伯父の家へひきとられたのだ。隆一にとっては、ここの仲間たちがどうしても理解出来なかった。彼等は何事においても天真らんまんすぎるのだ。同じ悩みは、町から転勤して来たばかりの正木先生にもあった。彼の従来のやり方では生徒たちが動かない。校長先生は彼の授業をはずみがないと批判した。そんなある日、父兄の授業参観日がやって来た。父兄の前で間違った隆一をつかまえ、岩崎先生は隆一君式間違いにしましょう、と言った。間違うのは決して恥かしくないという学校の方針からだ。ところが、隆一の伯父は面白くなかった。その日から伯父は参考書を買いこみ、隆一に勉強をおしつけるのだった。一人では手にあまる勉強をかかえ込んで困った隆一は、隣の席の英子に手助けを頼んだ。だが自分のことは自分でとすげなく断られ、隆一は逆上してとび出したまま夜になっても帰らなかった。やがて淋しくなった隆一が姿を現したのは岩崎先生のところだった。翌日、ホームルームでは隆一の事件がとりあげられた。隆一の伯父のやり方は批判され、皆にはじめて理解された隆一の顔も明るかった。正木先生もやがてしみじみと子供たちの良さを理解するのだった。
スタッフ
監督 木村荘十二
製作 坂斎小一郎 、 高林公毅 、 森谷玄
脚本 木村荘十二 、 山形雄策 、 西村勝巳 、 大内田圭彌
撮影 黒沢浩
音楽 長沢勝俊
美術 小川広
編集 岸富美子
録音 大野松雄
スチル 男沢浩
照明 上村栄喜
配役・キャスト
新島校長 西島悌四郎
浅川教務主任 日恵野晃
岩崎先生 木村俊恵
平山先生 武内亨
正木先生 島田屯
田村先生 中野誠也
川上先生 中野卯女
水谷先生 相生千恵子
栗木欽造 浜田寅彦
栗田タキ 川上夏代
イネ 桜井良子
PTAの母親 米丸幸見
PTAの母親 野田阿古
PTAの母親 安藤タキ子
PTAの母親 中谷文子
PTAの母親 豊島八重子
PTAの母親 細田陽子
東宝児童劇団
劇団あすなろ
劇団ひまわり
音響(効果)を担当したのが大野松雄さん。島小学校の分校などの現地に行って音を録音することなどを行った。利根川を渡の船で渡っていった記憶があり、斉藤喜博ともあったという。卒業式の場面では一人一人が手をあげてこたえる様子が映されている。チラシには、スタッフの中で音響として大野の名前があがっている。
ストーリー
北関東の山深い寒村、山の中腹には小さくひしゃげた小学校が見える。ここでは、今や卒業式の最中だ。心をこめて一人一人に卒業証書を手渡す校長先生。この学校は小さいが、皆の心が通い合い用務員の小父さんさえも職員会議に仲間入りするような解放的な雰囲気だ。「子供たちを理解せよ」をモットーに校長先生は生徒の生活の中に入りこみ、教室ですごす方が多かった。この学校へ隆一が大阪から転校して来た。隆一は父が死んだため、母親といっしょに伯父の家へひきとられたのだ。隆一にとっては、ここの仲間たちがどうしても理解出来なかった。彼等は何事においても天真らんまんすぎるのだ。同じ悩みは、町から転勤して来たばかりの正木先生にもあった。彼の従来のやり方では生徒たちが動かない。校長先生は彼の授業をはずみがないと批判した。そんなある日、父兄の授業参観日がやって来た。父兄の前で間違った隆一をつかまえ、岩崎先生は隆一君式間違いにしましょう、と言った。間違うのは決して恥かしくないという学校の方針からだ。ところが、隆一の伯父は面白くなかった。その日から伯父は参考書を買いこみ、隆一に勉強をおしつけるのだった。一人では手にあまる勉強をかかえ込んで困った隆一は、隣の席の英子に手助けを頼んだ。だが自分のことは自分でとすげなく断られ、隆一は逆上してとび出したまま夜になっても帰らなかった。やがて淋しくなった隆一が姿を現したのは岩崎先生のところだった。翌日、ホームルームでは隆一の事件がとりあげられた。隆一の伯父のやり方は批判され、皆にはじめて理解された隆一の顔も明るかった。正木先生もやがてしみじみと子供たちの良さを理解するのだった。
スタッフ
監督 木村荘十二
製作 坂斎小一郎 、 高林公毅 、 森谷玄
脚本 木村荘十二 、 山形雄策 、 西村勝巳 、 大内田圭彌
撮影 黒沢浩
音楽 長沢勝俊
美術 小川広
編集 岸富美子
録音 大野松雄
スチル 男沢浩
照明 上村栄喜
配役・キャスト
新島校長 西島悌四郎
浅川教務主任 日恵野晃
岩崎先生 木村俊恵
平山先生 武内亨
正木先生 島田屯
田村先生 中野誠也
川上先生 中野卯女
水谷先生 相生千恵子
栗木欽造 浜田寅彦
栗田タキ 川上夏代
イネ 桜井良子
PTAの母親 米丸幸見
PTAの母親 野田阿古
PTAの母親 安藤タキ子
PTAの母親 中谷文子
PTAの母親 豊島八重子
PTAの母親 細田陽子
東宝児童劇団
劇団あすなろ
劇団ひまわり