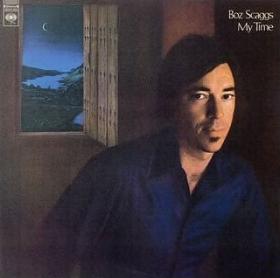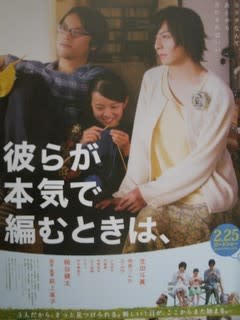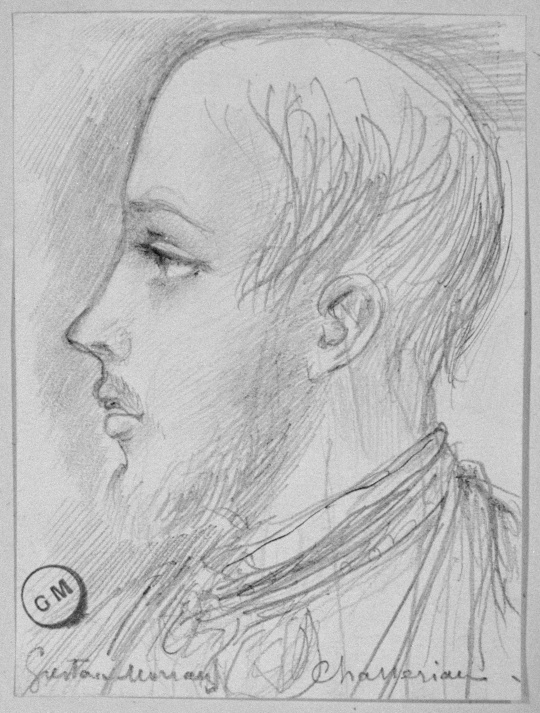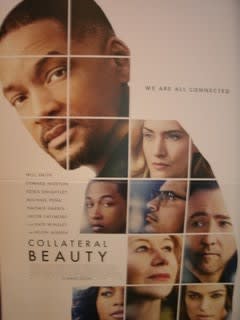原題:『The Conversation』
監督:フランシス・フォード・コッポラ
脚本:フランシス・フォード・コッポラ
撮影:ビル・バトラー
出演:ジーン・ハックマン/ジョン・カザール/アレン・ガーフィールド/シンディ・ウィリアムズ
1974年/アメリカ
映像や音への執着と「情報戦」のあり方について
本作を観るにあたって『欲望(Blowup)』(ミケランジェロ・アントニオーニ監督 1967年)と比べて観ることで理解が深まると思う。『欲望』において主人公のトーマスは写真家で、自分が撮った写真に写り込んだ「真実」を追求すればするほど「真実」から遠ざかってしまうというアイロニーが描かれていたのであるが、本作の主人公のハリー・コールは映像ではなく、音にこだわる盗聴のエキスパートである。
ハリーはある会社の専務から妻と浮気相手の会話を録音することを依頼され、その会話から雑音を排除すると相手の男が自分が殺される可能性を示唆していることに気がつく。ここまでは写真を引き伸ばして拳銃を見いだす『欲望』と展開が似ているのだが、「真実」のあり方が違ってくる。
ハリーは自分がした仕事で起ころうとする殺人事件を未然に防ごうと、2人が密会の約束をしていたホテルの部屋の隣の部屋を取る。女の叫び声は聞こえたし、隣の部屋へ忍び込むと部屋はきれいに整っているが、トイレの水を流すと「赤い水」が溢れてきた。ところが2人は生きており、女の夫は交通事故で死亡したことになっているのである。納得できないまま自宅に戻ると、知らない男から電話がかかり「盗聴している」という言葉と共にさっきまで自分が演奏していたサックスの音が聞こえてくる。ハリーは部屋を徹底的に調べるのであるが、盗聴器は見つからないのである。
同業者のバーニー・モランが最新の機器を披露したように、どちらが相手よりもより良い機器を使っているかによって「立場」はコントロールできるのであるが、実はハリーはもはや音にこだわる必要はない。警察に事実を語ればいいだけなのだが、まるで音に「憑かれた」かのようにハリーはわざわざ自宅に電話を引いてしまい音から逃れられないのである。