ゴンドラ
1987年/日本
‘父親’の敗北による生きる困難
総合
80点
ストーリー
0点
キャスト
0点
演出
0点
ビジュアル
0点
音楽
0点
アテネ・フランセ文化センターにおける『To each his own Japanese Cinema 世界のなかの日本映画』でローランド・ドメーニグ(ウィーン大学東アジア研究所日本研究准教授)が選んだ『翔んだカップル』(相米慎二監督 1980年)『泥の河』(小栗康平監督 1981年)『ゴンドラ』(伊藤智生監督 1986年)の三作品が上映された。まずは彼自身のコメントを引用してみたい。
「私が選んだ三作品には三つの共通点があります。それは監督たちの長編デビュー作であり、子どもが主役で、そしてバブル経済がはじける前の1980年代に公開されていることです。もうひとつのキーワードは‘移行(transition)’です。主人公の若者たちは子どもから大人へ変わっていくなかでもがき苦しみ、若い監督たちもまた職業監督としてのキャリアに身を投じるなかで同じ葛藤を抱えます。また、昔ながらの撮影所システムが決定的に崩壊し、テレビ会社が映画製作を開始する、この日本映画の過渡期に対する再評価は、長らく手つかずのまま持ち越されているのです。」
この三作品の共通点は『翔んだカップル』の山葉圭も、『泥の河』の松本銀子も、『ゴンドラ』の‘かがり’も思春期の女の子たちがみんな‘他人の家の風呂’に入ることである。まるで苦悩する女の子たちの‘駆け込み寺’のように‘他人の家の風呂’が機能しているという事実を鑑みる時、作風を全く異にする三人の映画監督が類似のテーマを扱うときに同じシーンを撮ってしまうことに驚かされる。
『泥の河』の時代設定は1951年で『ゴンドラ』は1980年代半ばだと思うが、ニ作品ともに共通するテーマは不甲斐ない(あるいは亡くなった)父親と、それ故に強く生きていかざるを得ない母親に翻弄される子どもたちの姿である。このニ作品はラストシーンも船が出現することで共通している。『泥の河』は小栗康平監督の無駄のない完璧な演出であるが故に、信雄に別れを告げないまま喜一と銀子が乗った船が去っていくシーンに全く救いが感じられない。『ゴンドラ』のラストシーンも応急修理された小舟(=ゴンドラ)に乗っているかがりと良のシーンで終わる。2人は、かがりが飼っていた2羽の白文鳥が争ったために1羽が死んでしまい、その亡骸を箱に納めて海に流すために小舟に乗る。その2羽の白文鳥はかがりの両親を象徴して、死んだ1羽は売れないミュージシャンだったかがりの父親なのかもしれないし、あるいはその2羽の白文鳥はかがりと母親の象徴で、死んだ1羽はかがり自身なのかもしれないが、いずれにしても‘父親’の‘喪に服す’ことはできても、そこから先をどのようにして生きていけばいいのか答えを見出すことはできない。
『ゴンドラ』においてそのような‘父親’の不甲斐なさを補うかのようにして‘女性’が堂々と赤裸々に描かれている。小学校の5年生のかがりを演じた上村佳子も、かがりの母親を演じた当時30代半ばの木内みどりも、良の母親役を演じた当時60歳前の佐々木すみ江も‘3世代’が全員ヌードになっている。児童ポルノの観点からいまでは不可能な演出であるが、両親が不和であるかがりの描く絵がどれも明るいのは演出ミスだと思う。
このレビューはこのまままとまらないまま『翔んだカップル』へ続くことになる。
最新の画像[もっと見る]
-
 『あまろっく』
9ヶ月前
『あまろっく』
9ヶ月前
-
 『スマホを落としただけなのに 最終章 ファイナル ハッキング ゲーム』
9ヶ月前
『スマホを落としただけなのに 最終章 ファイナル ハッキング ゲーム』
9ヶ月前
-
 『オアシス』
9ヶ月前
『オアシス』
9ヶ月前
-
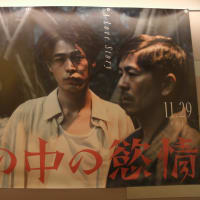 『雨の中の慾情』
9ヶ月前
『雨の中の慾情』
9ヶ月前
-
 『海の沈黙』
9ヶ月前
『海の沈黙』
9ヶ月前
-
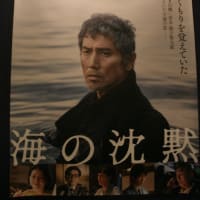 『海の沈黙』
9ヶ月前
『海の沈黙』
9ヶ月前
-
 『アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師』
9ヶ月前
『アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師』
9ヶ月前
-
 『六人の嘘つきな大学生』
9ヶ月前
『六人の嘘つきな大学生』
9ヶ月前
-
 『六人の嘘つきな大学生』
9ヶ月前
『六人の嘘つきな大学生』
9ヶ月前
-
 『正体』
9ヶ月前
『正体』
9ヶ月前














