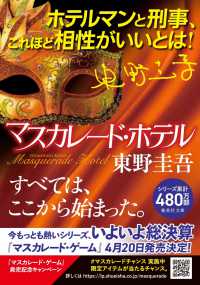「沸点桜」北原真理
馳星周バイオレンスを桐野夏生が描いたような作品。
面白さのツボは、性格も年齢も異なる女性2人が逃亡し過去を隠し生活する、って設定だ。
これだけで、十分おもしろい。
ミステリとしては多少ムリやり感があるが、作品に勢いがある。
一気に読ませるベクトルである。
感心した。
P43
「あれ、何て山なの」
「唐沢岳、右から三ツ岳、水晶岳、槍ヶ岳、穂高」
(これらを眺める場所ってどこだろう?水晶岳、って野口五郎岳の陰になって見えないのでは?)
【蛇足】
ミステリって作者も読者も「意外性」にこだわるように思う。
別に、ムリに「意外性」を作らなくてもいいのでは?
十分おもしろいんだから。
【ネット上の紹介】
新宿歌舞伎町でセキュリティをするコウは、生きるためなら手段を選ばないしたたかな女。元情夫のシンプの指示で、風俗店“天使と薔薇”から逃亡した淫乱で狡猾な美少女ユコを連れ戻しに成城の豪邸へと向かう。そこには敵対する角筈の殺し屋たちが待っていた。窮地を躱したコウはユコを連れ、幼いころに暮らした海辺の団地に潜伏する。束の間の平穏、団地の住民たちとの交流、闇の世界から抜け出し、別人に生まれ変わった危ない女とやっかいな女の奇妙な共同生活。幼いころから虐待され、悲惨な人生を歩んできた二人に、安息の日々は続くのか―。第21回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作。