
「 土漠の花 」月村了衛
海外に派遣された自衛官たちの話。
墜落ヘリの捜索救助にあたっていたところに、氏族間抗争で命を狙われている女性が逃げ込んでくる。
保護したことから、武力抗争に巻き込まれてしまう。
圧倒的な自然の猛威、テロの脅威。
武器もなく地理も分からず基地に戻れるのか?
以前、この著者の作品を読んだが、
ディーテイルにこだわり、複雑な国際情勢を絡めて描いていた。→「機龍警察未亡旅団」月村了衛
本作でも、圧倒的な描写力を堪能できた。
2015年 第68回 日本推理作家協会賞受賞作品。
近未来にあり得る話かもしれない。
【ネット上の紹介】
ソマリアの国境付近で、墜落ヘリの捜索救助にあたっていた陸上自衛隊第一空挺団の精鋭たち。その野営地に、氏族間抗争で命を狙われている女性が駆け込んだとき、壮絶な撤退戦の幕があがった。圧倒的な数的不利。武器も、土地鑑もない。通信手段も皆無。自然の猛威も牙を剥く。最悪の状況のなか、仲間内での疑心暗鬼まで湧き起こる。なぜここまで激しく攻撃されるのか?なぜ救援が来ないのか?自衛官は人を殺せるのか?最注目の作家が、日本の眼前に迫りくる危機を活写しつつ謳いあげる壮大な人間讃歌。男たちの絆と献身を描く超弩級エンターテインメント!

「タックスヘイヴン」橘玲
先日読んだ「マネーロンダリング」が良かったので、
引き続き、本作も読んだが、前作に劣らず、面白かった。
「マネーロンダリング」では、香港を舞台に進行したが、
今回は、シンガポールを中心に韓国、タイ、ミャンマーと展開する。
シンガポールのホテルで、日本人が墜落死する。
その妻・紫帆が現地に駆けつけると、夫には現地妻と子どもがいたことが判明する。
物語の中心となるのは4人=紫帆と高校時代の友人・牧島とコバ、シンガポールの女刑事・アイリスだが、他にも個性的な脇役多数登場し、最後まで飽きさせない。
私は、前回と同等か、それ以上に楽しめた。
P48
日本の税法では、贈与を受けた側が税金を支払う。一方、アメリカの税法では税金を払うのは贈与した側だ。親が日本で子どもがアメリカにいると、日米いずれも納税義務を負う人間が非居住者になるので、結果的に、何百億贈与しても合法的に税金を一円も支払わずにすむのだ。日本法人のプライベートバンキング部門はこの“脱税指南”だけでとてつもない利益をあげ、日本人トップは巨額の報酬を得た。
P223
日本国の税法は属地主義なので、原則として、日本国内に居住していなければ日本に税金を納める必要はない。だがこれではかんたんに贈与税・相続税を回避できてしまうので、2004年の租税特別措置法改正で、贈与者・授与者がともに5年以上海外に居住していなければ課税対象になることになった。(これに関しては先日読んだノンフィクション参照→「プライベートバンカー」清武英利)
P67
「こちらの方がもっとわかりやすいかもしれませんね」
それはスイスSG銀行のホームページに掲載された役員一覧で、上から三番目にエドワードが顔写真付きで紹介されていた。(この使い方は、少し違和感を感じる。日本では、ホームページとウエブサイトが、ほぼ同じ意味で用いられるが、実際は異なる。本来、ホームページはウエブサイトの表紙にあたる最初のページを指す)
P270
「そうなんや。でもなんか不安やなあ。晴美はしばらく黙ったままだった。「まあ、ええわ。わたしがいくら考えてもしゃあないし、花梨に訊いてみるわ。牧島さん、いつまで大阪におるん」(見事に大阪弁を駆使されているので感心した。ただ、ちょっと違和感を感じるのは晴美が「わたし」と言っている点。ここは、「うち」と言わせて欲しかった。実際、この後のページでは、晴美に「うち」と言わせている。ついでに言うと、最近の子どもは、アニメの影響か、標準語を話しアクセントも関東風になっている場合がある…残念なことだ)
【おまけ】
タックスヘイヴン:
「租税回避地」のこと。 外国資本&外貨獲得の為に、税金を優遇して、企業や富裕層の資産を誘致している国や地域。
tax は「税金」、 haven は「避難所」、すなわち「租税回避地」。
関連用語として「オフショア」がある。offshore「沖合」という意味。
本国以外での取引がオフショア取引。
オフショア取引が行われるのが、タックスヘイヴンというとこになる。(税金が高く、規制の多い場所で取引しても仕方ない)
…以上、本作品でにわか勉強。
【ネット上の紹介】
東南アジア最大のタックスヘイヴン、シンガポールのスイス系プライベートバンクから1000億円が消えた。日本人ファンドマネージャーは転落死、バンカーは失踪!マネーロンダリング、ODAマネー、原発輸出計画、北朝鮮の核開発、仕手株集団、暗躍する政治家とヤクザ…。名門銀行が絶対に知られてはならない秘密とは?そして、すべてを操る男は誰だ?


「お家さん」玉岡かおる
上下2巻、読みごたえがあった。
明治女性の一代記。
かつて、鈴木商店は日本一の年商を上げた巨大商社だった。
そのトップが「お家さん」と呼ばれた鈴木よね。
鈴木商店の興亡とともに、よねと周辺の人々が描かれる。
台湾の実情、神戸の米騒動、関東大震災など、当時の世相を交えた近代史としても興味深い。
読んでおいて損はない作品だ。
途中で、血の繋がりはないが、よねの娘のような存在となる珠喜が登場する。
作品を引っ張る重要な人物で作品の魅力のひとつ。
著者は、歴史と資料を丹念に調べて書かれているが、
本作品の面白いところは、事実を膨らませて、色づけした箇所だ。
登場人物の感情表現は秀逸。
遠いはずの「明治」の人々が生き生きと描写される。
上巻P177
「今日よりは、こない呼ばしてもろてよろしおますか?」
訊きかえす間もなかった、彼はそのまま膝で三歩下がって、頭を下げた。
「おかみさん、ではのうて、“お家さん”と」
それは古く、大阪商人の家に根づいた呼称であった。間口の小さいミセや振興の商売人など、小商いの女房ふぜいに用いることはできないが、土台も来歴も世間にそれと認められ、働く者たちのよりどころたる「家」を構えて、どこに逃げ隠れもできない商家の女主人にのみ許される呼び名である。
下巻P281
「欧米の言う近代文明いうんは、しょせん、こんなもんかもしれまへんな」
実際、欧米人の近代文明いうんは、何億年もの間地底で眠り続けた化石たちを掘り出し、それを燃やして蒸気を起こし、そしてとほうもない熱と煙を放出させて大きなものを動かすというのんだす。それは日本の、大地や空気や空といった、神々の領域には影響せえへんやりかたとは、そもそも出発点を異にしとりますわな。
【おまけ…鈴木商店の流れをくむ会社】
鈴木商店は滅びたが、その関連企業、後継者たちは生き延びて日本経済を支え続けた。
帝人、神戸製鋼所、サッポロビール、昭和シェル、ダイセル…。
日商は岩井産業と合併、更にニチメンと合併、双日となる。
【参考リンク】
「鈴木商店記念館」
【ネット上の紹介】
大正から昭和の初め、鈴木商店は日本一の年商を上げ、ヨーロッパで一番名の知れた巨大商社だった。扱う品は砂糖や樟脳、繊維から鉄鋼、船舶にいたるまで、何もかも。その巨船の頂点に座したのは、ひとりの女子だった。妻でない、店員たちの将でもない。働く者たちの拠り所たる「家」を構えた商家の女主人のみに許される「お家さん」と呼ばれた鈴木よね。彼女がたびたび口にした「商売人がやらねばならない、ほんまの意味の文明開化」とは、まぼろしの商社・鈴木商店のトップとして生きた女が、その手で守ったものは…。激動の時代を描く感動の大河小説。

「ついに、来た?」群ようこ
「老い」と「介護」をテーマにしたコメディタッチ短編集。
良くできている。共感しながらの一気読み。
例えば、第1話「母、出戻る?」では、父の死から始まる。
当時55歳の父が、自動車の自損事故で亡くなる。
母は53歳。
父の遺産分配が済んだ後、母が姿を消す。
手紙が残されていた。
「お母さんはしばらくいなくなります。心配しないでください。探さないでください。落ち着いたら連絡します。 トミコ」
なんと5歳年下の男性のもとに奔っていたのだ。
これで終わればよくある話。(よくあっても困るんだけど)
その後、年月が流れ、母が帰ってくる。
男が挨拶もせず母と荷物を家の前に置いていったのだ。
いったいどうなるのか?
こんな感じの作品が8編収録されている。
【おまけ】
途中で著者名を確認した。
あれ、平安寿子さんの作品だっけ?、と。
群ようこさんの作品でした。
ボケてどーする。(作品に共鳴しすぎ)
【ネット上の紹介】
どうしたものかなぁ……。 働いたり、結婚したり、出産したり、離婚したり……、バタバタと歳を重ねているうちに、気づいたら、あの問題がやってきた!? それは、待ったナシの、親たちの「老い」。 女性の人生に寄り添ってきた著者による、泣いて怒って笑って、大共感の連作小説。 父の死後、年下の男に奔ったサチの母。70歳で男に捨てられ戻ってきたけど、どうも様子がおかしい。「母、出戻る?」 元教師で真面目なマリの義父がどうやら惚けてしまった。夫に介護認定の相談をするも、頑として認めようとしない。「義父、探す?」 認知症と診断されたマドカの母を夫は引き取ろうと言ってくれた。でも、どうして息子を巻き込むのかと、義母はお冠で……。「母、歌う?」 ほか、「長兄、威張る?」「母、危うし?」「伯母たち、仲良く?」「母、見える?」「父、行きつ戻りつ?」全8編。誰もが避けて通れない「親」たちの老いというシリアスなテーマを、著者らしいユーモアを交えて綴る、大共感の連作小説。

「マネーロンダリング」橘玲
香港在住の秋生。
謎の美女・麗子が訪ねてくる。
「五億円を日本から海外に送金し、それを損金として処理したい」、と。
即ち「脱税」である。
その後、彼女は5億でなく50億の金と共に消える。
金の行方を探るにつれ、彼女の過去も明らかになってくる。
2002年の作品だが、旧さを感じず、面白く感じた。
ほとんど一気読み、である。
パソコンや脱税の描写は、今となっては古いものもあるかも知れないが、
それ以上に、物語の面白さが凌駕している。
【おまけ】
先日読んだ「言ってはいけない」と同著者だが、小説の方が読ませる内容だ。
これだけ優れた内容なのに、「このミス」「文春ミステリー」にランクインしていない。
「ミステリ」じゃなく「経済小説」としたのだろうか?
いずれにせよ、重大なモレ、と思う。
【おまけ】2
作中で「精神分裂病」と表記されるが、「統合失調症」である。
認知機能の低下によるもの、と現代では考えられている。
ちなみに、境界例を扱った傑作に「症例A」がある。(お薦め)
【ネット上の紹介】
香港在住の元・ウォール街のファンドマネジャー工藤秋生は、香港の銀行口座開設の手助けなど、脱税を目的とした、もぐりのコンサルタント業をしていた。ある日、日本の知人からの紹介で工藤を美しい一人の女・若林麗子が訪ねる。「じつは五億円を日本から海外に送金し、それを損金として処理したいのです」工藤に求められたスキーム、それは完全に脱税の指南だった…。そして四ヶ月後、麗子は消えた。五億ではなく五〇億の金とともに。麗子はどこへ消えたのか?金融のことを何も知らないはずの麗子が、五〇億もの金をどうやってあとかたもなく消し去ることができたのか?そして、そもそも麗子が話を持ち込んだ「五億の金」とは、どんな“ファンド”だったのか?金融を知り尽くした新人作家による、驚天動地の“脱税”小説。

「探偵は女手ひとつ」深町秋生
異色ハードボイルド探偵もの。
なぜ異色かと言うと、過疎の山形が舞台だから。
セリフも全編山形弁が駆使される。
それがとてもいい感じ。
深町秋生さんと言うと、高濃度のバイオレンスが特徴だが、
本作品では押さえている。
著者は、こういう地方を舞台にした日常に近い、探偵作品は初めてかと思う。
そこに住む人々の生活が感じられる。
例えば雪かきの状態で、独居老人が住んでいるとか…。
このような判断は、大阪に住んでいたら別世界の出来事で、言われないと分からない。
「アウトバーン」とは全く異なるが、とてもいい味を出していて、私は好みである。
(欲を言えば、シングルマザーの生活感をもう少し出してもよかったか、と)
【参考リンク】
深町秋生『探偵は女手ひとつ』 (03/21)

「いとの森の家」東直子
小学4年の加奈子は父の転勤により、都会から田舎の小学校に転校になる。
そこで出会った人々とエピソードが綴られている。
特に、おハルさんという、お婆さんは重要。
死刑囚の慰問を続けていて、「死刑囚の母」と呼ばれる白石ハルさんんがモデルとなっている。
自らの体験を元に書かれた作品で、舞台は福岡の糸島が舞台。
P10
名前を書き終わった先生が振り返ってふたたびこちらを向いたとき、教室はしずまりかえった。私はごくりと唾をのみこんだ。
「今日からこのクラスで一緒に勉強をすることになりました、山田加奈子さんです」
P139
布団たたみ雑巾しぼり別れとす
(中略)
「そうそう。死刑囚に、俳句や短歌の先生が教えに来てくれて、作るようになる人もいるのよ。この俳句は、昨日、この人が処刑の直前に書き残した俳句なの」
【参考リンク】
東直子さんインタビュー2015.4.7 (ブックショート)
直久(なおきゅう) (公式サイト)
【ネット上の紹介】
父の突然の思いつきで、小さな村に引っ越してきた加奈子は都会とのギャップにとまどいながらも、自然の恵みに満ちた田舎の暮らしに魅了されていく。そして、森で出会った笑顔の素敵なおばあさん・おハルさんと過ごす時間の中で、命の重みや死について、生きることについて考えはじめる―。著者初の自伝的小説。第31回坪田譲治文学賞受賞作。

「松田さんの181日 」平岡陽明
新人作家の作品。
「こんなの面白いのか?」と思われるかもしれない。
驚いた…とても面白かったのだ。
新人作品とは思えない。
短編集だけど、短い中に人生が凝縮された内容となっている。
ユーモアと泣かせ、絶妙のコンビネーション、私も泣かされた。
P264-265
「野球選手なら走攻守、どれかひとつでもズバ抜けてたらプロになれる。二つ揃えば一流、三つ揃えばイチローだ。ではコメディアンの三拍子とは何か?それはリズム、ユーモア、芝居っ気である。(後略)」
P270
かのアインシュタイン翁が言っている。「結婚に際し、女は男に変わってくれることを望みます。男は女に変わらないことを望みます。うまくいくはずがありません」。
P280
人間はピンチのとき「闘争か逃走か」を瞬時に択ぶ遺伝子が組み込まれているらしい。
【参考リンク】
平岡陽明『松田さんの181日』
【ネット上の紹介】
職業・役者。現在、末期がん。その人は、カネも女も才能もない私の、師なのだ―。オール讀物新人賞受賞。ユーモアと涙の傑作小説集!

「ジニのパズル」崔実
日本とアメリカを舞台にして、著者の分身と思える少女の青春を描く。
非常にビター、カカオ80%の作品だ。
2016年 第59回 群像新人文学賞受賞
2016年 第33回 織田作之助賞 大賞受賞
P46-47
「日本には私のような日本生まれの韓国人が通える学校が二種類あるんだ」
私は、そう靴紐をなぞりながら言った。
「もちろん日本の学校にも通えるけどね。コリアン系の学校もあってさ、南側の韓国学校と、北側の朝鮮学校がある。私はその北側の朝鮮学校に通っていたんだ。韓国学校は一校しかないし、生徒たちは韓国生まれの子ばかりで、日本生まれの韓国人なんてほとんどいないんだよ。朝鮮学校は、日本生まれの朝鮮籍や韓国籍を持った子たちが通う学校なんだ。すごく混乱しやすいと思うけど、大丈夫かな」
「ええ、なんとか」
そう答えたステファニーの眉間には、少ししわが寄っていた。
【感想】
P51の「最初の登校日」から、怒濤の展開。
一気読みのおもしろさ。
[要旨]
オレゴン州の高校を退学になりかけている女の子・ジニ。ホームステイ先でステファニーと出会ったことで、ジニは5年前の東京での出来事を告白し始める。ジニは日本の小学校に通った後、中学から朝鮮学校に通うことになった。学校で一人だけ朝鮮語ができず、なかなか居場所が見つけられない。特に納得がいかないのは、教室で自分たちを見下ろす金親子の肖像画だ。1998年の夏休み最後の日、テポドンが発射された。翌日、チマ・チョゴリ姿で町を歩いていたジニは、警察を名乗る男たちに取り囲まれ…。二つの言語の間で必死に生き抜いた少女の革命。21世紀を代表する青春文学の誕生!第59回群像新人文学賞受賞作。

「こんなわたしで、ごめんなさい」平安寿子
デビュー当時から巧かった。
それは今も健在。
文章も私の好み。
シニカル&アイロニーでユーモアもある。
特に短編が巧い。
短編の名手と言えば、ロバート・シェイクリイを思い出すけど、
日本で言うと「ガール」の奥田英朗さんか?
私は平安寿子さんも、かなりのレベルと判断している。
P8
悪魔に魂を売ったがごとく、バカに景気がよかった1980年代末の20代たちは、高収入、高学歴、高身長を相手に求めたという。
そんなわがままが言えたなんて、信じられない。大体、この日本に三拍子揃った男がいたのか!?
P88
老後の安心のために結婚し、子供を産むなんて、不純だ!
などと正論をぶつには、泉は世間を知りすぎている。介護が必要な弱者となったとき、なんと言っても頼れるのは肉親だという現実を痛感する毎日なのだ。
仲が悪くても、家族は見放せない。それが人情というものだ。そのため底知れない軋轢も生まれるのだが、それでも、ことが起こると行政や警察は、血縁に責任をとらせようとする。
【参考リンク】
作家の読書道:第38回 平安寿子さん
【関連リンク】
「さよならの扉」平安寿子
「おじさんとおばさん」平安寿子
「神様のすること」平安寿子
「こっちへお入り」平安寿子
【平安寿子さんから中高年の皆さんへのお言葉】(他作品より)
五十を過ぎると、むしろ、跡がつくほど傷つく経験でなければ思い出になり得ないとわかる。人が自分の幸せに気付かないのは、ハッピーな経験ほど、メモリーにインプットされないからだ。
傷つかなければ、忘れてしまう。人間とはそれほど大雑把な生き物だ。
女であることはわたしの属性のひとつであって、全部ではない――これは、80年代フェミニズムのスローガンだ。
当時三十台の久美子は、こんな言い方をする女になりたくないと思った。
(中略)
ところが、更年期を過ぎたら、このスローガンがピッタリ!
解決できない問題を、いつも両手一杯に抱えている。立っているだけで精一杯。それが、五十台だから。
【ネット上の紹介】
欠点や弱点、悪い癖を自分から引きはがせずに、あがく女たちの悲喜こもごも。ユーモラスでシニカルな「平節」炸裂の短編集!名手の傑作コメディ7編!

「虫たちの家」原田ひ香
九州にある孤島と東京にまたがってストーリーは展開する。
「虫たちの家」は一種のシェルター。
インターネットで被害にあった女性が共同生活を送っている。
そこに新たな入居者・母娘が入って、結束が崩れてくる。
緊迫したストーリー。
過去のエピソードとカットバックしながら重層的に描かれる。
一気に読ませる内容だ。
【おまけ】
こんな作品も書くのか、と驚いた。
でも、私の好みは、「失踪.com 東京ロンダリング」や「彼女の家計簿」のような作品。
今回は、少し好みがずれた。
さらにクレームをつけると、ストーリーに無理があるように感じる。
【ネット上の紹介】
九州の孤島にあるグループホーム「虫たちの家」は、インターネットで傷ついた女性たちがひっそりと社会から逃げるように共同生活をしている。新しくトラブルを抱える母娘を受け容れ、ミツバチとアゲハと名付けられる。古参のテントウムシは、奔放なアゲハが村の青年たちに近づいていることを知り、自分の居場所を守らなければと、「家」の禁忌を犯してしまう。『母親ウエスタン』『彼女の家計簿』で注目の作家が描く、女たちの希望の物語。

「マチネの終わりに」平野啓一郎
恋愛小説は読まないのだが、あまりに評判が良いので読んでみた。
確かに、面白かった、完成度の高い作品だ。
特に、第6章「消失点」の途中から俄然面白くなり一気読み。
ヒロインはジャーナリストの洋子40歳、フランス在住。
男性は天才ギタリスト・蒔野38歳、世界を股に活動。
東京、バグダッド、マドリード、パリ、台北、ニューヨークと舞台は移っていく。
イラク侵攻と自爆テロ、リーマンショック等の時事問題を背景に展開する。
個人の恋愛事情でありながら、社会の波に大きく翻弄される。
非常にリアリティのある演出で、大人の恋愛小説だ。
ヒロインのプロフィール
P23
「洋子さんって、え、何カ国語喋れるんですか?」
「基本は、日本語、フランス語、英語、あと、大学でドイツ語を。第一次大戦前後のドイツ文学を勉強してましたから。特にリルケを。あと、ラテン語は読めます。それで、多少わかる言葉もありますけど――ルーマニア語とか――会話は難しいです。だから、何カ国語っていうのか、……」
P31
最後に名残惜しく交わした眼差しが、殊に「繊細で、感じやすい」記憶として残った。それは、絶え間なく過去の下流へと向かう時の早瀬のただ中で、静かに孤独な光を放っていた。彼方には、海のように広がる忘却!その手前で、二人は未来に傷つく度に、繰り返し、この夜の闇に抱かれながら、見つめ合うことになる。
P66
洋子の最初の赴任は、フセイン政権崩壊後、ようやく制憲議会選挙にまで漕ぎ着け、ジャアファリー首相の移行政府が誕生して、丁度その新憲法の国民投票が行われた時期だった。その後、改めて議会選挙が行われ、2006年5月に、ようやく現在のマーリキー政権が発足している。
P74
美しくないから、快活でないから、自分は愛されないのだという孤独を、仕事や趣味といった取り柄は、そんなことはないと簡単に慰めてしまう。そうして人は、ただ、あの人に愛されるために美しくありたい、快活でありたいと切々と夢見ることを忘れてしまう。しかし、あの人に値する存在でありたいと願わないとするなら、恋とは一体、何だろうか?
P171
まっすぐに伸びた鉄道の線路は、彼方の消失点で結び合っているように見える。しかし、一駅経ても二駅経ても風景は同じであり、その平行するレールは、当然のように決して交錯しない。現在から見て、いつか必ず一つになるように見えるその点は、いわば幻に過ぎなかった。
P189
洋子はふと、自分だけは、他のみんなが持っている脚本とは、違うものを手渡されているような不安を感じた。そして、慌ててページを確かめるように、現在を見つめ直し、過去を振り返り、八月末の彼との再会の場面を、何も間違っていないはずだと自らに言い聞かせながら思い描いた。
【余計な分析】
恋愛小説に必要な要素、それは・・・
2人を隔てる壁とすれ違い、そして運命と偶然による効果的な演出。
しかし、これだけ便利で平和な世の中だと、壁もすれ違いも表現しにくい。
携帯、スマホ、スカイプで、すれ違いも起きにくく、(建前として)平等の世の中でもある。
そこを運命と偶然のスパイスを効かせて物語を紡いでいく困難な作業。
…見事な文章と構成である。
最初、「マチネの終わりに」って、さえないタイトルだな、と思っていたが、最後に意味が分かる仕掛けになっている。
2016年単行本で、屈指の作品と思う。
【ネット上の紹介】
深く愛し合いながら一緒になることが許されなかった蒔野と洋子は再び巡り逢えるのか。感涙必至。悲恋に泣いた切ない大人の恋愛小説。
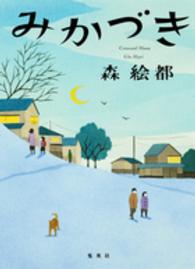
「みかづき」森絵都
とても面白かった。
昭和36年、大島吾郎は、勉強を教えていた児童の母親とともに学習塾を立ち上げる。
その子どもたち、さらに孫の世代と時代は移り変わっていく。
「塾」「教育」をテーマにした戦後史とも言える。
この作品を見逃してはいけない。
お薦めです。
P6
勉強ができない子は集中力がない。集中力がない子は瞳に落ちつきがない。この〈瞳の法則〉を見出して以来、吾郎はまず何よりも彼らの視線を一点にすえさせることに腐心した。
P25
「大島さん。私、学校教育が太陽だとしたら、塾は月のような存在になると思うんです。太陽の光を十分に吸収できない子どもたちを、暗がりの中に照らす月。今はまだ儚げな三日月にすぎないけれど、かならず、満ちていきますわ」
【おまけ】
久しぶりに、森絵都作品を読んだ。
もし、(本作以外で)森絵都ベスト3を選ぶとしたら…。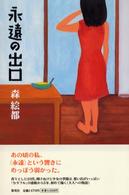
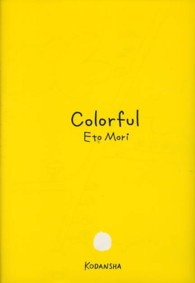
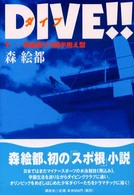
【ネット上の紹介】
昭和36年。小学校用務員の大島吾郎は、勉強を教えていた児童の母親、赤坂千明に誘われ、ともに学習塾を立ち上げる。女手ひとつで娘を育てる千明と結婚し、家族になった吾郎。ベビーブームと経済成長を背景に、塾も順調に成長してゆくが、予期せぬ波瀾がふたりを襲い―。山あり谷あり涙あり。昭和~平成の塾業界を舞台に、三世代にわたって奮闘を続ける家族の感動巨編!





















