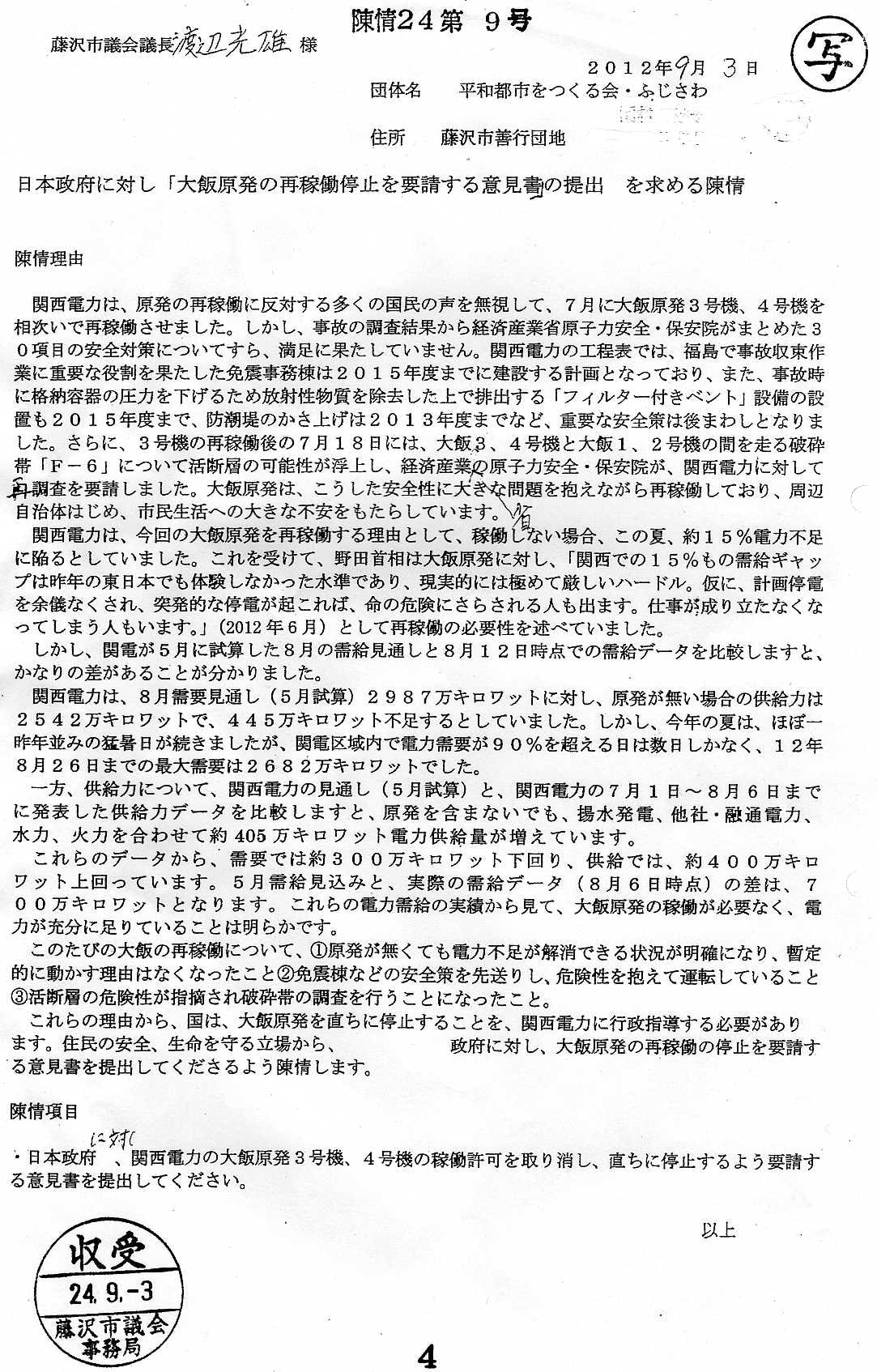6月26日の武田薬品工業株主総会
長谷川社長、湘南研究所のバイオ排水漏えい事故の
「外部調査会社」の公表を拒否

さる6月26日、大阪府立体育館に於いて、武田薬品第137回株主総会がもたれた。席上、株主より 2011年11月藤沢市にある湘南研究所で発生した遺伝子組み換え排水漏洩事故について、今年1月、その調査結果が発表されたが、調査を実施した企業名が記されていないので、その企業名を公表してほしいとの発言があった
しかし、答弁に立った長谷川社長は、調査を実施した第三者機関の企業名の公表を拒否。理由は、調査会社の選定については、数多くの外国のコンサルタントの中から、武田が信頼の置ける会社を選んだものであり、当該企業との約束もあって名前は公表できないと言うものであった。
株主は、企業名を公表しない等と言うことは、調査報告書の信頼性を著しく欠くものであり、どういう理由で公表しないことにしたのか分からないが、内外に調査実施を公約した武田薬品の社会的責任を果たす上からも、是非会社名を公表して欲しいと迫ったが、長谷川社長によって、それも拒否されたものである。
パソコン検索で外部調査会社の名前が明らかになっているのに、
公表を拒否し続ける武田薬品の非常識
株主は、更に、パソコン検索で明らかになった企業名を上げて公表を迫ったが、長谷川社長は、頑なに公表を拒否し続けた。パソコン検索で明らかになった調査会社の企業名は、英国に本社のあるERM(イー・アール・エム)日本という会社である。下記資料に示すように、武田薬品が公表した調査会社の概要とERM日本がパソコンで公表している会社概要が合致していることから、武田が秘匿し続ける調査実施企業の名前は、ERM日本と判明したものである。
長谷川社長はパソコン検索で企業名が明きらかになっているのに公表を拒否し続けるというのはどういうことなのか。湘南研究所のある地元市民からも、行政や藤沢市議会、鎌倉市議会からも公表を要請されながら、武田の私的な調査依頼だからとか、相手の企業との約束だから、と称して名前を公表しないなどと云うことは絶対に許されることではない。
資料1 <武田薬品が名前を秘匿して発表した調査会社の会社概要>
企業概要 ~外資系コンサルティング企業
労働安全衛生、社会、環境関連サービス
規模・拠点数~4,000名以上の専門家
世界で40ヶ国、140ヵ所以上のオフィス
実績 ~労働安全衛生、社会、環境関連サービスを40年以上にわたって提供、世界有数の環境
コンサルティング企業として、多数の受賞実績在り
強み ~日系企業を含む多くの多国籍企業に対する環境安全評価業務実績があり、国際的な事
例と比較した評価を行うことができる
資料2 <ERM日本(株)が、ホームページで公表している会社概要>
イー・アール・エム日本株式会社はERMグループの日本法人であり、日本企業、政府機関、日本で事業展 開する多国籍企業に対してサービスを提供しております。ERMは環境・社会・労働安全衛生に関わるリ スクマネジメントを専門に手がける世界有数のコンサルティング企業です。現在、世界約40ヶ国に140以上のオフィスを有し、4,000名超の専門家を擁しております。
商号 イー・アール・エム日本株式会社(ERM Japan Ltd.)
所在地 〒220-8119 横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー19階 TEL 045(640)3780
ERMグループ Global site
本社所在地 英国 ロンドン
事業所所在国数 40カ国(2012年1月現在)
オフィス数 140ヶ所(2012年1月現在)
従業員数 4000名(2012年1月現在)
何故、武田薬品は外部調査会社の名前の公表を拒否するのか
独善的で独りよがりの安全対策はもっとも危険
今回の調査会社名の非公開は、相手会社との約束によるものだとしているが、調査報告の中味を見る限り、公表して差しつかえるものは何も見当たらない。特に会社名を秘匿してまで機密を守らなければならない内容もない。一般常識から言えば、アセスを実施した会社名をあげ、その会社の調査である事によって、アセスの信憑性が高まるものであるが、今回のケースは逆で、調査会社を公表しなくても、武田薬品が最も適切であると判断して依頼した会社からの調査報告だから名前を公表しなくとも信用できるという武田薬品本位の長谷川社長の言い分には、呆れるばかりである。
何故、武田薬品は頑なに外部調査会社の名前の公表を拒否するのか。実際問題として、今回の調査報告書は、バイオ事故に対する調査報告になっていないところに問題がある。調査目的についても、単なる設備、機器、等の安全生ばかりで無く、バイオ研究所としての安全性を調べるのが本来の調査の目的であったはずなのに、その点についてほとんど触れられていない。肝心の事故を起こした集中滅菌方式についても、武田が従来からやっていた方式であり効率的である、行政から何の指摘もない、という武田の言い分を是認するだけで、調査会社独自の見解はほとんどみあたらない。調査会社としても、バイオ事故原因調査として請けたのではないのか。報告書は研究所全体の安全調査がほとんどである。自らが実施した調査報告に肝心の会社名すら公表しない調査報告など、信用性に乏しく、とうてい社会的認知が受けられるものではない。独善的で独りよがりの安全対策は最も危険である。真に武田薬品湘南研究所の安全性を検証するには、再度、名前を公開した別のバイオ専門の調査会社による安全調査が求められているといわなければならない。











 写真1 生ゴミを毎日プランタ-に埋める 写真2、生ゴミの上に米ぬかをかぶせる
写真1 生ゴミを毎日プランタ-に埋める 写真2、生ゴミの上に米ぬかをかぶせる