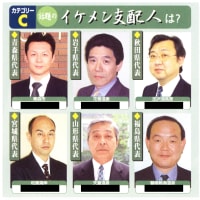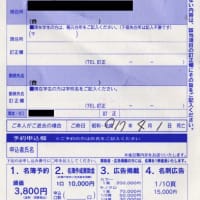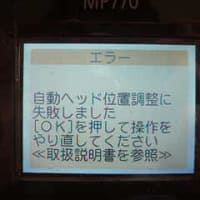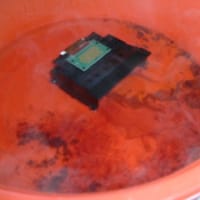藤谷美和子は、今回のご成婚をかなり喜んでいるだろうなぁ
大江健三郎や村上春樹の文庫の背表紙を見ますと、いつも、
「著者の新境地」
とか、
「あらたな地平を開く作品」
という文句が書いている、…………ようなイメージがあります。
まぁ、初期と現在の作品を比べると、文体やら思想やら文学の姿勢やら印税やら、いろいろと違うことは分かります。
が、結局、大江健三郎は大江健三郎だし、村上春樹は村上春樹であるのも当たり前です。
タイムリーに読んでいると、その作家の変遷が手に取るように分かるのですが、まとめて読んでしまうと、
「また、コレか…………」
という印象が残ってしまうものです。
……………もっとも、これは小説に限らないですけどね。
で、高橋和巳。
苦悩の巨人、です。
はてなダイアリーでは、こんな風に解説されております。
「革命の世代を生きるインテリゲンチャの苦悩をテーマ」。簡潔で要領を得たまとめです。
高橋和巳の作品は、知識人がエロ(女)で失敗して、周りの人間を不幸にして、自滅していく、という筋です。
で、根本的な訴えは、「おれは、こんなに苦しんでいるんだ! だから、どうか許しておくれ」という自己憐憫です。(「悲の器」「我が心は石にあらず」なんて、もうタイトルからして、自己憐憫の何ものでもないもんな)
でも、大好きな作家です。
本を読み返すよりは、新しい作品を手に取るタイプなのですが、「悲の器」に関しては二度読んでいます。そして、また読みたいと思っています。
その前に、どうしても読んでおきたかった「邪宗門」。
なかなか本屋で見つけられず、注文するのも億劫だったのですが(「どうしても読んでおきたかった」というわりには〝億劫〟って………)、引っ越したのを機に使い始めたAmazonで簡単に取り寄せ出来ました。
オウム事件の際に、ちょっと騒がれた本ですので、高橋和巳を知らなくても、この作品名を知っている方もいるのでは? ……………と言いたいところですが、そこまで騒がれていませんね。
上巻のストーリーをかい摘んで話すと、「ひのもと救霊会」という戦前の新興宗教団体が、統制を強め始めた政府(権力)によって弾圧され、幹部を根こそぎ検挙されるまでの第一部。
それか数年後、太平洋戦争を控えて、崩壊の瀬戸際まで追い詰められた「ひのもと救霊会」が、かつての支部組織から独立した救世軍に吸収されるまでを描いた第二部になります。
群像劇ではありますが、主人公は千葉潔という少年になります。
が、少年でありながら、ぬぐい難い罪を背負っているという設定。
最初に彼と見えた教主は、こんなことを話しています。
教団の児でありながら、無神論者…………もう、この設定だけで、しびれてしまいます。
宗教団体に属しながら、神を信じないで許される存在…………つまり、少年自身が神ということなんでしょうか? それを暗示させるような、少年の能力が発揮される場面もあるのですが、…………さて、どうなんだろう?
で、この少年が、天皇への直訴(正確には直訴ではないのですが)を図ります。今でも、一宗教団体がそのような行為に及ぶとなれば、どんな結末になるのかは言うまでもありません。
まして、戦前ですから、「ひのもと救霊会」は、この事件によって容赦なく弾圧されてしまいます。
で、第二部。
高橋和巳らしく、かつては理想に燃えていたキャラも、すっかり現実によって色あせて登場します。
この極端なまでの人間への酷薄さ。まさしく高橋和巳です。
こんなふうに、いつもと変わらずの陰陰滅滅とした世界を堪能できるようになっています。
でも、同じ群像劇である「憂鬱なる党派」よりも、物語の幅が広いので、個人的には飽きずに楽しめます。
人間が堕ちていくことを「クスクス」と読めるような方には、かっこうの小説となっています。(つまりは、いつもの高橋和巳です)
大江健三郎や村上春樹の文庫の背表紙を見ますと、いつも、
「著者の新境地」
とか、
「あらたな地平を開く作品」
という文句が書いている、…………ようなイメージがあります。
まぁ、初期と現在の作品を比べると、文体やら思想やら文学の姿勢やら印税やら、いろいろと違うことは分かります。
が、結局、大江健三郎は大江健三郎だし、村上春樹は村上春樹であるのも当たり前です。
タイムリーに読んでいると、その作家の変遷が手に取るように分かるのですが、まとめて読んでしまうと、
「また、コレか…………」
という印象が残ってしまうものです。
……………もっとも、これは小説に限らないですけどね。
で、高橋和巳。
苦悩の巨人、です。
はてなダイアリーでは、こんな風に解説されております。
| 作家。 1931年8月31日生まれ、大阪府出身。1971年5月3日没。享年39歳。京都大学文学部卒業。 小松左京らとの「現代文学」の発行などを経て作家に。61年、長編小説「悲の器」で第1回文芸賞を受賞。主な著作に「邪宗門」「憂鬱なる党派」「捨子物語」「我が心は石にあらず」「わが解体」など。革命の世代を生きるインテリゲンチャの苦悩をテーマに数多くの作品を残し「苦悩教の始祖」と呼ばれる。 はてなダイアリー「高橋和巳」 |
「革命の世代を生きるインテリゲンチャの苦悩をテーマ」。簡潔で要領を得たまとめです。
高橋和巳の作品は、知識人がエロ(女)で失敗して、周りの人間を不幸にして、自滅していく、という筋です。
で、根本的な訴えは、「おれは、こんなに苦しんでいるんだ! だから、どうか許しておくれ」という自己憐憫です。(「悲の器」「我が心は石にあらず」なんて、もうタイトルからして、自己憐憫の何ものでもないもんな)
でも、大好きな作家です。
本を読み返すよりは、新しい作品を手に取るタイプなのですが、「悲の器」に関しては二度読んでいます。そして、また読みたいと思っています。
その前に、どうしても読んでおきたかった「邪宗門」。
なかなか本屋で見つけられず、注文するのも億劫だったのですが(「どうしても読んでおきたかった」というわりには〝億劫〟って………)、引っ越したのを機に使い始めたAmazonで簡単に取り寄せ出来ました。
オウム事件の際に、ちょっと騒がれた本ですので、高橋和巳を知らなくても、この作品名を知っている方もいるのでは? ……………と言いたいところですが、そこまで騒がれていませんね。
上巻のストーリーをかい摘んで話すと、「ひのもと救霊会」という戦前の新興宗教団体が、統制を強め始めた政府(権力)によって弾圧され、幹部を根こそぎ検挙されるまでの第一部。
それか数年後、太平洋戦争を控えて、崩壊の瀬戸際まで追い詰められた「ひのもと救霊会」が、かつての支部組織から独立した救世軍に吸収されるまでを描いた第二部になります。
群像劇ではありますが、主人公は千葉潔という少年になります。
が、少年でありながら、ぬぐい難い罪を背負っているという設定。
最初に彼と見えた教主は、こんなことを話しています。
| 「温泉で思いだしたが、先刻、風呂にはいった時、薪をくべてくれていた少年は誰かね。先日ここへ帰った時も阿礼の後につき従うようにして玄関に出迎えていたが」 「堀江のお駒さんが拾ってかえった子でしてね。少し陰気なところのある子ですけれど、気立てはやさしい子のようです」 「なにかお気にさわることをしましたか」堀江駒が心配して言った。 「いやいや、植田が薪をくべているのかと思って声をかけてみたら、あの少年だった。君は誰かと訊いたら、旧姓は千葉潔だが、今はひのもと潔、つまり教団の児だというのでね。おぬし神を信ずるかときいてみた。すると、きっぱりと信じませんと答えおった」 高橋和巳「邪宗門 (上)」169頁 朝日文芸文庫 |
宗教団体に属しながら、神を信じないで許される存在…………つまり、少年自身が神ということなんでしょうか? それを暗示させるような、少年の能力が発揮される場面もあるのですが、…………さて、どうなんだろう?
で、この少年が、天皇への直訴(正確には直訴ではないのですが)を図ります。今でも、一宗教団体がそのような行為に及ぶとなれば、どんな結末になるのかは言うまでもありません。
まして、戦前ですから、「ひのもと救霊会」は、この事件によって容赦なく弾圧されてしまいます。
で、第二部。
高橋和巳らしく、かつては理想に燃えていたキャラも、すっかり現実によって色あせて登場します。
| だが彼は行かなかった。植田文麿はすでに純真な士官候彼生ではなかった。理想は破れ、自決することもできず、しかも出所して彼の世の中の動きは、彼が何者かに道具として利用されたことを如実に示していた。そして、失敗し裏切られた革命家が多くそうであるように、自分が無力であるゆえに、彼は今この社会がより堕落し、より悲惨になることを望んでいた。 高橋和巳「邪宗門 (上)」496頁 朝日文芸文庫 |
こんなふうに、いつもと変わらずの陰陰滅滅とした世界を堪能できるようになっています。
でも、同じ群像劇である「憂鬱なる党派」よりも、物語の幅が広いので、個人的には飽きずに楽しめます。
人間が堕ちていくことを「クスクス」と読めるような方には、かっこうの小説となっています。(つまりは、いつもの高橋和巳です)
 | 邪宗門〈上〉朝日新聞このアイテムの詳細を見る |