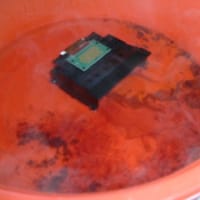日本人にとって戦争は遠すぎるね
かつてティム・オブライエンの「本当の戦争の話をしよう」を、まずまず楽しく読ませてもらいました。
で、今度は同じ作家の「ニュークリア・エイジ」にしようと本屋に行って、買ってしまったのが「本当の戦争の話をしよう」です。
自分でも意味が分かりません。
年を取ったということですね。
池澤夏樹の「マシアス・ギリの失脚」でも、やっちゃったんだよな。まぁ、「本当の戦争の話をしよう」も「マシアス・ギリの失脚」も、いい小説ですけどね。
で、また読ませてもらった「本当の戦争の話をしよう」。
著者のベトナム戦争体験をもとにした、短編小説集です。
戦争というものによって、日常が損なわれてしまった人間の物語が描かれています。例えば、「レイニー河で」という短編では、大学を卒業したばかりで徴兵通知を受け取ってしまった人間の話です。
が、主人公は、徴兵を前にして、カナダへの逃亡をはかろうとします。
子供のころから抱いていた素朴な信念が、社会からの試練によって無残に屈してしまうという構図であるため、戦争を体験していない僕でも、感じるものがあります。
そんなわけで、訳者の村上春樹は、あとがきで以下のように述べています。
分からんでもないです。
村上春樹も「極端な言い方かもしれないけれど」と予防線を張っていますので、重箱の隅をつつくのもなんですが、しかし「この本における戦争とは、あるいはこれはいささか極端な言い方かもしれないけれど、ひとつの比喩的な装置である」というのは、極論じゃないかな?
この本における「ベトナム戦争」という前景は、なにかと交換可能ではないからこそ、作者としてはこうまで拘泥せざる得ないように僕には思えます。
作者としては、やっぱり現実の戦争を描きたかったのでは?
本書の短編には、全て「ちゃんと結末があ」ります。掌編と呼べるような物語もありますが、どれも戦争を充満させている作品です。単純な反戦小説ではないことは確かですが、戦争の意味を考えさせられるものばかりです。
少しかための短編小説が読みたい方には、ちょうどよろしいのでは?
かつてティム・オブライエンの「本当の戦争の話をしよう」を、まずまず楽しく読ませてもらいました。
で、今度は同じ作家の「ニュークリア・エイジ」にしようと本屋に行って、買ってしまったのが「本当の戦争の話をしよう」です。
自分でも意味が分かりません。
年を取ったということですね。
池澤夏樹の「マシアス・ギリの失脚」でも、やっちゃったんだよな。まぁ、「本当の戦争の話をしよう」も「マシアス・ギリの失脚」も、いい小説ですけどね。
で、また読ませてもらった「本当の戦争の話をしよう」。
著者のベトナム戦争体験をもとにした、短編小説集です。
戦争というものによって、日常が損なわれてしまった人間の物語が描かれています。例えば、「レイニー河で」という短編では、大学を卒業したばかりで徴兵通知を受け取ってしまった人間の話です。
| 私は思うのだけれど、人は誰しもこう信じたがっているのだ。我々は道義上の緊急事態に直面すれば、きっぱりと勇猛果敢に、個人的損失や不真面目などものともせずに、若き日に憧れた英雄のごとく行動するであろうと。(ティム・オブライエン「本当の戦争の話をしよう」71頁 文春文庫) |
子供のころから抱いていた素朴な信念が、社会からの試練によって無残に屈してしまうという構図であるため、戦争を体験していない僕でも、感じるものがあります。
そんなわけで、訳者の村上春樹は、あとがきで以下のように述べています。
| オブライエンはもちろん戦争を憎んでいる。でもこれはいわゆる反戦小説ではない。あるいはまた戦争の悲惨さや愚劣さを訴えかける本でもない。この本における戦争とは、あるいはこれはいささか極端な言い方かもしれないけれど、ひとつの比喩的な装置である。それはきわめて効率的に、きわめて狡猾に、人を傷つけ狂わせる装置である。それがオブライエンにとってはたまたま戦争であったのだ。そういう文脈で言うなら、人は誰もが自分の中に自分なりの戦争を抱えている。(同書392頁 文春文庫) |
村上春樹も「極端な言い方かもしれないけれど」と予防線を張っていますので、重箱の隅をつつくのもなんですが、しかし「この本における戦争とは、あるいはこれはいささか極端な言い方かもしれないけれど、ひとつの比喩的な装置である」というのは、極論じゃないかな?
この本における「ベトナム戦争」という前景は、なにかと交換可能ではないからこそ、作者としてはこうまで拘泥せざる得ないように僕には思えます。
作者としては、やっぱり現実の戦争を描きたかったのでは?
| ミッチェル・サンダーズはじっと彼を見た。 「そんなことはさせねえ」 「させねって、何のことよ?」 「なあおい、そういうのはルールに反しているんだ!」とサンダーズは言った。「人間性ってものに背いてるんだ。よくできた話ってのにはな、ちゃんと結末があるんだ。いや、実は最後がどうなったか私は知りません、なんて話があるもんか。いいか、話をするにはそれなりの責務ってものがあるんだぞ」(同書182頁 文春文庫) |
本書の短編には、全て「ちゃんと結末があ」ります。掌編と呼べるような物語もありますが、どれも戦争を充満させている作品です。単純な反戦小説ではないことは確かですが、戦争の意味を考えさせられるものばかりです。
少しかための短編小説が読みたい方には、ちょうどよろしいのでは?
 | 本当の戦争の話をしよう文芸春秋このアイテムの詳細を見る |