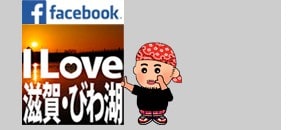炎のクリエイター 撮影 & 画像補正
このブログに使用の画像は、殆んどを「iPhone15 pro」で撮り「CANON Power Shot G7XⅡ」と「CANON一眼」などの撮影機器でフォローしています。画像に補正を施せば、とっておきの一枚を奇麗にできます。 ※画像の転載・転用は禁止させて頂きます。
 武家の政権下では、お米で家臣の報酬を決めていたため、お米の田植えは何よりも大事な時期としていた。しかし裏では飢饉に備えて「麦」を植えていて、この田植え時期が麦の収穫時期で、半年の締め括りとして大事な時期と考え、麦にとっての実りの秋と考え「麦秋」と表現したようだ。
武家の政権下では、お米で家臣の報酬を決めていたため、お米の田植えは何よりも大事な時期としていた。しかし裏では飢饉に備えて「麦」を植えていて、この田植え時期が麦の収穫時期で、半年の締め括りとして大事な時期と考え、麦にとっての実りの秋と考え「麦秋」と表現したようだ。
 武家の政権下では、お米で家臣の報酬を決めていたため、お米の田植えは何よりも大事な時期としていた。しかし裏では飢饉に備えて「麦」を植えていて、この田植え時期が麦の収穫時期で、半年の締め括りとして大事な時期と考え、麦にとっての実りの秋と考え「麦秋」と表現したようだ。
武家の政権下では、お米で家臣の報酬を決めていたため、お米の田植えは何よりも大事な時期としていた。しかし裏では飢饉に備えて「麦」を植えていて、この田植え時期が麦の収穫時期で、半年の締め括りとして大事な時期と考え、麦にとっての実りの秋と考え「麦秋」と表現したようだ。