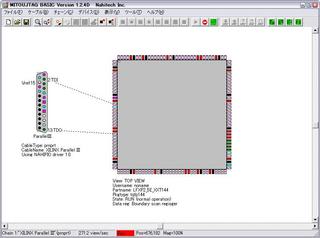「光る電子工作がしたい」の特集号のプレゼント応募締め切りがせまっています。5/1(当日消印有効)です。応募方法はp.8にある事項を書きこんでメールを送ります。
ちなみにエレキジャックNo.12のeJackino基板プレゼントの締め切りは5/17です。
ちなみにエレキジャックNo.12のeJackino基板プレゼントの締め切りは5/17です。











`default_nettype none
module main(LED);
output reg [1:0] LED = 2'b00;
wire clk;
OSCE clkgen(clk);
defparam clkgen.NOM_FREQ = "40.0";
reg [22:0] ctr;
wire ctr_en = ctr == 0;
always @(posedge clk)
ctr <= ctr + 1;
always @(posedge clk)
if(ctr_en) LED <= LED + 1;
endmodule
`default_nettype none
module main(
output reg [1:0] LED = 2'h0,
input clk);
reg [22:0] ctr = 23'h0;
wire ctr_en = ctr == 23'h0;
always @(posedge clk)
ctr <= ctr + 1;
always @(posedge clk)
if(ctr_en) LED <= LED + 2'h1;
endmodule