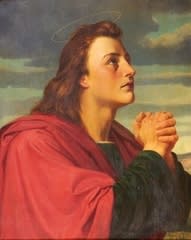
この世の福音現象を批評しますと、議論が軽薄に流れる傾向が生じますので、「ヨハネ伝解読」にもどりましょう。著書の売れ行きなどについては、また、流れの中で書きますからね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
=聖句=
 「過ぎ越の祭りの前だった。イエスはこの世を離れ父のみもとに行く時が来ていることを悟った。彼は自分のものとなった、この世の人々を常に愛された。彼らを最後まで愛し通された」(13章1節)
「過ぎ越の祭りの前だった。イエスはこの世を離れ父のみもとに行く時が来ていることを悟った。彼は自分のものとなった、この世の人々を常に愛された。彼らを最後まで愛し通された」(13章1節)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13章に入りました。ヨハネはここで、有名な出来事について記しています。イエスが弟子の足を洗う、という場面がそれであります。
だが、その前に、「イエスは、自分のものとなった、この世にいる人々を、最後まで愛し通された」とヨハネは記しています(1節)。13章は、まずはこれから・・・。

<イエス第一の使命は、悪魔の本性の証拠を挙げること>
ここでヨハネは、イエスが最後まで愛し通されたのは、「イエスのものとなった人々」といっています。「世の人々全部」とはいっていない。もしそうなら、他の人に対して、少し冷たいではないでしょうか。どうしてそんなことを書くのでしょうか。
むずかしいところですが、こういうことではないでしょうか。そもそも聖書で記されているイエスにとって、根本的なことは、父なる創主より与えられた自らの使命を全うすることであります。それは第一には、十字架で殺されることによって、悪魔の本性を表に出すことです。こうして、証拠を明らかにし、裁きを可能にする---これです。
それによって、同時に、天国に入る資格を失ってしまっている人類に、それが可能になる道が創られます。だから、これは、第一のことと表裏の位置にある。ですけれども、聖書の論理構造からみるとこれha
第二の使命、というべきものであります。
人間中心主義で聖書を読む人は、こういうと目をむくでしょうけどね。なかには「異端!」と言いふらす教職者も出ている。まあこれもしょうがないでしょうね。

<救いの道は条件付きの道>
イエスが開いた救いの道は、可能性の道であります。救いを現実化するには、「この道を真理だと受け入れて天国行きの資格を得る(これを「救い」と言います)」ことが必要だ。そういう条件付きの道です。

<自由意志が働く状態で、弟子に任せてバイバイ>
そして、この「救い」を現実化するというのは、100%イエスの仕事というわけではないのですね、聖書の論理構造では。なぜなら、これを認めて資格をうる際には、人間の自由意志が働く余地があるようにつくられていますから。
だから、認めない人も出うる。そういう状態にしておいてイエスは天国に帰っていってしまうのです。「救い」をうることの半分は人間個々人の問題でもあることにしてバイバイしていった。これが福音の構図です。

もちろんイエスは、真理として受け入れて「救われる」資格を得る方法を説いたメッセージをも発しています。そして、弟子が出来ます。でもこの弟子たちは、自由意志を認められた状態で、認知し、考え、決断して教えを受け入れてきている人々なのですね。
で、イエスは、自分は復活して父なる創主の王国である天国に帰っていってしまう。その後の、人間の救いに関することは、弟子の伝道に任せていってしまったことになります。
イエスは天国でもって、「自分のものとなった」人間の祈りを見て、それを全能の創造主に「とりなし」します。祈りが聞き届けられ、創主から応えられるように、です。
また、助け主、証し主としての聖霊を送ってきます(その話は後の章に出てきます)。だが、それだって、「宣べ伝えるものを」助けるだけの助け主です。聖霊が自ら人間の姿をとって、教えてしまうわけではないのです。

もう伝道の働きをするのは弟子たちだけとなるのです。彼らの伝道を受け入れて、また、新しい伝道者が出来ていきます。その輪が世界にまで広がります。それが現代の状態です。教えは最大の世界宗教になるほどまでに、展開してきています。
けれども、人間のやる伝道です。「救いを受けいれない人」もたくさん生まれ、死んできました。これまでのところでは、そういう人の数は、いわゆる「救いを受けた」人の何十倍でしょう。
イエスの第二の使命「人類の救い」というのは、結果的にそういう部分的なものになる。これを私たちはよく知らねばなりません。冷たいようですけどね。イエス様をもっと暖か~いイメージにしておきたい気持はわかりますけどね。

<受け入れたものだけが「イエスのもの」>
この、イエスの「教えを受け入れた者」を、ヨハネは「自分(イエス)のものとなった、この世の人々」といっています。そして、そういう人々(だけ)を「イエスは最後まで愛し通された」とヨハネはいうのです。
では、他の人は? イエスはまあ「哀れみ」は持たれたでしょう。だから福音を説いたのでしょうからね。だけど、それでも自分の者と成らなかったらどうか。もうこれはイエスもどうすることも出来ないのです。
では憎んだか? 憎むこともなかったでしょう。彼らにそうなるように影響を与える悪魔は憎みますけどね。では、愛したか? この人たちは「最後まで愛し通された」枠の外にいますから、愛することもない。
では、憎みも愛もしないというのはどういうこと? つまりそれは「どうでもいい」ということなんですね。どうでもいい存在なんだ、イエスにとって。冷たいかなあ~。だって論理的にそうしかならないんだからね・・・。






















