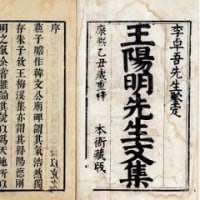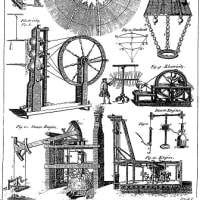よく知られているように、韓国、北朝鮮(以下、朝鮮と総称する)では戦後、数十年の長きにわたり公的には漢字が使用されていない。最近、ようやく韓国では小学校で漢字を教える方針に変えようとする報道があった。(2015年4月29日、韓国・SBSニュース)しかし、小学生自身はもちろんのこと親たちも、漢字学習で子供の勉強の負担が増える、といって反対する意見が8割ちかくもあるとのことだ。(2015年9月5日、ハンギョレ新聞)
しかし、ハングルだけではまともな教育ができないのは周知の事実だ。
韓国語では「素数」と「小数」がまったく同じ発音と綴りである。これではたして数学が理解できるであろうか? また韓国の新幹線である KTXの路線施工にミスが発生したが、これは設計書指定の「防水」を「放水」「防守」「防銹」「傍受」のどれか分からずに、「防水」とはまったく逆の意味に解釈して「吸水」の材料を使ったため、凍結膨張、破壊という惨事に至ったという報道があった。(出典: 『社会人のリベラルアーツ』 P.300)
と、ここまでのことは今さら蝶々するまでもなく、広く知られていることだ。しかし、かつての漢字圏(中国、朝鮮、日本、ベトナム)で漢字を廃止したのはなにも朝鮮だけではない。ベトナムも 19世紀のフランス支配下でローマ字表記がひろまり、戦後は完全に漢字を廃止した。
つまり、朝鮮とベトナムは漢字を完全に廃止したが、日本はそうではなかった。日本と朝鮮という二項対立で考えるのではなく、ベトナムもいれて三項で考えると、漢字を廃止する(あるいは廃止できる)条件が見えてくる。
朝鮮では、古くは高麗では高度な整版印刷技術が、また李氏朝鮮では活字印刷技術があったために自国で本を印刷していた。しかし、朝鮮文学史を読むと、15世紀にハングルが創字されてたが、ハングルで書かれた書物の数はかなり限定的であることが分かる。私見を述べれば、15世紀から20世紀にかけての500年間に書かれたハングル文学で、まともなものは 20作品にも満たない。(少し、大目にみても、せいぜい50作品程度である。)

一方ベトナムは中国(明)からの圧力で自国での印刷は長らくできなかった。それゆえ、自国の言葉をそのまま文字に表わすことが19世紀に至るまでできなかった。ベトナム文学史はまだきっちりとは調べていないが、少なくともベトナム史にでてくる情報から判断すると、ベトナム人の手になる漢文の文学作品はかなりあったようだ。しかし、庶民の生活を反映したいわゆる、世話物や風俗的なものは全く見当たらない。
この両国に共通しているのは、
1.庶民は文字(漢字)を使わない生活をしていた。
2.つまり、庶民は単語や文章は耳から聞いて理解していた。
ということだ。日本との比較で両国の状況を考えてみると、これら両国の庶民は、日本でいうと、琵琶法師が平家物語を、あるいは講談師が講談を語る時のように、耳で聞いて理解していたのだろう。つまり耳で聞くかぎり漢字は必要ではない。
一方、日本では江戸時代に庶民の生活に密着した段階にまで文字(漢字かな交じり文)が定着し、それによって、文学が知識階級だけでなく、国民全体の共有財産となった。つまり、漢字は音で理解するものではなく、視覚で理解するものだとの認識を日本人全体が持つようになったのだ。
このような比較から、なぜ朝鮮とベトナムでは漢字を捨てることができたのかを理解することができる。つまり、漢字を読むという習慣がこの2国では庶民にまで広まっていなかった、つまり国民全体が共有する伝統ではなかったということだ。その結果、漢字で綴られた文学作品は存在はするものの、国民の共有財産ではないのである。漢字に対する愛着心がないのだ。結局、これら両国は日本より早くから漢字が入ったものの、一度たりとも、彼らの国語にとって漢字が本当の身内になったことはないのである。
日本では漢字が血肉になっているので、漢字がない国語など想像することは困難であるが、彼らの状況を疑似体験する方法はある。それは、カタカナ表記されている英語(や他の言語)の単語の意味を理解しようとしてみることだ。カタカナ単語は馴染みの単語なら耳から聞けば意味は分かるが、正確な綴りや本当の意味は知らないことが多いだろう。あまり使わない単語、とりわけ抽象的な単語などは、ぼやっとした意味しかとらえることができないだろう。例えば、『パラダイム』『アジェンダ』『コンプライアンス』『フリンジベニフィット』などは、綴りもきっちりかけないし、意味もあやふやだろう。
朝鮮、ベトナムのどちらの言語も語彙の7割から8割は漢字由来である。したがって、日常生活はさておき、少しでも高度な話になると抽象的な漢字の単語が使われるが、その時に両国の大多数の庶民の感じる不安感はまさしく、『コンプライアンス』『フリンジベニフィット』などのカタカナ単語に戸惑い、苛立つ日本人の気持ちそのものであろうと、想像する。それだけでなく、本場中国も含め、漢字に侵された国々では漢字を見て、視覚情報(文字)を正しく理解できない限り、本当の意味はつかめない。
これから敷衍すると、日本語において馴染みのないカタカナ語は英語の意味を理解していないといつまで経っても正しく理解できないのと同様、英語においても、難解単語のベースとなっているギリシャ語やラテン語を知らないと、いつまで経っても英語の語彙力は伸びないままだ。この意味で私は『社会人のリベラルアーツ』の第6章では、英語力の向上のためにギリシャ語やラテン語を『草野球式』に学習することを勧めているのである。
しかし、ハングルだけではまともな教育ができないのは周知の事実だ。
韓国語では「素数」と「小数」がまったく同じ発音と綴りである。これではたして数学が理解できるであろうか? また韓国の新幹線である KTXの路線施工にミスが発生したが、これは設計書指定の「防水」を「放水」「防守」「防銹」「傍受」のどれか分からずに、「防水」とはまったく逆の意味に解釈して「吸水」の材料を使ったため、凍結膨張、破壊という惨事に至ったという報道があった。(出典: 『社会人のリベラルアーツ』 P.300)
と、ここまでのことは今さら蝶々するまでもなく、広く知られていることだ。しかし、かつての漢字圏(中国、朝鮮、日本、ベトナム)で漢字を廃止したのはなにも朝鮮だけではない。ベトナムも 19世紀のフランス支配下でローマ字表記がひろまり、戦後は完全に漢字を廃止した。
つまり、朝鮮とベトナムは漢字を完全に廃止したが、日本はそうではなかった。日本と朝鮮という二項対立で考えるのではなく、ベトナムもいれて三項で考えると、漢字を廃止する(あるいは廃止できる)条件が見えてくる。
朝鮮では、古くは高麗では高度な整版印刷技術が、また李氏朝鮮では活字印刷技術があったために自国で本を印刷していた。しかし、朝鮮文学史を読むと、15世紀にハングルが創字されてたが、ハングルで書かれた書物の数はかなり限定的であることが分かる。私見を述べれば、15世紀から20世紀にかけての500年間に書かれたハングル文学で、まともなものは 20作品にも満たない。(少し、大目にみても、せいぜい50作品程度である。)

一方ベトナムは中国(明)からの圧力で自国での印刷は長らくできなかった。それゆえ、自国の言葉をそのまま文字に表わすことが19世紀に至るまでできなかった。ベトナム文学史はまだきっちりとは調べていないが、少なくともベトナム史にでてくる情報から判断すると、ベトナム人の手になる漢文の文学作品はかなりあったようだ。しかし、庶民の生活を反映したいわゆる、世話物や風俗的なものは全く見当たらない。
この両国に共通しているのは、
1.庶民は文字(漢字)を使わない生活をしていた。
2.つまり、庶民は単語や文章は耳から聞いて理解していた。
ということだ。日本との比較で両国の状況を考えてみると、これら両国の庶民は、日本でいうと、琵琶法師が平家物語を、あるいは講談師が講談を語る時のように、耳で聞いて理解していたのだろう。つまり耳で聞くかぎり漢字は必要ではない。
一方、日本では江戸時代に庶民の生活に密着した段階にまで文字(漢字かな交じり文)が定着し、それによって、文学が知識階級だけでなく、国民全体の共有財産となった。つまり、漢字は音で理解するものではなく、視覚で理解するものだとの認識を日本人全体が持つようになったのだ。
このような比較から、なぜ朝鮮とベトナムでは漢字を捨てることができたのかを理解することができる。つまり、漢字を読むという習慣がこの2国では庶民にまで広まっていなかった、つまり国民全体が共有する伝統ではなかったということだ。その結果、漢字で綴られた文学作品は存在はするものの、国民の共有財産ではないのである。漢字に対する愛着心がないのだ。結局、これら両国は日本より早くから漢字が入ったものの、一度たりとも、彼らの国語にとって漢字が本当の身内になったことはないのである。
日本では漢字が血肉になっているので、漢字がない国語など想像することは困難であるが、彼らの状況を疑似体験する方法はある。それは、カタカナ表記されている英語(や他の言語)の単語の意味を理解しようとしてみることだ。カタカナ単語は馴染みの単語なら耳から聞けば意味は分かるが、正確な綴りや本当の意味は知らないことが多いだろう。あまり使わない単語、とりわけ抽象的な単語などは、ぼやっとした意味しかとらえることができないだろう。例えば、『パラダイム』『アジェンダ』『コンプライアンス』『フリンジベニフィット』などは、綴りもきっちりかけないし、意味もあやふやだろう。
朝鮮、ベトナムのどちらの言語も語彙の7割から8割は漢字由来である。したがって、日常生活はさておき、少しでも高度な話になると抽象的な漢字の単語が使われるが、その時に両国の大多数の庶民の感じる不安感はまさしく、『コンプライアンス』『フリンジベニフィット』などのカタカナ単語に戸惑い、苛立つ日本人の気持ちそのものであろうと、想像する。それだけでなく、本場中国も含め、漢字に侵された国々では漢字を見て、視覚情報(文字)を正しく理解できない限り、本当の意味はつかめない。
これから敷衍すると、日本語において馴染みのないカタカナ語は英語の意味を理解していないといつまで経っても正しく理解できないのと同様、英語においても、難解単語のベースとなっているギリシャ語やラテン語を知らないと、いつまで経っても英語の語彙力は伸びないままだ。この意味で私は『社会人のリベラルアーツ』の第6章では、英語力の向上のためにギリシャ語やラテン語を『草野球式』に学習することを勧めているのである。