《管理者から一言》2015年5月、水谷保孝・岸 宏一著『革共同政治局の敗北 1975~2014――あるいは中核派の崩壊』(白順社)が出版された。同書の帯には次のように書かれている。「1960年代以来、ラディカル左翼のトップランナーだった中核派が、テロ・リンチの果てに政治的頽廃を重ね、無惨に顚落して行く……。/闇の党首清水丈夫を仮借なくひき剥がす。/日本の社会運動史上類のない瞠目の党内闘争ドキュメント。」と…。確かに、同書は当事者自身が同時代的な、あるいは同時進行的な党内闘争のドキュメントを明らかにしたのである。それに賛同、共感するか、批判、敵対するかを問わず、同書が戦後日本の階級闘争の歴史においてほとんど例をみない文献となっていることはまちがいないと言えよう。議論が広がり、深まることを期待する。当ブログでは、まず同書の「諸言」を転載する。
………………………………………………………………………………………………………
『革共同政治局の敗北 1975~2014』から「緒言」

本書を執筆する動機と目的について、簡潔に記しておきたい。
本書のテーマは革命的共産主義者同盟全国委員会(革共同、いわゆる中核派)の分裂と転落の歴史および実相の切開である。これは、筆者らにとって臓腑をえぐられるほどつらいものであり、元同志らをはじめ左翼運動に関心をもつより多くの読者の皆さんにとっても、暗く、重く、失望の念を禁じえないような幾多の事象をつづることになる。しかし、どうしても書いておかなければならない、と筆者らは考えたのである。
一つは、革共同の党員および党籍をおいた者は、二〇〇六年三・一四党内リンチ=クーデターをめぐって起こった、数年間にわたるすべての事実を知る権利があるということである。
三・一四Ⅱ(以下、七五年三月一四日のカクマルによる本多延嘉書記長虐殺と区別するために、三・一四Ⅱあるいは三・一四党内リンチと表記)をめぐって革共同は大きくは中央政治局派(議長・清水丈夫、副議長・故中野洋、書記長・天田三紀夫、田中康宏[松丘静司]、現中央労対部長・辻川慎一[大原武史]など。以下、中央派)、革共同再建協議会派(議長・橋本利昭[塩川三十二]、書記長・椿邦彦、毛利晋一[筆名=飛田一二三]ら。以下、関西派)、三・一四Ⅱ反対派(旧革共同九州地方委員会、旧全国青年戦闘同志会、筆者らのような諸個人)の三つに分裂した。前二者が組織として形態上のまとまりをもっているのに比して、三・一四Ⅱ反対派はそれぞれ独自の存在であり、諸個人は分散している。
この大分裂によって革共同の組織内にくりかえし激震が走るという異様な事態が連続したのだった。それはいまも続いている。しかし明らかにされていない事実があまりにも多い。
ひるがえって革共同政治局は本多延嘉書記長がカクマル(当時議長・黒田寛一、副議長・松崎明、政治局員・根本仁ら)によって虐殺された一九七五年三月一四日以降、八一年第五回大会ごろから政治局の絶対化と徹底的な秘密主義をもって組織運営を押し通してきた。それは正しいことではなかった。そのことの一つの結果として〇六年三・一四党内リンチ=クーデターも引き起こされた。
また、革共同の関係者は、これら事実を見すえるそれぞれの義務があると考える。どんなに苦々しい現実であり、どれほどつらい事実であろうとも、そうしてほしい。筆者らの力不足のために大幅に遅れてしまったことが悔やまれるが、いまからでも知る権利と義務をひとしく行使できる条件が提示されなければならない。
筆者らは〇六年までかなりの長きにわたって政治局員であった。その立場で経験し知りえたこと、考えたことを基本的に公開し、革共同の関係者が権威主義から自由で率直な議論を交わすことができるよう本書を執筆した。いや、もともとそうしなければならない立場にあったのである。
二つは、現在の革共同・中央派の政治局が、すでに公刊されている機関紙誌の上で、創立から一九六〇年代以降のすべての革共同史の偽造をはかっているからである。『現代革命への挑戦――革命的共産主義運動の50年』(以下、革共同五〇年史)上巻が一三年一二月に、同下巻が一四年九月に出版された。同書は議長・清水による極めつきの右翼的清算主義と歴史偽造の「序章」を始めとして、全篇これ嘘と歪曲と居直りの書である。組織内部ではより露骨な表現で偽造にいそしんでいる。その内実はじつに卑劣、傲岸なものである。
とりわけ次の諸点は重大である。①何よりも「動労千葉特化路線」「階級的労働運動路線」の名によって、革共同が深化・発展させてきた革命論・革命戦略と戦闘的労働運動論を歪め否定し、革共同の歴史を動労千葉唯一主義でことごとく偽造している。根本的には戦後日本の労働者運動の豊かな経験とさまざまな苦闘をないがしろにしている。②七〇年、華僑青年闘争委員会からの糾弾を受けての七・七自己批判とそれにもとづくアジア人民・在日アジア人民への七・七自己批判路線(血債の思想◆1)を「血債主義」と罵倒して全面否定するにいたっている。③安保・沖縄闘争が日本革命・アジア革命の核心をなす戦略的たたかいであること、革共同はここに死力を尽くすべき党であることを押し隠している。④八〇年代に革共同が文字通り総力をあげた三里塚基軸論にもとづく三里塚二期決戦の展開を驚くほど過小に低めている。⑤八九~九〇年天皇決戦を始めとする対権力武装闘争をことごとく清算している。⑥本多書記長が最先頭に立ち一人一人が血みどろになって革命の命運をかけてたたかった対カクマル戦争の革命論的意義を抹殺し、単にカクマルとの政治・軍事力学の問題に解消し、かつ対カクマル戦争のもつ矛盾の内在的な総括から逃げている。
それら偽造の作業は〇六年三・一四党内リンチ以降、一気に前面化したものであるが、革共同でありかつ革共同であったすべての人々とそのたたかいを踏みにじるものでなくてなんであろう。そればかりではない。日本階級闘争史における一個の組織的犯罪行為といわなければならない。
現在の腐り果てた惨状からすれば、まさに昔日の感であるが、かつて革共同は故本多延嘉書記長を中心として、日本階級闘争の疾風怒濤の時代を労働者階級人民の先頭に立って、文字どおり身を挺して切りひらいていた。かつて中核派はその実践と理論において、そして「個に死して類に生きる」という本多精神の発露において、きわだった輝きを放っていた。共産主義社会の樹立をめざし、反帝国主義・反スターリン主義世界革命の旗をかかげて、帝国主義国家権力の暴力的打倒のために命をかけるにふさわしい政治的結集体、それが革共同(中核派)であった。だからこそ、革共同に自らの生死をかけてきたすべての人間の魂に照らして、どのような歴史の偽造も認めるわけにはいかない。
革共同にかかわる真実を明らかにする本書の作業は、筆者ら革共同に籍をおいた者の人間としての尊厳をかけたつとめでもある。
三つは、革共同はすでに死んでいるということである。筆者らは〇六年三月一四日から四月はじめの過程で、革共同は最終的に死んだと考えている。しかも、筆者らを含む政治局の腐敗と死滅の過程は残念ながら、そのかなり以前の一九八一年前後から始まっていたと認めなければならない。そのことの検証は筆者らの自己批判を含めて本書で詳しく明らかにした。だからこそ、革共同を名のる政治組織がいま堕落した姿をあらわにしながら恥知らずにも延命をつづけていることには、がまんがならない。ここでは、中央派のことをいっているが、関西派にしてもしかりである。自らがなした三・一四党内リンチのもつ組織論的・思想的かつ歴史的な誤りと錯覚についての反省がまったくなく、これまた恥ずべき姿をさらしている。
はっきりいって、腐りきった革共同、革共同ならざる革共同は、まるごと歴史の屑籠に放りこまなければならない。そうすることによってのみ、はじめて次の新しい可能性を生み出すことができると信じる。あるいは、そうすることによってのみ、次代の青年労働者・学生たちが、われわれの時代の輝きと敗北を教訓として、自らの進むべき道を切りひらくことにつながるであろう。
本書の構成は次のようである。
序章では、革共同あるいは中核派とは何であったのか、その輝きと誤りについて概括的に述べる。
第1部は、〇六年三・一四党内リンチのドキュメントである。そして今日の革共同の堕落しきった惨状への批判であり、筆者らの自己批判である。
第2部は、本多書記長が虐殺されて以降の革共同政治局史をあえて暗部をえぐり出す視角からほぼ全面的に明らかにしたものである。本多時代の革共同の若干の重大な誤りについても自己批判的総括の視点を提起した。
もって筆者らの自己解剖、自己批判とし、日本革命運動の前進への教訓にしていただければと念じている。ただし、本書は本来書かれるべき革共同の正史の核心部ではあるが、一部をなすにすぎないことをお断りしておく。
諸言の最後に一言させていただく。私たち筆者は本書において、革共同にかかわった多くの人たちからの証言の聞き取りを重ね、多角的な検証を行った。この意味で本書は協力してくれた人々との共同の作業の産物でもあり、できるだけ多くの革共同関係者の意思を尊重するようつとめた。とはいえ、あくまで筆者二人の考えを記しているにすぎない。異なる視点、異論、反論、別の教訓化があることは当然である。しかし本多書記長虐殺以降の革共同政治局の歴史の内在的な検証としては、けっして誤りのないよう書き記したつもりである。
ところで革共同は、自らが先頭に立つ現代の共産主義運動を〈反スターリン主義・革命的左翼〉〈反スターリン主義・革命的共産主義運動〉、あるいはたんに〈革命的左翼〉〈革命的共産主義運動〉と規定してきた。ここには、深くかつ重々しい意味をこめている。けれども本書では、革共同を含めていわゆる新左翼を〈ラディカル左翼〉と表現することをお断りしておく。また本書で引用した本多延嘉、清水丈夫の論文はそれぞれ『本多延嘉著作選』『清水丈夫選集』(ともに前進社)に収録されている。
証言に応じてくれた人々に心から感謝するとともに、読者のみなさんの忌憚のないご批判を乞うしだいである。
………………………………………………………………………………………………………
『革共同政治局の敗北 1975~2014』から「緒言」

※本書で登場する革命的共産主義者同盟全国委員会の関係者氏名は、政治局員で対外的に本名を使用している場合は本名で、その他はおおむね組織名ないし筆名で表記した。また、すべて敬称を略すことをお断りしておく。
本書を執筆する動機と目的について、簡潔に記しておきたい。
本書のテーマは革命的共産主義者同盟全国委員会(革共同、いわゆる中核派)の分裂と転落の歴史および実相の切開である。これは、筆者らにとって臓腑をえぐられるほどつらいものであり、元同志らをはじめ左翼運動に関心をもつより多くの読者の皆さんにとっても、暗く、重く、失望の念を禁じえないような幾多の事象をつづることになる。しかし、どうしても書いておかなければならない、と筆者らは考えたのである。
一つは、革共同の党員および党籍をおいた者は、二〇〇六年三・一四党内リンチ=クーデターをめぐって起こった、数年間にわたるすべての事実を知る権利があるということである。
三・一四Ⅱ(以下、七五年三月一四日のカクマルによる本多延嘉書記長虐殺と区別するために、三・一四Ⅱあるいは三・一四党内リンチと表記)をめぐって革共同は大きくは中央政治局派(議長・清水丈夫、副議長・故中野洋、書記長・天田三紀夫、田中康宏[松丘静司]、現中央労対部長・辻川慎一[大原武史]など。以下、中央派)、革共同再建協議会派(議長・橋本利昭[塩川三十二]、書記長・椿邦彦、毛利晋一[筆名=飛田一二三]ら。以下、関西派)、三・一四Ⅱ反対派(旧革共同九州地方委員会、旧全国青年戦闘同志会、筆者らのような諸個人)の三つに分裂した。前二者が組織として形態上のまとまりをもっているのに比して、三・一四Ⅱ反対派はそれぞれ独自の存在であり、諸個人は分散している。
この大分裂によって革共同の組織内にくりかえし激震が走るという異様な事態が連続したのだった。それはいまも続いている。しかし明らかにされていない事実があまりにも多い。
ひるがえって革共同政治局は本多延嘉書記長がカクマル(当時議長・黒田寛一、副議長・松崎明、政治局員・根本仁ら)によって虐殺された一九七五年三月一四日以降、八一年第五回大会ごろから政治局の絶対化と徹底的な秘密主義をもって組織運営を押し通してきた。それは正しいことではなかった。そのことの一つの結果として〇六年三・一四党内リンチ=クーデターも引き起こされた。
また、革共同の関係者は、これら事実を見すえるそれぞれの義務があると考える。どんなに苦々しい現実であり、どれほどつらい事実であろうとも、そうしてほしい。筆者らの力不足のために大幅に遅れてしまったことが悔やまれるが、いまからでも知る権利と義務をひとしく行使できる条件が提示されなければならない。
筆者らは〇六年までかなりの長きにわたって政治局員であった。その立場で経験し知りえたこと、考えたことを基本的に公開し、革共同の関係者が権威主義から自由で率直な議論を交わすことができるよう本書を執筆した。いや、もともとそうしなければならない立場にあったのである。
二つは、現在の革共同・中央派の政治局が、すでに公刊されている機関紙誌の上で、創立から一九六〇年代以降のすべての革共同史の偽造をはかっているからである。『現代革命への挑戦――革命的共産主義運動の50年』(以下、革共同五〇年史)上巻が一三年一二月に、同下巻が一四年九月に出版された。同書は議長・清水による極めつきの右翼的清算主義と歴史偽造の「序章」を始めとして、全篇これ嘘と歪曲と居直りの書である。組織内部ではより露骨な表現で偽造にいそしんでいる。その内実はじつに卑劣、傲岸なものである。
とりわけ次の諸点は重大である。①何よりも「動労千葉特化路線」「階級的労働運動路線」の名によって、革共同が深化・発展させてきた革命論・革命戦略と戦闘的労働運動論を歪め否定し、革共同の歴史を動労千葉唯一主義でことごとく偽造している。根本的には戦後日本の労働者運動の豊かな経験とさまざまな苦闘をないがしろにしている。②七〇年、華僑青年闘争委員会からの糾弾を受けての七・七自己批判とそれにもとづくアジア人民・在日アジア人民への七・七自己批判路線(血債の思想◆1)を「血債主義」と罵倒して全面否定するにいたっている。③安保・沖縄闘争が日本革命・アジア革命の核心をなす戦略的たたかいであること、革共同はここに死力を尽くすべき党であることを押し隠している。④八〇年代に革共同が文字通り総力をあげた三里塚基軸論にもとづく三里塚二期決戦の展開を驚くほど過小に低めている。⑤八九~九〇年天皇決戦を始めとする対権力武装闘争をことごとく清算している。⑥本多書記長が最先頭に立ち一人一人が血みどろになって革命の命運をかけてたたかった対カクマル戦争の革命論的意義を抹殺し、単にカクマルとの政治・軍事力学の問題に解消し、かつ対カクマル戦争のもつ矛盾の内在的な総括から逃げている。
それら偽造の作業は〇六年三・一四党内リンチ以降、一気に前面化したものであるが、革共同でありかつ革共同であったすべての人々とそのたたかいを踏みにじるものでなくてなんであろう。そればかりではない。日本階級闘争史における一個の組織的犯罪行為といわなければならない。
現在の腐り果てた惨状からすれば、まさに昔日の感であるが、かつて革共同は故本多延嘉書記長を中心として、日本階級闘争の疾風怒濤の時代を労働者階級人民の先頭に立って、文字どおり身を挺して切りひらいていた。かつて中核派はその実践と理論において、そして「個に死して類に生きる」という本多精神の発露において、きわだった輝きを放っていた。共産主義社会の樹立をめざし、反帝国主義・反スターリン主義世界革命の旗をかかげて、帝国主義国家権力の暴力的打倒のために命をかけるにふさわしい政治的結集体、それが革共同(中核派)であった。だからこそ、革共同に自らの生死をかけてきたすべての人間の魂に照らして、どのような歴史の偽造も認めるわけにはいかない。
革共同にかかわる真実を明らかにする本書の作業は、筆者ら革共同に籍をおいた者の人間としての尊厳をかけたつとめでもある。
三つは、革共同はすでに死んでいるということである。筆者らは〇六年三月一四日から四月はじめの過程で、革共同は最終的に死んだと考えている。しかも、筆者らを含む政治局の腐敗と死滅の過程は残念ながら、そのかなり以前の一九八一年前後から始まっていたと認めなければならない。そのことの検証は筆者らの自己批判を含めて本書で詳しく明らかにした。だからこそ、革共同を名のる政治組織がいま堕落した姿をあらわにしながら恥知らずにも延命をつづけていることには、がまんがならない。ここでは、中央派のことをいっているが、関西派にしてもしかりである。自らがなした三・一四党内リンチのもつ組織論的・思想的かつ歴史的な誤りと錯覚についての反省がまったくなく、これまた恥ずべき姿をさらしている。
はっきりいって、腐りきった革共同、革共同ならざる革共同は、まるごと歴史の屑籠に放りこまなければならない。そうすることによってのみ、はじめて次の新しい可能性を生み出すことができると信じる。あるいは、そうすることによってのみ、次代の青年労働者・学生たちが、われわれの時代の輝きと敗北を教訓として、自らの進むべき道を切りひらくことにつながるであろう。
本書の構成は次のようである。
序章では、革共同あるいは中核派とは何であったのか、その輝きと誤りについて概括的に述べる。
第1部は、〇六年三・一四党内リンチのドキュメントである。そして今日の革共同の堕落しきった惨状への批判であり、筆者らの自己批判である。
第2部は、本多書記長が虐殺されて以降の革共同政治局史をあえて暗部をえぐり出す視角からほぼ全面的に明らかにしたものである。本多時代の革共同の若干の重大な誤りについても自己批判的総括の視点を提起した。
もって筆者らの自己解剖、自己批判とし、日本革命運動の前進への教訓にしていただければと念じている。ただし、本書は本来書かれるべき革共同の正史の核心部ではあるが、一部をなすにすぎないことをお断りしておく。
諸言の最後に一言させていただく。私たち筆者は本書において、革共同にかかわった多くの人たちからの証言の聞き取りを重ね、多角的な検証を行った。この意味で本書は協力してくれた人々との共同の作業の産物でもあり、できるだけ多くの革共同関係者の意思を尊重するようつとめた。とはいえ、あくまで筆者二人の考えを記しているにすぎない。異なる視点、異論、反論、別の教訓化があることは当然である。しかし本多書記長虐殺以降の革共同政治局の歴史の内在的な検証としては、けっして誤りのないよう書き記したつもりである。
ところで革共同は、自らが先頭に立つ現代の共産主義運動を〈反スターリン主義・革命的左翼〉〈反スターリン主義・革命的共産主義運動〉、あるいはたんに〈革命的左翼〉〈革命的共産主義運動〉と規定してきた。ここには、深くかつ重々しい意味をこめている。けれども本書では、革共同を含めていわゆる新左翼を〈ラディカル左翼〉と表現することをお断りしておく。また本書で引用した本多延嘉、清水丈夫の論文はそれぞれ『本多延嘉著作選』『清水丈夫選集』(ともに前進社)に収録されている。
証言に応じてくれた人々に心から感謝するとともに、読者のみなさんの忌憚のないご批判を乞うしだいである。
◆1 血債の思想。血債ということばは魯迅に由来する。「これは事件の結末ではない。事件の発端である。墨で書かれた虚言は、血で書かれた事実を隠すことはできない。血債は必ず同一物で返済されねばならない。支払いが遅ければ遅いほど、利息は増さねばならない。」(「花なきバラの二」、一九二六年三月)。この魯迅の章句は華僑青年闘争委員会および『底流』編集委員会が革共同の入管闘争論を批判するなかで引用した。彼らは朝鮮・中国・アジアへの侵略・植民地支配を強行した日本帝国主義およびそれに加担した労働者人民と、アジア人民との間には依然として民族抑圧―被抑圧の構造が続いていること、血債が支払われていないことを革共同は認識していないと糾弾した。革共同は、華青闘・『底流』編集委員会、その背後にある厖大なアジア人民の苦しみと怒りに向き合い連帯する上でアジア人民への血債の関係があるという認識をもたなければならないこと、その認識を綱領的な次元で位置づけることを確認した。そしてその後、七四年一月、阿部繁(=清水丈夫)「狭山闘争への反革命的介入ねらうカクマルを血債にかけて粉砕せよ」(『前進』六六六号)において「血債」ということばを公式にはじめて使用した。以後、民族問題を始めとする差別・抑圧の問題で思想的・路線的意味を込めて血債という概念を位置づけてきた。
ただし狭山闘争論での清水による血債の語句の使用には重大な政治的利用主義と七・七自己批判の立場の政治力学主義的歪曲が孕まれている。このことに、筆者らは近年ようやく気がついた(第10章第5節)。
ただし狭山闘争論での清水による血債の語句の使用には重大な政治的利用主義と七・七自己批判の立場の政治力学主義的歪曲が孕まれている。このことに、筆者らは近年ようやく気がついた(第10章第5節)。



















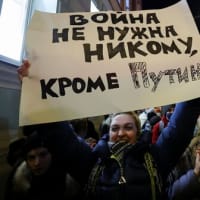
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます