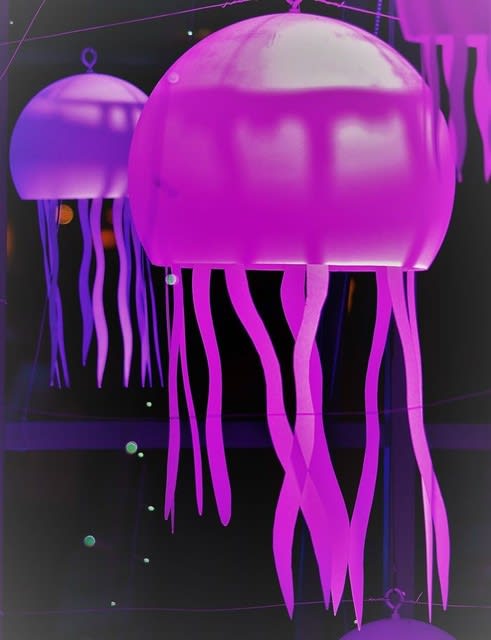190305城南宮
当然のことだが季節は移り行き、啓蟄前の昨日5日、
天気も良いので城南宮に行ってみた。
昼過ぎまでは用事があり、城南宮着は14時頃。
城南宮の春先は梅の香で満たされる。しだれ梅が有名になって久しい。
ここは古くは邑の鎮守社のような役割を担っていたのだろうけど、
平安時代に72代白河天皇・74代鳥羽天皇が院政を執った所として、
にわかに開けて、「都移り」の感を呈したらしい。
この社の歴史についての詳述はしないが、明治維新の時の鳥羽伏見の
戦いの場としても知られている。
そのように歴史的には非常に重要な位置を占めていることは論をまたない。
さて、しだれ梅。飽きもせずに毎年のように見に行っているが、今年は
花が少し少ないか?という気もした。ひょっとしたら昨年9月の台風禍の
影響がほんの少しはあるのかもしれないとも思う。
ともあれ、ほぼ満開の梅が競うように咲き誇っていて、花に酔い痴れる。
初めの写真は安楽寿院の近衛天皇陵。ここはもともとは美福門院の陵墓と
して建立されたものだが近衛天皇が夭折したために近衛天皇陵としたらしい。
もちろん建立当時のものではなくて豊臣秀頼の寄進になる。
下の4枚は城南宮でのもの。散った花弁が水路に浮かんでいたけれども、設定が悪い。
花弁がぼけても良いので、わずかにあった水流を感じさせる写真でないとダメ。味がない。
絵になっていない。もう一度撮り直しにとは思ったが、行かないままである。

以下はしだれ梅。



城南宮での写真は下にあります。御覧願います。