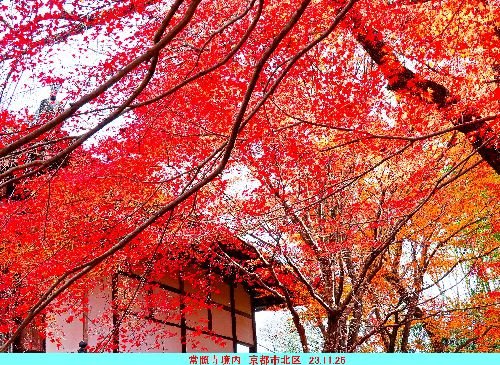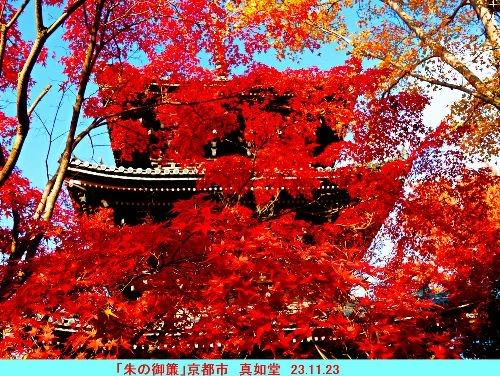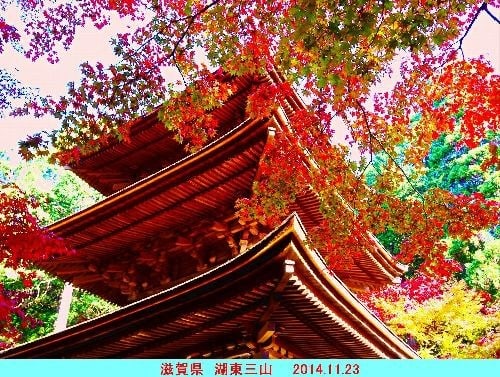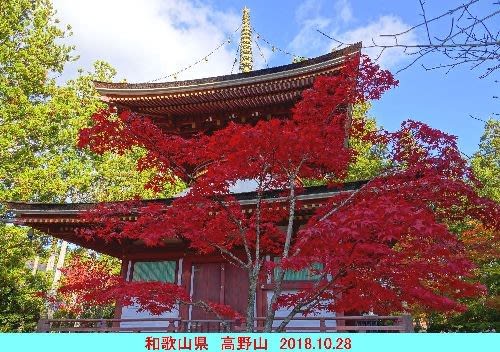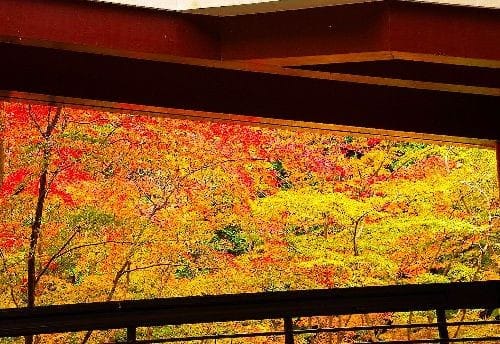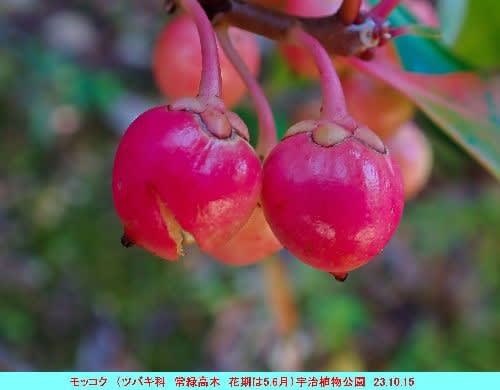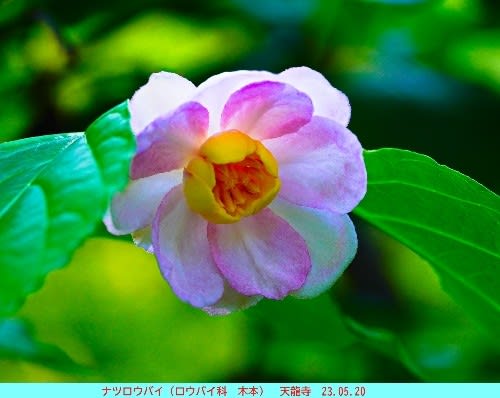この年もすでに二週間を余すばかりになった。
長い歳月を振り返りみれば「光陰は矢の如し」なのだが、
1年というサイクルで見た場合にも、そんなに感じるのは、
私が馬齢を重ね過ぎた証拠でもあるのかもしれない。
先回のブログアップから1か月になんなんとしている。
少し間隔があきすぎたきらいもあるが、仕方ないという
思いもある。
先回は撮りためていた花の「ホトトギス」の画像を出して、
お茶を濁した感もあるのだが、今回はこの間に撮影した画像を
披瀝します。
11/19に御苑と植物園に行ったのだが紅葉の色付きは「まだまだ」と
いう感じだった。「まだまだ」どころではない、今年の京都には紅葉がない・・・
とも思ったものだった。
それで今年の紅葉は無理だろうと半ばあきらめていた。
長く紅葉行脚を続けていて毎年のように20か所かそれ以上の
紅葉を見ていたのだが、コロナの以後はその機会も作らなったように思う。
久しぶりに紅葉撮影に積極的な自分を発見していたのだが、
これでは撮影する意味も無いという思いもよぎっていた。
ところが、わずか四日後の金戒光明寺・栄摂院、永観堂に行ってみると、
充分に紅葉している樹々が観られて、望外のことでラッキーだとも思った。
紅葉の見所はやはり良い。色付きのすばらしい紅葉自体はさらに良い。
今年はもう他に見なくても、充分に満足したような思いもあった。
26日には大阪府豊中市の「服部緑地公園」。28日には「しょうざん・
常照寺・光悦寺・源光庵」。30日には「東福寺・智積院」にと行く。
それで私の今年の紅葉は終わった。行った場所の数量的には物足りないが、
それでも今年の紅葉はもう十分だとも思った。
来年にまた見る機会があれば、少しでも良いから見たいものだと思う。
さて、今年も残りは2週間。その間にどこかに撮影に行って、良いのが
撮れれば年内にもう一度ブログアップすることにします。
例によって一番上をクリックするとワンドライブに飛び、大きな
画像が表示されます。