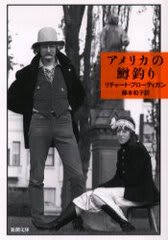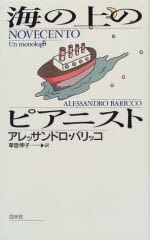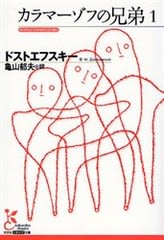好色にして粗野な地主フォードル・カラマーゾフにはミーチャ、イワン、アリョーシャの三人の息子がいた。妖艶な美人グルーシェニカと遺産問題を巡り、対立する父とミーチャ。婚約者カテリーナの金を横取りしたミーチャの金銭問題。カテリーナに寄せるイワンの愛情。そしてそんな家族に苦悩する修道僧のアリョーシャ。家族の種々の問題は、やがて父殺しにつながっていく。
ロシアの文豪ドストエフスキーの最後の作品にして最高傑作。
亀山郁夫 訳
出版社:光文社(光文社古典新訳文庫)
『カラマーゾフの兄弟』は数年前に新潮文庫の方で読んだ。だがそのときはストーリーのおもしろさは理解できたものの、その哲学性まで正確に把握できたかはいささか自信がなかった。
しかし今回の亀山訳では、文章がすらすらとよどみなく入ってくるため、プロットだけでなく、そこに流れる哲学的なテーマまで、(自分なりにではあるが)以前よりも読み取ることができた。それに各巻の末尾にある読書ガイドと、最終巻の解題のおかげで、より一層、『カラマーゾフの兄弟』という作品の深淵に触れることができたと思う。
解説や、各巻のあらすじも含めて、初心者向けの優れた名訳であると言っても差し支えないだろう。
『カラマーゾフの兄弟』を初めて読むという人は、新潮でも岩波でもなく、光文社古典新訳の方を読むべきだ、とまず初めに声を大にして言いたい。
さて中身の方であるが、単純におもしろく、わくわくしながら作品を読み進めることができた。テーマ性、プロット、キャラクターなど(むかしの作品と言うこともあって展開に遅さはあるものの)、すべてにおいて一級の仕上がりになっている。
プロットとしては、哲学的なテーマをはらんでいるため小難しさはあるものの、恋の鞘当がどのような形で進んでいくのか、父殺しがどのように展開されていくのか、裁判がどのように進んでいくのか、などに興味をそそられて、飽きることがない。
キャラという観点から言えば、三兄弟はどれもすばらしい造形だ。
ミーチャの破壊的で直情的な行動力は見ていても小気味いいし、イワンのインテリらしいたたずまいと暗さは雰囲気があり、魔性的な思想はどこか魅力的だ。アリョーシャの偽善者すれすれの姿も好ましさがある。
またキャラにからむこととしては、人物の心理描写が上げられるだろう。心理描写はとにかく綿密で、多面的な人間像と複雑さにはぞくぞくするものがある。これぞ、ドストエフスキーの真骨頂だ。
特にカテリーナとグルーシェニカのふたりの心理描写が存在感を放っている。
第一部での女の争いは際立っているし、プライドの高いカテリーナの微妙な心理の移ろいなどは人間観察に優れたドストエフスキーらしく、一筋縄ではいかない複雑さをはらんでいる。カテリーナ当人でさえも多分わかっていないかもしれない心理描写を丹念に描き取った文豪の筆力に圧倒されるばかりだ。
テーマ的な面に目を向けてみると、やはり神を巡る議論と、父殺しが際立っている。
その一方のテーマである神を巡る議論を解くカギはまちがいなく、イワンの「大審問官」の中にある。
イワンという人は人間の残虐性と弱さを把握した理想主義者なのだろう。
イワンは天上のパンに象徴される高尚な存在に、大多数の人間は達することができないことに気付いていた。しかし天上のパンに達することができなければ、子どもたちに示すような残虐性を人間が発揮することを、人が本質的に悪を欲することも、彼は知っていた。
そこでイワンが得た結論は、天上のパンを得ることができる天才たちが、地上のパンしか得ることができない人間を導く、というものだった。それはそれなりに筋が通っているように見える。
しかしイワンの代弁者である大審問官の態度は、その苦悩は認めつつも、独善的で冷笑的で傲慢だ。ひと言で言えば、愛が足りないのである。
それは「民衆は神を信じている。神を信じない実践家は、どんなに誠実な心をもち、どんなに天才的な知性をもっていようと、何ごともなしえない」と語るゾシマの、ひいてはアリョーシャの思想と好対照を成していて、おもしろい。
そんなゾシマ側の思想を端的に言うなら、原罪を基にした謙虚な態度による博愛主義と言ったところだろう。
苦しんでいる人間に、一本の葱を差し出す。それをつかんでくれるという保証はないけれど、それを差し出すという実践的な愛の行為だ。行動の基盤が愛にある、という点がすばらしい。それが天上のパンをつかみうる天才の側のもうひとつの態度表明なのだ。
その主義主張は理想主義にすぎるきらいはあるけれど、むしろそういった偽善と見えかねない言葉を堂々と語る姿に、僕は好印象を持った。
父殺しもこの神の理論と密接に結びついていて、深い議論が展開されている。
ミーチャもイワンも、苦しんでいる子どものことを語ったり、夢を見たりしているが、これがフョードルからひどい扱いを受けてきた自分たちの象徴であることは確かだろう。ミーチャもイワンも父を憎み、殺してしまいたいという気持ちは少なからずあったし、そう思うのも自然な流れだ。
しかし裁判中でフェチュコーヴィチが語った理論と反するが、だからと言って、実際に父が殺されていいはずなどはなく、犯罪は犯罪として憎まなければならない。
理想ではあるが、イリューシャのように父を守るために、戦う姿こそが美しいのだろう。それをふたりともが気付いていたはずだ。
それゆえにミーチャもイワンも苦しむ結果となったのだ。その際、ミーチャはキリストに自身を重ねようとしているが、ミーチャは弱くそんな真似は不可能だし、イワンは性格的に狂気に陥るしかない。
そういう人たちのためにこそ、アリョーシャのような一本の葱を差し出してくれる存在が非常に重要なのだろう。アリョーシャの存在と思想が、父殺しという苦悩に満ちた問題に、光を与えており、幾分かの希望を感じられたのが心に残った。
蛇足ながら、スメルジャコフがフョードルを殺した理由を自分なりに考察したい。
実際の父親が誰かはともかく、スメルジャコフ自身は自分の親をフョードルと思い込んでいたのではないか、と思う。
そしてそう考えたとき、兄弟でもっともひどい扱いを受けているのは当然スメルジャコフだ。憎悪が生まれるのも必然であり、金銭的な絡みもあるだろうが、殺害を思うのも自然な流れとなる。
そして実際に父殺しを行なったスメルジャコフは、そんな自分の殺害の動機の言い訳に、イワンを利用したのではないだろうか。そうすることでミーチャとイワンという、同じ兄弟なのに、遺産を相続する可能性があるふたりに復讐を試みたのではないだろうか。
もちろん論駁可能な意見ではあるが(じゃあアリョーシャはどうなる、という話になる)、そういう発想もありかな、と思ったので付け加えておく。
何かまとまりを欠いている上に、ムダに長くなってしまったが、読み終わった後には多くのことを語りたくなる作品ということなのだろう。そういう作品をこそ傑作と呼ぶのだ、と僕は思っている。
『カラマーゾフの兄弟』は、まさに傑作とよぶに値する作品なのである。
評価:★★★★★(満点は★★★★★)
そのほかのドストエフスキー作品感想
『悪霊』
『虐げられた人びと』
『白痴』