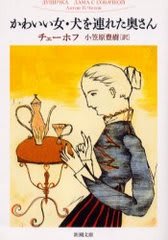凄惨な戦争を生きのび11年ぶりに再会した恋人は、芸能界の放埒な生活に身を委ねていた。心の傷を抱えながら失われた青春を取り戻そうとする二人――従来の戦争文学の枠を越えた傑作。
ヴェトナム戦争を内側から描き、多くの文学賞に輝いたヴェトナム人作家バオ・ニンの話題作。
池澤夏樹=個人編集 世界文学全集 Ⅰ-06
井川一久 訳
出版社:河出書房新社
正直言ってこの作品は決して読みやすいわけではない。意識的に時系列がいじられた作品だけあり、事実の前後の関係性が後になるまでわからない部分もあり、読むのも時折だが、難儀に感じる。
だが読み進むにつれて、徐々に明らかになる事実や、タイトルにもなっている「戦争の悲しみ」が立ち上がってくる様は非常に刺激的である。
戦争文学としてはレマルクの『西部戦線異状なし』が有名だが、この作品でも『西部戦線』同様、戦争の後遺症によるPTSDが示されている。たとえば主人公のキエンが過去の戦争での情景を街の真ん中で思い出すシーンは言うまでもなくPTSDの症状だろう。
その症状が起こるのはもちろん戦争において、苛酷な体験をしてきたからだ。
戦時中には自分の後ろを歩いていた人間に銃弾が当たって死ぬこともあったし、部下を置いて逃げたこともあった。自分を助けるために、輪姦されて殺されたホアのような女性もいたし、ほかにも女性兵士の多くがレイプされたことが示唆されている(『性犯罪被害にあうということ』を読んだ直後だけによけいつらく思う)。それだけでなく戦争が終わった後も、彼は遺骨収集のために、多くの死を眼前に見ることになってしまった。
若いときは戦争に身を投じる覚悟を持ったキエンも、その後、自分だけ生き残ってしまったがゆえにかなり心を苦しめられる結果となっている。その事実があまりにも悲しい。
そして戦争という重たい現実は、キエン本人のみならず、フォンとの関係性においても影を落としている点があまりに重い。
キエンとフォンの関係が決定的に損なわれたきっかけは、戦争下における集団レイプにあるだろう。その後の水浴のシーンで生じた互いの感情のずれが後々まで二人の関係性を暗くしているようにも見える。
そしてその間に起きた戦争は、長い時間が愛し合っていたはずの二人の運命さえ変えてしまった。
運命という言葉を使うと安直に見えかねないが、そう呼ばざるをえない残酷な状況がそこにある。
それらの暗い記憶や、壊れてしまった関係を清算するためにもキエンは小説を書かなければならなかったのかもしれない。
だがその湧き続ける記憶にうながされるように書いてきた小説を、彼は最終的に全否定するかのように焼こうとしてしまう。そこにキエンの絶望のすべてを見る思いがする。
魂を込めて、記憶に苦しみながら書き続けた作品を焼かざるをえない。その行為には重苦しいまでの苦しさに満ちている。
だが、それもまた戦争が落とした影の一つでもあるのだろう。
戦争は生きている限り、どこまでもキエンに影のようについて離れてくれない。その事実が読み手の心に強く訴えかけてきてやまない。
この小説には、戦争の悲劇が現実的な爆撃や銃弾の中にのみあるわけではないことを、静かに伝えてくれる。まさに良質の作品である。
評価:★★★★(満点は★★★★★)
同時収録: 残雪『暗夜』
そのほかの『池澤夏樹=個人編集 世界文学全集』作品感想
Ⅰ-05 ミハイル・ブルガーコフ『巨匠とマルガリータ』
Ⅰ-06 残雪『暗夜』
Ⅰ-11 J・M・クッツェー『鉄の時代』