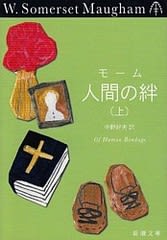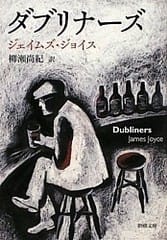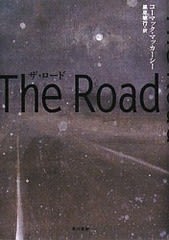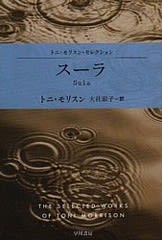少年は、十四歳で家出し、物乞いや盗みで生計を立て各地を放浪していた。時はアメリカ開拓時代。あらゆる人種と言語が入り乱れ、荒野は暴力と野蛮と堕落に支配されていた。行くあてのない旅の末、少年は、以前より見知っていた「判事」と呼ばれる二メートル超の巨漢の誘いで、グラントン大尉率いるインディアン討伐隊に加わった。哲学、科学、外国語に精通する一方で、何の躊躇もなく罪なき人々を殺していくこの奇怪な判事との再会により、少年の運命は残酷の極みに呑み込まれるのだった――。
《ニューヨーク・タイムズ》紙上で、著名作家の投票によるベスト・アメリカン・ノヴェルズ(2006-1981)に選出。少年と不法戦士たちの旅路を冷徹な筆致で綴る、巨匠の代表作。
黒原敏行 訳
出版社:早川書房
コーマック・マッカーシーの文体は、どこか突き放したかのような冷徹な感じがある。
その叙事的でクールなタッチが僕好みの文体である、はずだった。
だが、この『ブラッド・メリディアン』の文体はなぜか好きになれなかった。
やはりどこか冷たいタッチの文体なのに、文章に乗ることができない。多分それは以前読んだ作品よりも、文章の修飾表現が多いからかもしれない。
おかげで、物語そのものにもなかなか入り込むことができなかった。
最初は普通に読めていたのだけど、中盤から退屈になり、読むのをやめようかなとも考えた。
しかしなぜかはわからないけれど、後半から物語が突然おもしろくなり、ラストまで一気読みしてしまった。
これは読み手である僕のせいなのか、書き手のせいなのかはわからない。
何かどうでもいいことばかり書いた。
だがそんなことを長々と書くのは、要するに評価に迷ってしまう作品だからなのである。
本書は19世紀の西部を舞台にしており、インディアン討伐隊に参加した家出少年の話となっている。
ここで描かれるインディアンの殺戮シーンが本当にひどい。つうか、えぐい。
元々白人がインディアンを討伐しに行く理由も、「自らを統治できない連中」に代わってほかの者が統治するのだ、という身勝手な理屈でしかない。
治安や作物、物流の維持の関係もあり、インディアンと白人は対立していることが根本にあるとは言え、その論理は一方的だ。
そしてその誤った(と現代人の僕には見える)正義の元、彼らはインディアンたちを殺していく。
彼らはインディアンの村に突入して、住人を銃で撃ち、棍棒で頭を叩き割っていく。そして捕らえたインディアンたちの頭皮をはいでいく。
平たく言えば、彼らのやっていることは虐殺である。討伐隊は殺人集団と断言してもいい。
実際この討伐隊に参加しているのは、基本的に無法者ばかりで、犯罪集団と言えなくもない。
近隣の住民たちはインディアンを殺しまくる彼らを英雄して迎え入れているが、数日経つと、住民たちも彼らの無法行為におびえるようにもなっているからだ。
どれだけ大層な理念を掲げようと、内実なんてものはそんなものでしかないのだろう。
それは本当にただの殺人でしかない。
そしてそれは現代アメリカにも通じる、歴史的な負の側面なのかもしれない。
そんな討伐隊の中で、圧倒的存在感を放っているのが、ホールデン判事だ。
彼は『血と暴力の国』の暗殺者シュガーにどこか似ている。
命を奪うことに何のためらいもなく、それを当然の権利と思っているような輩だからだ。
「万物のうちのどんなものであれ(略)私の知らないうちに存在しているものは私に無断で存在しているということだ」って語るくらいだから、その程度がわかる。
言うなれば暴力の肯定者であり、あらゆる事物への支配欲求が強いのだろう。
それでいて、彼は人に対して紳士的にふるまうこともできる。その二面性が独特だ。
ラストシーンで踊り続ける判事の姿はどこかこわく見える。
血の栄光を賞賛し続ける判事の姿勢に寒気を覚えてしまうのだ。
しかしその判事のラストの姿に覚える寒気こそ、この小説全体を象徴する感覚と言えるのかもしれない。
物語に入り込めなかったポイントも多いので、誉めづらいのだが、独特の冷たさが余韻を残す一品である。
評価:★★★(満点は★★★★★)
そのほかのコーマック・マッカーシー作品感想
『ザ・ロード』
『すべての美しい馬』
『血と暴力の国』