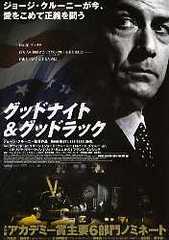2006年度作品。イギリス=フランス=イタリア映画。
1997年8月31日、チャールズ皇太子と離婚したダイアナが自動車事故で死亡する。ダイアナの死に対し、若き首相トニー・ブレアはいち早く対応し存在感を示すが、エリザベス女王はじめ、イギリス王室は何のコメントもせず、民衆の不信感は増していく。
監督は「ヘンダーソン夫人の贈り物」のスティーヴン・フリアーズ。
出演は本作でアカデミー賞主演女優賞を獲得したヘレン・ミレン。「サハラに舞う羽根」のマイケル・シーン ら。
実話風につくられていて、まずその手法に驚かされた。王室内でのやりとりのどこまでが事実かは知らないが、リアリティを感じさせ、なかなか見応えのある作品に仕上がっている。
保守的な王室の中にあって、基本的に女王の意見は筋が通っているように見える。
特に中盤の、母を失った孫を置いて出て行けるか、とか、いまは静かに悲しみに浸っている時間なのだ、といったニュアンスの発言は一人の人間としても、共感できるものがある。それにエディンバラ公の、会ったこともない人間になぜそこまで悲しむことができるのだ、とか、ヒステリックだ、という意見も核心をついていて皮肉を感じさせる。
だがそんな筋を通しても、だれがどう見ても彼らの対応は問題がある。
女王は私人として行動することは許されず、常に公人としての行動が望まれる存在なのだからだ。
王室の人間として、それにふさわしい行動を取り続けようと願いながら、時代の変化によって変わらなければいけないという現実。それに悩む女王の姿が胸に迫る。
特に花束の言葉を読むシーンは秀逸である。女王はなんだかんだ言って、敬意を集めているものの、必ずしもその目に見える敬意だけがすべてではないのだ。そういったときに女王として、どう行動すべきなのか、そういった苦悩がよく感じられる。
自分で車を運転したり、快活そうに見えるけれど、こうやって見ると、女王というのはなんとも生きていくのがつらいものだ、ということを思い知らされる。
そしてそういった女王の苦悩をヘレン・ミレンうまく体現できていたと思う。彼女の演技で映画により真実性を加味できていた。ブレアといい、それぞれの役者もうまく人物を再現できていた。
派手さはないが、なかなかの佳品といったところである
評価:★★★★(満点は★★★★★)
制作者・出演者の関連作品感想:
・マイケル・シーン出演作
「ブラッド・ダイヤモンド」